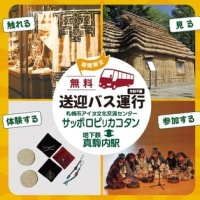歴史人5/13(月) 16:30
前回はかの有名な忠犬ハチ公と同じ秋田犬で、全国的にはほとんど無名である忠犬シロの物語を紹介した。今回は北海道の忠犬物語を2つ紹介したい。
■主のために雪山を40km以上走った忠犬
北海道はかつてアイヌの大地だった。何より地名がそれを示している。たとえば登別(のぼりべつ)は、アイヌ語の「ヌプリペツ」に漢字を当てはめたものである。留萌(るもい)のように、元々日本語にはないラ行の入った地名もある。
アイヌの人々は犬のことを「セタ」あるいは「シタ」と呼んでいた。アイヌ犬というのは、幕末にこの地を訪れたイギリス人、トーマス・ブラキストンがつけた呼称である。このアイヌ犬時代の忠犬として、明治33年(1900年)に起きた、『ジッセン』の物語を紹介したい。
ジッセンは厚真(あつま)地方の犬で、名猟犬の呼び声が高かった。飼い主の中村イサヌクテはアイヌの若き酋長(しゅうちょう)で、名猟師としても尊敬を集めていた人物だった。それはまだ雪の残る3月のことだった。近くの幾春別(いくしゅんべつ)に巨大な熊が現れ、家畜を襲っているとの連絡が来た。
そこでイサヌクテは息子と甥、それにジッセンを連れて出猟した。そして山に入ること3日、ジッセンが熊の足跡を発見したのである。その足跡を追っていると突然、熊が現れた。
意表を突かれた上に、そこは熊猟にとって最悪の場所だった。イサヌクテの力闘、そしてジッセンの猛攻にも関わらず、人間たちは傷つき、イサヌクテは命を落としてしまったのである。
ジッセンは傷だらけの体で血を流しながら、約40km以上の山越えの道を歩き、家に戻って急を知らせた。そして数日後、主人の後を追うように息絶えたのだった。ジッセンのこの行動に胸を打たれた村人たちは、イサヌクテの墓の横にジッセンをねんごろに葬ったのである。
アイヌ犬は明治35年(1904年)、青森第五連隊の雪中行軍遭難事件が起きた際、落部(おとしべ)コタンの長、弁開凧次郎(べんかいたこじろう)一行に率いられて捜索に参加。大活躍して名を高めた。
弁開凧次郎のアイヌ名はイカシバで、「偉大で何でもできる」という意味である。猟の達人であるだけでなく薬草にも詳しく、14歳で日高へ行き馬の勉強をした。地域に戻ってきてからは獣医の役割も果たしていた。
その2年後、つまりイサヌクテとジッセンが命を落としてから9年後の明治44年(1911年)、皇太子(のちの大正天皇)が室蘭製鋼所を視察した。その時、厚真村の長老がアイヌの酋長、中村コシカリを同伴してアイヌ犬の『ピン子』を紹介。気に入られて、そのまま献上となった。
このピン子こそ忠犬ジッセンの曾孫で、飼い主のコシカリはイサヌクテの息子だったのである。ピン子は厚真地方に多かった虎毛で、生後6ヶ月の頃、熊祭り(イオマンテ)の視察に訪れた八田三郎博士ら、学術関係者の目に留まった立派な犬だった。
■大正時代の郵便犬『ポチ』
次に大正時代の忠犬ポチ、またの名を郵便犬ポチの物語である。この話は、日本初の愛犬雑誌『犬の雑誌』の大正7年(1918年)3月号に、中央新聞の記者・金井紫雲が「大正忠犬談」と題して書いている。
この年は、前年末より北陸から北海道にかけて大雪が降り、家は倒れ鉄道は止まり、家畜たちが凍死するという大変な事態になっていた。ことに北海道では近年稀な大雪で、歩くのもままならない状態だったという。
こうした中、ニセコに近い北海道西部の真狩(まっかり)郵便局では、集配が全くできない状態になっていた。真狩村は洞爺湖の北にあり、ニセコから車で30分、羊蹄山を臨む自然豊かな地である。
それだけに冬の寒さは厳しい。加えて例年にない大雪に見舞われていた。そこに12月16日、電報が1通届いた。しかし、大雪で出勤もできないから配達人もいない。そこで局長の村上政太郎がみずから、吹雪の中を愛犬ポチを伴って出発した。
ポチは子犬の頃、村上が保護して育てた犬で、ふだんから郵便配達に同行していた。その日も村上は、ポチと共に何とか電報を届けた。しかしその帰途、吹雪はいよいよすさまじくなり、ちょうど起きた雪崩のため、ポチともども埋もれてしまったのである。
ポチは何とか雪の中から這い出した。そして雪をかき分け、村上局長の衣服を口でくわえて引っ張るなどして、助け出そうとした痕跡があった。しかし局長は動かず、ポチは仕方なく体の上に覆いかぶさって、体を温めていたらしい。
やがて、戻ってこない局長を心配した村人たちが捜索隊を出したところ、彼方から悲しげな犬の声が聞こえてくる。近づいてみると、犬が主人の上に覆いかぶさって守っていたのだ。急いで助けようとしたが、犬が主人を守っていて動かず、なかなか近づけなかったという。
金井は「此の犬、主人の死体を雪中に埋まること実に2昼夜、見る人感動せぬは無かったと申します」と、見てきたように描写している。「誠に、此の犬の如きは感ずべきものではありませんか。犬は今でも立派に同村内で養われ、夫れから夫れへと忠犬の名を届かせて居るのです」。この悲劇とポチの忠犬ぶりは新聞で伝えられ、蝦夷富士の麓に記念碑が建てられた。
ポチは17歳で犬生を終えると、剥製となって東京逓信博物館に展示された。その後、地元高校生たちの要望によって里帰りして、真狩村公民館に飾られている。ネットでも見られるが、老いてなおかわいい風貌だ。
昭和2年(1927年)に篤志家の寄贈で、「忠犬ポチ乃碑」も建てられた。『名犬ポチ物語 吹雪にきえた郵便屋さん』(ハート出版)という、子ども向けの本もある。
しかし、本州から人がどんどん流入してくるにつれて、アイヌ犬全体がどんどん減っていった。アイヌの人々も猟では食べていけなくなり、犬は必須ではなくなったのである。
そんなアイヌ犬の危機に、アイヌコタン(部落)の近くで育った犬好きの北海タイムス(現在の)記者、伝法貫一が立ち上がり、アイヌ犬保存会を立ち上げた。そして昭和12年、天然記念物の指定を受ける時に北海道犬という名称に変更して、今日に至っている。
川西玲子
https://news.yahoo.co.jp/articles/768d8ce8057b0a2f418d1f843c259375124ad8b8