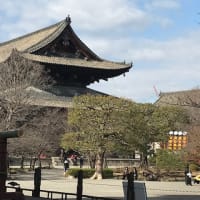語彙史研究について、リマインダーから、集めた。ちょうど1年前の記事になる。11月から12月まで、その研究について触れていることである。あらためて眺めてみて、ここに再録することにするが、この続編をまた、しばらく載せることとしよう。
さて、語彙史研究は語誌の研究であるとして、その学的分野の名称にいささかの疑義を持ちながら、その語誌について、語史としての記述があれば、それを集大成すればまた、語彙の研究となり、語彙史とはなり得ようかと捉えなおして、語史研究というものを想定して、するとそれは語誌であるのだから、国語辞書の用例を集めることとなると、そこに時代的な語例が並ぶことでもあると思う。その用例がそれぞれ時代の移り変わりにどのような用法のもとに記録、資料に現われていたかということになる。
その羅列をまた、語の意味内容に分けて、辞書では、その細目を立てて記述している。
語彙史研究の内容は多くその問題を取り上げた。
いま、ふたたび、という語を考える。
再び、と表記する。もとは、二度、とあって、ふた たび 、この語構成に、漢字表記をもって再度の意味をあてている。
辞書には、デジタル大辞泉は次のようである。
>1 同じ動作や状態を繰り返すこと。副詞的にも用いる。「―の来訪」「―過ちを犯す」
2 二番目。二度目。「―の御祓(はら)へのいそぎ」〈源・葵〉
ここには、いまはその意味では古語の用例として、もとの意味を2番目に記述する、1番目には副詞的な用法を注意している現代語である。これをいつの時代に、再び、となったかを説明するところがない。
また、日本国語大辞典は次のようである。その時代の用例を挙げて、意味内容を資料から見ることができる。
>日本国語大辞典
ふた‐たび 【二度・再】解説・用例
〔名〕
(1)同じ動作や状態の重なることをいう。再度。副詞的にも用いる。
*万葉集〔8C後〕五・八九一「一世には二遍(ふたたび)見えぬ父母を置きてや長く吾(あ)が別れなむ〈山上憶良〉」
*古今和歌集〔905〜914〕春下・一三一「声たえずなけや鶯ひととせにふたたひとだにくべき春かは〈藤原興風〉」
*浄瑠璃・女殺油地獄〔1721〕中「二たび侍の立つべき思案せずば此の分で刀は差されぬ」
*日本読本〔1887〕〈新保磐次〉三「こだまは響きの返りて二たび聞ゆる者なれば、亦返響とも云ふなり」
(2)順番としての第二をいう。二番目。二遍目。
*源氏物語〔1001〜14頃〕葵「ふたたひの御祓へのいそぎ、とり重ねてあるべきに」
*歌舞伎・小袖曾我薊色縫(十六夜清心)〔1859〕二幕「子細あって父を打ち、一度(ひとたび)逐電なしたれど、二た度我に討れんと、覚期極めし甲斐もなく」
語彙史研究1-10
2013-11 | 語と語彙
語彙論に語彙史の分野がある。語彙というわけであるから、語彙史なのだろう。しかしこの語をよくとらえてみると、語彙の歴史であるから、日本語の歴史とか、若者言葉の歴史であるとか、そのような内容だろうかと想像する。この語彙史があつかっているのは実は、語誌である。語史とも書いたと思われるが、語の意味の変遷が議論の多くを占めるようであるのでその語の歴史的なとらえ方であることには変わりない。
語彙史と言われて何を連想するか、それは語の発生また由来、語の意味内容についての用例、そこに生じている意味の議論である。国語語彙史研究会というのがあって、そこで尽くされている議論の詳細は、研究論集が発行されていて、それによるとわかりよい。語彙史に語彙という語の歴史的研究があれば詳しくするところだろうか。
最新研究情報では次の話題が見える。つまるところ、国語義の歴史的研究であったものを、語に関する資料、語史、語彙を扱った辞書など、その内容が見える。
日本語語彙史を考える。国語と日本語は実際には同じ言語である。何をもって日本語語彙とするか。歴史は連続する。日本語では1000年以上のあいだ、その語によって言語の記録を辿ることができる。そうすれば国語史であり日本語史である。
国語の由来が国字であり、和字、和語であるなら日本語はもと大和語である。語彙をとらえて日本語漢語、日本語大和語、日本語外来語とする語彙史ができる。日本語にある語彙をその範囲と単位の設定においてそれぞれ語の集合がある。その取り決めた範囲の語彙において歴史記述を試みることになるだろう。
それで国語か、日本語かとなる。
国語国字はキリシタン資料ではやわらげであり、日本地域の言葉であった和字和語のとらえ方に淵源があるし、国の意識がある国家語となるには国字国語問題を明治期に経ることになる。
あるいは国語は国語教育の言語でもある。その歴史経緯に於いて国語が日本語になることはない。国家語との規定は国の憲法に関わることがないし、国語教育と日本語教育は学習者を対象としてみると異なっている。
日本語語彙はどうとらえるか。語彙史である限り先ほどの国語と日本語の連続は避けられない。そうならば、これまで国語と呼ぶでいたものをすべて日本語に置き換えるかどうかとなって、国語学会が日本語学会となったようなことである。
国語語彙史研究の論集から、その研究テーマをタイトルで見てみよう。時代的には1980年5月から定期刊行されてもう30余集を数える。ここにはタイトルを年代順に並べることで第13集までを載せる。引き続き論集から紹介をしたいと思う。
国語語彙史研究テーマの一覧である。なお、特集など号によって掲載されているものを割愛している。執筆者のお名前もここでは載せていないので、その点につき、ご海容を願う。出典サイトは次である。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/kokugo/goishi/g-mokuji.html
語彙史研究の論集は第30集に総目次を載せる。サイトから検索すると、それまでのタイトルは第24集までを見ることができるのは既に紹介をしている。次のようである。
> 国語語彙史研究の体系化と共に、語彙史研究の新たな方法論や隣接分野との関わりにも取り組んだ論文集。三十集までの総目次を付す
国語語彙史研究の論集から、その研究テーマをタイトルで見てみよう。時代的には1980年5月から定期刊行されてもう30余集を数える。ここには語彙史研究3に続いてタイトルを年代順に並べることで第24集までを載せる。引き続き論集から紹介をしたいと思う。
国語語彙史研究テーマの一覧である。なお、特集など号によって掲載されているものを割愛している。執筆者のお名前もここでは載せていないので、その点につき、ご海容を願う。出典サイトは次である。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/kokugo/goishi/g-mokuji.html 第十四集 1994年8月30日発行から、第二十四集 2005年3月31日発行まで。
語彙研究の方法は語彙また語の設定にある。語彙史研究はその語彙また語の歴史変遷をあつかう。意味の変化を追求したのは19世紀の言語学である。日本語の意味の歴史的変遷は資料の制約からまれに時代を経てさかのぼることが可能である。漢語語彙の脈絡は古代漢語の文献、辞書にさかのぼる。それは日本語ではない、日本語ではないにもかかわらず日本にもたらされた文献を伝えて日本語に読み解いてきている。その一方で和語語彙は和歌に独自資料を遺した。物語と称される日本語資料は和歌の語と相関関係をもち日本語文法の骨格を成してきた。仮名文字だけで日本語を表そうとし、そこに漢語を交えた文献は漢文訓読として日本語になった。物語に軍記物、仏教経典に説話、そして公卿の記録に日本語が形成されてくる。辞書はその日本語を収載する。歴史資料に扱うものは次のようなものがある。それは項目としてさまざまに見えるが、漢語を日本語化した証である。
次は、日本国語大辞典があげる辞書である。
凡例に述べる。
平安時代から明治中期までに編まれた辞書のなかから代表的なものを選んで、本辞典の各見出しと対照し、その辞書に記載がある場合には、辞書の欄にそれぞれの略称を示す。
新撰字鏡〔京都大学文学部国語学国文学研究室編「新撰字鏡─本文篇・索引篇」による〕 …… 字鏡
和名類聚抄〔京都大学文学部国語学国文学研究室編「諸本集成和名類聚抄─本文篇・索引篇」による〕 …… 和名
色葉字類抄〔中田祝夫・峯岸明編「色葉字類抄研究並びに索引─本文索引編」による〕 …… 色葉
類聚名義抄〔正宗敦夫編「類聚名義抄─第壹巻・第貮巻仮名索引」による〕 …… 名義
下学集〔亀井孝校「元和本下学集」森田武編「元和本下学集索引」による〕 …… 下学
和玉篇〔中田祝夫・北恭昭編「倭玉篇研究並びに索引」による〕 …… 和玉
文明本節用集〔中田祝夫著「文明本節用集研究並びに索引─影印篇・索引篇」による〕 …… 文明
伊京集〔中田祝夫他編「改訂新版古本節用集六種研究並びに総合索引─影印篇・索引篇」による〕 …… 伊京
明応五年本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 明応
天正十八年本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 天正
饅頭屋本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 饅頭
黒本本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 黒本
易林本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 易林
日葡辞書〔イエズス会宣教師編による〕 …… 日葡
和漢音釈書言字考合類大節用集〔中田祝夫・小林祥次郎著「書言字考節用集研究並びに索引─影引篇・索引篇」による〕 …… 書言
和英語林集成(再版)〔東洋文庫複製本による〕 …… ヘボン
言海〔大槻文彦著の明治二四年刊初版による〕 …… 言海
(イ)「新撰字鏡」は天治本と享和本とを一括して扱う。ただし、万葉がなで記されたもの、ないしそれに準ずるものを採る。
(ロ)「和名類聚抄」は、箋注本(十巻本)と元和本(二十巻本)とを一括して扱う。ただし、採否については、「新撰字鏡」の場合に同じ。
(ハ)「色葉字類抄」は、前田本と黒川本とを一括して扱う。ただし、上巻・下巻において、前田本と黒川本で掲げる語形に違いがある場合は、前田本のみを対象とする。一字漢語については単語と確定できるものは採るが、字音語素と考えられるものは採らない。
(ニ)「類聚名義抄」は観智院本名義抄によるが、高山寺本・蓮成院本等によって誤字が訂正される場合はそのかたちを採る。
(ホ)「下学集」は、元和三年版により、本文左右の訓をはじめ、注の部分にある語も訓のある限り対象とする。
(ヘ)「和玉篇」は、慶長十五年版和玉篇により、和訓のみを対象とする。
(ト)「文明本節用集」は、「下学集」の扱いに準ずる。
(チ)「伊京集」はじめ六種の節用集は、「下学集」の扱いに準ずるが、「天正十八年本節用集」にみられる後筆による書き込みは一切対象としない。
(リ) 日葡辞書は、見出し語を対象とする。
(ヌ)「書言字考節用集」は、享保二年版本の見出し語について、左右の付訓すべてと、注部分の語も訓のある限り対象とする。
語彙史には日本語資料の用例が帰納される。その語が使われる資料に、漢語語彙は漢詩、漢文、和語語彙には韻文、散文による作品、そのどちらにもわたる記録、消息などである。外来語語彙にはその範囲を言語ごとの出自をとると、ポルトガル語借用語彙というふうになる。言語資料、言語作品に日本語の歴史にかかわるものは、記録されたものだけでも膨大であるから、そのうちに語彙の範囲を取るものと、その語の消長を追うものとがある。語について語史とするような、語誌には言語使用の場面を作品から用例とすることがあり、そこに掲載される用例の出典がまず挙げられることになる。時代と作品による用例の歴史記述は、やはり辞書などが行うところを参照できる。日本国語大辞典はその用例の典拠を一覧にする別冊子にして検索が簡便に工夫されていた。いまそれは、電子化された辞書の使用ではきわめて有効になった一覧である。辞書に用例が示されることは語彙心を考えるうえで、裨益すること大である。その解説するところを次に引用し、恩恵を受けることに感謝を申し上げる。
http://www.japanknowledge.com/contents/material/nikkoku/html/authority.html
主要出典一覧
【 凡例 】
「日本国語大辞典第二版」に用例として採録した文献を抄出する。本辞典で示す書名を見出しとするが、ジャンルまたは叢書名を示すものは、それらを見出しとし、そこに一括して掲げる。
書名には、読みを付し、以下の注記を施す。
(1) 作者または編者名
編者が複数の場合は、一、二名にしぼって示す。
作者が不明のもの、あるいは不確実なもの等は省略する。
(2) 成立年・刊行年
成立年あるいは刊行年のはっきりしているものは西暦年で示す。ただし、およそのことしかわからないものは、世紀(前・中・後・終)、時代等で示す。
私家集などで作者の没年を当てたものもある。
近代の作品の成立年は、初出の年を、また連載形式で発表されたものは、その連載の年を示す。ただし、初出または発表の年の不明なものは単行本の刊行年を示す場合もある。
序・跋の記された年などで示す場合もある。
(3) 底本名
本辞典において底本として採用したテキストを示す。
叢書などの類は、その叢書名のみを示し、単行本については、書名、または編者名、あるいは発行者名などいずれかを示す。
影印本・版本などについては、所蔵者名・書写年・刊記などを必要に応じて示す。
(4) 補助注記
略称で示した場合の正式の名称、あるいは特に著名な別称、分野、資料の性格、翻訳書における原作者等を必要に応じて示す。
http://www.japanknowledge.com/contents/material/nikkoku/html/furoku.html
付録の使い方
主要出典一覧
「日本国語大辞典第二版」は、三万余の文献から用例文を収録していますが、それらの文献のうち頻出するものを掲げました。これによって、その文献の成立年または刊行年、作者または編者、あるいは、この辞典で用いたテキストなどがわかるようになっています。引用文献の作者や編者を知りたい場合、原文についてもっと知りたい場合などにご利用ください。
http://www.japanknowledge.com/contents/hanrei/nikkoku/nikkoku08.html#nikkoku08-2
出典・用例について
採用する出典・用例
用例を採用する文献は、上代から現代まで各時代にわたるが、選択の基準は、概略次の通り。
(イ) その語、または語釈を分けた場合は、その意味・用法について、もっとも古いと思われるもの
(ロ) 語釈のたすけとなるわかりやすいもの
(ハ) 和文・漢文、あるいは、散文・韻文など使われる分野の異なるもの
(ニ) 用法の違うもの、文字づかいの違うもの
なお、文献からの用例が添えられなかった場合、用法を明らかにするために、新たに前後の文脈を構成して作った用例(作例)を「 」に入れて補うこともある。
用例の並べ方は、概略次の通りとする。
(イ) 時代の古いものから新しいものへと順次並べる。
(ロ) 漢籍および漢訳仏典の用例は、末尾へ入れる。
語彙史研究には索引が有効なツールとなる。索引と言えば、いまやコンピュター利用で瞬時に用例検索ができる。それは入力されたものという資料に限定されるが、その資料はコンピュータの能力によって無限になる。索引にはインデックス、コンコーダンス、コーパスといった用語で示されるものが一般となって用途にも広がりを見せている。語の検索には用語索引、総索引、自立語索引などの語で示されたころの思いから比すれば時代の変化、情報の革新には驚きを隠せない。
用語索引を例にして、万葉集索引を挙げると、万葉集総索引が編まれたころに、その労苦は想像を超える。その後に文学作品の用例を検索するのに個別に索引が編まれるようになるのは、上代から近世までの古典文学が刊行された1950年代以降のこととして、刊行された索引集をとらえることができる。それは岩波古典文学大系で、第1期、第1巻~第66巻は1957年から1962年にかけ、第2期、第67巻 - 第100巻は1967年までに、次々と作品を定本とすべく、底本を議論して編集された。これはさらに新日本古典文学大系となって、さきの万葉集ほかに索引が添えられる。そして文学作品で特筆すべきは、その間には源氏物語の総索引があり、索引の嚆矢を為す。
http://www.hanawashobo.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-8273-0110-6
>『萬葉集索引』(古典索引刊行会編、2003年)がなされ、今回の電子総索引となったのである。
1929年の『萬葉集総索引』が『万葉集』研究の飛躍をもたらしたことは知られるとおりである。『萬葉集大成』に組み込まれ、単行本としても刊行されて、広く利用されてきたが、本文および注釈研究の進展をとりいれた、あたらしい総索引がもとめられてもきた。2003年の『萬葉集索引』はこれにこたえたものであった。そして、状況は電子化を必須のものとしている。現在web上には、『万葉集』テキストもあり、検索システムも提供されている。こうした状況のなかだからこそ、いま、もっとも信頼できるテキストによる、CD版、電子総索引がなされることの意義はきわめておおきい。ことは、なによりテキストの信頼性にかかるのである。
>索引編[編集]
一般語彙編、助詞・助動詞編、項目一覧からなる。索引編は、校異編の完成以後の作業の中心となったものであり、このような作業にコンピュータを利用することなど考えられなかった時代に、この索引編を作成するために、一般語彙については約50万枚、助詞・助動詞については約60万枚の紙によるカードを作成したとされている[42]。
なお、この索引編を作る作業自体は早くから始められていたらしく、校異源氏物語と同じ中央公論社から出版されていた谷崎潤一郎の旧訳源氏物語の付録(月報第11号及び13号)には、「池田亀鑑の『校異源氏物語』は昭和15年の時点では索引が計画されていた」旨が記されており[43]、1943年(昭和18年)に東京帝国大学で池田亀鑑から源氏物語の講義を受けた今井源衛は、「講義の中で当時すでに一部完成していたらしい索引を元にして源氏物語語意論を語っていた」と述べている。
限定版
1953年(昭和28年)6月から1956年(昭和31年)12月にかけて発売された。
源氏物語大成 巻4 索引篇 1953年(昭和28年)8月発売 ISBN 4-12400-444-3
一般語彙索引
源氏物語大成 巻5 索引篇 1956年(昭和31年)4月発売 ISBN 4-12400-445-1
助詞・助動詞索引
普及版
源氏物語大成 第七冊 索引編 1985年(昭和60年)4月発売 ISBN 4-1240-2477-0
一般語彙索引上(あ~し)
源氏物語大成 第八冊 索引編 1985年(昭和60年)5月発売 ISBN 4-1240-2478-9
一般語彙索引下(す~を)
源氏物語大成 第九冊 索引編 1985年(昭和60年)6月発売 ISBN 4-1240-2479-7
助詞・助動詞索引上
源氏物語大成 第十冊 索引編 1985年(昭和60年)7月発売 ISBN 4-1240-2480-0
助詞・助動詞索引下
http://www.ism.ac.jp/~murakami/senden.htm
「源氏物語」語彙用例総索引の部屋
www.ism.ac.jp/~murakami/senden.htm
この索引は源氏物語の語彙を計量分析するために作成した品詞コード付本文データベースを用いて、前後10語程度の文脈付索引(KWIC)として出力したもです。 本文は『源氏物語大成』(中央公論社 刊)を用い、『日本古典文学大系』 (岩波書店 刊)と『日本古典 ...
索引 とは - コトバンク
kotobank.jp/word/索引
世界大百科事典 第2版 索引の用語解説 - 書籍,雑誌,辞典などの著作物における主要な内容,事柄を単一な検索法によって簡便に引き出せるように,一定の方式にしたがい編集したもの。ただし中国語では,内容別に分類した目録を索引と呼び,indexの訳語 ...
索引とは - はてなキーワード - はてなダイアリー
d.hatena.ne.jp/keyword/索引
「索引」とは - indexの日本語訳。テキストの見たい部分にいきつけるように、用語や人名など主要な項目を抜き出してそれぞれ参照すべきページを示したリスト。検索の便宜のために五十音順などで並べてある。
索引 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/索引
索引(さくいん)とは、百科事典・学術書などの書籍やコンピュータのデータにおいて、特定の項目を素早く参照できるよう、項目を特定の順番に並べ、その項目が出現する物理的な位置をまとめたもの。コンピュータで用いられる際にはインデックス (index (pl.
Wikipedia:索引 とは - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:索引_とは
Wikipedia:索引 とはは読み仮名が「とは」で始まる記事の一覧である。 .... 次ページ ⇒Wikipedia:索引 と#とひ. 「http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:索引_とは&oldid=48781445」から取得. カテゴリ: 索引 ...
索引とは - 短編小説作品名 Weblio辞書
www.weblio.jp › 品詞の分類 › 体言 › 名詞 › 名詞(道具)
索引とは?短編小説作品名。 (名)ある書物に載っている項目・人名・用語などを書き出して五十音順などに並べ、その所在ページなどを示した表。インデックス。 (名)スル(綱で)引っ張ること。 「車両を―する」 「索引」に似た言葉&ra...
岩波書店
別巻 萬葉集索引
佐竹 昭広,山田 英雄,工藤 力男,
大谷 雅夫,山崎 福之 編
■体裁=A5判・上製・函入・558頁
■定価 5,040円(本体 4,800円 + 税5%)
■2004年3月26日
■ISBN4-00-240105-7 C0391
現存最古の歌集として,素朴直截な表現で人びとの心をとらえつづけてきた『萬葉集』.大胆な構想力と緻密な考証と漢語表現の視点を取り入れて万葉注釈史に新生面を開いた新日本古典文学大系版『萬葉集』全4冊の理解と鑑賞のための索引.全句索引,人名索引,地名索引,枕詞索引,作品関係年表の5種を収録.
Amazon.co.jp: 萬葉集索引 (新日本古典文学大系): 佐竹 昭広, 工藤 力 ...
www.amazon.co.jp › 本 › 文学・評論 › 全集・選書 › 日本文学
Amazon.co.jp: 萬葉集索引 (新日本古典文学大系): 佐竹 昭広, 工藤 力男, 大谷 雅夫, 山田 英雄, 山崎 福之: 本.
萬葉集索引 - 岩波書店
www.iwanami.co.jp/.BOOKS/24/7/2401050.html
現存最古の歌集として,素朴直截な表現で人びとの心をとらえつづけてきた『萬葉集』.大胆な構想力と緻密な考証と漢語表現の視点を取り入れて万葉注釈史に新生面を開いた新日本古典文学大系版『萬葉集』全4冊の理解と鑑賞のための索引.全句索引,人名 ...
万葉集電子総索引 CD-ROM版 - BookSS
www.hanawashobo.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-8273-0110...
塙書房から、このたび『萬葉集電子総索引』(古典索引刊行会編)が刊行される。さきに木下正俊『萬葉集CD-ROM版』(2001年)を刊行したのに続く電子版である。塙書房の『萬葉集 本文篇』(佐竹昭広・木下正俊・小島憲之。補訂版1998年、初版1983年)は、 ...
『万葉集』の歌を調べたい。 | レファレンス協同データベース
crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000055103
万葉集索引 / 佐竹昭広 [ほか] 編 岩波書店 , 2004 (新日本古典文学大系 / 佐竹昭広 [ほか] 編 ; 別巻) ISBN:4002401057. 萬葉集索引 / 古典索引刊行会編 塙書房 , 2003 ISBN:4827300925. 新編国歌大観 第2巻;私撰集編 / 「新編国歌大観」編集委員会編 ...
語彙として扱われる語の研究には用例から初出を探索することになる。
初出は文献による記録されたものから証拠を求める。
出典また典拠として文献学の説明によって明らかにされる。
国語学が文献学であったゆえんである。
文献学であったとするのは、徳川時代からの国語の自覚においてその伝統的な手法が打ち立てられて、明治時代にPhylologyが西欧の学問分野の一つとして移入されて国語学が継承してきた文献による言語研究が行われたからであるが、その国語の分野に日本語としての立場の研究が現れるようになり、いまは、日本語学が広く分野を形成しつつある。
語彙史は資料によって、史料とするので、それは国語語彙史であった。19世紀の歴史言語学の影響によって語の発生と消長が議論されることに加えて、その語の意味の変遷が歴史時代と文献資料によって証明されてきた。
またその語の意味記述に用例による説明が、帰納法、つまり方法論として確立してきている。
古典対照語彙表が増補改訂されるようだ。語彙調査は文学の古典作品にも索引が研究対象に大きく進められた。古典対照語彙表が作られた。それまでの文学作品はざまざまに出版されていたが、文学全集の編集のもとにテキストが選定されて国語資料の底本が研究成果として定められてきた。いわば定本の選定が進んだのである。いくつかの文学作品の索引作成は総索引というふうに自立語、付属語を対象にした全数調査であった。その結果、自立語における作品の語彙量がわかった。
日本語語彙論 語彙調査2
2013-10-16 13:07:05 | 現代日本語百科
語彙調査は文学の古典作品にも索引が研究対象に大きく進められた。古典対照語彙表が作られた。それまでの文学作品はざまざまに出版されていたが、文学全集の編集のもとにテキストが選定されて国語資料の底本が研究成果として定められてきた。いわば定本の選定が進んだのである。いくつかの文学作品の索引作成は総索引というふうに自立語、付属語を対象にした全数調査であった。その結果、自立語における作品の語彙量がわかった。
笠間書院/古典対照語い表 媒体:FD #FD
作成:宮島達夫氏・中野洋氏・鈴木泰氏・石井久雄氏
登録:『フロッピー版 古典対照語い表および使用法』(1989.9、笠間書院刊)
底本:宮島達夫編『古典対照語い表』(笠間書院刊)
FILE:CSV形式、PC98用検索プログラム(C言語ソース付属)、BASICプログラム
価格:\6,500+税
内容:万葉集、竹取物語、伊勢物語、古今和歌集、土佐日記、後撰和歌集、蜻蛉日記、枕草子、源氏物語、紫式部日記、更級日記、大鏡、方丈記、徒然草の14作品の自立語を統計データとしたもの。
備考:書籍版の宮島達夫編『古典対照語い表』(笠間書院刊)もあります。
古典分類語彙表(稿) - 学習院
glim-re.glim.gakushuin.ac.jp/bitstream/.../keisankisenta_33_40_121.pdf
の一つとして,古典語を対象としたものとしては日本で最初の本格的なものとなる、古典語彙のシ. ソーラス(体系 ... 宮島達夫『古典対照語い表』(1971 年 笠間書院刊)が. 取り上げた 14 ... 宮 島達夫・鈴木泰・石井久雄・安部清哉編『日本古典対照分類語彙表』.
古典索引刊行会『万葉集索引』(2003 年 塙書房刊)
山田忠雄『竹取物語総索引』(1958 年 武蔵野書院刊)
伴 久美「伊勢物語に就きての研究 索引篇」(大津有一編『伊勢物語に就きての研究』
所収,1961 年 有精堂出版刊)
西下経一・滝沢貞夫『古今集総索引』(1958 年 明治書院刊)
日本大学文理学部国文学研究室『土左日記総索引』(1967 年 桜楓社刊)
大阪女子大学国文学研究室『後撰和歌集総索引』(1965 年 大阪女子大学刊)
佐伯梅友・伊牟田経久『かげろふ日記総索引』(1963 年 風間書房刊)
榊原邦彦・武山隆昭・塚原清・藤掛和美『枕草子総索引』(1967 年 右文書院刊)
池田亀鑑『源氏物語大成 索引篇』(1953 年 中央公論社刊)
東京教育大学中古文学研究部会『紫式部日記用語索引』(1956 年 日本学術振興会刊)
東 節夫・塚原鉄雄・前田欣吾『更級日記総索引』(1956 年 武蔵野書院刊)
秋葉安太郎「校本大鏡総索引」(『大鏡の研究 上巻 本文篇』所収,1960 年 桜楓社刊)
滝沢貞夫『新古今集総索引』(1970 年 明治書院刊) *
青木伶子『方丈記総索引』(1965 年 武蔵野書院刊)
増田繁夫・長野照子『宇治拾遺物語総索引』(1975 年 清文堂出版刊) *
近藤政美・武山隆昭・近藤三佐子『平家物語語彙用例総索引』(1996 年 勉誠社刊) *
時枝誠記『徒然草総索引』(1955 年 至文堂刊)
古典語彙を,意味による分類番号の順序で配列する。
意味による分類番号は,次による。
国立国語研究所編『国立国語研究所資料集14 分類語彙表 増補改訂版』
(2004 年,大日本図書刊)
分類は大きく次である。
1 体の類 名詞
2 用の類 動詞
3 相の類 形容詞・副詞
4 その他の類 接続詞・感動詞など
この番号のあとにピリオドを置いて,さらに4桁の番号で細分する。分類項目および番号の体系
については,本稿では説明を省略する。
ただし,本稿では,分類項目のすべてを載せる。古典語彙に該当するものがない項目では例えば
「1.1401(弾力・動力・圧力など)……該当なし」のように,「……該当なし」と記す。『分類語彙表』
の番号は必ずしも連続していないので,本稿での欠番は『分類語彙表』でもともと欠けている。なお,
古典語彙のために項目「3.9999(枕詞)」を新設し,また「意味不明」の項目も設ける。
古典17 作品における語の五十音順総覧は,近刊の予定である。
宮 島達夫・鈴木泰・石井久雄・安部清哉編『日本古典対照分類語彙表』
(2013 年春予定,笠間書院)
『古典対照語い表』の増補改訂版として,一語ごとに,語種・品詞・作品ごと出現頻度を示し,
さらに意味分類番号を添える。総語数34,366 である。
日本古典 対照分類語彙表 NEW
宮島達夫 他
税込価格:9,450円
発行年月:2013.12
「古典対照語い表」の改訂増補版が
1971年刊の「古典対照語い表」(笠間書院)が、来春、改訂増補版「日本古典対照分類語彙表」として刊行予定とのことです。
文学作品を追加し、エクセルデータ収録CDが付いてくるというので、基礎データとして使いやすそう。出版が楽しみです。
語彙研究の講座を見よう。語彙史研究を画期にまとめたのは、講座日本語の語彙である。1981年から1983年にかけて全11巻、別巻1からなる。語彙史に絞ってみれば、古代の語彙、中世の語彙、近世の語彙、現代の語彙と時代に編纂している。また、講座日本語の語彙9 語誌1、講座日本語の語彙10 語誌2 講座日本語の語彙11 語誌3 まとめられた文献は便利である。語史は語誌であるとするようなことであるが、ここの文献にはそれまでの語の研究情況を網羅しようとしている。講座日本語の語彙はその編集において論客を配して実践研究に示唆を与える。その巻の目次を紹介するにとどまるが、壮観である。
さて、語彙史研究は語誌の研究であるとして、その学的分野の名称にいささかの疑義を持ちながら、その語誌について、語史としての記述があれば、それを集大成すればまた、語彙の研究となり、語彙史とはなり得ようかと捉えなおして、語史研究というものを想定して、するとそれは語誌であるのだから、国語辞書の用例を集めることとなると、そこに時代的な語例が並ぶことでもあると思う。その用例がそれぞれ時代の移り変わりにどのような用法のもとに記録、資料に現われていたかということになる。
その羅列をまた、語の意味内容に分けて、辞書では、その細目を立てて記述している。
語彙史研究の内容は多くその問題を取り上げた。
いま、ふたたび、という語を考える。
再び、と表記する。もとは、二度、とあって、ふた たび 、この語構成に、漢字表記をもって再度の意味をあてている。
辞書には、デジタル大辞泉は次のようである。
>1 同じ動作や状態を繰り返すこと。副詞的にも用いる。「―の来訪」「―過ちを犯す」
2 二番目。二度目。「―の御祓(はら)へのいそぎ」〈源・葵〉
ここには、いまはその意味では古語の用例として、もとの意味を2番目に記述する、1番目には副詞的な用法を注意している現代語である。これをいつの時代に、再び、となったかを説明するところがない。
また、日本国語大辞典は次のようである。その時代の用例を挙げて、意味内容を資料から見ることができる。
>日本国語大辞典
ふた‐たび 【二度・再】解説・用例
〔名〕
(1)同じ動作や状態の重なることをいう。再度。副詞的にも用いる。
*万葉集〔8C後〕五・八九一「一世には二遍(ふたたび)見えぬ父母を置きてや長く吾(あ)が別れなむ〈山上憶良〉」
*古今和歌集〔905〜914〕春下・一三一「声たえずなけや鶯ひととせにふたたひとだにくべき春かは〈藤原興風〉」
*浄瑠璃・女殺油地獄〔1721〕中「二たび侍の立つべき思案せずば此の分で刀は差されぬ」
*日本読本〔1887〕〈新保磐次〉三「こだまは響きの返りて二たび聞ゆる者なれば、亦返響とも云ふなり」
(2)順番としての第二をいう。二番目。二遍目。
*源氏物語〔1001〜14頃〕葵「ふたたひの御祓へのいそぎ、とり重ねてあるべきに」
*歌舞伎・小袖曾我薊色縫(十六夜清心)〔1859〕二幕「子細あって父を打ち、一度(ひとたび)逐電なしたれど、二た度我に討れんと、覚期極めし甲斐もなく」
語彙史研究1-10
2013-11 | 語と語彙
語彙論に語彙史の分野がある。語彙というわけであるから、語彙史なのだろう。しかしこの語をよくとらえてみると、語彙の歴史であるから、日本語の歴史とか、若者言葉の歴史であるとか、そのような内容だろうかと想像する。この語彙史があつかっているのは実は、語誌である。語史とも書いたと思われるが、語の意味の変遷が議論の多くを占めるようであるのでその語の歴史的なとらえ方であることには変わりない。
語彙史と言われて何を連想するか、それは語の発生また由来、語の意味内容についての用例、そこに生じている意味の議論である。国語語彙史研究会というのがあって、そこで尽くされている議論の詳細は、研究論集が発行されていて、それによるとわかりよい。語彙史に語彙という語の歴史的研究があれば詳しくするところだろうか。
最新研究情報では次の話題が見える。つまるところ、国語義の歴史的研究であったものを、語に関する資料、語史、語彙を扱った辞書など、その内容が見える。
日本語語彙史を考える。国語と日本語は実際には同じ言語である。何をもって日本語語彙とするか。歴史は連続する。日本語では1000年以上のあいだ、その語によって言語の記録を辿ることができる。そうすれば国語史であり日本語史である。
国語の由来が国字であり、和字、和語であるなら日本語はもと大和語である。語彙をとらえて日本語漢語、日本語大和語、日本語外来語とする語彙史ができる。日本語にある語彙をその範囲と単位の設定においてそれぞれ語の集合がある。その取り決めた範囲の語彙において歴史記述を試みることになるだろう。
それで国語か、日本語かとなる。
国語国字はキリシタン資料ではやわらげであり、日本地域の言葉であった和字和語のとらえ方に淵源があるし、国の意識がある国家語となるには国字国語問題を明治期に経ることになる。
あるいは国語は国語教育の言語でもある。その歴史経緯に於いて国語が日本語になることはない。国家語との規定は国の憲法に関わることがないし、国語教育と日本語教育は学習者を対象としてみると異なっている。
日本語語彙はどうとらえるか。語彙史である限り先ほどの国語と日本語の連続は避けられない。そうならば、これまで国語と呼ぶでいたものをすべて日本語に置き換えるかどうかとなって、国語学会が日本語学会となったようなことである。
国語語彙史研究の論集から、その研究テーマをタイトルで見てみよう。時代的には1980年5月から定期刊行されてもう30余集を数える。ここにはタイトルを年代順に並べることで第13集までを載せる。引き続き論集から紹介をしたいと思う。
国語語彙史研究テーマの一覧である。なお、特集など号によって掲載されているものを割愛している。執筆者のお名前もここでは載せていないので、その点につき、ご海容を願う。出典サイトは次である。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/kokugo/goishi/g-mokuji.html
語彙史研究の論集は第30集に総目次を載せる。サイトから検索すると、それまでのタイトルは第24集までを見ることができるのは既に紹介をしている。次のようである。
> 国語語彙史研究の体系化と共に、語彙史研究の新たな方法論や隣接分野との関わりにも取り組んだ論文集。三十集までの総目次を付す
国語語彙史研究の論集から、その研究テーマをタイトルで見てみよう。時代的には1980年5月から定期刊行されてもう30余集を数える。ここには語彙史研究3に続いてタイトルを年代順に並べることで第24集までを載せる。引き続き論集から紹介をしたいと思う。
国語語彙史研究テーマの一覧である。なお、特集など号によって掲載されているものを割愛している。執筆者のお名前もここでは載せていないので、その点につき、ご海容を願う。出典サイトは次である。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/kokugo/goishi/g-mokuji.html 第十四集 1994年8月30日発行から、第二十四集 2005年3月31日発行まで。
語彙研究の方法は語彙また語の設定にある。語彙史研究はその語彙また語の歴史変遷をあつかう。意味の変化を追求したのは19世紀の言語学である。日本語の意味の歴史的変遷は資料の制約からまれに時代を経てさかのぼることが可能である。漢語語彙の脈絡は古代漢語の文献、辞書にさかのぼる。それは日本語ではない、日本語ではないにもかかわらず日本にもたらされた文献を伝えて日本語に読み解いてきている。その一方で和語語彙は和歌に独自資料を遺した。物語と称される日本語資料は和歌の語と相関関係をもち日本語文法の骨格を成してきた。仮名文字だけで日本語を表そうとし、そこに漢語を交えた文献は漢文訓読として日本語になった。物語に軍記物、仏教経典に説話、そして公卿の記録に日本語が形成されてくる。辞書はその日本語を収載する。歴史資料に扱うものは次のようなものがある。それは項目としてさまざまに見えるが、漢語を日本語化した証である。
次は、日本国語大辞典があげる辞書である。
凡例に述べる。
平安時代から明治中期までに編まれた辞書のなかから代表的なものを選んで、本辞典の各見出しと対照し、その辞書に記載がある場合には、辞書の欄にそれぞれの略称を示す。
新撰字鏡〔京都大学文学部国語学国文学研究室編「新撰字鏡─本文篇・索引篇」による〕 …… 字鏡
和名類聚抄〔京都大学文学部国語学国文学研究室編「諸本集成和名類聚抄─本文篇・索引篇」による〕 …… 和名
色葉字類抄〔中田祝夫・峯岸明編「色葉字類抄研究並びに索引─本文索引編」による〕 …… 色葉
類聚名義抄〔正宗敦夫編「類聚名義抄─第壹巻・第貮巻仮名索引」による〕 …… 名義
下学集〔亀井孝校「元和本下学集」森田武編「元和本下学集索引」による〕 …… 下学
和玉篇〔中田祝夫・北恭昭編「倭玉篇研究並びに索引」による〕 …… 和玉
文明本節用集〔中田祝夫著「文明本節用集研究並びに索引─影印篇・索引篇」による〕 …… 文明
伊京集〔中田祝夫他編「改訂新版古本節用集六種研究並びに総合索引─影印篇・索引篇」による〕 …… 伊京
明応五年本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 明応
天正十八年本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 天正
饅頭屋本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 饅頭
黒本本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 黒本
易林本節用集〔伊京集に同じ〕 …… 易林
日葡辞書〔イエズス会宣教師編による〕 …… 日葡
和漢音釈書言字考合類大節用集〔中田祝夫・小林祥次郎著「書言字考節用集研究並びに索引─影引篇・索引篇」による〕 …… 書言
和英語林集成(再版)〔東洋文庫複製本による〕 …… ヘボン
言海〔大槻文彦著の明治二四年刊初版による〕 …… 言海
(イ)「新撰字鏡」は天治本と享和本とを一括して扱う。ただし、万葉がなで記されたもの、ないしそれに準ずるものを採る。
(ロ)「和名類聚抄」は、箋注本(十巻本)と元和本(二十巻本)とを一括して扱う。ただし、採否については、「新撰字鏡」の場合に同じ。
(ハ)「色葉字類抄」は、前田本と黒川本とを一括して扱う。ただし、上巻・下巻において、前田本と黒川本で掲げる語形に違いがある場合は、前田本のみを対象とする。一字漢語については単語と確定できるものは採るが、字音語素と考えられるものは採らない。
(ニ)「類聚名義抄」は観智院本名義抄によるが、高山寺本・蓮成院本等によって誤字が訂正される場合はそのかたちを採る。
(ホ)「下学集」は、元和三年版により、本文左右の訓をはじめ、注の部分にある語も訓のある限り対象とする。
(ヘ)「和玉篇」は、慶長十五年版和玉篇により、和訓のみを対象とする。
(ト)「文明本節用集」は、「下学集」の扱いに準ずる。
(チ)「伊京集」はじめ六種の節用集は、「下学集」の扱いに準ずるが、「天正十八年本節用集」にみられる後筆による書き込みは一切対象としない。
(リ) 日葡辞書は、見出し語を対象とする。
(ヌ)「書言字考節用集」は、享保二年版本の見出し語について、左右の付訓すべてと、注部分の語も訓のある限り対象とする。
語彙史には日本語資料の用例が帰納される。その語が使われる資料に、漢語語彙は漢詩、漢文、和語語彙には韻文、散文による作品、そのどちらにもわたる記録、消息などである。外来語語彙にはその範囲を言語ごとの出自をとると、ポルトガル語借用語彙というふうになる。言語資料、言語作品に日本語の歴史にかかわるものは、記録されたものだけでも膨大であるから、そのうちに語彙の範囲を取るものと、その語の消長を追うものとがある。語について語史とするような、語誌には言語使用の場面を作品から用例とすることがあり、そこに掲載される用例の出典がまず挙げられることになる。時代と作品による用例の歴史記述は、やはり辞書などが行うところを参照できる。日本国語大辞典はその用例の典拠を一覧にする別冊子にして検索が簡便に工夫されていた。いまそれは、電子化された辞書の使用ではきわめて有効になった一覧である。辞書に用例が示されることは語彙心を考えるうえで、裨益すること大である。その解説するところを次に引用し、恩恵を受けることに感謝を申し上げる。
http://www.japanknowledge.com/contents/material/nikkoku/html/authority.html
主要出典一覧
【 凡例 】
「日本国語大辞典第二版」に用例として採録した文献を抄出する。本辞典で示す書名を見出しとするが、ジャンルまたは叢書名を示すものは、それらを見出しとし、そこに一括して掲げる。
書名には、読みを付し、以下の注記を施す。
(1) 作者または編者名
編者が複数の場合は、一、二名にしぼって示す。
作者が不明のもの、あるいは不確実なもの等は省略する。
(2) 成立年・刊行年
成立年あるいは刊行年のはっきりしているものは西暦年で示す。ただし、およそのことしかわからないものは、世紀(前・中・後・終)、時代等で示す。
私家集などで作者の没年を当てたものもある。
近代の作品の成立年は、初出の年を、また連載形式で発表されたものは、その連載の年を示す。ただし、初出または発表の年の不明なものは単行本の刊行年を示す場合もある。
序・跋の記された年などで示す場合もある。
(3) 底本名
本辞典において底本として採用したテキストを示す。
叢書などの類は、その叢書名のみを示し、単行本については、書名、または編者名、あるいは発行者名などいずれかを示す。
影印本・版本などについては、所蔵者名・書写年・刊記などを必要に応じて示す。
(4) 補助注記
略称で示した場合の正式の名称、あるいは特に著名な別称、分野、資料の性格、翻訳書における原作者等を必要に応じて示す。
http://www.japanknowledge.com/contents/material/nikkoku/html/furoku.html
付録の使い方
主要出典一覧
「日本国語大辞典第二版」は、三万余の文献から用例文を収録していますが、それらの文献のうち頻出するものを掲げました。これによって、その文献の成立年または刊行年、作者または編者、あるいは、この辞典で用いたテキストなどがわかるようになっています。引用文献の作者や編者を知りたい場合、原文についてもっと知りたい場合などにご利用ください。
http://www.japanknowledge.com/contents/hanrei/nikkoku/nikkoku08.html#nikkoku08-2
出典・用例について
採用する出典・用例
用例を採用する文献は、上代から現代まで各時代にわたるが、選択の基準は、概略次の通り。
(イ) その語、または語釈を分けた場合は、その意味・用法について、もっとも古いと思われるもの
(ロ) 語釈のたすけとなるわかりやすいもの
(ハ) 和文・漢文、あるいは、散文・韻文など使われる分野の異なるもの
(ニ) 用法の違うもの、文字づかいの違うもの
なお、文献からの用例が添えられなかった場合、用法を明らかにするために、新たに前後の文脈を構成して作った用例(作例)を「 」に入れて補うこともある。
用例の並べ方は、概略次の通りとする。
(イ) 時代の古いものから新しいものへと順次並べる。
(ロ) 漢籍および漢訳仏典の用例は、末尾へ入れる。
語彙史研究には索引が有効なツールとなる。索引と言えば、いまやコンピュター利用で瞬時に用例検索ができる。それは入力されたものという資料に限定されるが、その資料はコンピュータの能力によって無限になる。索引にはインデックス、コンコーダンス、コーパスといった用語で示されるものが一般となって用途にも広がりを見せている。語の検索には用語索引、総索引、自立語索引などの語で示されたころの思いから比すれば時代の変化、情報の革新には驚きを隠せない。
用語索引を例にして、万葉集索引を挙げると、万葉集総索引が編まれたころに、その労苦は想像を超える。その後に文学作品の用例を検索するのに個別に索引が編まれるようになるのは、上代から近世までの古典文学が刊行された1950年代以降のこととして、刊行された索引集をとらえることができる。それは岩波古典文学大系で、第1期、第1巻~第66巻は1957年から1962年にかけ、第2期、第67巻 - 第100巻は1967年までに、次々と作品を定本とすべく、底本を議論して編集された。これはさらに新日本古典文学大系となって、さきの万葉集ほかに索引が添えられる。そして文学作品で特筆すべきは、その間には源氏物語の総索引があり、索引の嚆矢を為す。
http://www.hanawashobo.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-8273-0110-6
>『萬葉集索引』(古典索引刊行会編、2003年)がなされ、今回の電子総索引となったのである。
1929年の『萬葉集総索引』が『万葉集』研究の飛躍をもたらしたことは知られるとおりである。『萬葉集大成』に組み込まれ、単行本としても刊行されて、広く利用されてきたが、本文および注釈研究の進展をとりいれた、あたらしい総索引がもとめられてもきた。2003年の『萬葉集索引』はこれにこたえたものであった。そして、状況は電子化を必須のものとしている。現在web上には、『万葉集』テキストもあり、検索システムも提供されている。こうした状況のなかだからこそ、いま、もっとも信頼できるテキストによる、CD版、電子総索引がなされることの意義はきわめておおきい。ことは、なによりテキストの信頼性にかかるのである。
>索引編[編集]
一般語彙編、助詞・助動詞編、項目一覧からなる。索引編は、校異編の完成以後の作業の中心となったものであり、このような作業にコンピュータを利用することなど考えられなかった時代に、この索引編を作成するために、一般語彙については約50万枚、助詞・助動詞については約60万枚の紙によるカードを作成したとされている[42]。
なお、この索引編を作る作業自体は早くから始められていたらしく、校異源氏物語と同じ中央公論社から出版されていた谷崎潤一郎の旧訳源氏物語の付録(月報第11号及び13号)には、「池田亀鑑の『校異源氏物語』は昭和15年の時点では索引が計画されていた」旨が記されており[43]、1943年(昭和18年)に東京帝国大学で池田亀鑑から源氏物語の講義を受けた今井源衛は、「講義の中で当時すでに一部完成していたらしい索引を元にして源氏物語語意論を語っていた」と述べている。
限定版
1953年(昭和28年)6月から1956年(昭和31年)12月にかけて発売された。
源氏物語大成 巻4 索引篇 1953年(昭和28年)8月発売 ISBN 4-12400-444-3
一般語彙索引
源氏物語大成 巻5 索引篇 1956年(昭和31年)4月発売 ISBN 4-12400-445-1
助詞・助動詞索引
普及版
源氏物語大成 第七冊 索引編 1985年(昭和60年)4月発売 ISBN 4-1240-2477-0
一般語彙索引上(あ~し)
源氏物語大成 第八冊 索引編 1985年(昭和60年)5月発売 ISBN 4-1240-2478-9
一般語彙索引下(す~を)
源氏物語大成 第九冊 索引編 1985年(昭和60年)6月発売 ISBN 4-1240-2479-7
助詞・助動詞索引上
源氏物語大成 第十冊 索引編 1985年(昭和60年)7月発売 ISBN 4-1240-2480-0
助詞・助動詞索引下
http://www.ism.ac.jp/~murakami/senden.htm
「源氏物語」語彙用例総索引の部屋
www.ism.ac.jp/~murakami/senden.htm
この索引は源氏物語の語彙を計量分析するために作成した品詞コード付本文データベースを用いて、前後10語程度の文脈付索引(KWIC)として出力したもです。 本文は『源氏物語大成』(中央公論社 刊)を用い、『日本古典文学大系』 (岩波書店 刊)と『日本古典 ...
索引 とは - コトバンク
kotobank.jp/word/索引
世界大百科事典 第2版 索引の用語解説 - 書籍,雑誌,辞典などの著作物における主要な内容,事柄を単一な検索法によって簡便に引き出せるように,一定の方式にしたがい編集したもの。ただし中国語では,内容別に分類した目録を索引と呼び,indexの訳語 ...
索引とは - はてなキーワード - はてなダイアリー
d.hatena.ne.jp/keyword/索引
「索引」とは - indexの日本語訳。テキストの見たい部分にいきつけるように、用語や人名など主要な項目を抜き出してそれぞれ参照すべきページを示したリスト。検索の便宜のために五十音順などで並べてある。
索引 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/索引
索引(さくいん)とは、百科事典・学術書などの書籍やコンピュータのデータにおいて、特定の項目を素早く参照できるよう、項目を特定の順番に並べ、その項目が出現する物理的な位置をまとめたもの。コンピュータで用いられる際にはインデックス (index (pl.
Wikipedia:索引 とは - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:索引_とは
Wikipedia:索引 とはは読み仮名が「とは」で始まる記事の一覧である。 .... 次ページ ⇒Wikipedia:索引 と#とひ. 「http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:索引_とは&oldid=48781445」から取得. カテゴリ: 索引 ...
索引とは - 短編小説作品名 Weblio辞書
www.weblio.jp › 品詞の分類 › 体言 › 名詞 › 名詞(道具)
索引とは?短編小説作品名。 (名)ある書物に載っている項目・人名・用語などを書き出して五十音順などに並べ、その所在ページなどを示した表。インデックス。 (名)スル(綱で)引っ張ること。 「車両を―する」 「索引」に似た言葉&ra...
岩波書店
別巻 萬葉集索引
佐竹 昭広,山田 英雄,工藤 力男,
大谷 雅夫,山崎 福之 編
■体裁=A5判・上製・函入・558頁
■定価 5,040円(本体 4,800円 + 税5%)
■2004年3月26日
■ISBN4-00-240105-7 C0391
現存最古の歌集として,素朴直截な表現で人びとの心をとらえつづけてきた『萬葉集』.大胆な構想力と緻密な考証と漢語表現の視点を取り入れて万葉注釈史に新生面を開いた新日本古典文学大系版『萬葉集』全4冊の理解と鑑賞のための索引.全句索引,人名索引,地名索引,枕詞索引,作品関係年表の5種を収録.
Amazon.co.jp: 萬葉集索引 (新日本古典文学大系): 佐竹 昭広, 工藤 力 ...
www.amazon.co.jp › 本 › 文学・評論 › 全集・選書 › 日本文学
Amazon.co.jp: 萬葉集索引 (新日本古典文学大系): 佐竹 昭広, 工藤 力男, 大谷 雅夫, 山田 英雄, 山崎 福之: 本.
萬葉集索引 - 岩波書店
www.iwanami.co.jp/.BOOKS/24/7/2401050.html
現存最古の歌集として,素朴直截な表現で人びとの心をとらえつづけてきた『萬葉集』.大胆な構想力と緻密な考証と漢語表現の視点を取り入れて万葉注釈史に新生面を開いた新日本古典文学大系版『萬葉集』全4冊の理解と鑑賞のための索引.全句索引,人名 ...
万葉集電子総索引 CD-ROM版 - BookSS
www.hanawashobo.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-8273-0110...
塙書房から、このたび『萬葉集電子総索引』(古典索引刊行会編)が刊行される。さきに木下正俊『萬葉集CD-ROM版』(2001年)を刊行したのに続く電子版である。塙書房の『萬葉集 本文篇』(佐竹昭広・木下正俊・小島憲之。補訂版1998年、初版1983年)は、 ...
『万葉集』の歌を調べたい。 | レファレンス協同データベース
crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000055103
万葉集索引 / 佐竹昭広 [ほか] 編 岩波書店 , 2004 (新日本古典文学大系 / 佐竹昭広 [ほか] 編 ; 別巻) ISBN:4002401057. 萬葉集索引 / 古典索引刊行会編 塙書房 , 2003 ISBN:4827300925. 新編国歌大観 第2巻;私撰集編 / 「新編国歌大観」編集委員会編 ...
語彙として扱われる語の研究には用例から初出を探索することになる。
初出は文献による記録されたものから証拠を求める。
出典また典拠として文献学の説明によって明らかにされる。
国語学が文献学であったゆえんである。
文献学であったとするのは、徳川時代からの国語の自覚においてその伝統的な手法が打ち立てられて、明治時代にPhylologyが西欧の学問分野の一つとして移入されて国語学が継承してきた文献による言語研究が行われたからであるが、その国語の分野に日本語としての立場の研究が現れるようになり、いまは、日本語学が広く分野を形成しつつある。
語彙史は資料によって、史料とするので、それは国語語彙史であった。19世紀の歴史言語学の影響によって語の発生と消長が議論されることに加えて、その語の意味の変遷が歴史時代と文献資料によって証明されてきた。
またその語の意味記述に用例による説明が、帰納法、つまり方法論として確立してきている。
古典対照語彙表が増補改訂されるようだ。語彙調査は文学の古典作品にも索引が研究対象に大きく進められた。古典対照語彙表が作られた。それまでの文学作品はざまざまに出版されていたが、文学全集の編集のもとにテキストが選定されて国語資料の底本が研究成果として定められてきた。いわば定本の選定が進んだのである。いくつかの文学作品の索引作成は総索引というふうに自立語、付属語を対象にした全数調査であった。その結果、自立語における作品の語彙量がわかった。
日本語語彙論 語彙調査2
2013-10-16 13:07:05 | 現代日本語百科
語彙調査は文学の古典作品にも索引が研究対象に大きく進められた。古典対照語彙表が作られた。それまでの文学作品はざまざまに出版されていたが、文学全集の編集のもとにテキストが選定されて国語資料の底本が研究成果として定められてきた。いわば定本の選定が進んだのである。いくつかの文学作品の索引作成は総索引というふうに自立語、付属語を対象にした全数調査であった。その結果、自立語における作品の語彙量がわかった。
笠間書院/古典対照語い表 媒体:FD #FD
作成:宮島達夫氏・中野洋氏・鈴木泰氏・石井久雄氏
登録:『フロッピー版 古典対照語い表および使用法』(1989.9、笠間書院刊)
底本:宮島達夫編『古典対照語い表』(笠間書院刊)
FILE:CSV形式、PC98用検索プログラム(C言語ソース付属)、BASICプログラム
価格:\6,500+税
内容:万葉集、竹取物語、伊勢物語、古今和歌集、土佐日記、後撰和歌集、蜻蛉日記、枕草子、源氏物語、紫式部日記、更級日記、大鏡、方丈記、徒然草の14作品の自立語を統計データとしたもの。
備考:書籍版の宮島達夫編『古典対照語い表』(笠間書院刊)もあります。
古典分類語彙表(稿) - 学習院
glim-re.glim.gakushuin.ac.jp/bitstream/.../keisankisenta_33_40_121.pdf
の一つとして,古典語を対象としたものとしては日本で最初の本格的なものとなる、古典語彙のシ. ソーラス(体系 ... 宮島達夫『古典対照語い表』(1971 年 笠間書院刊)が. 取り上げた 14 ... 宮 島達夫・鈴木泰・石井久雄・安部清哉編『日本古典対照分類語彙表』.
古典索引刊行会『万葉集索引』(2003 年 塙書房刊)
山田忠雄『竹取物語総索引』(1958 年 武蔵野書院刊)
伴 久美「伊勢物語に就きての研究 索引篇」(大津有一編『伊勢物語に就きての研究』
所収,1961 年 有精堂出版刊)
西下経一・滝沢貞夫『古今集総索引』(1958 年 明治書院刊)
日本大学文理学部国文学研究室『土左日記総索引』(1967 年 桜楓社刊)
大阪女子大学国文学研究室『後撰和歌集総索引』(1965 年 大阪女子大学刊)
佐伯梅友・伊牟田経久『かげろふ日記総索引』(1963 年 風間書房刊)
榊原邦彦・武山隆昭・塚原清・藤掛和美『枕草子総索引』(1967 年 右文書院刊)
池田亀鑑『源氏物語大成 索引篇』(1953 年 中央公論社刊)
東京教育大学中古文学研究部会『紫式部日記用語索引』(1956 年 日本学術振興会刊)
東 節夫・塚原鉄雄・前田欣吾『更級日記総索引』(1956 年 武蔵野書院刊)
秋葉安太郎「校本大鏡総索引」(『大鏡の研究 上巻 本文篇』所収,1960 年 桜楓社刊)
滝沢貞夫『新古今集総索引』(1970 年 明治書院刊) *
青木伶子『方丈記総索引』(1965 年 武蔵野書院刊)
増田繁夫・長野照子『宇治拾遺物語総索引』(1975 年 清文堂出版刊) *
近藤政美・武山隆昭・近藤三佐子『平家物語語彙用例総索引』(1996 年 勉誠社刊) *
時枝誠記『徒然草総索引』(1955 年 至文堂刊)
古典語彙を,意味による分類番号の順序で配列する。
意味による分類番号は,次による。
国立国語研究所編『国立国語研究所資料集14 分類語彙表 増補改訂版』
(2004 年,大日本図書刊)
分類は大きく次である。
1 体の類 名詞
2 用の類 動詞
3 相の類 形容詞・副詞
4 その他の類 接続詞・感動詞など
この番号のあとにピリオドを置いて,さらに4桁の番号で細分する。分類項目および番号の体系
については,本稿では説明を省略する。
ただし,本稿では,分類項目のすべてを載せる。古典語彙に該当するものがない項目では例えば
「1.1401(弾力・動力・圧力など)……該当なし」のように,「……該当なし」と記す。『分類語彙表』
の番号は必ずしも連続していないので,本稿での欠番は『分類語彙表』でもともと欠けている。なお,
古典語彙のために項目「3.9999(枕詞)」を新設し,また「意味不明」の項目も設ける。
古典17 作品における語の五十音順総覧は,近刊の予定である。
宮 島達夫・鈴木泰・石井久雄・安部清哉編『日本古典対照分類語彙表』
(2013 年春予定,笠間書院)
『古典対照語い表』の増補改訂版として,一語ごとに,語種・品詞・作品ごと出現頻度を示し,
さらに意味分類番号を添える。総語数34,366 である。
日本古典 対照分類語彙表 NEW
宮島達夫 他
税込価格:9,450円
発行年月:2013.12
「古典対照語い表」の改訂増補版が
1971年刊の「古典対照語い表」(笠間書院)が、来春、改訂増補版「日本古典対照分類語彙表」として刊行予定とのことです。
文学作品を追加し、エクセルデータ収録CDが付いてくるというので、基礎データとして使いやすそう。出版が楽しみです。
語彙研究の講座を見よう。語彙史研究を画期にまとめたのは、講座日本語の語彙である。1981年から1983年にかけて全11巻、別巻1からなる。語彙史に絞ってみれば、古代の語彙、中世の語彙、近世の語彙、現代の語彙と時代に編纂している。また、講座日本語の語彙9 語誌1、講座日本語の語彙10 語誌2 講座日本語の語彙11 語誌3 まとめられた文献は便利である。語史は語誌であるとするようなことであるが、ここの文献にはそれまでの語の研究情況を網羅しようとしている。講座日本語の語彙はその編集において論客を配して実践研究に示唆を与える。その巻の目次を紹介するにとどまるが、壮観である。