例によって「既に終わった展覧会だが」で始まる感想である。
目黒区美術館で「前田利為 春雨に真珠をみた人」展を見に行った。
3/21までで3/20に行ったのだからこれはもうどうしようもない。
名前からわかるように「前田利為」という人は加賀の前田の殿様の裔である。
本人は幼少の頃に分家から本家に養子として迎えられ、長じて陸軍に入った人である。


加賀百万石の前田家は文化への深い理解と愛情があった。
政治的な意図もあったろうが、泰平の時代にそれはいよよ深度を増したようで、たとえば町民も宝生流を嗜み「謡が天から降ってくる」といわれもした。
そのご本家の養子となった利為氏は文化的な前田家の中興の祖ともいえる前田綱紀を尊敬し、自身も二人目の綱紀公にならんとしたようだ。
実際明治末には下村観山に公の肖像画を描かせもした。
利為氏自身展覧会にも足しげく通い、外国でも好みに合う作家に作品を発注もする。
折々の記念には画家たちに画題を与え、作品を作らせる。
気に入らなければ自分の意図を明確にし、文句も付ける。
また、多くの美術品を購入するだけでなくそれを死蔵しようとはしなかった。
かれは「前田育徳会」を創設し、「公益に広く人々に見せよう」と考えたようだ。
これについては今回の展覧会のために作成された第18代当主・前田利祐氏のインタビュー動画にその言葉がある。
熊本の細川家もそうだが、由緒ある家柄で経済的にもゆとりのある御家はそうした働きをする。特に欧州の貴族にはその考えがきちんと身についている。
青池保子さんの「エロイカより愛をこめて」でもイギリスの伯爵は作中でこう述べている。
「芸術家を保護するのは貴族の義務です」
その言葉通り、利為氏も多くの芸術家を支援した。
今回その一端をこの美術館で見ることが叶い、とても嬉しい。
ジャン=バティスト=アルマン・ギョーマン 湖水1894

一目見て日本人の好みそうな風景画だと思った。わたしはこの画家を知らないが、色彩感覚は児島善三郎に似ていると感じた。いい感じの秋の風景である。
この画家は印象派の一人で50歳になった1891年に宝くじに当たり、以後は画家一本で生きたそうだ。
後で調べると一度だけこの画家の絵を見て感想を挙げている。
エルミタージュ美術館所蔵の『セーヌ川』である。
「艀というのか、ガタロ船と言うのか。映画『アタラント号』を思い出した。ジャン・ヴィゴの映画はこの絵から70年後の風景だった」と記している。
大エルミタージュ展の感想
ラファエル・コラン 庭の隅 1895 三人の美人が庭の芝生の上でくつろいでいる。
布の質感が伝わってくる。春らしい薄物の…コランは良いなあ。三美人がくつろいでいるこの情景がとても優雅なのだよ。
素敵だ。「美」であることの尊さを思う。

ジャン=レオン=ジェローム アラビア人に馬 この絵はたいへん気に入って購入されたそう。倒れた馬に優しく寄り添うアラビア男性。利為氏が軍人だということも関係あるかもしれない。よく走ってくれる馬への愛情と哀惜と。
画家はオリエンタリズムな作品に良いのが多いヒトだが、ヨーロッパだけでなくこうして東アジアにもそのファンはいるのだった。
川の絵が二点ばかり並ぶがどちらも静かでいい。家の中に飾るのにふさわしいし。
額縁も花をモチーフにしてなかかな綺麗。
ピーテル=フランシス=ピーテルス 月光 ドイツロマン派風なオランダ人画家の絵。夜の海。二隻の船の間に月光。
この額縁はアールヌーヴォー風な花と茎の装飾が施されていた。
下村観山 楠公奉勅下山之図 1910 これは注文発注した絵だが人物より笠置の山の中にいる人々を上からのぞく、という構図が気に入らなかったそうだ。
絵としてはいい絵だが、理由を知って納得。
この絵は利為氏の子供の二歳の誕生記念にたのんだ作品なので、これはやはりミスだと思う。応需ならばやっぱり楠公と家来たちをばばーんと描く方が利為氏も喜んだろうし、子供もかっこいいなと思ったかもしれない。
巻物がある。
牛田雞村 鎌倉の一日 1917 本画と小下絵と。どちらも人のいない百年前の鎌倉風景である。そこに一日の時間の推移も織り込まれる。
横山大観「生々流転」のように時間がゆく。
…あっ「生々流転」より先に作られた絵だな、これ。あれは1923年。関東大震災の日にお披露目…
ところで今だと「生々流転」は水の呼吸の型としての方がよく知られてるよね。義勇さん。
吉田登穀 孔雀図屏風 1918 二曲一隻でカプぽい孔雀がいい位置に落ち着いている図。
円山派や狩野派の御大層な孔雀ではなく、むしろアールヌーヴォー風な風情もある孔雀。
エドモン・アマン=ジャン 婦女弾琴図 1922 この画家を知ったのは大原美術館からだから、やはりその時代のパリでいい感じの婦人図だと日本のバイヤーなり画家なりは思ったのだろうね。わたしも実際にかれの描くややぽっちゃり美人さんたち、好き。
チェロとバイオリンと。しかも実際には演奏しているわけでもないのがいい。
ある種のけだるさ、これが魅力。
グザヴィエ・ブリカール 少女海水浴図 1924以前 なかなかの美少女が海水浴用のふんわり帽子をかぶっている。背景はエメラルド色の海。ヒスイ色をもっと明るくしたあの色。
この色を見ると海老原喜之助のやはり海と縁のある女の絵を思い出す。洲之内コレクションの魚入りのざるを乗せた女の絵ね。
動物彫刻三体をみる。
フランソワ・ポンポンの白熊、バンがいる。どちらも1930年で受注発注。
ポンポンと言えば白熊。可愛いなあ。バンは鳥の鷭ね。鏡花の小説「鷭狩」のあの鷭。シンプルな造形で大きめの足。キョトンとして可愛い。
ジャンヌ・ピファール ヒョウ 黒豹。ロデムのような精悍さはない。
ルノワール アネモネ 横長画面に明るくアネモネが咲きこぼれる。

この絵の購入のエピソードが面白い。
利為氏のために現地で画家や画商とじかに交渉する役目を負った岡見富雄という画家の献身がいい。
かれは大原美術館の児島虎次郎のような役目を担っていたのだな。
その岡見富雄の油彩画もある。
利為氏は彼を使者として働かせるだけでなく、画家の本文も支援した。
前田家の遺族の為に画家も作品を拵え続けたそう。
ここから日本画
栖鳳 南支風色 1926 中国のとある町の情景を切り取る。あの個性的な形の橋を子豚ちゃんたちが走る。酒飲むのもいれば働く人もいて、和やかな日常の1シーン。
これはやはりいいなあ。

前田家という名家を養子として継いだ利為氏は生まれながらの跡取りの人たち以上に「前田家」の価値について深く考えていたと思う。
近代住友家の中興の祖たる春翠・住友友純は徳大寺家から養子に入るや熱心に実業と文化の庇護者として活躍した。
どちらも本当に立派な方々である。
さて前田家は武家の家柄であるため様々な武勲やそうした逸話を伝える家系であった。
先祖の勲しを絵に、と考えるのは洋の東西を問わず考えるもので、欧州では特にお抱えの画家たちに肖像画と共に先祖の功績を描かせてきた。
利為氏も無論その例に漏れない。
これらは前田家のご先祖の事件を描いたもの。
川邊御楯 末森赴援画巻 1903
邨田丹陵 高徳公赴末森城之救援図 1927
邨田は歴史画の上手。金毘羅さんの富士の間に富士山を描いたり、二条城での大政奉還図を描いてもいる。
そして外国人のお客さんが来たとき、利為氏は木下杢太郎にその事績の通訳を頼んだが、彼は興味がなくて簡素な説明しかしていない。その顛末を自作「宝物拝観」に加工して発表している。
堂本印象 春遊図 1927 長女の生誕祝の為の絵。さすがに印象は心得ていて、春の野を遊ぶ貴婦人とおかっぱの幼女とを絵巻の人物のような描線と淡彩で表現している。
利為氏は同時代の先鋭的な作品は嫌いで、やはり美しいもの・愛らしいものを愛する人であった。
それだけにこうした祝絵はその方向性に向いたものでなくてはならない、とわたしも思う。
永井幾麻 葛葉物語 1940 「恋しくば訪ね来てみよ 信太なる和泉の森の うらみ葛の葉」のあの信太妻の話である。
哀しい物語は多くの人が描きもし、語りも継いだ。
ここでは葛の葉狐が正体を現し、千年の森たる信太の森へ帰って来たところのよう。多くの狐たちがいる。
図録には別なシーンが出ていて、この狐たちはいない。一期一会になるかもしれないが、この絵を見ることが出来て良かった。
他にも西村五雲の春の海、山元春挙の富士裾野などがあるが、総じて温厚な作品が揃っている。
面白いものがあった。
下村観山 臨幸絵巻 1931 これは本郷の洋館に行幸・臨幸の様子を描いたもので四巻ある。

麟、鳳、亀、龍と分かれているが、それぞれの様子がよく描けていて、とても面白い。
・お客様を迎え入れるために立ち働く男性たち。階段の綺麗な形がいい。ロビーで何をどう飾り付けるか会話まできこえてきそう。
・やがて来場される貴顕。
・お能を観る人々。加賀の前田家だからたぶん宝生流。
・伝世のお宝を眺める人々
ところで今回この辺りのことをもっと知りたいと調べたところ、こちらのサイトにかなり興味深い記事があった。
東京大学コレクションX その中の「加賀殿再訪」と言うタイトルで本郷の邸宅設計から行幸あたりまでの詳しい資料と、当時の本郷の前田家の航空写真などがある。
そこに記された行幸でのおもてなしについてサイトから引用する。
「明治四三年七月八日、明治天皇は午前十一時十二分から午後五時五七分まで前田侯爵家本郷邸に滞在した。
邸の中で天皇が目にしたものは、この日のために利為が描かせた日本画(川端玉章「花鳥の図」、荒木寛畝「松林山水の図」、竹内栖鳳「瀑布の図」、山元春挙「保津川の図」)、能楽と狂言(桜間伴馬「俊寛」、野口政吉「熊坂」、梅若六郎「土蜘」、山本東次郎「二九十八」、野村万造「鞠座頭」)、前田家伝来の宝物(西洋館二階の各室および和館奥小座敷に文書や太刀などが陳列され帝室博物館総長股野琢が説明役を務めた)、薩摩琵琶の演奏(西幸吉による「小楠公」「金剛石」)などであった。
和館の一室には、画家の荒木寛畝、竹内栖鳳、福井江亭が詰めており、天皇が画題を与え、それに応じてそれぞれが「竹鶏図」、「月兎図」、「犬図」を描くという席画の趣向もあった。そして、仕上がったそれらを天皇は気に入り、先の寛畝、栖鳳の作品と合わせて持ち帰った。」
なるほどなあ。これは元は展示図録だったようだが、もう今はなさそうである。それでweb公開されているのかもしれない。
東京大学総合研究博物館、ありがとうございます。
東京帝国大学との話し合いにより本郷の地を東大に売却し、駒場に移動し、生活上の変化を前田家に齎したのは利為氏であったが、これにより経済的な変化も取り入れることが出来たそうで、やはりこれは前田家がよい養子を後継者にしたからこそであり、利為氏の英断だと思えた。
現代では愛すべき文学館となった駒場の大邸宅の図が並んでいた。作者は久保田金僊。米僊の息子である。

かれは京都から東京へ出て日清日露に従軍してその様子を描きもした。日露の図は兵庫歴博にあるようだ。
そして1940前後で利為氏に随行していくつかの絵巻を拵えている。
加越紀行絵巻、能登紀行絵巻、鎌倉別邸風景なども描いている。
わたしはかれの描いたものではこれまでに「細見良氏画伝」を細見美術館で見ている。
そして建築好きな者にとってはこの金僊の駒場御本邸画帖はとても見ごたえのあるものだった。
また設計図面が展示されているのもたいへんよかった。
青焼きのものでタイポが可愛い。
利為氏は最初の夫人と後妻となった夫人と自分とをそれぞれ外国人画家によって肖像画を作らせている。
興味深いことに自分はフェルディナン・ウンベールという画家に、最初の渼子夫人、後妻・菊子夫人はマルセル・バッシェの手に任せている。
やがて利為氏はボルネオでの行軍図を最期に戦死する。2602年つまり1942年のことである。
清水登之が丸眼鏡姿の利為氏の肖像を残している。
展示は絵画ばかりではなく実際に使用されたガラス製品などもあった。
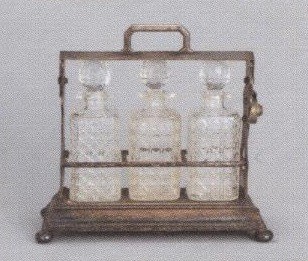
カッティングの綺麗なグラスや瓶が多く、センスの良さを感じさせる。
ワイングラスで面白いのが赤ワイン用のが透明、白ワイン用のが赤グラス。どちらも赤く見えるように設えられている。
それから蓋付カラフェがエリザベスカラーをつけ、胸元にカッティング刺繍の入ったドレスを着た貴婦人の人形のようにみえた。
たいへん興味深く、好ましい展覧会だった。
しかも図録は1200円と言うありがたさ。
良いものを見せて貰えて本当に良かった。
目黒区美術館で「前田利為 春雨に真珠をみた人」展を見に行った。
3/21までで3/20に行ったのだからこれはもうどうしようもない。
名前からわかるように「前田利為」という人は加賀の前田の殿様の裔である。
本人は幼少の頃に分家から本家に養子として迎えられ、長じて陸軍に入った人である。


加賀百万石の前田家は文化への深い理解と愛情があった。
政治的な意図もあったろうが、泰平の時代にそれはいよよ深度を増したようで、たとえば町民も宝生流を嗜み「謡が天から降ってくる」といわれもした。
そのご本家の養子となった利為氏は文化的な前田家の中興の祖ともいえる前田綱紀を尊敬し、自身も二人目の綱紀公にならんとしたようだ。
実際明治末には下村観山に公の肖像画を描かせもした。
利為氏自身展覧会にも足しげく通い、外国でも好みに合う作家に作品を発注もする。
折々の記念には画家たちに画題を与え、作品を作らせる。
気に入らなければ自分の意図を明確にし、文句も付ける。
また、多くの美術品を購入するだけでなくそれを死蔵しようとはしなかった。
かれは「前田育徳会」を創設し、「公益に広く人々に見せよう」と考えたようだ。
これについては今回の展覧会のために作成された第18代当主・前田利祐氏のインタビュー動画にその言葉がある。
熊本の細川家もそうだが、由緒ある家柄で経済的にもゆとりのある御家はそうした働きをする。特に欧州の貴族にはその考えがきちんと身についている。
青池保子さんの「エロイカより愛をこめて」でもイギリスの伯爵は作中でこう述べている。
「芸術家を保護するのは貴族の義務です」
その言葉通り、利為氏も多くの芸術家を支援した。
今回その一端をこの美術館で見ることが叶い、とても嬉しい。
ジャン=バティスト=アルマン・ギョーマン 湖水1894

一目見て日本人の好みそうな風景画だと思った。わたしはこの画家を知らないが、色彩感覚は児島善三郎に似ていると感じた。いい感じの秋の風景である。
この画家は印象派の一人で50歳になった1891年に宝くじに当たり、以後は画家一本で生きたそうだ。
後で調べると一度だけこの画家の絵を見て感想を挙げている。
エルミタージュ美術館所蔵の『セーヌ川』である。
「艀というのか、ガタロ船と言うのか。映画『アタラント号』を思い出した。ジャン・ヴィゴの映画はこの絵から70年後の風景だった」と記している。
大エルミタージュ展の感想
ラファエル・コラン 庭の隅 1895 三人の美人が庭の芝生の上でくつろいでいる。
布の質感が伝わってくる。春らしい薄物の…コランは良いなあ。三美人がくつろいでいるこの情景がとても優雅なのだよ。
素敵だ。「美」であることの尊さを思う。

ジャン=レオン=ジェローム アラビア人に馬 この絵はたいへん気に入って購入されたそう。倒れた馬に優しく寄り添うアラビア男性。利為氏が軍人だということも関係あるかもしれない。よく走ってくれる馬への愛情と哀惜と。
画家はオリエンタリズムな作品に良いのが多いヒトだが、ヨーロッパだけでなくこうして東アジアにもそのファンはいるのだった。
川の絵が二点ばかり並ぶがどちらも静かでいい。家の中に飾るのにふさわしいし。
額縁も花をモチーフにしてなかかな綺麗。
ピーテル=フランシス=ピーテルス 月光 ドイツロマン派風なオランダ人画家の絵。夜の海。二隻の船の間に月光。
この額縁はアールヌーヴォー風な花と茎の装飾が施されていた。
下村観山 楠公奉勅下山之図 1910 これは注文発注した絵だが人物より笠置の山の中にいる人々を上からのぞく、という構図が気に入らなかったそうだ。
絵としてはいい絵だが、理由を知って納得。
この絵は利為氏の子供の二歳の誕生記念にたのんだ作品なので、これはやはりミスだと思う。応需ならばやっぱり楠公と家来たちをばばーんと描く方が利為氏も喜んだろうし、子供もかっこいいなと思ったかもしれない。
巻物がある。
牛田雞村 鎌倉の一日 1917 本画と小下絵と。どちらも人のいない百年前の鎌倉風景である。そこに一日の時間の推移も織り込まれる。
横山大観「生々流転」のように時間がゆく。
…あっ「生々流転」より先に作られた絵だな、これ。あれは1923年。関東大震災の日にお披露目…
ところで今だと「生々流転」は水の呼吸の型としての方がよく知られてるよね。義勇さん。
吉田登穀 孔雀図屏風 1918 二曲一隻でカプぽい孔雀がいい位置に落ち着いている図。
円山派や狩野派の御大層な孔雀ではなく、むしろアールヌーヴォー風な風情もある孔雀。
エドモン・アマン=ジャン 婦女弾琴図 1922 この画家を知ったのは大原美術館からだから、やはりその時代のパリでいい感じの婦人図だと日本のバイヤーなり画家なりは思ったのだろうね。わたしも実際にかれの描くややぽっちゃり美人さんたち、好き。
チェロとバイオリンと。しかも実際には演奏しているわけでもないのがいい。
ある種のけだるさ、これが魅力。
グザヴィエ・ブリカール 少女海水浴図 1924以前 なかなかの美少女が海水浴用のふんわり帽子をかぶっている。背景はエメラルド色の海。ヒスイ色をもっと明るくしたあの色。
この色を見ると海老原喜之助のやはり海と縁のある女の絵を思い出す。洲之内コレクションの魚入りのざるを乗せた女の絵ね。
動物彫刻三体をみる。
フランソワ・ポンポンの白熊、バンがいる。どちらも1930年で受注発注。
ポンポンと言えば白熊。可愛いなあ。バンは鳥の鷭ね。鏡花の小説「鷭狩」のあの鷭。シンプルな造形で大きめの足。キョトンとして可愛い。
ジャンヌ・ピファール ヒョウ 黒豹。ロデムのような精悍さはない。
ルノワール アネモネ 横長画面に明るくアネモネが咲きこぼれる。

この絵の購入のエピソードが面白い。
利為氏のために現地で画家や画商とじかに交渉する役目を負った岡見富雄という画家の献身がいい。
かれは大原美術館の児島虎次郎のような役目を担っていたのだな。
その岡見富雄の油彩画もある。
利為氏は彼を使者として働かせるだけでなく、画家の本文も支援した。
前田家の遺族の為に画家も作品を拵え続けたそう。
ここから日本画
栖鳳 南支風色 1926 中国のとある町の情景を切り取る。あの個性的な形の橋を子豚ちゃんたちが走る。酒飲むのもいれば働く人もいて、和やかな日常の1シーン。
これはやはりいいなあ。

前田家という名家を養子として継いだ利為氏は生まれながらの跡取りの人たち以上に「前田家」の価値について深く考えていたと思う。
近代住友家の中興の祖たる春翠・住友友純は徳大寺家から養子に入るや熱心に実業と文化の庇護者として活躍した。
どちらも本当に立派な方々である。
さて前田家は武家の家柄であるため様々な武勲やそうした逸話を伝える家系であった。
先祖の勲しを絵に、と考えるのは洋の東西を問わず考えるもので、欧州では特にお抱えの画家たちに肖像画と共に先祖の功績を描かせてきた。
利為氏も無論その例に漏れない。
これらは前田家のご先祖の事件を描いたもの。
川邊御楯 末森赴援画巻 1903
邨田丹陵 高徳公赴末森城之救援図 1927
邨田は歴史画の上手。金毘羅さんの富士の間に富士山を描いたり、二条城での大政奉還図を描いてもいる。
そして外国人のお客さんが来たとき、利為氏は木下杢太郎にその事績の通訳を頼んだが、彼は興味がなくて簡素な説明しかしていない。その顛末を自作「宝物拝観」に加工して発表している。
堂本印象 春遊図 1927 長女の生誕祝の為の絵。さすがに印象は心得ていて、春の野を遊ぶ貴婦人とおかっぱの幼女とを絵巻の人物のような描線と淡彩で表現している。
利為氏は同時代の先鋭的な作品は嫌いで、やはり美しいもの・愛らしいものを愛する人であった。
それだけにこうした祝絵はその方向性に向いたものでなくてはならない、とわたしも思う。
永井幾麻 葛葉物語 1940 「恋しくば訪ね来てみよ 信太なる和泉の森の うらみ葛の葉」のあの信太妻の話である。
哀しい物語は多くの人が描きもし、語りも継いだ。
ここでは葛の葉狐が正体を現し、千年の森たる信太の森へ帰って来たところのよう。多くの狐たちがいる。
図録には別なシーンが出ていて、この狐たちはいない。一期一会になるかもしれないが、この絵を見ることが出来て良かった。
他にも西村五雲の春の海、山元春挙の富士裾野などがあるが、総じて温厚な作品が揃っている。
面白いものがあった。
下村観山 臨幸絵巻 1931 これは本郷の洋館に行幸・臨幸の様子を描いたもので四巻ある。

麟、鳳、亀、龍と分かれているが、それぞれの様子がよく描けていて、とても面白い。
・お客様を迎え入れるために立ち働く男性たち。階段の綺麗な形がいい。ロビーで何をどう飾り付けるか会話まできこえてきそう。
・やがて来場される貴顕。
・お能を観る人々。加賀の前田家だからたぶん宝生流。
・伝世のお宝を眺める人々
ところで今回この辺りのことをもっと知りたいと調べたところ、こちらのサイトにかなり興味深い記事があった。
東京大学コレクションX その中の「加賀殿再訪」と言うタイトルで本郷の邸宅設計から行幸あたりまでの詳しい資料と、当時の本郷の前田家の航空写真などがある。
そこに記された行幸でのおもてなしについてサイトから引用する。
「明治四三年七月八日、明治天皇は午前十一時十二分から午後五時五七分まで前田侯爵家本郷邸に滞在した。
邸の中で天皇が目にしたものは、この日のために利為が描かせた日本画(川端玉章「花鳥の図」、荒木寛畝「松林山水の図」、竹内栖鳳「瀑布の図」、山元春挙「保津川の図」)、能楽と狂言(桜間伴馬「俊寛」、野口政吉「熊坂」、梅若六郎「土蜘」、山本東次郎「二九十八」、野村万造「鞠座頭」)、前田家伝来の宝物(西洋館二階の各室および和館奥小座敷に文書や太刀などが陳列され帝室博物館総長股野琢が説明役を務めた)、薩摩琵琶の演奏(西幸吉による「小楠公」「金剛石」)などであった。
和館の一室には、画家の荒木寛畝、竹内栖鳳、福井江亭が詰めており、天皇が画題を与え、それに応じてそれぞれが「竹鶏図」、「月兎図」、「犬図」を描くという席画の趣向もあった。そして、仕上がったそれらを天皇は気に入り、先の寛畝、栖鳳の作品と合わせて持ち帰った。」
なるほどなあ。これは元は展示図録だったようだが、もう今はなさそうである。それでweb公開されているのかもしれない。
東京大学総合研究博物館、ありがとうございます。
東京帝国大学との話し合いにより本郷の地を東大に売却し、駒場に移動し、生活上の変化を前田家に齎したのは利為氏であったが、これにより経済的な変化も取り入れることが出来たそうで、やはりこれは前田家がよい養子を後継者にしたからこそであり、利為氏の英断だと思えた。
現代では愛すべき文学館となった駒場の大邸宅の図が並んでいた。作者は久保田金僊。米僊の息子である。

かれは京都から東京へ出て日清日露に従軍してその様子を描きもした。日露の図は兵庫歴博にあるようだ。
そして1940前後で利為氏に随行していくつかの絵巻を拵えている。
加越紀行絵巻、能登紀行絵巻、鎌倉別邸風景なども描いている。
わたしはかれの描いたものではこれまでに「細見良氏画伝」を細見美術館で見ている。
そして建築好きな者にとってはこの金僊の駒場御本邸画帖はとても見ごたえのあるものだった。
また設計図面が展示されているのもたいへんよかった。
青焼きのものでタイポが可愛い。
利為氏は最初の夫人と後妻となった夫人と自分とをそれぞれ外国人画家によって肖像画を作らせている。
興味深いことに自分はフェルディナン・ウンベールという画家に、最初の渼子夫人、後妻・菊子夫人はマルセル・バッシェの手に任せている。
やがて利為氏はボルネオでの行軍図を最期に戦死する。2602年つまり1942年のことである。
清水登之が丸眼鏡姿の利為氏の肖像を残している。
展示は絵画ばかりではなく実際に使用されたガラス製品などもあった。
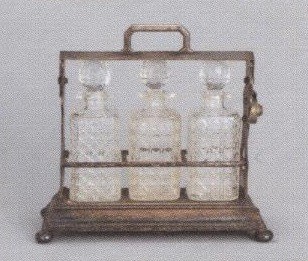
カッティングの綺麗なグラスや瓶が多く、センスの良さを感じさせる。
ワイングラスで面白いのが赤ワイン用のが透明、白ワイン用のが赤グラス。どちらも赤く見えるように設えられている。
それから蓋付カラフェがエリザベスカラーをつけ、胸元にカッティング刺繍の入ったドレスを着た貴婦人の人形のようにみえた。
たいへん興味深く、好ましい展覧会だった。
しかも図録は1200円と言うありがたさ。
良いものを見せて貰えて本当に良かった。



















