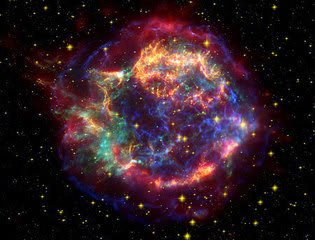歴史の中で興味があるのはやはり戦国時代ではないでしょうか?
今回は”織田信長”にスポットを当て、桶狭間の戦いについてお話しようと思います。
戦国時代は末期、多くの武将が天下統一を目指し、しのぎを削っていた。
主な武将は「越後の上杉」「甲斐の武田」「駿河・遠江・三河の今川」そして、「尾張の織田」
などが挙げられる。
まず、天下統一のためにはどこを攻略するか?
当時の政治の中心である所を攻略したくなるはず。
それが 京都なのだ。
京都攻略の為にまず動いたのが、三河の今川義元。
その道中、まず一番の敵になるのが「尾張の織田」
1560年駿府城を出発した今川はその6日後に尾張の国境近くの沓掛城に入り、
戦の準備をする。
それを知った信長はその翌日清洲城出陣に際し、敦盛の舞を舞うことになる。
この敦盛の舞いとは、一ノ谷の合戦で16歳の平敦盛が熊谷直実に討たれ、
我が子と同い年の若者を殺してしまったことを悔いた直実が出家するまでを描いた物語で、室町時代に能『敦盛』として戯曲化され、更に幸若舞の演目になった。
この桶狭間の戦いの際に信長が舞ったことから信長を語る上では欠かせないものとして捉えられるようになった。
『人間わずか五十年、下天の内をくらぶれば夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり、一度生を受け滅せぬ者のあるべきか』
今川軍優勢・・・今川軍は2万5千人の大軍。一方織田側はたかだか数千人の軍勢。織田は果敢にも今川軍に挑んでいこうとするが、劣勢であることを知っている家来達は攻撃に賛成しなかった。なんと最初は7,8人ほどしか従わなかったとされている。しかし、織田はその7,8人と共に清洲城を出発し、今川軍と真っ向勝負を挑むのであった。
あまりの劣勢・・・しかし、言えることは、織田は勝つのである!
Part2へ続く
今回は”織田信長”にスポットを当て、桶狭間の戦いについてお話しようと思います。
戦国時代は末期、多くの武将が天下統一を目指し、しのぎを削っていた。
主な武将は「越後の上杉」「甲斐の武田」「駿河・遠江・三河の今川」そして、「尾張の織田」
などが挙げられる。
まず、天下統一のためにはどこを攻略するか?
当時の政治の中心である所を攻略したくなるはず。
それが 京都なのだ。
京都攻略の為にまず動いたのが、三河の今川義元。
その道中、まず一番の敵になるのが「尾張の織田」
1560年駿府城を出発した今川はその6日後に尾張の国境近くの沓掛城に入り、
戦の準備をする。
それを知った信長はその翌日清洲城出陣に際し、敦盛の舞を舞うことになる。
この敦盛の舞いとは、一ノ谷の合戦で16歳の平敦盛が熊谷直実に討たれ、
我が子と同い年の若者を殺してしまったことを悔いた直実が出家するまでを描いた物語で、室町時代に能『敦盛』として戯曲化され、更に幸若舞の演目になった。
この桶狭間の戦いの際に信長が舞ったことから信長を語る上では欠かせないものとして捉えられるようになった。
『人間わずか五十年、下天の内をくらぶれば夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり、一度生を受け滅せぬ者のあるべきか』
今川軍優勢・・・今川軍は2万5千人の大軍。一方織田側はたかだか数千人の軍勢。織田は果敢にも今川軍に挑んでいこうとするが、劣勢であることを知っている家来達は攻撃に賛成しなかった。なんと最初は7,8人ほどしか従わなかったとされている。しかし、織田はその7,8人と共に清洲城を出発し、今川軍と真っ向勝負を挑むのであった。
あまりの劣勢・・・しかし、言えることは、織田は勝つのである!
Part2へ続く