LPG充填拒否問題を考える。 2010-02-04 08:33:47 | アウトドア?
改めて読み直しても得る処の少ない自分の過去記事を再掲して恐縮だが・・・、この昨年2月のエントリーへのコメント欄に数日前にコメントを頂いた。そのコメントは、ブログ主の私・・・ではなく昨年6月ににコメント欄にコメントを寄せて下さった『九州某県にてLPG充填所保安係員』をなさっている方に向けての御質問だった。ずうずうしく、私が知った風にコメントを返しても仕方がないと数日放置してみたが、ブログのコメント欄と云う「場」を、当該コメントをなさった方が再び読み直す事などは有り得ないだろうと思うので、新エントリーを立ててみた。コメント欄への書き込みなので、既に広く公開されている事だとして、ここで全文を引用させて頂く事にする。
『九州某県にてLPG充填所保安係員』をなさっている方のコメント(改行位置を変更)
> 我が社では (某LPG充填所従業者) 2010-06-13 10:58:06
>
> 初めまして。九州某県にてLPG充填所保安係員(LPG充填所にて
> 製造の責任者)をしております。大変興味深く拝見させていただきました。
> 我が社では全く逆の対応をしております。自社の容器は貸し出しをなるべ
> く抑え、お客様に自己所有の容器を買う事をお勧めしております。なぜな
> ら、容量20ℓ以下の容器は6年毎に容器検査に出さなければならずその
> 費用を自社で負担するよりはお客様に負担していただこうとの考えからで
> す。頻繁に充填にみえるお客様であっても地元の方でない場合は自社の容
> 器を貸し出す場合すぐに回収できない場合もありこちらの方をお断りして
> いるのが現状です。
>
> 自社の容器は財産であり、回転しないことには利益を生まず、一定の
> お客様のところに所在し続けることは利益にならないからです。質量販売
> においても一般家庭におけるメータ供給と同じように供給開始時調査と定
> 期消費設備調査をしなければ販売することはできません。しかしながら頻
> 度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答
> を液化石油協会からの回答を頂いております。
>
> したがって販売のたびに検査をしなければならないという事もありません。
>
> 供給開始時の調査と定期の調査の記録を残し使用している器具の確認が
> できればなんら問題があるとは思いません。LPGの販売業者は保安台帳
> といって顧客の全ての使用器具、使用状況、質量販売であれば容器の製造
> 番号を把握しております。しなければなりません。それはけして面倒なこ
> とではなく義務になっております。
>
> 充填の拒否をされているとの事ですが、我が社では理解できない事と思
> います。社の方針であれば仕方のない事なのかもしれませんがとても残念
> ですね。
>
> 一応、参考までにコメントさせていただきました。確かに事故が起これ
> ば大変なことになりますが我が社では使用についての注意や周知を徹底し
> て行っております。使用に当たって事故のないように使っていただきたい
> との考えからです。けして使用を進めているという訳ではないのですが
> 一従業者としての考えです。
>
> 長くなり要領の得ないコメントで申し訳ありませんでした。
数日前に、頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントです。(改行位置を変更)
> 某LPG充填所従業者へのご質問 (某販売店従業員)2011-03-26 22:29:54
>
> 当社では、キャンカーへのガス充てんについて、ご要望は多いもののお断り
> させていただいております。
>
> というのも、本県では液石法該当の販売については販売範囲を地図で示して
> 県監督課に届けており、緊急時対応ができる20キロ、30分以内で到着
> できる場所のみで液化ガスの販売をするというルールになっています。
>
> キャンカーはこの範囲を出て液化ガスを使用するので、万一の際の緊急時
> 対応ができないこととなり、販売店としての業務を全うできないため販売
> できないと解しているからです。
>
> 御社におきましては、このような縛りはございませんか?もしあればどの
> ようにクリアしておられますか?協会にも問合せしてみましたが、キャン
> カーのボンべに充填ができそうな規定は探せませんでした。
>
> もしよかったら教えてください。
過去記事にも書いた通り・・・私自身はLPG依存率の低い自走キャンピングカーに買い換えているので、新車導入後から今日まで搭載するLPGボンベに充填した事が無い。ジル520はLPガスをボイラーとコンロに供給する構造となっているが、実情としてコンロでしかLPガスを使わない上に、多くが気軽な外食中心の車中泊旅行なので車内で調理する頻度が少ないので納車時に充填された2Kgボンベには2年後の今でも半分以上残っている。更に予備ボンベ2Kgは満充填のままボンベ庫に入っているが、予備ボンベは充填期限が切れているので、空になったら検査を受けなければ再充填は出来ない。(ボンベ庫は走行用燃料タンク横に有るので、軽油補給の際には・・・ガソリンスタンドの係員の方に充填期限切れである事をほぼ毎回指摘を受けている。充填期限切れのボンベは使用が出来ない訳では無く充填が受けられないと了解しているので、その予備ボンベを使い切った頃に検査に出せば良いと思っている)
誉められた話では無いが、これ以外にもカセットガス用のアダプターを積んでいる(2本用と5本用)ので、最悪・・・出先でLGガスボンベを使い切ったらカセットガスを使えば良いと割り切っているので、昨今のLPガスの充填拒否問題を痛痒にも感じていない。過去記事にも書いた通り・・・これもやはり誉められた話ではないが・・・現在の充填先は私の関与先の大口オートガス供給先なので・・・公私混同も甚だしいが・・・もし、私のキャンピングカーで使う2KgLPGボンベの充填を断ったら、オートガスの充填先を変更するツモリであるから・・・、キャンピングカーへの充填拒否が例外なく日本全体で徹底されない限り・・・当面は問題ないだろうと思っている。
だから・・・?、キャンピングカーへの充填拒否問題は、私自身の問題では無いのかも知れない。だが、共にRVを駆りキャンプをする仲間達が充填拒否で困っていると云う事実は看過出来ない事である。私の所属するユーザーグループでも、私の所属する災害時炊き出しを行うNPOでも、この充填拒否問題は懸案事項である。
数日前に、コメントを頂戴した『某販売店従業員』さんの勤務先が、そうである様に・・・、多分、多くのLPG充填施設で充填拒否が行われているのだろうと思う。ユーザーグループのメーリングリストでも度々話題に上る事からも、多くの方々が困っているのだと思う。
RVの製造メーカー(及び、輸入代理店)では、当初は業界としてLPG充填拒否問題に取り組む姿勢を見せていたが、昨今登場する新型のRVではLPGへの依存度を減らしている。走行用燃料タンクを持つ自走式では、走行用燃料を使用するFFヒーターに暖房を切り替えて久しいが、被牽引車であり走行用燃料タンクを持たないトラベル・トレーラーでも軽油・灯油タンクを備え付けてFFヒーターを搭載する新型車が登場し始めた。そう云った新機軸のRVではLPGを燃料とした方が都合の良い調理用コンロはカセットガス・コンロか、大容量インバーター経由でのIHコンロ、又は、LPGガスボンベ対応のコンロをカセットガスアダプターを使用しカセットガスを使用する方向へ転進中である。トラベル・トレーラーでは3Wayの冷蔵庫を備え付けている場合が多いので、そう云った新機軸のRVでは、滞在時の冷蔵庫冷却もカセットガスを燃料とする様だ。(恐らく、その内にはトラベルトレーラーでもDC12V1Way冷蔵庫を搭載するモデルも登場するカモ知れない)
従来型のLPGボンベを搭載する新型RVの数が減ってきた事からも、RV業界はLPG充填拒否問題に対しては、既に白旗を揚げた感が強い。これは従来型のRVを所有する方々にとっては由々しき事態である。私も以前所有していた巨大な5thホイールトレーラー時代には、冬場のスキー場滞在では1泊2日で8Kgボンベを空にしていたから、他人事とは思えない。
これは液化石油ガス業界全体の考え方の変遷が原因であると思う。私は過去記事で、リスク多くして利が薄い質量販売からの撤退こそが理由だと(無責任に)断じたが、それに対して『九州某県にてLPG充填所保安係員』さんからのコメントを頂戴して、それは決して業界全体では無い事は知った。だが、歴然として・・・キャンピングカーへの充填拒否は継続されている。
最近は、このLPG充填拒否問題とは無縁の生活だったので問題自体を忘れがちだったが、今般の東日本大震災で、私は認識を新たにした。私の所属する災害時炊き出しを行うNPOは、災害発生後の早い時期から有志精鋭部隊が現地に入り炊き出しや支援活動を継続しているが、その過程でも、LPG充填拒否問題がクローズアップされてしまった。我々の災害時炊き出しを行うNPOは、それなりの政治力を発揮して災害時対応として(?)充填のお墨付きを協会から取り付けたらしい。だが、その陰では、やはり多くのRVユーザーが引き続き充填を拒否されているらしい。又、自粛ブームで頻度は減るのかも知れないが、RVユーザー並に質量販売に依存している屋台とかでのLPG使用は、どう扱われているのか非常に気になる次第だ。
家庭で使う調理用の燃料ソースが、LPGが良いのか、都市ガスが良いのか、IHヒーター等に代表される電気が良いのかを一方的に断じる事は出来ないが、こう云った災害発生時には、やはりLPGが最良ではないかと認識を新たにした。正しくは・・・メータ売りを前提にするLPGを、メーター等の既設の設備から切り離して、ボンベ単体で使う事は窃盗にも等しい事カモ知れない。だが、緊急避難の原則から、自宅内にある燃料備蓄を緊急時に借りる事を咎め立てはされない筈だ。都市ガスや電気は、自宅外の供給インフラが復旧するまでは、調理用コンロは使えないままとなる。又、今日の様に・・・原発事故に起因する「輪番停電」等が実施されている事を考えると・・・オール電化住宅は他の燃料ソースより自宅内での安全性は高いのだろうが・・・、電力に依存し切る事自体が問い直されているのカモ知れない。
昨年6月にコメントを頂戴した『九州某県にてLPG充填所保安係員』さんの事業所は、使用開始時の「供給開始時調査」と3年に1回の「定期消費設備調査」を行っていて保安台帳(顧客の全ての使用器具、使用状況、質量販売であれば容器の製造番号を把握)が存在するキャンピングカーへのLPG充填は行っておられるそうで、その事業所様の判断では、「供給開始時の調査と定期の調査の記録を残し使用している器具の確認ができればなんら問題」は無いと云う御認識です。又、(質量販売に於いても)頻度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答を液化石油協会からの回答を頂いておられるそうだ。
だが、数日前にコメントを頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントに依ると、その方の「本県では液石法該当の販売については販売範囲を地図で示して県監督課に届けており、緊急時対応ができる20キロ、30分以内で到着できる場所のみで液化ガスの販売をするというルール(恐らく、県のルール)」になっているので、その範囲を超えて移動するだろうと判断されるキャンピングカーには(県)ルールを守れば充填してはならない・・・と成る。その他の条件に関して特段の御指摘は無いので、「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」と云う県のルールに抵触するからキャンピングカーには充填できないのだそうだ。
例の有名な『江戸川区の事故』(亡くなられた方にはお悔やみを表明します)の後、監督官庁たる『東京都』は、ガスを販売した業者に『体積・質量販売に対する点検調査義務違反』による3ヶ月の業務停止命令を出している。その後、各県担当課への調査の過程や、経済産業省の立ち入り検査の過程で多くの法令違反が見つかり改善命令が出ている。その経産省からの改善命令が出た都道府県では、担当課が「保安台帳」の完備と原子力安全委員会の答申である「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」が徹底されたのだと考えている。
実態として・・・平成11年の質量販売先消費世帯は、全LPガス消費世帯数の約1.9%の約45万世帯であり、このうち、使用形態として見た場合、一般家庭が約68%と最も多かったが、一時的なガスの使用や器具の増設などで体積販売と併用し、質量販売のLPガスを使用しているものが多いと推定された。また、質量販売に携わる販売業者は45%だった。質量販売は国内の全LPガス消費量の1%未満であるにも関わらず、LPGに関する事故の10%が質量販売で発生しているそうだ。
つまり、扱い量としては非常に少量であるにも関わらず、非常に高い事故発生率である事・・・が、販売業者を質量販売から遠ざける遠因になっている・・・と思う。そして、『江戸川区の事故』後に強化された安全施策をクリアして質量販売を継続するメリットは販売店側には存在しないのだと思う。
尚、地元岡山県の保安連絡協議会への「質量販売にかかる保安業務の確実な実施について(要請)」は以下の通り・・・(画像)

液化石油ガスの質量販売の実態調査結果及び対応について 2008年4月10日(PDF形式(272kb))
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年三月十日通商産業省令第十一号)
第十六条第十三号 液化石油ガスは、計量法 (平成四年法律第五十一号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法 の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法 に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。
第十六条第三号 充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合
ロ 調整器が接続された内容積が八リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合
ハ 内容積が二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年十二月二十八日法律第百四十九号)
(保安業務を行う義務)
第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
三 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
四 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
3 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第二十九条第一項の認定を受けなければならない。
規則第三十七条第一号
ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備
(1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上
第四十四条 法第三十五条の五 の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二 第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(4) 充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。
(6) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
第四十四条 第二号 ロ 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。
(2) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
(3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。
第十八条 法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二十 調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
規則第三十七条第一号
表「ロ」 第四十四条第二号に掲げる消費設備 の点検調査の回数は「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」となる。
地元岡山県の事業者とは書いていないのでドコの事業者かは判らないが立ち入り検査を受けて「質量販売にかかる保安業務が適切に行われていなかった法令違反事案」・・・供給開始時点検・調査を行わずに充填してしまった・・・事がバレちゃったと云う事なのだろうか?だから、質量販売に於ける保安業務を岡山県の保安連絡協議会に所属する事業者に徹底して欲しいと云う要請を下知する書類なのだろう。で、『九州某県にてLPG充填所保安係員』の方が『頻度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答を液化石油協会からの回答を頂いて』居られるそうですが・・・私が条文を読む限りでは・・・上記条文の引用の通り・・・
消費設備の点検調査の頻度回数は「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」となるみたいだ。つまり、充填して頂く度に点検が必要と読める。その代わりに、充填に行かない月は点検不要となる。又、1ヶ月以内に複数回充填に訪れた場合は点検検査は1回だけで良いのだろう。だから、過去記事に書いた某西隣の県名を冠した都市ガス会社の液化石油ガス事業部岡山支店さんで充填する際には必ず毎回RVを持ち込んで数十分を要する点検(但し、無料だった)をしないと充填はして貰えなかった・・・と云うのは厳しすぎるのではなく完全に法に則った結果だった訳だ。巨大な5thホイールトレーラー時代には、この敷地内で方向転換するのが面倒で・・・足が遠のいてしまったのだが、価格も良心的なココ(が、今でも充填を引き受けてくれるのなら)を自宅にも近いので利用しても良いなぁ~と思った次第。
因みに・・・「平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正」で『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が適用される筈。尚、仲間内での使用実績が多い8Kボンベでは、「高圧接続部が外れた場合に自動的に放出を遮断する機能を備えたワンタッチカップリングを取り付けた容器であり、適合するワンタッチカップリングを備えたガス集合設備・配管設備・圧力調整器・燃焼器具のいずれかに接続する場合」に限定されるので要注意。
数日前にコメントを頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントにあった「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」と云う某県のルールは、私が検索しても見つけられなかった。但し、「平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正」で「内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器」に関しては、「接続条件、設置場所、資格条件」の制限無しなので、その某県に於いても制限がないのでは無いのかと思う。(思いたい)
キャンピングカーに対して、有資格者が例示基準に定める手順により適切に漏えい試験・調整器の圧力確認を行う事を・・・充填の度に無料で行うのは、それだけで面倒な話である。手間が掛かるからと充填の度に有料で漏えい試験・調整器の圧力確認を行うのではユーザーサイドが受け入れられないのカモ?但し、これらを行えば販売店側も合法に充填出来るが、その「有資格者が例示基準に定める手順により適切に漏えい試験・調整器の圧力確認を行う事」を、いつ何時に来るか来ないか判らない質量販売を希望するキャンピングカーの為に常駐させておく事など無駄の極致だろう。運営上・・・合法に充填する事に要する経費より利益が少ないなら・・・民間企業の常として、利の薄い商材からは撤退する事を非難する権利は私にはない。私自身が液化石油ガス販売事業者を経営していたら、RVユーザーには申し訳ないが、キャンピングカーへの充填は止めようと従業員には指示する筈だ。他の考え方もあるのカモ知れないが・・・私は、これらの理由でLPG充填拒否問題が起きている・・・と思っている。これは我々ユーザー団体や我々NPOが頑張ろうとも、その供給開始時点検・調査を無料で行う理由は個々の供給販売事業所には無いだろう。それを無料で引き受けて下さるLPG販売事業所さんに感謝しこそすれ、充填拒否をする事業所を恨むべき謂われはない。『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が、供給開始時点検・調査も不要、毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上の点検調査も不要と明言して下されば、キャンピングカーへの充填拒否問題は一気に解決する筈だ。役所である経済産業省が、そんな大胆な明言をして下さるとは思えない。もしも、『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が、供給開始時点検・調査も不要、毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上の点検調査も不要として、万が一にも事故が発生したら責任問題に至るからだ。今の小さな自走なら充填所に持ち込んで充填の度に検査を受けるのも吝かでは無いのだが、以前の巨大な5thホイールトレーラーでは同社が営業している平日の日中に持ち込み検査を受けるのはユーザー側にも大きな労力が必要だったのも事実だ。事前予約をしていかないと、保安資格を持った人が居ないと検査が出来ず充填出来なかった。ユーザー側だけではなく充填業者様側も、手間と云う大きな犠牲を割いて充填して下さっていた訳だ。
こうして法規を確認して考え直すとキャンピングカーへのLPガス充填拒否問題は、法を遵守する限り止むを得ない事なのかも知れない。『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』と成っているし、「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」の点検も受けるツモリで居る。これならば完全に合法なのだから売って欲しいと関係法令のコピーを持って理論武装して行ってみても、社の方針でキャンピングカーに充填しない事に決まっていると云われたら、諦めるしかないのだろう。我が家が次に充填する頃にはキャンピングカーへLPガスを充填して下さる充填業者さんが地元に残っているのだろうか?
Google マップで「持ち込み充填可能なLPG販売所マップ」という地図を作ったので、キャンピングカー搭載のLPGボンベに充填して下さる販売店さんを御存知の方は御記入下さい。
改めて読み直しても得る処の少ない自分の過去記事を再掲して恐縮だが・・・、この昨年2月のエントリーへのコメント欄に数日前にコメントを頂いた。そのコメントは、ブログ主の私・・・ではなく昨年6月ににコメント欄にコメントを寄せて下さった『九州某県にてLPG充填所保安係員』をなさっている方に向けての御質問だった。ずうずうしく、私が知った風にコメントを返しても仕方がないと数日放置してみたが、ブログのコメント欄と云う「場」を、当該コメントをなさった方が再び読み直す事などは有り得ないだろうと思うので、新エントリーを立ててみた。コメント欄への書き込みなので、既に広く公開されている事だとして、ここで全文を引用させて頂く事にする。
『九州某県にてLPG充填所保安係員』をなさっている方のコメント(改行位置を変更)
> 我が社では (某LPG充填所従業者) 2010-06-13 10:58:06
>
> 初めまして。九州某県にてLPG充填所保安係員(LPG充填所にて
> 製造の責任者)をしております。大変興味深く拝見させていただきました。
> 我が社では全く逆の対応をしております。自社の容器は貸し出しをなるべ
> く抑え、お客様に自己所有の容器を買う事をお勧めしております。なぜな
> ら、容量20ℓ以下の容器は6年毎に容器検査に出さなければならずその
> 費用を自社で負担するよりはお客様に負担していただこうとの考えからで
> す。頻繁に充填にみえるお客様であっても地元の方でない場合は自社の容
> 器を貸し出す場合すぐに回収できない場合もありこちらの方をお断りして
> いるのが現状です。
>
> 自社の容器は財産であり、回転しないことには利益を生まず、一定の
> お客様のところに所在し続けることは利益にならないからです。質量販売
> においても一般家庭におけるメータ供給と同じように供給開始時調査と定
> 期消費設備調査をしなければ販売することはできません。しかしながら頻
> 度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答
> を液化石油協会からの回答を頂いております。
>
> したがって販売のたびに検査をしなければならないという事もありません。
>
> 供給開始時の調査と定期の調査の記録を残し使用している器具の確認が
> できればなんら問題があるとは思いません。LPGの販売業者は保安台帳
> といって顧客の全ての使用器具、使用状況、質量販売であれば容器の製造
> 番号を把握しております。しなければなりません。それはけして面倒なこ
> とではなく義務になっております。
>
> 充填の拒否をされているとの事ですが、我が社では理解できない事と思
> います。社の方針であれば仕方のない事なのかもしれませんがとても残念
> ですね。
>
> 一応、参考までにコメントさせていただきました。確かに事故が起これ
> ば大変なことになりますが我が社では使用についての注意や周知を徹底し
> て行っております。使用に当たって事故のないように使っていただきたい
> との考えからです。けして使用を進めているという訳ではないのですが
> 一従業者としての考えです。
>
> 長くなり要領の得ないコメントで申し訳ありませんでした。
数日前に、頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントです。(改行位置を変更)
> 某LPG充填所従業者へのご質問 (某販売店従業員)2011-03-26 22:29:54
>
> 当社では、キャンカーへのガス充てんについて、ご要望は多いもののお断り
> させていただいております。
>
> というのも、本県では液石法該当の販売については販売範囲を地図で示して
> 県監督課に届けており、緊急時対応ができる20キロ、30分以内で到着
> できる場所のみで液化ガスの販売をするというルールになっています。
>
> キャンカーはこの範囲を出て液化ガスを使用するので、万一の際の緊急時
> 対応ができないこととなり、販売店としての業務を全うできないため販売
> できないと解しているからです。
>
> 御社におきましては、このような縛りはございませんか?もしあればどの
> ようにクリアしておられますか?協会にも問合せしてみましたが、キャン
> カーのボンべに充填ができそうな規定は探せませんでした。
>
> もしよかったら教えてください。
過去記事にも書いた通り・・・私自身はLPG依存率の低い自走キャンピングカーに買い換えているので、新車導入後から今日まで搭載するLPGボンベに充填した事が無い。ジル520はLPガスをボイラーとコンロに供給する構造となっているが、実情としてコンロでしかLPガスを使わない上に、多くが気軽な外食中心の車中泊旅行なので車内で調理する頻度が少ないので納車時に充填された2Kgボンベには2年後の今でも半分以上残っている。更に予備ボンベ2Kgは満充填のままボンベ庫に入っているが、予備ボンベは充填期限が切れているので、空になったら検査を受けなければ再充填は出来ない。(ボンベ庫は走行用燃料タンク横に有るので、軽油補給の際には・・・ガソリンスタンドの係員の方に充填期限切れである事をほぼ毎回指摘を受けている。充填期限切れのボンベは使用が出来ない訳では無く充填が受けられないと了解しているので、その予備ボンベを使い切った頃に検査に出せば良いと思っている)
誉められた話では無いが、これ以外にもカセットガス用のアダプターを積んでいる(2本用と5本用)ので、最悪・・・出先でLGガスボンベを使い切ったらカセットガスを使えば良いと割り切っているので、昨今のLPガスの充填拒否問題を痛痒にも感じていない。過去記事にも書いた通り・・・これもやはり誉められた話ではないが・・・現在の充填先は私の関与先の大口オートガス供給先なので・・・公私混同も甚だしいが・・・もし、私のキャンピングカーで使う2KgLPGボンベの充填を断ったら、オートガスの充填先を変更するツモリであるから・・・、キャンピングカーへの充填拒否が例外なく日本全体で徹底されない限り・・・当面は問題ないだろうと思っている。
だから・・・?、キャンピングカーへの充填拒否問題は、私自身の問題では無いのかも知れない。だが、共にRVを駆りキャンプをする仲間達が充填拒否で困っていると云う事実は看過出来ない事である。私の所属するユーザーグループでも、私の所属する災害時炊き出しを行うNPOでも、この充填拒否問題は懸案事項である。
数日前に、コメントを頂戴した『某販売店従業員』さんの勤務先が、そうである様に・・・、多分、多くのLPG充填施設で充填拒否が行われているのだろうと思う。ユーザーグループのメーリングリストでも度々話題に上る事からも、多くの方々が困っているのだと思う。
RVの製造メーカー(及び、輸入代理店)では、当初は業界としてLPG充填拒否問題に取り組む姿勢を見せていたが、昨今登場する新型のRVではLPGへの依存度を減らしている。走行用燃料タンクを持つ自走式では、走行用燃料を使用するFFヒーターに暖房を切り替えて久しいが、被牽引車であり走行用燃料タンクを持たないトラベル・トレーラーでも軽油・灯油タンクを備え付けてFFヒーターを搭載する新型車が登場し始めた。そう云った新機軸のRVではLPGを燃料とした方が都合の良い調理用コンロはカセットガス・コンロか、大容量インバーター経由でのIHコンロ、又は、LPGガスボンベ対応のコンロをカセットガスアダプターを使用しカセットガスを使用する方向へ転進中である。トラベル・トレーラーでは3Wayの冷蔵庫を備え付けている場合が多いので、そう云った新機軸のRVでは、滞在時の冷蔵庫冷却もカセットガスを燃料とする様だ。(恐らく、その内にはトラベルトレーラーでもDC12V1Way冷蔵庫を搭載するモデルも登場するカモ知れない)
従来型のLPGボンベを搭載する新型RVの数が減ってきた事からも、RV業界はLPG充填拒否問題に対しては、既に白旗を揚げた感が強い。これは従来型のRVを所有する方々にとっては由々しき事態である。私も以前所有していた巨大な5thホイールトレーラー時代には、冬場のスキー場滞在では1泊2日で8Kgボンベを空にしていたから、他人事とは思えない。
これは液化石油ガス業界全体の考え方の変遷が原因であると思う。私は過去記事で、リスク多くして利が薄い質量販売からの撤退こそが理由だと(無責任に)断じたが、それに対して『九州某県にてLPG充填所保安係員』さんからのコメントを頂戴して、それは決して業界全体では無い事は知った。だが、歴然として・・・キャンピングカーへの充填拒否は継続されている。
最近は、このLPG充填拒否問題とは無縁の生活だったので問題自体を忘れがちだったが、今般の東日本大震災で、私は認識を新たにした。私の所属する災害時炊き出しを行うNPOは、災害発生後の早い時期から有志精鋭部隊が現地に入り炊き出しや支援活動を継続しているが、その過程でも、LPG充填拒否問題がクローズアップされてしまった。我々の災害時炊き出しを行うNPOは、それなりの政治力を発揮して災害時対応として(?)充填のお墨付きを協会から取り付けたらしい。だが、その陰では、やはり多くのRVユーザーが引き続き充填を拒否されているらしい。又、自粛ブームで頻度は減るのかも知れないが、RVユーザー並に質量販売に依存している屋台とかでのLPG使用は、どう扱われているのか非常に気になる次第だ。
家庭で使う調理用の燃料ソースが、LPGが良いのか、都市ガスが良いのか、IHヒーター等に代表される電気が良いのかを一方的に断じる事は出来ないが、こう云った災害発生時には、やはりLPGが最良ではないかと認識を新たにした。正しくは・・・メータ売りを前提にするLPGを、メーター等の既設の設備から切り離して、ボンベ単体で使う事は窃盗にも等しい事カモ知れない。だが、緊急避難の原則から、自宅内にある燃料備蓄を緊急時に借りる事を咎め立てはされない筈だ。都市ガスや電気は、自宅外の供給インフラが復旧するまでは、調理用コンロは使えないままとなる。又、今日の様に・・・原発事故に起因する「輪番停電」等が実施されている事を考えると・・・オール電化住宅は他の燃料ソースより自宅内での安全性は高いのだろうが・・・、電力に依存し切る事自体が問い直されているのカモ知れない。
昨年6月にコメントを頂戴した『九州某県にてLPG充填所保安係員』さんの事業所は、使用開始時の「供給開始時調査」と3年に1回の「定期消費設備調査」を行っていて保安台帳(顧客の全ての使用器具、使用状況、質量販売であれば容器の製造番号を把握)が存在するキャンピングカーへのLPG充填は行っておられるそうで、その事業所様の判断では、「供給開始時の調査と定期の調査の記録を残し使用している器具の確認ができればなんら問題」は無いと云う御認識です。又、(質量販売に於いても)頻度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答を液化石油協会からの回答を頂いておられるそうだ。
だが、数日前にコメントを頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントに依ると、その方の「本県では液石法該当の販売については販売範囲を地図で示して県監督課に届けており、緊急時対応ができる20キロ、30分以内で到着できる場所のみで液化ガスの販売をするというルール(恐らく、県のルール)」になっているので、その範囲を超えて移動するだろうと判断されるキャンピングカーには(県)ルールを守れば充填してはならない・・・と成る。その他の条件に関して特段の御指摘は無いので、「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」と云う県のルールに抵触するからキャンピングカーには充填できないのだそうだ。
例の有名な『江戸川区の事故』(亡くなられた方にはお悔やみを表明します)の後、監督官庁たる『東京都』は、ガスを販売した業者に『体積・質量販売に対する点検調査義務違反』による3ヶ月の業務停止命令を出している。その後、各県担当課への調査の過程や、経済産業省の立ち入り検査の過程で多くの法令違反が見つかり改善命令が出ている。その経産省からの改善命令が出た都道府県では、担当課が「保安台帳」の完備と原子力安全委員会の答申である「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」が徹底されたのだと考えている。
実態として・・・平成11年の質量販売先消費世帯は、全LPガス消費世帯数の約1.9%の約45万世帯であり、このうち、使用形態として見た場合、一般家庭が約68%と最も多かったが、一時的なガスの使用や器具の増設などで体積販売と併用し、質量販売のLPガスを使用しているものが多いと推定された。また、質量販売に携わる販売業者は45%だった。質量販売は国内の全LPガス消費量の1%未満であるにも関わらず、LPGに関する事故の10%が質量販売で発生しているそうだ。
つまり、扱い量としては非常に少量であるにも関わらず、非常に高い事故発生率である事・・・が、販売業者を質量販売から遠ざける遠因になっている・・・と思う。そして、『江戸川区の事故』後に強化された安全施策をクリアして質量販売を継続するメリットは販売店側には存在しないのだと思う。
尚、地元岡山県の保安連絡協議会への「質量販売にかかる保安業務の確実な実施について(要請)」は以下の通り・・・(画像)

液化石油ガスの質量販売の実態調査結果及び対応について 2008年4月10日(PDF形式(272kb))
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年三月十日通商産業省令第十一号)
第十六条第十三号 液化石油ガスは、計量法 (平成四年法律第五十一号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法 の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法 に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。
第十六条第三号 充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合
ロ 調整器が接続された内容積が八リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合
ハ 内容積が二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年十二月二十八日法律第百四十九号)
(保安業務を行う義務)
第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
三 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
四 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
3 液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第二十九条第一項の認定を受けなければならない。
規則第三十七条第一号
ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備
(1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上
第四十四条 法第三十五条の五 の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二 第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(4) 充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。
(6) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
第四十四条 第二号 ロ 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。
(2) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
(3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。
第十八条 法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二十 調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
規則第三十七条第一号
表「ロ」 第四十四条第二号に掲げる消費設備 の点検調査の回数は「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」となる。
地元岡山県の事業者とは書いていないのでドコの事業者かは判らないが立ち入り検査を受けて「質量販売にかかる保安業務が適切に行われていなかった法令違反事案」・・・供給開始時点検・調査を行わずに充填してしまった・・・事がバレちゃったと云う事なのだろうか?だから、質量販売に於ける保安業務を岡山県の保安連絡協議会に所属する事業者に徹底して欲しいと云う要請を下知する書類なのだろう。で、『九州某県にてLPG充填所保安係員』の方が『頻度としてはこれもメータ供給と変わらず3年に一度程度で良い。との回答を液化石油協会からの回答を頂いて』居られるそうですが・・・私が条文を読む限りでは・・・上記条文の引用の通り・・・
消費設備の点検調査の頻度回数は「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」となるみたいだ。つまり、充填して頂く度に点検が必要と読める。その代わりに、充填に行かない月は点検不要となる。又、1ヶ月以内に複数回充填に訪れた場合は点検検査は1回だけで良いのだろう。だから、過去記事に書いた某西隣の県名を冠した都市ガス会社の液化石油ガス事業部岡山支店さんで充填する際には必ず毎回RVを持ち込んで数十分を要する点検(但し、無料だった)をしないと充填はして貰えなかった・・・と云うのは厳しすぎるのではなく完全に法に則った結果だった訳だ。巨大な5thホイールトレーラー時代には、この敷地内で方向転換するのが面倒で・・・足が遠のいてしまったのだが、価格も良心的なココ(が、今でも充填を引き受けてくれるのなら)を自宅にも近いので利用しても良いなぁ~と思った次第。
因みに・・・「平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正」で『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が適用される筈。尚、仲間内での使用実績が多い8Kボンベでは、「高圧接続部が外れた場合に自動的に放出を遮断する機能を備えたワンタッチカップリングを取り付けた容器であり、適合するワンタッチカップリングを備えたガス集合設備・配管設備・圧力調整器・燃焼器具のいずれかに接続する場合」に限定されるので要注意。
数日前にコメントを頂戴した『某販売店従業員』さんのコメントにあった「緊急対応が出来る20キロ、30分以内で到着できる場所のみ」と云う某県のルールは、私が検索しても見つけられなかった。但し、「平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正」で「内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器」に関しては、「接続条件、設置場所、資格条件」の制限無しなので、その某県に於いても制限がないのでは無いのかと思う。(思いたい)
キャンピングカーに対して、有資格者が例示基準に定める手順により適切に漏えい試験・調整器の圧力確認を行う事を・・・充填の度に無料で行うのは、それだけで面倒な話である。手間が掛かるからと充填の度に有料で漏えい試験・調整器の圧力確認を行うのではユーザーサイドが受け入れられないのカモ?但し、これらを行えば販売店側も合法に充填出来るが、その「有資格者が例示基準に定める手順により適切に漏えい試験・調整器の圧力確認を行う事」を、いつ何時に来るか来ないか判らない質量販売を希望するキャンピングカーの為に常駐させておく事など無駄の極致だろう。運営上・・・合法に充填する事に要する経費より利益が少ないなら・・・民間企業の常として、利の薄い商材からは撤退する事を非難する権利は私にはない。私自身が液化石油ガス販売事業者を経営していたら、RVユーザーには申し訳ないが、キャンピングカーへの充填は止めようと従業員には指示する筈だ。他の考え方もあるのカモ知れないが・・・私は、これらの理由でLPG充填拒否問題が起きている・・・と思っている。これは我々ユーザー団体や我々NPOが頑張ろうとも、その供給開始時点検・調査を無料で行う理由は個々の供給販売事業所には無いだろう。それを無料で引き受けて下さるLPG販売事業所さんに感謝しこそすれ、充填拒否をする事業所を恨むべき謂われはない。『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が、供給開始時点検・調査も不要、毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上の点検調査も不要と明言して下されば、キャンピングカーへの充填拒否問題は一気に解決する筈だ。役所である経済産業省が、そんな大胆な明言をして下さるとは思えない。もしも、『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』が、供給開始時点検・調査も不要、毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上の点検調査も不要として、万が一にも事故が発生したら責任問題に至るからだ。今の小さな自走なら充填所に持ち込んで充填の度に検査を受けるのも吝かでは無いのだが、以前の巨大な5thホイールトレーラーでは同社が営業している平日の日中に持ち込み検査を受けるのはユーザー側にも大きな労力が必要だったのも事実だ。事前予約をしていかないと、保安資格を持った人が居ないと検査が出来ず充填出来なかった。ユーザー側だけではなく充填業者様側も、手間と云う大きな犠牲を割いて充填して下さっていた訳だ。
こうして法規を確認して考え直すとキャンピングカーへのLPガス充填拒否問題は、法を遵守する限り止むを得ない事なのかも知れない。『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』と成っているし、「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」の点検も受けるツモリで居る。これならば完全に合法なのだから売って欲しいと関係法令のコピーを持って理論武装して行ってみても、社の方針でキャンピングカーに充填しない事に決まっていると云われたら、諦めるしかないのだろう。我が家が次に充填する頃にはキャンピングカーへLPガスを充填して下さる充填業者さんが地元に残っているのだろうか?
Google マップで「持ち込み充填可能なLPG販売所マップ」という地図を作ったので、キャンピングカー搭載のLPGボンベに充填して下さる販売店さんを御存知の方は御記入下さい。













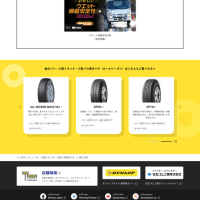













> 私も被害者です。ブログ主さんもキャンピングカーを使っているのに充填拒否が正しいと思うのですか?
多くの方がお困りである事は、私も認識しています。
「町田の独り言」と云うRV界での有名ブログの記事「2008年02月14日 LPGの充填拒否」のURL
http://campingcar.blog.hobidas.com/archives/article/39738.html
YAHOO!JAPAN 知恵袋から
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1441711769
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214878927?fr=rcmd_chie_detail
私自身も過去記事に書いたように数回充填拒否を受けています。いつも充填していた地元の最大手さん(そこでボンベや調整器や高圧ホースを買っていた)でも、何度か御世話になった筈の旅先の充填所でも、です。非常に残念に思いましたが、そこで店頭の充填員の方と争ってみても仕方がないので、ついに来たか・・・と諦めた次第です。(その某大手さんは、役員さんにも面識があったので苦情は伝えましたが・・・毎回検査が実情対応できないので止むを得ないとの事でした)
私は「両論併記」をモットーにしているツモリなので、他のネタの時も論旨が分かり難いから・・・、双方から敵方と見なされる事が多いのですが・・・。
言外には匂わせているツモリなのですが、RVユーザーの端くれとして当然に充填拒否を正当化しているツモリはありません。
被害者・・・と云う意味が私には良くは判りませんが、私が勝手に想像するのは・・・、LPGの充填を問題なく受けられる事が前提として御購入なさったRVが作られているのに、LPGの充填拒否があり・・・購入の目的を満足に達せられないって事でしょうか?でしたら、月並みな言い方ですが、お悔やみ申し上げます。RV製造メーカー(輸入代理店)も、今の事態を想像できなかったのだと思います。
充填拒否が正しいとは思いません。今までLPGの充填拒否問題の理由は、例の爆発死亡事故に端を発する「経産省の通達から」と多くの識者の方が書いておられます。恐らく、その通りだと私も思います。ですが、その事故を受けて法律が厳格化した訳ではなく・・・、運用が厳格化したのでしょう。
今回私なりに調べて判った事は・・・それ以前は問題なく持ち込んだLPGボンベに充填してくれていた当たり前だと思っていた事は、実は法律違反だったのです。
多くの方のブログ等に書いてある・・・ボンベの脱着は有資格者しか出来ない云々は、「平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正」で『内容積8ℓLPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。』となっているので、ユーザーサイドで交換しても合法です。
それではなく、キャンピングカーへの充填拒否に至る最大の理由は・・・次の法律。
規則第三十七条第一号 表「ロ」
第四十四条第二号に掲げる消費設備 の点検調査の回数は「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上」となる。
「LPG販売事業所には監督官庁からの許認可事業である以上、法規を遵守する必然がある」と云う事(そして、例の事故以降は監督官庁からの立ち入り検査を含む強力な指導が入っている)と、「監督官庁は、事故発生を未然に防ぐ法整備を行う義務がある」事と、RVユーザーがLPGの充填を希求している事を、相反する事としない工夫が必要なのでは・・・と思っています。そこまで論を進めなかったのは、私の蒙昧が為せる「落ち度」だと反省致します。但し、そこまで論を進めても・・・田舎のオッサンが何を書いても仕方がないなぁ~と云う諦めもあります。
もしRV協会等の供給側の団体がアクションを起こすのならば、RVのLPG消費設備の保安を団体として担保する仕組みが必要で、それと並行して、経産省側にRV限定の保安員と保安体制の樹立を働き掛ける事が必要だと思います。これは元記事に引用した「山小屋」の例外事項と同じ類の事です。RV協会に加盟するRV販売店では講習を受け液化石油ガス消費施設の保安員と同等の資格を持つ人材をおき、充填以前に消費施設の保安点検検査を実行し安全を担保していれば・・・その設備で使うLPG充填を嫌がる充填事業所は無くなる筈です。その上で、円滑にLPG充填を受けたいユーザーは、「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月一回以上」に代わる実状に即した点検検査の回数を、RV販売店で受けておけば良い事になるのです。
RV協会は、所謂・・・販売側の団体ですが、こうして消費施設の保安点検の名目で、ユーザーが訪れる機会が増える事を、新たな商機と捉えられるなら・・・利の薄いLPG販売事業所が得体の知れないRVの保安を担保するのとは違う展開になる・・・と思います。
ですが、本文に書いたとおり・・・、LPGに依存しないRV開発に転進している風にお見受けするので、既に白旗を揚げたのでは無いかと皮肉ったツモリです。
何れにしろ、例の事故以前のように、所定の検査もなくガス充填が受けられると云う違法行為がまかり通る事はないと思います。コメントを下さった方の様に・・・購入の目的を満足に達せられないって被害者の方が声を大にしてRV協会等の団体のお尻を叩く以外に解決に近づける方法は無いのかも知れません。
又、法律に則って「液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月一回以上」の点検をして充填して下さる親切なLPG販売事業所様をみんなで共有し大切にお付き合いをさせて頂くと云うムーブメントが出来れば・・・自宅がLPG世帯ならRVに供給して下さる事業所に使うガス会社を切り替える等の営業的な協力も行いつつ・・・キチンと法律に則ってRVにもLPGを供給する充填所こそが上手く商売が運ぶとなれば、点検検査の手間を面倒だと切り捨てた充填所も喜んで受入する様に成るカモ知れませんし・・・ね。全消費量の1%未満の質量販売でも、その動向次第で体積販売での顧客獲得に繋がるとなればLPG販売業界も無視できなくなる・・・と思いませんか?
第44条第2号ロの屋外において移動して
使用される消費設備に該当するため、
第37条第1号ロ(3)の調査を行う事項、
ロ(1)、(2)(略)(3)に掲げる基準であり、
「最初の引き渡し時及び4年に1回以上」に
なります。
ただ、社内方針や運用により、毎回調査している
場合もあります。
> 第44条第2号ロ
ロ 内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。
(2) 調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
(3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。
で、充てん容器等の技術基準は・・・
ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
調整器の技術基準は・・・
二十 調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
ロ 調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。
(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ハ 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。
(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。
燃焼器の技術基準は・・・
ワ 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
・・・等を
「液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上」行えば良いのですね。
4年に1回以上なら、以前のリプライに思い付きで書いた様に・・・RV販売店に保安員が居るとすれば、車検毎に点検して貰えばOKとなる訳ですねぇ。
あ?! でも、「液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上」を行う義務者は、液化石油ガスの販売所なのだろうから・・・、例えRV販売店に保安員の資格を持つ人が居て4年に1回以上の調査を受けていたとしても、その調査結果を鵜呑みにして調査をしないで充填する訳にはいかないカモ知れませんねぇ。
う~ん、この部分がネックになるのかなぁ。
もしも、そうなら液化石油ガスの消費設備の調査が出来る資格者が居ない充填所では、やはり充填拒否するしか無いのカモ?ましてや、充填も上部組織に依存している充填取次所では、充填拒否・・・と云うより、充填してはダメとなるのでしょうか?
それと・・・
> ただ、社内方針や運用により、毎回調査している
> 場合もあります。
私が知っている充填所は毎回検査なんです。そう云う規則になっていると検査される(保安員?)の方が云われるので・・・。
私のジル520の場合の検査って・・・、圧力計を使って行う配管のガス漏れ検査と、コンロの燃焼炎の色の目視検査と、容器庫周辺(調整器の有効期限等も含む)の目視点検です。この圧力計を使ってのガス漏れ検査が結構時間が掛かるので・・・
法律ではなく、その会社の規則なんでしょうね。ま、それはそれで安心だと思います。
有り難う御座いました。
岡山県岡山市中区神下429 の「永燃」がキャンピングカーに理解あります。
値段も割りとお安いかと・・・
ガス改造改良の相談も乗ってくれます。
googleマップ追加してくださいませ。
#ナカナカ出動する機会に恵まれず・・・ご無沙汰ばかりで・・・
> 岡山県岡山市中区神下429 の「永燃」がキャンピングカーに理解あります。
> 値段も割りとお安いかと・・・
> ガス改造改良の相談も乗ってくれます。
情報有り難う御座います。あ~、そこ知っています。知人がオートガス車に乗っていた時ガスチャージに一緒に行きました。(オートガスを入れるとヤクルトをくれる)
マップに追加しておきました。が・・・、閲覧件数47なので、この目論見は失敗カモ。誰でも編集出来る設定なのですが・・・、編集にはGoogleアカウントが必要なのでしょうね・・・。
ま、これからも宜しくお願い致します。
調べたら「保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示」平成9年3月13日通商産業省告示第122号の第二条第三号に「緊急時対応にあっては次に掲げる要件に適合するものとする」とされ、ロに「保安業務に係る一般消費者等の供給設備及び消費設備には原則として三〇分以内に到着し、所要の措置を行うことができる体制を確保すること。」とされています。この体制が確保できないため、充填できないと解しているわけです。
充填されている事業者さんはここをどうクリアしておられるのかが知りたかったんですが・・・。
なお、配管への接続ではなく、調整器を付けた状態での販売が可能なのは、カップリング付きでない場合、内容量10Lまでですので、三キロ容器が上限だと思います。
ただ、先の規定さえなければ、キャンピングカーごと来ていただければ、供給開始時及び四年以内ごとの設備調査で充填引渡しは可能なはずなんですが。屋外移動使用なので容器の大きさは問いませんが、高圧ガス保安法で一般の車両に積めるのは八キロ二本が上限となります。
屋台でガスを使用される業者さんにも容器を買っていただいておりますが、出店先を聞き取りして、範囲外で使われるようなら充填をお断りしています。
根拠となる告示「平成9年通商産業省告示第122号」の情報有り難う御座います。確かに、その告示に間違いないと確認出来ましたが、私の方で「平成9年通商産業省告示第122号」全文が載せられているWebサイトを見つける事が出来ませんでした。
結局、キャンピングカー等の「保安業務に係る一般消費者等の供給設備及び消費設備には原則として三〇分以内に到着し、所要の措置を行うことができる体制を確保すること。」が実現されないまま充填されて居られる事業者様(又、その事業者の関係者様)からの回答はありませんでした。
素人である私が、何を書いても某販売店従業員さんの役に立つとは思えませんが、「平成9年通商産業省告示第122号」検索の中で「経済産業省 平成17・03・16原第8号」大臣通達を見つけました。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分に係る 審査基準等について 平成17年4月1日」http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa746.pdf
この中には、同省が各一般事業者に於ける保安業務規定のひな形として「保安業務規程( 例 )」が記されています。
例4 (緊急時対応)
一 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
一般消費者等からその事実を通知されたとき、委託者である液化石油ガス販売事
業者に当該事実を速やかに連絡するとともに、以下の措置を行うこととする。
イ 電話等の通信手段により、一般消費者等に対し適確な助言等を与えること。
ロ 出動の際には、必要な機材を携行し、可及的速やかに(又は、原則30分以
内に)現場に到着し適確な措置(点検。調査、何らかの措置が必要な場合の委
託者等への連絡、安全が確保できた場合の復帰作業等)を講ずること。
「平成9年通商産業省告示第122号」の全文を見ていないので憶測が混じりますが、「一般消費者等からその事実を通知されたとき」必ずしも「原則30分以内に現場に到着し」適確な措置を講じなくても、その事実を通知された時に・・・(それは恐らく電話で通知されると思いますが)「ボンベの元栓を閉めて使用は中止して下さい」と伝えられれば緊急時対応は完了した事に成るのではないでしょうか?
一般消費者からの「液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある」と通知される事実とは、キャンピングカーでの事例として考えると私の貧困な想像力の中では、「ガス臭いです」位しか思い付きません。勿論、「配管から火が出ています」とか「爆発しました」等も在るでしょうが、それは液化石油ガスの保安機関に電話するより前に119番している筈です。
ネットワークでの常時監視が義務化されていない中での、緊急時対応とは、当に「一般消費者等からその事実を通知されたとき」にしか起こり得ません。万が一、キャンピングカーでガスを消費する一般消費者が・・・ガス漏れを発生させようが、燃えようが、爆発しようが、保安機関としては「一般消費者等からその事実を通知されたとき」にしか緊急時対応は発動しないのでは無いでしょうか?それが、「ガス臭いです」と云うレベルなら、当然に使用の中止を通知し一般消費者が口頭で承諾すれば緊急時ではなくなります。序でに助言として、「どこか信頼出来るガス屋さんで配管の漏れを見て貰う迄は絶対使ってはダメですよ」と伝えられればミッション・コンプリートです。体積販売(メータ売り)の大部分の御客様にした処で同じ筈です。緊急時対応とは、当に「一般消費者等からその事実を通知されたとき」にしか起こり得ません。ま、メーター機の機能として・・・長時間少量消費でガス漏れ検知や、中量消費でも時間が長引けばガス火の消し忘れ検知や、短時間大量消費で管破損検知や、地震の揺れ検知等々で・・・ガスを遮断する事で、「ガス臭い」と云う通知の他に「ガスが出ません」と云う通知が加わるのでしょう。
この引用の経産省が作った・・・ひな形では、緊急時対応として「イ 電話等の通信手段により、一般消費者等に対し適確な助言等を与えること。」で目的が果たせたら、それでも尚、確認に行く必要性を示してはいません。一般の保安機関の「保安業務規程」が所轄官庁のひな形通りで在ればお咎めは無い筈だから、この例示の通りで良いのでは無いのでしょうか?
・・・と、充填して下さっている充填事業者の方は考えているのでは無いでしょうか?
取り上げて頂いたことに大変恐縮しております。
早速、内容にありましたが、「有資格者が例示基準に定める手順により適切に漏えい試験・調整器の圧力確認を行う事」というのはLPG充填所において常駐しなければならない保安係員はその有資格者になります。
ですからそれはその為に有資格者を置くこてとは言えずいないこと自体がおかしいことになりますので問題ないかと思います。
某販売店従業員様のコメントにありました20㌔圏内30分以内というしばりはわが県にもあります。
しかしながら質量販売にて使用される事が主であるお客様は所謂テキヤ(言い方が相応しくないかもしれません)が主でありその方に対して20㌔30分のしばりはほぼ無意味といえます。
内容がこんがらかってしまいましたが、液石協会や行政がもっとも懸念しているところはCO中毒による事故ではないかとの私の見解です。
その為、密閉空間での使用が限りなく少ないであろうテキヤさんに対しては肝要な対応であると感じております。
私が言いたい事の内容はわかり難いでしょうが質量販売においては使う方のかたも所謂「プロ」という認識ではないでしょうか?ということです。
法を厳密に解釈すればするほどしばりは増えますが、わが県では(かなり法に対するしばりは厳しい方の県)そういう感じで質量販売には肝要だと思っております。
どうやら行き違いになってしまった様で・・・
元記事の主旨も、その元々の記事の主旨も、キャンピングカーで使うボンベへの充填を断られる事例が増えている事が発端でした。
私自身も便利に使っていた自宅に最も近い充填所に断られましたから・・・
ナンとか時代の流れに抗って、アウトドアで使える便利な燃料としてのLPGボンベへの充填継続に期待を繋いでみたのですが・・・どうやら将来では難しいようです。
トヨタ自動車もタクシー用LPG車の製造打ち切りまでのスケジュールを公表しましたから、今後LPGはガスメーターを使う体積販売に完全移行していくのだろうと思います。
私自身はLPG依存度の低いキャンピングカーに買い換えたし、キャンピングカーの業界はLPGへの依存度を下げべく設計変更を行っている処です。
今後は、LPGボンベは諦めてカセットガスやキャンプガスに移行していくしか無いのでしょうね。