[2020年7月14日 更新]
1956年(昭和31年)、都立高校入試がそれまでの国語・数学・社会・理科から、9教科で行われることになった。
実は当時、9教科入試を行う公立高校は珍しくなかった。
しかしこれは短命に終わった。
1966年度をもって9教科入試は終了し、翌1967年度からの学力検査はなんと「国語・数学・英語」の3教科入試に変わる。
2020年度、9教科入試を行う公立高校はない。
9教科入試が短命に終わった理由の一つが「実技教科のテストが簡単すぎる」という点。英語や数学を頑張るより実技4教科を頑張った方が短時間で得点につながるから(公式発表ではなく、あくまで私の見解)
◆3教科入試の始まりと終わり
1967年(昭和42年)から都立高校入試は3教科になった。
この年の入試日は2/13(月)、発表は2/17(金)というスピード採点。当時は国語の200字作文などもなく採点が楽だったということもあろう。
学力検査の時間割は
9:30-10:30 国語
11:00-12:00 数学
13:00-14:00 英語
1教科60分もあったが、3教科なので入試は短時間で終わる。
当時は英語のリスニングもない。
なおこの年の入学考査料(=受験料)は1,000円。
なのだが、この後に大幅なディスカウントが起こる。
1973年度(昭和48年)の受験料は350円! 破格だ。
それから500円に値上げされ、1981年度には1,000円と2倍になる。
その後1,500円、2,100円と値上げが続き、2001年度(平成13年)に2,200円に値上げしてから現在に至る。
この3教科入試は1981年度入試まで続くが、学校群制度が廃止されグループ合同選抜制度に変わるタイミングに5教科入試になった。
学校群制度などの詳細はWilipediaをご覧いただきたい。
細かい変更はあったが、ここから現在の5教科入試に至るのだ。
◆普通科の推薦入試はない?
現在当たり前のようにある都立高校推薦入試。
グループ合同選抜制度が導入された当時は、「農、水産、工、家庭」の学科のみで実施。普通科高校では推薦入試がなく、一発勝負だった。
現在のように「通知表の点がいい子が、1~2ランク下げて安全な都立高校を受ける」ということはできなかった。
◆通知表は相対評価
2003年度の都立改革で、通知表が絶対評価になったのを覚えている読者もいよう。
それまでの通知表は相対評価。
「5」と「1」がその中学校の生徒の7%、「4」と「2」が24%で残りが「3」と決まっていた。中学校長はその成績一覧を提出せねばならず、不正はできなかったのである。
例えば1学年100人の生徒がいる中学校では、「5」は7人までしか付けられない
中間・期末テストで100点、全部の提出物を出した子が9人いたとしても、「5」がもらえるのは7人だけという仕組みだ。
なお1967年当時は「技術家庭科は男女それぞれで上記の割合にする」と決められていた。いまでは考えにくいね。
◆今の入試制度を「吉」と考えよう
絶対評価の導入により、現在では通知表の点が取りやすくなった。
導入直後の感覚だと、平均の調査書点が2~3は上がったように思えたものだ。
絶対評価のいいところは、結果さえ出せば同級生にどんな優秀な奴がいても「5」が狙えるということ。
これを「吉」ととらえ、通知表の成績向上に臨んでもらいたい。
都立に入る! ツイッター 毎日役立つ情報。ミンナニナイショダヨ





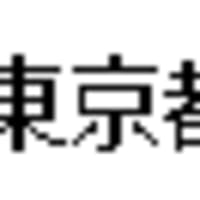





コメントを投稿するにはgooブログのログインが必要です。