Because it's there.
山岳事情:登山のリアル×名誉棄損
エベレスト登頂について、ちょっと最近ギモンだったので。
ここ数年、エベレストに登ろうって芸能人&テレビ企画が多いですけど。
その「登ろう」って理由はナンなんだろう?なんだってソンナ企画ワザワザするの?
って話をする前に・・知らないと「?」が解けないエベレスト&登山ちょっと簡単まとめを、笑
1.エベレストの登山ルート
どの山も共通することですが、ノーマル・ルート=普通の登山道があります。
このノーマル・ルートは最も危険度が低い、遭難可能性が低いルートです。
逆に難易度が高いのはバリエーション・ルート、道を見失いやすい+危険地帯が多く登山技術が要されます。
それより難しいのは未踏ルート=ルート開拓です、ファイナリスト・クラスのみに許されることで素人だと遭難死直結です。
エベレストの場合、
ネパール側からの南東稜ルートがノーマル・ルートにあたります。
チベット側からだと難易度がUP。
2.エベレスト登山適期
春が適期です、理由は天候安定期+雪と氷が少なめな時季だから。
標高3,000m以下=100mごと0.5~0.6度
標高3,000m以上=100mごと1度
気温はコンナ↑カンジに標高ごと変化します、ようするに標高が高くなるほど気温低下するってワケです。
(気温変化は緯度も関係=同じ標高2,000mなら奥多摩@東京より北海道の山の方が寒くなります。)
日照条件によっても気温が変化=北斜面は南斜面より気温が低くなります、地形に影響されるってことです。
湿度や風速も体感温度に影響=濡れた体に風が吹けば気化熱で体温が奪われる→低体温症など体調悪化=死。
↓
標高・斜面の方角・地形・天候により同じ山でも難易度=遭難危険性が変化するってことです。
たとえば富士山も積雪期は難易度まったく変化します。
コンクリート硬度に氷化した雪面はアイゼンもピッケルも効かず、シャッターぶっ壊す豪風に吹き飛ばされます。
そして遮るものない滑落の摩擦で身ぐるみはがれ体温を奪われて、そんな全裸凍死体が毎シーズン無残な姿で発見されます。
そのため唯一の通年営業している山小屋は宿泊予約がくると経験値や装備・レベルを聴いて中止させるべきか考えられるそうです。
エベレストは標高8,848m、標高0地点と山頂の気温差は単純計算で約マイナス73度になります。
↓
ようするにホトンドの地点が通年零下、
それでも春は天候も恵まれやすいため登山適期とされているワケです。
3.エベレスト登山は入山料がカナリ高額
ネパール政府は「標高5,300mにあるベースキャンプより上に行くものは入山料を収める」と定めています。
これは登頂してもしなくても同一料金です。
↓
2016年5月の南東稜ルート概算=125,00ドル=約1,365,000円(110円/ドル)
入山料は2015年度の改定により減額されました。
ネパール側+適期の春+ノーマル・ルート南東稜は1人あたり=11,000ドル+諸経費1,500ドル。
諸経費の内訳は=リエゾン・オフィサー、医療サポート、ロープ設置など各登山隊単位で掛かります。
エベレストにおけるリエゾン・オフィサーはネパール政府代理人で、登山隊の監視役として付けられます。
↓
詳しい計算式を書くなら、
入山料11,000ドル+(諸経費1,500ドル÷登山隊人数)
これ↑が1人あたりの費用となるんですけど、この入山料は2015年度改定より前は約250万円でした。
とはいえ改定以前は7人グループで申込むと780万円になる割引制度があり=約111万円/1人でした。
三点とりあえず簡単に書きましたけど、
たぶん3の入山料について驚かれる方もあるかと思います。
この入山料+諸経費の負担が冒頭=芸能人やテレビ企画による登山の問題を起こしています。
で、なんで芸能人やテレビ企画が問題になるのか?っていうと、山の原則が無視されてるから。
4.自助と相互扶助
登山はスポーツかもしれません、が、他種目と違うのは生死の危険度が高いことです。
この危険性のために「自助と相互扶助」という原則があります。
自助=登山は自己責任、自分で責任をとれる以上のチャレンジはするな。
相互扶助=もし遭難者を見たら救助に協力する、が、救えなくても責任は遭難者本人。
この↑自助&相互扶助は山の常識です、山ならどんな低山でもアタリマエ。
なので山岳救助隊員がもし遭難者の命を救えなかったとしても、責任は遭難者本人です。
なぜなら山=危険=遭難可能性があることが大前提で、だから自助と相互扶助という原則があります。
低山でも遭難ポイントがいくつもあります。
今年のゴールデン・ウィークも遭難事故が多発しましたけど、低山での事故が多くありました。
標高が低い=難易度が低い、っていうのは山を知らなすぎるカン違いだ~ってことは上述1・2の応用で解かるかと、笑
エベレストのルート+費用+自助と相互扶助
っていう前提を挙げたところで「エベレスト登山」ここんとこの風潮疑問。
まず・テレビ企画で遭難死したら誰が責任とれるの?ってことです。
どの山でも遭難の危険があります、大ケガしても救助の人が行けない場所もあり見棄てざるを得ない時もあります。
遺体を回収されないことも当然ありえます、実際にエベレストではポイント確認の道標にされている氷漬け遺体もあります。
死だけじゃなく遺体放置の可能性もある、それを理解して山を人生に選んでいるのが職業的登山者=山ヤさん&プロクライマーです。
危険を解かりながら山に登った=他人に迷惑をかけてはいけない、だから遭難しても自力で下山することは当りまえ。
そういう自己責任=自助の覚悟と準備が山ヤさん達はしっかりある。
だから実際、遭難しても自分で応急処置して自力で下りて来るワケです。
こうした「自己責任による登山」は本来、登山するなら誰でもアタリマエにする心構えでもあります。
そんなふうに山で死んでも後悔しないと覚悟して、芸能人が山に登るでしょうか?
本音のトコロは「テレビ企画だから」芸能人の仕事として登っている、それがアタリマエだと思います。
そういうアタリマエはあっちゃいけないことじゃないかなあって思うんですよね、
「生死をテレビ企画にしている=命を売り物にしている」
視聴率とるために「生死の際を映したい」それがテレビ企画の本音なんじゃないでしょうか?
そういう番組は登る芸能人はヒロイズム化しやすいし、観ている方も感動してみたりしやすいわけで、
「命を売り物にすることを感動している」
っていう風潮が疑問なんですよね。
って書くと反論する人もあるかもしれないですけど、そういうテレビ企画で登山した芸能人が死んだら・どんな反応しますか?
山で死ねて本望だったなあ、
なんてこと遺族に言えませんよ?だって「テレビ企画で」死んだのであって「山で」死んだんじゃナイですから。
だからもし「山に好きで登って死んだんだから文句言うな」なんて言ったら遺族の方に刺されて当然ですよ?
だってその人は「芸能人=テレビ界で生きる人」であって「山ヤ=山で生きる人」じゃない。
プロクライマーや山ヤさんも山で亡くなることがあります。
そのとき遺族の方は覚悟ごと呑みこんで受けとめます、「山で生きる人」だから「山に死ぬ」ことも覚悟なわけです。
山は自助と相互扶助、もし救助されなくても恨みっこなし、誰のせいでもなく本人の判断ミスと運の尽きだと呑みこむ。
なにより遭難した人のために救助者が死ぬなどあってはいけない、そうした巻きこみ二次災害は遭難者本人への名誉棄損です。
↑
そこらへん勘違いした漫画家がいるんですよね、遺族が遭難救助隊に土下座させるなんてシーンを描いて。
遭難事故現場に遺族を救助ヘリで連れて行く~なんて描いてるあたり山と救助のリアルを知らない人間だなと。
ああいう安易なヒロイズムは本職の救助隊員さんたちに迷惑をかけます。
そういうヒロイズムが誇大化したのかなあって思ったのが「芸能人の登山理由」への疑問です。
“福島への応援としてエベレスト登頂しました”
ああいう考え方は傲慢に想えます、だって「自分がやりたくて危険に踏みこむ」のが山だからです。
ただ「自分がやりたいこと」を正当化するため「応援として」を利用していると思えてしまいます。
エベレストの登山費用は高額です、その費用集めに登山家たちは誰もが苦労します。
そのためスポンサーを探す方も多いです、それを「テレビ企画」や「チャリティー」にすればスポンサーがつきやすいのも現実です。
いわゆる商業化・ショービジネス化=「有名になるor金を得るチャンス」としての登山、これだと資金もサポート隊員も集めやすくなります。
そこでの目的は「山」じゃなく「著名度or金」賭博のようなもんです、だからこそ自費で登る山ヤさんもいます。
山野井泰史さん、って方がいるんですけど世界最強のクライマーと言われていました。
未踏ルート開拓、単独無酸素登頂、北壁踏破、偉大な記録たくさんな山ヤさんですけど、山好きじゃないと知らないかと、笑
なんであまり知られていないかって言うと「宣伝が下手というかしたくない」ようするに「好きなことやってるだけ」だから。
商業化したら山に対して純粋じゃなくなる、登ることに理由づけしたら山に失礼だ、そういう考えをされる方です。
そんな鉄人かつ哲人な方ですけど、雪崩からの自力下山で負った凍傷から指をいくつか失ってしまいました。
それでもトレーニング黙々とされているんだとか。
ただ山に登りたいから登る、山の危険性を越える努力しても良いから登りたい。
ただそれだけで山野井さんはトレーニングを続け、山を執筆&撮影し、奥さんと奥多摩で静かに暮らしています。
田中陽希さん「グレート・トラバース」っていう企画で日本百名山・二百名山を「自力」で踏破した方です。
延々ほんとに歩き続けます、山も一般公道も、海はカヌーで自力で渡る、カメラマン一名だけ交替で付いた?ってカンジ。
これはホント大変だろうなと…期間長いし体力保持も難しい、タイムロスすれば季節の変化で登頂の難易度も変ってしまう。
エベレストなど八千峰みたいに目立つわけもなく、テレビ企画でもスポンサーつこうが普通あまりやりたくないんじゃないかと。
ただ淡々と登って走る姿を追うだけのドキュメンタリー登山です、
そういう「淡々と」に皆が応援するわけなんですよね、励まされて病床から回復→登頂して田中さんに挨拶していた方もいました。
応援の人から差入されることも多くなって、でも「重量やカロリー計算などあるので」という理由で断ったりもするわけです。
たしかに登山の時はザックの重量は計算がある、標高変化と腹具合もある、そして「特別視は違う」ってことだそうです。
自分はただ好きなことをしているだけ、褒め讃えられることではないしヒーローじゃない。
そういうこと言うアタリ本物の山ヤなんだなあ、と思いました。
それは彼自身への戒めでもあるだろうし、感謝ある謙虚なんだなと。
ほんとうに「好き」だから感謝も謙虚もそこにある、それは「山」が彼の本分だからこそです。
山で記録を作ることは「ただ登りたい」にくっついてくるオマケみたいなもので、人の賞讃もオマケでしかない。
そういう単純さが山ヤさんたちにはあります、
この単純な「登りたい」が無くなってしまうと「山で無理をする」になり遭難事故にもつながりやすくなる。
だからナンラカの目的=名誉欲や金銭など報酬のために登ることを忌むワケです、遭難事故はホント迷惑だとプライドを持っているから。
だからこそ疑問になるわけです「福島のため」ってなんで言っちゃうのかな?と。
ただ好きで登りますって登っても同郷なら「同郷人が登ったんだ、すごいなー」ってなる、それだけで良かったろうに?
それを「ふるさと福島のため」なんて宣伝すると「おまえのために俺は苦労してやるんだ」と押し売り的になってしまう。
そういう押し売りは山の世界ではしちゃいけないNGなんですよね「登山は危険行為=他人に迷惑をかける可能性」だから。
なぜ登山で感動するかっていうと「危険行為を乗り越える」からで、だからこそ「感動を与える」目的で登っちゃいけない。
もし「感動を与える」ことを目的にしたいならエベレスト登山なんて選ぶべきじゃない。
危険とは=他人と生命に迷惑をかける可能性です、その迷惑によって「与える」感動などニセモノです。
被災地支援を目的にすれば「立派だ」と讃えてもらえる、金も集まる、どっちも現実に得られる利益です。
その利益についても周囲は反対意見を言い難いっていう特典もあります、だって「被災地支援=人道的行為」だから。
けれど遭難したら逆に支援を求めることになります、そうした現実にたいして「人道的支援」を目的と言っても矛盾でしかありません。
人道目的の登山と言えるのは山岳救助隊の方くらいです、が、そんなことご本人たちは決して言いません。
じゃ何すればいいのか?っていうなら例)その莫大な費用と時間で「福島の現実」を歩いて撮って記録する。
芸能人ならその本分で応援すれば良い、なぜなら「その人にしか出来ない」から。
同郷人にしか見えない本音がある、同郷人だからこそ映せるリアルな現実があるはずです。
復興の手伝いにいつも行っているなら、その記録を撮って記録映画として発表すればリアルな感動が生まれるのに?
エベレスト4回分の時間と費用をそこに懸けたなら、どんだけ素晴らしい記録映画を遺せたろう?残念だなあ…って思います。
ふるさとの哀しみと希望、そこに生きる人の心で遺せたなら?
それを国際映画祭に出品したら、どれだけの支援が福島に向けられるだろうかと。
そういうことは「芸能人」である彼の本分、彼にしかできない応援かなと。
だからモッタイナイと惜しみます、その4回分の費用と時間。
なんでソウイウ発想を彼自身しないのか?は、言ってしまえば「目立ちたがり」な本性だろうと、笑
地味に地道に映画こつこつ撮るよりも、世界最高峰エベレストに一発登って当てる方がヒロイズムは満ちる。
たしかにエベレスト登頂は大変です、が、ノーマル・ルート+ガイド付きなら体力適性と資金あればいけるのも事実です。
ある意味で記録映画はずっと大変かもしれません、映画技術を学ぶ労力、製作メンバーの人間関係、簡単なことじゃありません。
その「簡単じゃない」は一過性ではなくてズッと付きまとう苦労です、そんな苦労が隠されている作品こそ無限大の力を生めると思います。
ただ「登る」じゃない、大義名分モットモラシイ正当化は「山」に名誉棄損だなと。
そういう人は事故ると他人に責任を被せたがります、そういう迷惑登山は哀しいです。
ただ好き、それだけの理由に覚悟+準備してコレカラの山シーズン楽しめたらいいですね、笑
 さぁ広めよう24ブログトーナメント
さぁ広めよう24ブログトーナメント←ギモン広めてください。
 にほんブログ村
にほんブログ村  さぁ広めよう25ブログトーナメント
blogramランキング参加中!
さぁ広めよう25ブログトーナメント
blogramランキング参加中! 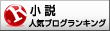






 にほんブログ村
にほんブログ村


















































