前回台湾に行ったのは2002年、台北であった。ほんとうにしばらくぶり、今回は南部に行くことにし、「秋夕」(旧盆)の9月初め、台南、高雄を旅した。前回は団体ツアーだったが、今回は個人旅行である。空港がある高雄に宿を取り、高雄と台南に1日づつ、3日目はぶらぶら気の向くまま、ということにした。
しかし不案内なことは外国の他の町と同じなので、やはり案内人を頼んだのだが、今回はずいぶん高くついた。また3日目の独りでぶらぶら歩きというのが予想外の大変な目にあった。これらについてはあとでお話しよう。
台湾にはどんな町にも「歴史博物館」があるようだ。台北はもちろん、台南や高雄、そして霧社事件で知られた山奥の霧社にさえ歴史博物館、記念館があるようだ。
まず訪れたのは台南の国立歴史博物館である。


真っ先にあったのはたくさんの原住民族の資料であった。16の原住民が認定されている。原住民は台湾の重要な民族として最大の閩南(福建)系と全く同じように扱われ、社会的進出も差別なく行われているようだ。
それは日本時代からの伝統だったそうで、当然のこととうなずける。




集落の様子は青森の三内丸山遺跡を思い起こさせる。きっと海と航海を介して日本の先史時代ともなんらかの繋がりがあったに違いない。
上の首飾りは「黄金銅製」と書いてあった。下は多分貴石で、中には赤い透明な石も含まれていた。ルビーだったのかも知れない。これらを作った技術は大変なものだ。
資料は時代順に展示してあった。続いてオランダなどの西洋列強、大陸の明、清時代の資料があったが、これらには余り興味が湧かなかった。続く日本統治時代では、われわれが期待しているような社会制度、インフラ整備などの貢献についてはあまり見るものがなかった。
日本の撤退から蒋介石軍の進駐、そして二二八事件関連の資料はふんだんで、初めて目にするものも多く、衝撃的ですらあった。台湾の人々にとってはいまなお最大の事件なのだろう。

これは日本の撤退のち進駐してくる国民党軍の到着を喜びに溢れ旗を持って待つ生徒たち。この期待は無惨にも破られることになるのだが・・・

全国で荒れ狂った二二八事件の凄惨な現場の一つ。上のウィキペディアによく似た写真があり、民衆による官公署の焼き討ちらしいのだが、軍による民間施設の襲撃、新参の大陸人による台湾人の略奪のようにも見える。案内人はこの辺りからとても口数が少なかった。長年の恐怖の白色テロの時代もあり、今なおいろいろと判断に迷うことが多いのだろう。
たしかに、この時期最大の被害者は台湾人だった。しかし蒋介石の軍事独裁の圧制の時代は他面台湾が大陸の共産党に呑み込まれるのを防いだ。また蒋介石はスターリン、ルーズベルト、毛沢東にだまされ翻弄されて大陸から追い払われたのであり、さらに国民党も次世代の蒋経国、李登輝時代から大きく変わっている。しかし馬英九は親中ながら反共を宣言しており、蔡英文は離中だがリベラル色が強い、などなど、われわれにはとても評価が難しい。しかも当時のわが政権や民主党米国は1970年代に大陸政権と天秤にかけて台湾を裏切っている。

台湾人に暴虐を働き略奪する国民党軍と彼らが連れてきた大陸の外省人。
この後、以後先端工業国になるまでの70年に及ぶ中華民国台湾の業績が連ねられていた。
博物館を出る時一群の青年男女に出会った。「こんな若い人たちが博物館に?」とやや不審に思って案内人に「かれらは『認識台湾』の勉強にきているのだろうか」と尋ねると、「そう思う」と答えた。
次に行ったのは市内の「飛虎将軍廟」である。先の大戦で台湾も戦場となっていたのは恥ずかしながら初めて知った。
その時戦闘機の日本兵がこの町の上空で被弾しながら町を避けて墜落させ、落下傘で脱出したものの機銃掃射で落下傘が破れ墜落死した、
その兵士が死をもって自分らを守ってくれたと感じた地元の人々がここに兵士を祀ったのである。6名で毎日お世話くださっているそうだ。兵士は「杉浦茂峰」、20才を過ぎたばかりだったそうだ。

翌日は高雄を回った。下は市立歴史博物館の昔の写真。戦前は市役所だった。今も建設当時と彩色以外なんら変わっていない。中は立派な造りで、よく手入れされていた。

展示資料は市独自のもので、高雄における二二八事件に関するものの他、とくに戦前からの教育の歴史に関するものが多かった。ここでは戦前の日本の貢献が大きな部分を占めていた。

戦前の児童の遠足風景。身なりもきちんとしている。日本の昭和40年代かと見紛うほどだ。よい学校生活を送っていたのだろう、と一安心した。

戦前、高雄にはこのようなりっぱな小学校が建てられていた。(私の学んだ学校よりはるかに立派だ!)

日本の総督府は教育にはずいぶん力を注いだようだ。毎年のように学校を建設している。
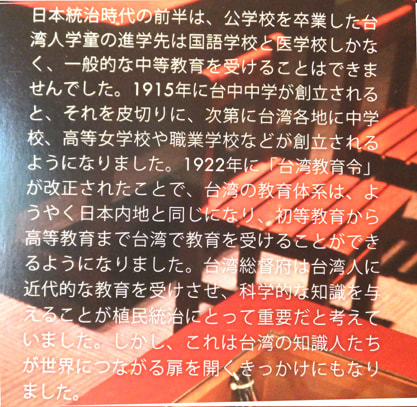
これら諸学校は台北帝国大学の後継である国立台湾大学を初め現在も立派に生き残っているようだ。
埠頭に行く途中街中に一段と緑濃い木立に囲まれた立派な建物があり、案内人に尋ねると「昔の高等女学校、今は市随一の名門女子高で、女性が医師になるコースとなっている」と答えた。
埠頭に近く、古い戦前の建物群を残した一画があり、いま台湾で流行となっている、若い世代が古い建物に「リノベ」を行って独自の特色あるカフェやミニホテルを作っているところに案内された。その一つであるこのカフェは、「読書喫茶」とでも言うべきか、しかしもう80年以上前の建物である。主人は日本に関心が深いらしく、下の「薫風」という雑誌も発行しているそうである。



さすが80年の古さはあるが、とても清潔で整っている。


本棚の本は多分日本関係のものばかりだろう。
この主人が発行している「薫風」は、今回はおそらく「モガ」がテーマだったようだ。
静かな落ち着いたひとときを過ごした後、港に向かう。

高雄港、かつての軍港の面影は見当たらなかった。ここは最も繁栄している「ばなな埠頭」と呼ばれる埠頭。横浜みなとみらいの倉庫群と同様、かつての巨大なばなな倉庫が改装されて食品店やレストラン、雑貨店となり賑わっていた。
余りに広大なので、食べ物を扱っているほんの入り口付近しか歩き回れなかった。

驚いたことにこれはわが「おでん」そのものではないか! 宿に戻ってからの酒のつまみにと少しばかり買った。日本のコンビニと同様の入れ物に汁と一緒に入れて密封して渡してくれた。味は・・・ 申し分なかった。残したスープが今なお心残りである。ついでに酒は金門島の56度の高粱焼酎をコンビニで買い3日間で1本消費した。

これはすべて干し肉である。何の肉か、どうやって食べるのか、見当もつかない。
ならんでいる食欲をそそる珍しい食べ物は数限りなく、あんまり列挙するのもナンだが、
下のこれはまた日本のしゃぶしゃぶ風鍋料理そっくりである。
台湾料理といえば 大きな円卓に大皿が何皿もならぶ・・・とばかり思っていたが、この食堂街の食べ物屋はそんな思い込みを打ち破りとても新鮮であった。

そろそろ宿に帰らねば・・・
宿は全館禁煙で、タバコを吸うにはたとえ深夜であってもその都度外に出なければならなかった。
となりに生演奏の音楽バーがあり、夜おそくまで青年男女で賑わっていた。
夜でカメラのピントが甘くなってしまった。小さな画面のステレオ写真でご紹介する。

線香花火をする少女たち。そうだった、花火はお盆の風物だった・・・

バーの青年客たち。となりのホテルから一服しに出てきた日本人客、とすぐに見抜いて、親指を立てて挨拶してくれた。

























