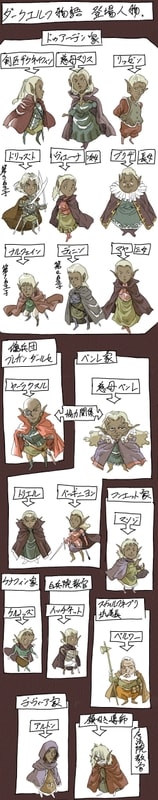メンゾベランザン(ダークエルフの都市)の貴族階級に属するダークエルフは、然るべき年齢に達すると、その資質に応じて3つの進路が示されます。
一つは、尼僧院。
これは、主に支配家分家の中でも最も優れた女子が、直接蜘蛛の女王の秘技に接し、且つその教義を深く理解する事によってメンゾベランザンの指導者になるべく教育を受ける、いわばエリートコースです。
一つは、魔法院。
これは、フォーゴットン・レルム(ダークエルフ物語の舞台となる世界)における、一般的な魔法を習得するための教育機関。
この世界では、戦闘に関しては魔法使いの技の方が戦士のそれよりも圧倒的に有利のようです。
尼僧院とは違い、魔法院には才能が認められれば男のダークエルフでも入学が認められます。
そして、もう一つが白兵院。
ここは、まぁ、士官学校みたいなものでしょうか。
有能な指揮官、あるいは頑健な兵士を育成すべく、日々苛烈な訓練が施されます。
この3つの教育機関のいずれかを経て、ダークエルフの子弟は立派なメンゾベランザンの市民へと成長していく訳です。
しかし、これら教育機関の果たす役割というのは、なにも優れた人材の育成に限った事ではなく、むしろ、然るべきメンゾベランザンの市民にふさわしい道徳観念を刷り込む事の方がより重要であるとも言えます。
つまり、悪の思想教育。洗脳ですね。
作中では、邪悪なダークエルフの子供たちが、生まれながらにして邪悪な精神の素養をことさら顕著に有しているとは、必ずしも断定していません。
社会との接触によって次第に悪に染まってゆく過程というのを、もしかしたらサルバトーレ(ダークエルフ物語の作者)は、この教育期間によって浮き上がらせようとしたんでしょうね。
それは、現代におけるイスラム過激派とテロリスト養成過程の問題や、紛争地帯における少年兵士等の問題を物語の中に反映させた、若干安易なメタファーであるとも言えます。
なんといっても、悪を行使するための規律ある悪の社会、なんていうのは、やっぱり無理がある訳です。
したがって、この設定を現実世界に反映させた物語をやろうとしても、まず間違いなくひどい結果を招いた事でしょう。
しかしです。
こうした無謀な設定も、ファンタジーの世界では大いに輝きを放ってしまうから不思議です。
それは、おそらく神という存在が実態を持って人間の世界に接触しているからなんでしょうね。
あとは魔法ですか。
こうした超常的な力が社会の一定の秩序を維持していく事によって、一見、突拍子もない悪の社会の設定も、破綻なく物語に組み込む事ができた訳です。
現実の世界では、歴史上、いわゆる悪徳を励行した国家(指導者と言うべきか)というのは、すべからく破滅しています。
市民が彼らを見放しちゃうんですね。
私が子供の頃に見た、確かドラえもんだったと思うんですが、古代エジプトのピラミッド建設をのび太が見に行く話だったと思います。
そこでは、多くの奴隷たちがムチを打たれながら、ピラミッドの石材を引いている姿が描かれていました。
「こうした重労働がピラミッド完成までの30年間にわたって続き、その間の死者はエジプトの砂漠に累々と云々・・・」 とありました。
しかし、こうした歴史の見方も、いまでは随分変わってきたようです。
ピラミッド建設事業が、ナイル川の氾濫期の公共事業的役割を担って雇用の創出にあたったとか、実際の労働には貴族の子弟も数多く参加していたとか。
まぁ、素人の私には、実際にどちらが正しいのか、確信を持って判断する事は難しいんですが、それでも、ムチャクチャな強制労働が30年続くことよりは、はるかに実際的な考察のように思えます。
だって、そんなムチャクチャをやってたら、まず間違いなく反乱が起きますよ。
スターゲイト(ローランド・エメリッヒ監督のSF映画)でも似たような描写があったじゃないですか。
というわけで、実際には不可能な設定でも、ファンタジーという媒体を用いれば、何とも面白い仕掛けに化けるという、その証左がダークエルフ物語ではないでしょうか。
ドリッズトの暗黒の学生時代は、真っ当な学生物語を超絶する何かがあるように思えます。