現在、大阪市立中学で非常勤講師をしています。現場にいるだけに、大阪の公教育の危機を感じています。次の文章は『思想運動』に寄稿したものですが、できればお読みください。
「君が代」条例からメリット・ペイまで
―維新流公教育の壊し方―
本年8月2日、大阪市吉村市長の発言に激震が走った。全国学力・学習調査(全国学テ)の結果が政令指定市2年連続で最下位だったことを受けて、来年度から全国学力テの結果を校長や教員の人事評価とボーナスに反映させ、学校予算もそれに応じて決めると檄を飛ばしたからである。市民の中には、学力を向上させるためならと歓迎する向きもなくはない。
しかし、実は、これは子どもの学力の問題ではなく、それを利用した人事評価による教員格付けと学校の格付け、いわば橋下徹時代から描かれていた既定の路線を押し進めるものに他ならない。つまり学テ結果が政令都市中最下位という情報で危機を煽りながら維新流「改革」を進めるという、まさに維新お得意の“ショックドクトリン”なのである。
かつて吉村市長は、ツイッターで「今の教員給与システムは信じられないよ。完全に共産国家 。」(2017.7)と、さも教員給与システムが前時代的であるかのような情報を流している。
彼らの狙いは、11月14日に開催された大阪市総合教育会議でさらにはっきりする。総合教育会議とは、2015年4月から設置された、首長と教育委員会が教育行政の指針となる大綱を策定する会議である。ここで大活躍をしたのが、橋下時代に招聘され教育委員さらには大阪市教育長となり、学校選択制や全国学力調査の学校別結果の公表を導入した、あの大森不二夫氏である。現在も大阪市特別顧問として維新流「改革」の旗振り役をしている。その大森不二夫特別顧問が、吉村市長に意向を受け、全国学力調査だけではなく、「経年テスト」(大阪市小学校)や、「チャレンジテスト」(大阪府統一中学テスト)までを用い、教員の人事評価に反映させる制度案を持ち出してきたのだ。すでに大阪市教育委員会は制度設計を始め、来年度から試行実施を始めるつもりである。
「数値」、つまりテストの点を目標に掲げた過度の競争主義が何をもたらすか、イギリスやアメリカの先例ではっきりしている。いじめ、排除、不正、格差の肯定、さらには、地域破壊、教育関連業者との癒着、およそ教育の理念とは反するものばかりである。それがわかっていながら、なぜ維新政治は数値による競争主義推し進めようとするのか。そこにこの問題を解く鍵があるように思う。
教員の勤務成績を反映した給与制度をメリットペイという。これを全国でも最初に盛り込んだのが、大阪維新の会が、2011年に提起した教育基本条例案であった。
話は10年前に遡る。2008年橋下府政が誕生し、彼が華々しくスローガンとしてあげたのは「教育日本一 子どもが笑う大阪」だった。そして、真っ先に手がけたのが「教育改革」であった。彼は徹底的に教員を攻撃した。教員vs市民の構図を見事なまでに作り上げたわけだ。そもそも公教育においては、子ども・保護者・市民・教員・行政それぞれ立場が違う。それだけにその思いは異なる。だからこそ共通のコンセプトを求めて対話が必要なのだが、維新政治は、その対話を阻害することに専心した。教育は政治が決めると言わんばかりであった。政治が決めたことに教員も子どもも従えというのが維新の基本スタンツだ。そして、それが、現状の教育や教員に不満を持つ市民の間で残念ながらそれなりに受け入れられていった。
次に、橋下知事(当時)は教員の管理支配の徹底をもくろむ。その時、彼は実にうまく「君が代」を利用した。大阪には、歴史や平和・人権教育を通して、「君が代」に抵抗を示す教員は少なくなかった。私もその一人であるが、徐々に強まる「君が代」強制に、卒業式では、不起立というスタイルで意思表示をし、抗っていた。そういう「空気を読まず」に抵抗を続ける教員の姿に、彼は、組織のルールに従えない教員はクビにしてやるとまで息巻いたのだ。結果、大阪に全国で初となる公立学校の教員に「君が代」を義務付ける君が代条例が成立したことはご存知の方も多いだろう。
橋下徹氏の狙いはなんだったのであろうか。ひとつは、「愛国教育」を図る安倍政権との連携。もうひとつは、たとえ理不尽なことであってもルールとして決められれば服従する教員集団作りではなかったろうか。あれからほぼ10年、現場では確かに声をあげにくい空気が生まれている。行政サイドからの(それはすでに政治からと言っても過言ではないと思われるほどだが)助言や指示の類は、忖度からか、まるで命令と同じように機能している。「君が代」条例の究極の危険性がまさに表れている。
「君が代」条例からメリットペイへ、それは、維新政治がこの10年間において一貫して目指してきた教育施策である。学校から「もの言う」少数者を排除し、子どもらを、教員を、学校を、点数というひとつの価値基準によって有無を言わせず競わせる。それが公教育にどのような影響を及ぼすか。その危険は実は測り知れない。
なぜ、今、大阪市はメリットペイを持ち出して来たのか。失敗だとわかっていながらあえてそれをやろうとする意図はどこにあるのか。ひょっとしたら維新勢力はこれまでの公教育そのものを壊しにかかってきたのではないか。教育にお金をかけないことを市民を納得させるためには、教員にも子どもにも保護者にも誰にも批判させないことが必要だ。そう考えれば納得がいく。
最後に中学3年生の声を紹介しておこう。
「学力テストの結果だけがすべてじゃない。このまま点数だけの競争になれば潰される生徒が出てきて、必ず体罰教師も増えてくる。」
体罰教師――私はそこまで考えていなかったのだが、生徒は当時者だけにこの問題をリアルに実感しているのかもしれない。
学校を格付けし、点数で子どもを序列化し、子どもにまで自己責任論を押しつけかねない維新教育「改革」は仕上げの段階に入っているのかもしれない。私たちは手をこまねいて見ているわけにはいかない。大阪では、12月22日「学力テストの点数で教員・学校を査定!?子どもをテストで追いつめるな!12.22大阪集会」を開催する。近隣の方はどうかご参加くださればうれしい。

「君が代」条例からメリット・ペイまで
―維新流公教育の壊し方―
本年8月2日、大阪市吉村市長の発言に激震が走った。全国学力・学習調査(全国学テ)の結果が政令指定市2年連続で最下位だったことを受けて、来年度から全国学力テの結果を校長や教員の人事評価とボーナスに反映させ、学校予算もそれに応じて決めると檄を飛ばしたからである。市民の中には、学力を向上させるためならと歓迎する向きもなくはない。
しかし、実は、これは子どもの学力の問題ではなく、それを利用した人事評価による教員格付けと学校の格付け、いわば橋下徹時代から描かれていた既定の路線を押し進めるものに他ならない。つまり学テ結果が政令都市中最下位という情報で危機を煽りながら維新流「改革」を進めるという、まさに維新お得意の“ショックドクトリン”なのである。
かつて吉村市長は、ツイッターで「今の教員給与システムは信じられないよ。完全に共産国家 。」(2017.7)と、さも教員給与システムが前時代的であるかのような情報を流している。
彼らの狙いは、11月14日に開催された大阪市総合教育会議でさらにはっきりする。総合教育会議とは、2015年4月から設置された、首長と教育委員会が教育行政の指針となる大綱を策定する会議である。ここで大活躍をしたのが、橋下時代に招聘され教育委員さらには大阪市教育長となり、学校選択制や全国学力調査の学校別結果の公表を導入した、あの大森不二夫氏である。現在も大阪市特別顧問として維新流「改革」の旗振り役をしている。その大森不二夫特別顧問が、吉村市長に意向を受け、全国学力調査だけではなく、「経年テスト」(大阪市小学校)や、「チャレンジテスト」(大阪府統一中学テスト)までを用い、教員の人事評価に反映させる制度案を持ち出してきたのだ。すでに大阪市教育委員会は制度設計を始め、来年度から試行実施を始めるつもりである。
「数値」、つまりテストの点を目標に掲げた過度の競争主義が何をもたらすか、イギリスやアメリカの先例ではっきりしている。いじめ、排除、不正、格差の肯定、さらには、地域破壊、教育関連業者との癒着、およそ教育の理念とは反するものばかりである。それがわかっていながら、なぜ維新政治は数値による競争主義推し進めようとするのか。そこにこの問題を解く鍵があるように思う。
教員の勤務成績を反映した給与制度をメリットペイという。これを全国でも最初に盛り込んだのが、大阪維新の会が、2011年に提起した教育基本条例案であった。
話は10年前に遡る。2008年橋下府政が誕生し、彼が華々しくスローガンとしてあげたのは「教育日本一 子どもが笑う大阪」だった。そして、真っ先に手がけたのが「教育改革」であった。彼は徹底的に教員を攻撃した。教員vs市民の構図を見事なまでに作り上げたわけだ。そもそも公教育においては、子ども・保護者・市民・教員・行政それぞれ立場が違う。それだけにその思いは異なる。だからこそ共通のコンセプトを求めて対話が必要なのだが、維新政治は、その対話を阻害することに専心した。教育は政治が決めると言わんばかりであった。政治が決めたことに教員も子どもも従えというのが維新の基本スタンツだ。そして、それが、現状の教育や教員に不満を持つ市民の間で残念ながらそれなりに受け入れられていった。
次に、橋下知事(当時)は教員の管理支配の徹底をもくろむ。その時、彼は実にうまく「君が代」を利用した。大阪には、歴史や平和・人権教育を通して、「君が代」に抵抗を示す教員は少なくなかった。私もその一人であるが、徐々に強まる「君が代」強制に、卒業式では、不起立というスタイルで意思表示をし、抗っていた。そういう「空気を読まず」に抵抗を続ける教員の姿に、彼は、組織のルールに従えない教員はクビにしてやるとまで息巻いたのだ。結果、大阪に全国で初となる公立学校の教員に「君が代」を義務付ける君が代条例が成立したことはご存知の方も多いだろう。
橋下徹氏の狙いはなんだったのであろうか。ひとつは、「愛国教育」を図る安倍政権との連携。もうひとつは、たとえ理不尽なことであってもルールとして決められれば服従する教員集団作りではなかったろうか。あれからほぼ10年、現場では確かに声をあげにくい空気が生まれている。行政サイドからの(それはすでに政治からと言っても過言ではないと思われるほどだが)助言や指示の類は、忖度からか、まるで命令と同じように機能している。「君が代」条例の究極の危険性がまさに表れている。
「君が代」条例からメリットペイへ、それは、維新政治がこの10年間において一貫して目指してきた教育施策である。学校から「もの言う」少数者を排除し、子どもらを、教員を、学校を、点数というひとつの価値基準によって有無を言わせず競わせる。それが公教育にどのような影響を及ぼすか。その危険は実は測り知れない。
なぜ、今、大阪市はメリットペイを持ち出して来たのか。失敗だとわかっていながらあえてそれをやろうとする意図はどこにあるのか。ひょっとしたら維新勢力はこれまでの公教育そのものを壊しにかかってきたのではないか。教育にお金をかけないことを市民を納得させるためには、教員にも子どもにも保護者にも誰にも批判させないことが必要だ。そう考えれば納得がいく。
最後に中学3年生の声を紹介しておこう。
「学力テストの結果だけがすべてじゃない。このまま点数だけの競争になれば潰される生徒が出てきて、必ず体罰教師も増えてくる。」
体罰教師――私はそこまで考えていなかったのだが、生徒は当時者だけにこの問題をリアルに実感しているのかもしれない。
学校を格付けし、点数で子どもを序列化し、子どもにまで自己責任論を押しつけかねない維新教育「改革」は仕上げの段階に入っているのかもしれない。私たちは手をこまねいて見ているわけにはいかない。大阪では、12月22日「学力テストの点数で教員・学校を査定!?子どもをテストで追いつめるな!12.22大阪集会」を開催する。近隣の方はどうかご参加くださればうれしい。











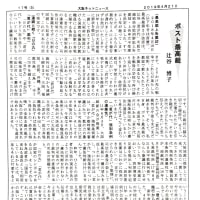
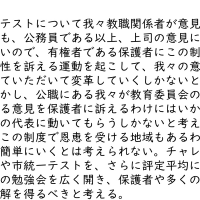
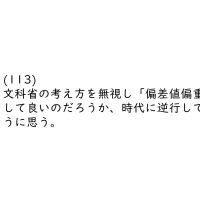
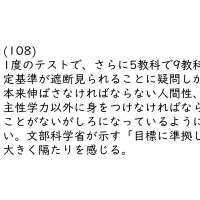
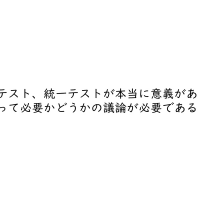
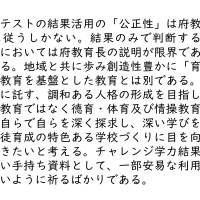
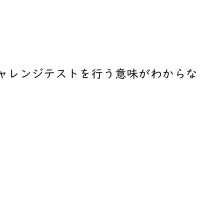
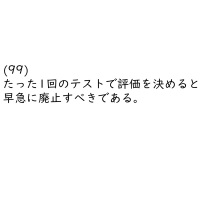
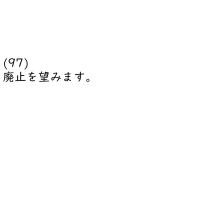
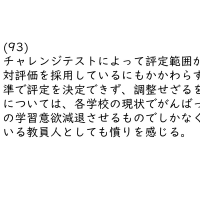
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます