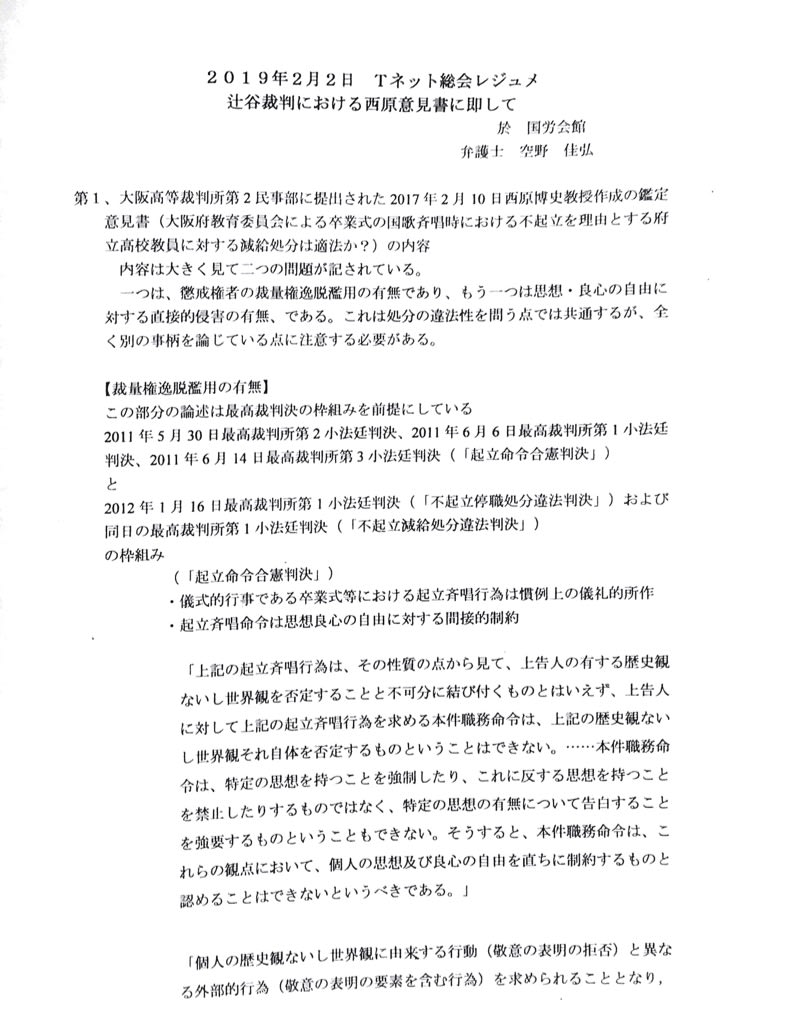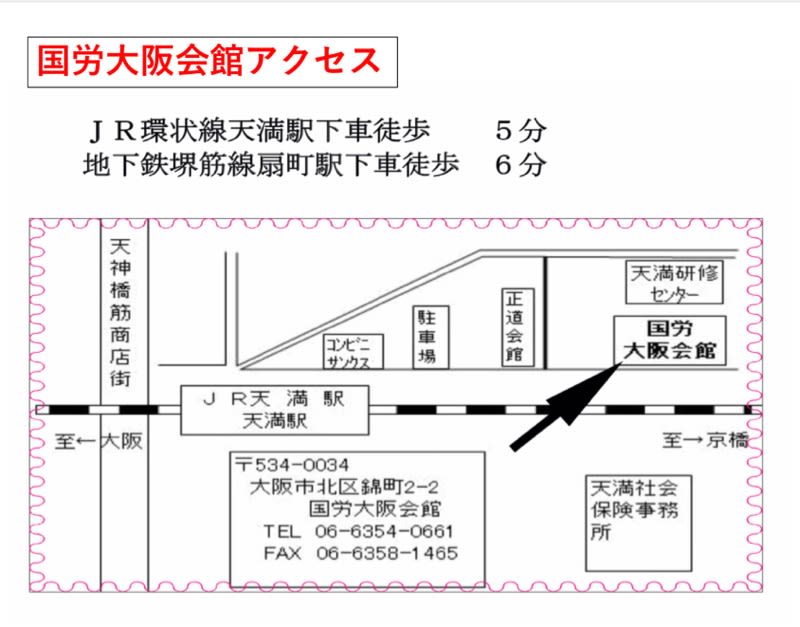Tネット第7回総会における空野佳弘弁護士の講演は、「いま」がどんな時代なのか考える上え非常に示唆に富むものでした。大阪ネットの寺本勉さんの聞き書きまとめ(メモ)を掲載します。
空野弁護士による講演「辻谷裁判における西原意見書に即して」を聞いて(メモ)
寺本勉
辻谷さんの「日の丸・君が代」訴訟の代理人減給撤回訴訟控訴審で、西原先生に意見書を書いていただいたが、昨年交通事故で亡くなられた。惜しい人を亡くした思いだが、西原意見書の内容を紹介し、その論旨をまとめてみたいと思う。
第1
2017.2.10に「西原意見書」を大阪高裁に提出、主な論点は以下の2つ、
1.減給処分は裁量権の逸脱にあたる。
2.大阪における処分メカニズムは「思想・良心の自由」に対する直接的な侵害にあたる。
1. 2つの最高裁判決をもとにした意見
① 起立命令合憲判決
判決からの引用
「上記の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。・・・本件職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,本件職務命令は,これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。」
「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり,その限りにおいて,当該職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」
結論は、不起立処分は合憲というもの〜儀礼的所作、間接的制約、合理的理由があれば良い
② 停職・減給処分違法判決
判決からの引用
「不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるのは、過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為等の前後における態度等に鑑み、学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要する。」
櫻井裁判官の補足意見からの引用(判決の趣旨がよくわかる)
「本件の不起立行為は,既に多数意見の中で説示しているように,それぞれの行為者の歴史観等に起因してやむを得ず行うものであり,その結果式典の進行が遅れるなどの支障を生じさせる態様でもなく,また行為者も式典の妨害を目的にして行うものではない。不起立の時間も短く,保護者の一部に違和感,不快感を持つものがいるとしても,その後の教育活動,学校の秩序維持等に大きく影響しているという事実が認められているわけではない。」
「処分対象者の多くは,そのような葛藤の結果,自らの信じるところに従い不起立行為を選択したものであろう。式典のたびに不起立を繰り返すということは,その都度,葛藤を経て,自らの信条と尊厳を守るためにやむを得ず不起立を繰り返すことを選択したものと見ることができる。前記2(1)の状況の下で,毎年必ず挙行される入学式,卒業式等において不起立を行えば,次第に処分が加重され,2,3年もしないうちに戒告から減給,そして停職という形で不利益の程度が増していくことになるが,これらの職員の中には,自らの信条に忠実であればあるほど心理的に追い込まれ,上記の不利益の増大を受忍するか,自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状態に置かれる者がいることを容易に推測できる。不起立行為それ自体が,これまで見たとおり,学校内の秩序を大きく乱すものとはいえないことに鑑みると,このように過酷な結果を職員個人にもたらす前記2(1)のような懲戒処分の加重量定は,法が予定している懲戒制度の運用の許容範囲に入るとは到底考えられず,法の許容する懲戒権の範囲を逸脱するものといわざるを得ない。」
東京高裁判決からの引用(2015年5月28日判決)
「「自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られる」こととなるような事態は「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」(後に最高裁判所第3小法廷の2016年5月31日上告棄却・上告申立不受理決定により確定)
減給・停職には、相当性を基礎付ける具体的な事情が認められなければ裁量権逸脱になる。
そこで、辻谷さんの行為が、減給処分を選択する相当性を基礎付ける事情が認められる場合に当たるかどうか、を考えてみると、
西原意見書では〜減給処分を選択する相当性を基礎付ける具体的事情はないと。
西原意見書からの引用
「卒業式の進行が特別に滞り、生徒や保護者を始めとする列席者に対して直接的な影響が生じたとする認定がなされていない本件において、不起立行為の秩序侵害性は特別に大きいものであったと判断する根拠は存在しないことになる。」
「丸椅子の持ち込んでの不起立についても、卒業生を送り出す式典に同席することに対する教員の教育上の利益を前提にした場合には、「本件不起立に積極的かつ意図的に及んだ」とする認定は適切ではなく、あくまで同席する場に国歌斉唱があったことによりやむを得ず不起立に及んだものと同視することが適切といえる。」
「本件の処分対象は2012年4月の入学式における不起立行為と同種の行為と評価すべきものである。にもかかわらず、それが2回目であることによって減給処分へと加重されているわけであるが、前回行為と比較した場合に特別に重く処罰すべき事情は処分対象行為の性質それ自体の中には存在しない。」
「処分権者としては、「次は免職」としての意味合いを十分に考慮に入れ、そうした意味を持つ加重処分としての条件に合致する処分選択となっているかどうかにつき、十分な検討を行うことが必要とされる」が、そのような検討はなされていない。
「処分対象となる行為の悪質さに比して不必要に重い意味を持つ処分が選択されたことになり、権衡を失する状態に立ち至ったものと認められるのであり、比例原則違反を認定せざるを得ない状況にある。」
府教委は、次は免職という警告書を出しながらも、スリーアウト制とは関係ないと言い張った、判決もそれを追認した
最高裁判決の枠組みからしても、裁量権の範囲を逸脱していると主張したが受け入れらなかった。
2. 維新の会が発表した大阪府教育基本条例案(2011.8.19)条例案
(職務命令違反に対する処分)
第38条 職務命令に違反した教員等は、戒告又は減給とする。
2 過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反した場合は、停職とする。
3 前項による停職処分を行ったときは、第27条の規定にもかかわらず、教員等の所属及び氏名も併せて公表する。ただし、前条に基づく不服の申立てが有効になされており、停職処分が取り消される可能性のある場合は、停職処分が確定したのちに公表を行うものとする。
4 府立学校の教員等に対して、第2項に基づく停職処分を行ったときは、府教育委員会は、分限処分に係る対応措置として、第31条第6項に基づき警告書の交付及び指導研修を実施し、必要に応じ同条第7項から第14項までに定める措置を実施しなければならない。
5 府費負担教職員については、本条の規定に沿って、別に規則で定める。
(常習的職務命令違反に対する処分)
第39条 前条第4項で規定される指導研修が終了したのちに、5回目の職務命令違反又は同一の職務命令に対する3回目の違反を行った教員等は、直ちに免職とする。ただし、第37条に規定する不服の申立てが有効になされている場合は、要件に該当することが確定したのちに処分を行う。
2 前項の規定にもかかわらず、懲戒処分とする事由がある場合は、懲戒免職とする。
読売新聞の報道からの引用(讀賣新聞大阪本社版2011年5月17日夕刊)
「大阪府の橋下徹知事は17日、入学式や卒業式の国歌斉唱時に起立しない府立学校や公立小中学校の教員を免職する処分基準を定めた条例を9月の定例府議会に提案する考えを示した。府によると、同様の条例は全国でも例がないという。
知事は報道陣に、『府教育委員会が国歌は立って歌うと決めている以上、公務員に個人の自由はない。従わない教員は大阪府にはいらない』と指摘し、『繰り返し違反すれば、免職になるというルールを作り、9月議会をめどに成立を目指したい』と述べた。」
これに対する西原意見書の記述
「ここに表明されているのは、国歌を歌うことを是とする思想を絶対化し、少なくとも府内の公立学校教員に対してその思想の無条件の受容を要求するとともに、その思想を受け容れることのできない者を公立学校教員として排除しようとする、明確な思想差別の意図である。」
この条例案が形を少し変えて、職員基本条例が制定(27条)が制定され、辻谷さんは29条2項に基づいて、警告書を出された。
西原意見書からの引用
「こうした制定の経緯を踏まえると、大阪府国旗国歌条例における教職員に対する無条件で国歌斉唱に参加できる信条の強制と、大阪府職員基本条例27条2項における免職条項は一体として構想されたものであり、後者が前者の手段として位置づけられて成立したものであることが明らかになる。」
「しかし、国歌斉唱に参加することが自らの信条に照らして不可能であるとする教員を、その思想・信条のゆえに公立学校教員としての地位から排除しようとする権力的措置は、憲法19条の思想・良心の自由に対する直接的な侵害となる。」
「条例上の斉唱義務に基づく起立斉唱行為は、前記1に引用の最高裁起立命令合憲判決の用語法でいえば、「その性質の点から見て」当該教員の有する「歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付く」ものであり、それを義務づける大阪府国旗国歌条例およびそれを実施するための職務命令は当該教員に対して「上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するもの」に該当することになる。」
「本件減給処分が大阪府国旗国歌条例と大阪府職員基本条例によって作り出された思想強制システムが作動する中で生じたものである」
「最高裁は現在までのところ、各自治体における学習指導要領の具体化手続を善意の教育目的のものと捉えるスタンスを維持し、特定思想に対する狙い撃ち的な排除構想の存在を認定しようとしてこなかった。」
「下級審段階で入手可能な証拠の範囲において思想・良心の自由を違憲な形で意図的に無視して特定思想に対する排除を追求する邪悪な意図を立証する手段が入手不可能であったことにも依存している現実である。」
「しかし、大阪府の状況は異なる。」
「日本国憲法が19条を定めることによって防ごうとしていた権力の暴走そのものである。」
「大阪発で日本全体を害しようとする危険な傾向の発露であることが見えてくる。本件の処理を間違えると、21世紀の日本で憲法に保障された個人の基本的人権は、暴力的なコンフォーミズムの中で有名無実化し、空洞化する動きを積極的に追認する意味を持ちかねない、危険な岐路に我々は立たされている。」
特定思想に対する排除構造を立証する証拠はこれまで入手不可能だったが、大阪では明白な証拠としての条例が存在するから、直接的な侵害と言っていいのだ。
・・・これが西原先生の遺言となってしまった。
最高裁は、この西原先生の意見に耳を傾けなかったようだ、昨年4月に上告棄却している。
第2、日の丸・君が代不起立処分の本質―教育の国家統制、政治的介入
そもそも私は、「君が代」処分の本質は、教育の国家統制であり、政治的介入であると考えている。教育の中における生徒が対象となっており、政府の考えでひとつにまとめ上げようとするために、反対する教員を排除しようとするものである。
これまでにもこの主張はされてきたが、最高裁はこれに正面から向き合っていない。
ピアノ伴奏拒否最高裁判決(2007.2.27)
藤田裁判官は学者出身の判事であったが、今は、実際のところで学者判事といえる人は一人もいないのが実情である。
藤田裁判官の反対意見
「1 多数意見は,本件で問題とされる上告人の「思想及び良心」の内容を,上告人の有する「歴史観ないし世界観」(すなわち,「君が代」が過去において果たして来た役割に対する否定的評価)及びこれに由来する社会生活上の信念等であるととらえ,このような理解を前提とした上で,本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,この歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできないとして,上告人に対して同伴奏を命じる本件職務命令が,直ちに,上告人のこの歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないとし,また,このようなピアノ伴奏を命じることが,上告人に対して,特定の思想を持つことを強制したり,特定の思想の有無について告白することを強要するものであるということはできないとする。これはすなわち,憲法19条によって保障される上告人の「思想及び良心」として,その中核に,「君が代」に対する否定的評価という「歴史観ないし世界観」自体を据えるとともに,入学式における「君が代」のピアノ伴奏の拒否は,その派生的ないし付随的行為であるものとしてとらえ,しかも,両者の間には(例えば,キリスト教の信仰と踏み絵とのように)後者を強いることが直ちに前者を否定することとなるような密接な関係は認められない,という考え方に立つものということができよう。しかし,私には,まず,本件における真の問題は,校長の職務命令によってピアノの伴奏を命じることが,上告人に「『君が代』に対する否定的評価」それ自体を禁じたり,あるいは一定の「歴史観ないし世界観」の有無についての告白を強要することになるかどうかというところにあるのではなく(上告人が,多数意見のいうような意味での「歴史観ないし世界観」を持っていること自体は,既に本人自身が明らかにしていることである。そして,「踏み絵」の場合のように,このような告白をしたからといって,そのこと自体によって,処罰されたり懲戒されたりする恐れがあるわけではない。),むしろ,入学式においてピアノ伴奏をすることは,自らの信条に照らし上告人にとって極めて苦痛なことであり,それにもかかわらずこれを強制することが許されるかどうかという点にこそあるように思われる。」
「そうであるとすると,本件において問題とされるべき上告人の「思想及び良心」としては,このように「『君が代』が果たしてきた役割に対する否定的評価という歴史観ないし世界観それ自体」もさることながら,それに加えて更に,「『君が代』の斉唱をめぐり,学校の入学式のような公的儀式の場で,公的機関が,参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価(従って,また,このような行動に自分は参加してはならないという信念ないし信条)」といった側面が含まれている可能性があるのであり,また,後者の側面こそが,本件では重要なのではないかと考える。」
「そして,これが肯定されるとすれば,このような信念ないし信条がそれ自体として憲法による保護を受けるものとはいえないのか,すなわち,そのような信念・信条に反する行為(本件におけるピアノ伴奏は,まさにそのような行為であることになる。)を強制することが憲法違反とならないかどうかは,仮に多数意見の上記の考えを前提とするとしても,改めて検討する必要があるものといわなければならない。」
「このことは,例えば,「君が代」を国歌として位置付けることには異論が無く,従って,例えばオリンピックにおいて優勝者が国歌演奏によって讃えられること自体については抵抗感が無くとも,一方で「君が代」に対する評価に関し国民の中に大きな分かれが現に存在する以上,公的儀式においてその斉唱を強制することについては,そのこと自体に対して強く反対するという考え方も有り得るし,また現にこのような考え方を採る者も少なからず存在するということからも,いえるところである。この考え方は,それ自体,上記の歴史観ないし世界観とは理論的には一応区別された一つの信念・信条であるということができ,このような信念・信条を抱く者に対して公的儀式における斉唱への協力を強制することが,当人の信念・信条そのものに対する直接的抑圧となることは,明白であるといわなければならない。そしてまた,こういった信念・信条が,例えば「およそ法秩序に従った行動をすべきではない」というような,国民一般に到底受け入れられないようなものであるのではなく,自由主義・個人主義の見地から,それなりに評価し得るものであることも,にわかに否定することはできない。本件における,上告人に対してピアノ伴奏を命じる職務命令と上告人の思想・良心の自由との関係については,こういった見地から更に慎重な検討が加えられるべきものと考える。」
最高裁多数意見の立場に対し、
藤田裁判官の意見は、「上告人にとって極めて苦痛、それを強制することが許されるかどうか・・・」
この反対意見は、実に重要なことを指摘している。慣例的儀礼的所作論に対する批判、公の式典で全員が一致した行動を強制されることこそ問題の本質である。これは、これまでの「日の丸・君が代」裁判の中での最高の地平と言える。
最高裁多数意見は、藤田裁判官の着目した点を認めると、教育の国家統制に入って行かざるを得ないため、一種の詭弁を弄して、ごまかしているのだと思う。
藤田反対意見を中心に置いた場合、辻谷さんの「式場外警備」という職務命令は、特定の教員の排除になり、教育統制の一種の手段としてあることになる。裁判は一種の詭弁の世界であり、結論が先にあって、その理由は後でなんとでもつけられる。
上告棄却の意味
最高裁判決の枠組みでは、減給処分は撤回されなければならないはずだが、審理なしに上告棄却されたということだが、2012年1月16日最高裁の「不起立停職・減給処分違法判決」における、あの枠組みは、原則と例外を逆転させたものであり、案外軽いものかもしれない。
大阪の条例についても実質審理しなかったのは、直接的制約という問題には一切関わらないという最高裁の態度を明らかにしたものだ。
社会を大きく変えていこうとする動きの一環として、この判決をとらえる必要がある。その動きが始まったのは90年代からではなかったか。
1937年に南京に入城した元日本兵士東史郎さんが90年代に日記を公表したが、元上官から訴えられた裁判を担当したことがあった。地裁では敗訴したが、高裁では尋問もあり逆転するのではないかと思っていた。一般的には高裁で尋問をやるということはひっくり返る可能性が大きいのだが、ところが、裁判官が3人とも入れ替わり、結果は地裁と同じく敗訴だった。今考えると明らかに政治的な意思が働いていたに違いない確信している。驚くべきことに、日本会議に会長職には元最高裁判事が2人もなっている。
社会は急激に変わる時がある。学会の通説であった天皇機関説が、たった2年間で不敬罪に問われた。その1930年代とは違って、まだ話せる自由が完全には封じられていない。綱引きと一緒で、力のバランスが崩れると、一気に進んでしまう。だからこそ、こうした裁判は重要だと思っている。
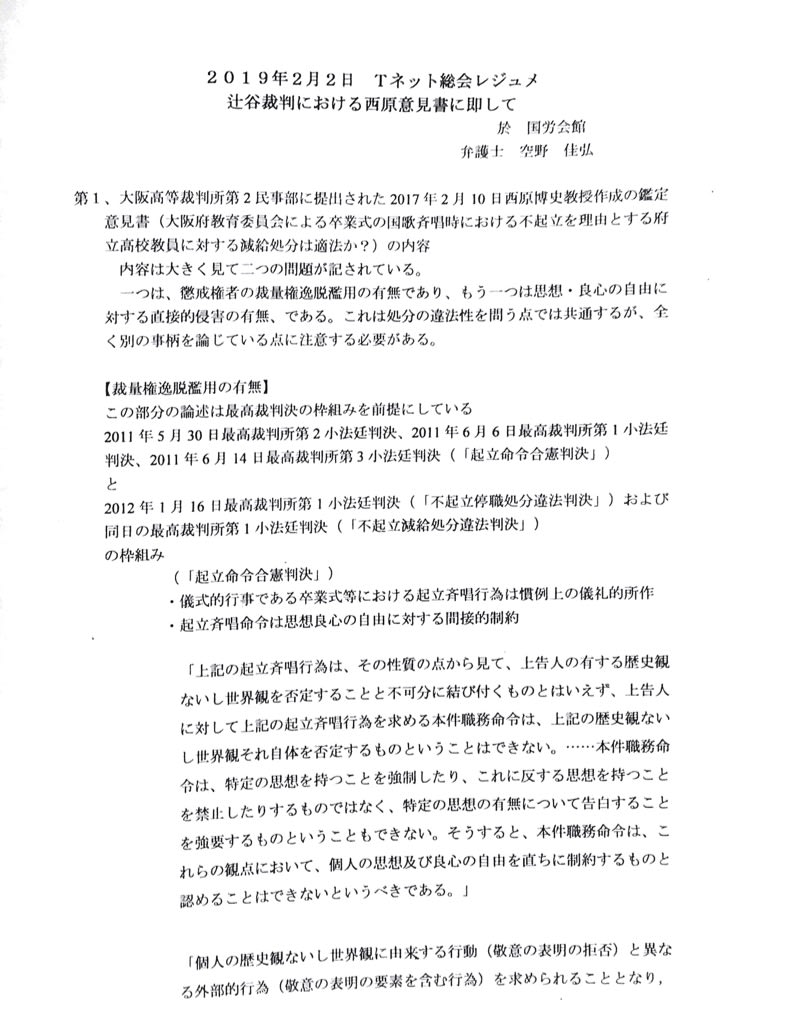
空野弁護士による講演「辻谷裁判における西原意見書に即して」を聞いて(メモ)
寺本勉
辻谷さんの「日の丸・君が代」訴訟の代理人減給撤回訴訟控訴審で、西原先生に意見書を書いていただいたが、昨年交通事故で亡くなられた。惜しい人を亡くした思いだが、西原意見書の内容を紹介し、その論旨をまとめてみたいと思う。
第1
2017.2.10に「西原意見書」を大阪高裁に提出、主な論点は以下の2つ、
1.減給処分は裁量権の逸脱にあたる。
2.大阪における処分メカニズムは「思想・良心の自由」に対する直接的な侵害にあたる。
1. 2つの最高裁判決をもとにした意見
① 起立命令合憲判決
判決からの引用
「上記の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。・・・本件職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,本件職務命令は,これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。」
「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり,その限りにおいて,当該職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」
結論は、不起立処分は合憲というもの〜儀礼的所作、間接的制約、合理的理由があれば良い
② 停職・減給処分違法判決
判決からの引用
「不起立行為等に対する懲戒において戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるのは、過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為等の前後における態度等に鑑み、学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要する。」
櫻井裁判官の補足意見からの引用(判決の趣旨がよくわかる)
「本件の不起立行為は,既に多数意見の中で説示しているように,それぞれの行為者の歴史観等に起因してやむを得ず行うものであり,その結果式典の進行が遅れるなどの支障を生じさせる態様でもなく,また行為者も式典の妨害を目的にして行うものではない。不起立の時間も短く,保護者の一部に違和感,不快感を持つものがいるとしても,その後の教育活動,学校の秩序維持等に大きく影響しているという事実が認められているわけではない。」
「処分対象者の多くは,そのような葛藤の結果,自らの信じるところに従い不起立行為を選択したものであろう。式典のたびに不起立を繰り返すということは,その都度,葛藤を経て,自らの信条と尊厳を守るためにやむを得ず不起立を繰り返すことを選択したものと見ることができる。前記2(1)の状況の下で,毎年必ず挙行される入学式,卒業式等において不起立を行えば,次第に処分が加重され,2,3年もしないうちに戒告から減給,そして停職という形で不利益の程度が増していくことになるが,これらの職員の中には,自らの信条に忠実であればあるほど心理的に追い込まれ,上記の不利益の増大を受忍するか,自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状態に置かれる者がいることを容易に推測できる。不起立行為それ自体が,これまで見たとおり,学校内の秩序を大きく乱すものとはいえないことに鑑みると,このように過酷な結果を職員個人にもたらす前記2(1)のような懲戒処分の加重量定は,法が予定している懲戒制度の運用の許容範囲に入るとは到底考えられず,法の許容する懲戒権の範囲を逸脱するものといわざるを得ない。」
東京高裁判決からの引用(2015年5月28日判決)
「「自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られる」こととなるような事態は「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」(後に最高裁判所第3小法廷の2016年5月31日上告棄却・上告申立不受理決定により確定)
減給・停職には、相当性を基礎付ける具体的な事情が認められなければ裁量権逸脱になる。
そこで、辻谷さんの行為が、減給処分を選択する相当性を基礎付ける事情が認められる場合に当たるかどうか、を考えてみると、
西原意見書では〜減給処分を選択する相当性を基礎付ける具体的事情はないと。
西原意見書からの引用
「卒業式の進行が特別に滞り、生徒や保護者を始めとする列席者に対して直接的な影響が生じたとする認定がなされていない本件において、不起立行為の秩序侵害性は特別に大きいものであったと判断する根拠は存在しないことになる。」
「丸椅子の持ち込んでの不起立についても、卒業生を送り出す式典に同席することに対する教員の教育上の利益を前提にした場合には、「本件不起立に積極的かつ意図的に及んだ」とする認定は適切ではなく、あくまで同席する場に国歌斉唱があったことによりやむを得ず不起立に及んだものと同視することが適切といえる。」
「本件の処分対象は2012年4月の入学式における不起立行為と同種の行為と評価すべきものである。にもかかわらず、それが2回目であることによって減給処分へと加重されているわけであるが、前回行為と比較した場合に特別に重く処罰すべき事情は処分対象行為の性質それ自体の中には存在しない。」
「処分権者としては、「次は免職」としての意味合いを十分に考慮に入れ、そうした意味を持つ加重処分としての条件に合致する処分選択となっているかどうかにつき、十分な検討を行うことが必要とされる」が、そのような検討はなされていない。
「処分対象となる行為の悪質さに比して不必要に重い意味を持つ処分が選択されたことになり、権衡を失する状態に立ち至ったものと認められるのであり、比例原則違反を認定せざるを得ない状況にある。」
府教委は、次は免職という警告書を出しながらも、スリーアウト制とは関係ないと言い張った、判決もそれを追認した
最高裁判決の枠組みからしても、裁量権の範囲を逸脱していると主張したが受け入れらなかった。
2. 維新の会が発表した大阪府教育基本条例案(2011.8.19)条例案
(職務命令違反に対する処分)
第38条 職務命令に違反した教員等は、戒告又は減給とする。
2 過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反した場合は、停職とする。
3 前項による停職処分を行ったときは、第27条の規定にもかかわらず、教員等の所属及び氏名も併せて公表する。ただし、前条に基づく不服の申立てが有効になされており、停職処分が取り消される可能性のある場合は、停職処分が確定したのちに公表を行うものとする。
4 府立学校の教員等に対して、第2項に基づく停職処分を行ったときは、府教育委員会は、分限処分に係る対応措置として、第31条第6項に基づき警告書の交付及び指導研修を実施し、必要に応じ同条第7項から第14項までに定める措置を実施しなければならない。
5 府費負担教職員については、本条の規定に沿って、別に規則で定める。
(常習的職務命令違反に対する処分)
第39条 前条第4項で規定される指導研修が終了したのちに、5回目の職務命令違反又は同一の職務命令に対する3回目の違反を行った教員等は、直ちに免職とする。ただし、第37条に規定する不服の申立てが有効になされている場合は、要件に該当することが確定したのちに処分を行う。
2 前項の規定にもかかわらず、懲戒処分とする事由がある場合は、懲戒免職とする。
読売新聞の報道からの引用(讀賣新聞大阪本社版2011年5月17日夕刊)
「大阪府の橋下徹知事は17日、入学式や卒業式の国歌斉唱時に起立しない府立学校や公立小中学校の教員を免職する処分基準を定めた条例を9月の定例府議会に提案する考えを示した。府によると、同様の条例は全国でも例がないという。
知事は報道陣に、『府教育委員会が国歌は立って歌うと決めている以上、公務員に個人の自由はない。従わない教員は大阪府にはいらない』と指摘し、『繰り返し違反すれば、免職になるというルールを作り、9月議会をめどに成立を目指したい』と述べた。」
これに対する西原意見書の記述
「ここに表明されているのは、国歌を歌うことを是とする思想を絶対化し、少なくとも府内の公立学校教員に対してその思想の無条件の受容を要求するとともに、その思想を受け容れることのできない者を公立学校教員として排除しようとする、明確な思想差別の意図である。」
この条例案が形を少し変えて、職員基本条例が制定(27条)が制定され、辻谷さんは29条2項に基づいて、警告書を出された。
西原意見書からの引用
「こうした制定の経緯を踏まえると、大阪府国旗国歌条例における教職員に対する無条件で国歌斉唱に参加できる信条の強制と、大阪府職員基本条例27条2項における免職条項は一体として構想されたものであり、後者が前者の手段として位置づけられて成立したものであることが明らかになる。」
「しかし、国歌斉唱に参加することが自らの信条に照らして不可能であるとする教員を、その思想・信条のゆえに公立学校教員としての地位から排除しようとする権力的措置は、憲法19条の思想・良心の自由に対する直接的な侵害となる。」
「条例上の斉唱義務に基づく起立斉唱行為は、前記1に引用の最高裁起立命令合憲判決の用語法でいえば、「その性質の点から見て」当該教員の有する「歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付く」ものであり、それを義務づける大阪府国旗国歌条例およびそれを実施するための職務命令は当該教員に対して「上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するもの」に該当することになる。」
「本件減給処分が大阪府国旗国歌条例と大阪府職員基本条例によって作り出された思想強制システムが作動する中で生じたものである」
「最高裁は現在までのところ、各自治体における学習指導要領の具体化手続を善意の教育目的のものと捉えるスタンスを維持し、特定思想に対する狙い撃ち的な排除構想の存在を認定しようとしてこなかった。」
「下級審段階で入手可能な証拠の範囲において思想・良心の自由を違憲な形で意図的に無視して特定思想に対する排除を追求する邪悪な意図を立証する手段が入手不可能であったことにも依存している現実である。」
「しかし、大阪府の状況は異なる。」
「日本国憲法が19条を定めることによって防ごうとしていた権力の暴走そのものである。」
「大阪発で日本全体を害しようとする危険な傾向の発露であることが見えてくる。本件の処理を間違えると、21世紀の日本で憲法に保障された個人の基本的人権は、暴力的なコンフォーミズムの中で有名無実化し、空洞化する動きを積極的に追認する意味を持ちかねない、危険な岐路に我々は立たされている。」
特定思想に対する排除構造を立証する証拠はこれまで入手不可能だったが、大阪では明白な証拠としての条例が存在するから、直接的な侵害と言っていいのだ。
・・・これが西原先生の遺言となってしまった。
最高裁は、この西原先生の意見に耳を傾けなかったようだ、昨年4月に上告棄却している。
第2、日の丸・君が代不起立処分の本質―教育の国家統制、政治的介入
そもそも私は、「君が代」処分の本質は、教育の国家統制であり、政治的介入であると考えている。教育の中における生徒が対象となっており、政府の考えでひとつにまとめ上げようとするために、反対する教員を排除しようとするものである。
これまでにもこの主張はされてきたが、最高裁はこれに正面から向き合っていない。
ピアノ伴奏拒否最高裁判決(2007.2.27)
藤田裁判官は学者出身の判事であったが、今は、実際のところで学者判事といえる人は一人もいないのが実情である。
藤田裁判官の反対意見
「1 多数意見は,本件で問題とされる上告人の「思想及び良心」の内容を,上告人の有する「歴史観ないし世界観」(すなわち,「君が代」が過去において果たして来た役割に対する否定的評価)及びこれに由来する社会生活上の信念等であるととらえ,このような理解を前提とした上で,本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,この歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできないとして,上告人に対して同伴奏を命じる本件職務命令が,直ちに,上告人のこの歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないとし,また,このようなピアノ伴奏を命じることが,上告人に対して,特定の思想を持つことを強制したり,特定の思想の有無について告白することを強要するものであるということはできないとする。これはすなわち,憲法19条によって保障される上告人の「思想及び良心」として,その中核に,「君が代」に対する否定的評価という「歴史観ないし世界観」自体を据えるとともに,入学式における「君が代」のピアノ伴奏の拒否は,その派生的ないし付随的行為であるものとしてとらえ,しかも,両者の間には(例えば,キリスト教の信仰と踏み絵とのように)後者を強いることが直ちに前者を否定することとなるような密接な関係は認められない,という考え方に立つものということができよう。しかし,私には,まず,本件における真の問題は,校長の職務命令によってピアノの伴奏を命じることが,上告人に「『君が代』に対する否定的評価」それ自体を禁じたり,あるいは一定の「歴史観ないし世界観」の有無についての告白を強要することになるかどうかというところにあるのではなく(上告人が,多数意見のいうような意味での「歴史観ないし世界観」を持っていること自体は,既に本人自身が明らかにしていることである。そして,「踏み絵」の場合のように,このような告白をしたからといって,そのこと自体によって,処罰されたり懲戒されたりする恐れがあるわけではない。),むしろ,入学式においてピアノ伴奏をすることは,自らの信条に照らし上告人にとって極めて苦痛なことであり,それにもかかわらずこれを強制することが許されるかどうかという点にこそあるように思われる。」
「そうであるとすると,本件において問題とされるべき上告人の「思想及び良心」としては,このように「『君が代』が果たしてきた役割に対する否定的評価という歴史観ないし世界観それ自体」もさることながら,それに加えて更に,「『君が代』の斉唱をめぐり,学校の入学式のような公的儀式の場で,公的機関が,参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価(従って,また,このような行動に自分は参加してはならないという信念ないし信条)」といった側面が含まれている可能性があるのであり,また,後者の側面こそが,本件では重要なのではないかと考える。」
「そして,これが肯定されるとすれば,このような信念ないし信条がそれ自体として憲法による保護を受けるものとはいえないのか,すなわち,そのような信念・信条に反する行為(本件におけるピアノ伴奏は,まさにそのような行為であることになる。)を強制することが憲法違反とならないかどうかは,仮に多数意見の上記の考えを前提とするとしても,改めて検討する必要があるものといわなければならない。」
「このことは,例えば,「君が代」を国歌として位置付けることには異論が無く,従って,例えばオリンピックにおいて優勝者が国歌演奏によって讃えられること自体については抵抗感が無くとも,一方で「君が代」に対する評価に関し国民の中に大きな分かれが現に存在する以上,公的儀式においてその斉唱を強制することについては,そのこと自体に対して強く反対するという考え方も有り得るし,また現にこのような考え方を採る者も少なからず存在するということからも,いえるところである。この考え方は,それ自体,上記の歴史観ないし世界観とは理論的には一応区別された一つの信念・信条であるということができ,このような信念・信条を抱く者に対して公的儀式における斉唱への協力を強制することが,当人の信念・信条そのものに対する直接的抑圧となることは,明白であるといわなければならない。そしてまた,こういった信念・信条が,例えば「およそ法秩序に従った行動をすべきではない」というような,国民一般に到底受け入れられないようなものであるのではなく,自由主義・個人主義の見地から,それなりに評価し得るものであることも,にわかに否定することはできない。本件における,上告人に対してピアノ伴奏を命じる職務命令と上告人の思想・良心の自由との関係については,こういった見地から更に慎重な検討が加えられるべきものと考える。」
最高裁多数意見の立場に対し、
藤田裁判官の意見は、「上告人にとって極めて苦痛、それを強制することが許されるかどうか・・・」
この反対意見は、実に重要なことを指摘している。慣例的儀礼的所作論に対する批判、公の式典で全員が一致した行動を強制されることこそ問題の本質である。これは、これまでの「日の丸・君が代」裁判の中での最高の地平と言える。
最高裁多数意見は、藤田裁判官の着目した点を認めると、教育の国家統制に入って行かざるを得ないため、一種の詭弁を弄して、ごまかしているのだと思う。
藤田反対意見を中心に置いた場合、辻谷さんの「式場外警備」という職務命令は、特定の教員の排除になり、教育統制の一種の手段としてあることになる。裁判は一種の詭弁の世界であり、結論が先にあって、その理由は後でなんとでもつけられる。
上告棄却の意味
最高裁判決の枠組みでは、減給処分は撤回されなければならないはずだが、審理なしに上告棄却されたということだが、2012年1月16日最高裁の「不起立停職・減給処分違法判決」における、あの枠組みは、原則と例外を逆転させたものであり、案外軽いものかもしれない。
大阪の条例についても実質審理しなかったのは、直接的制約という問題には一切関わらないという最高裁の態度を明らかにしたものだ。
社会を大きく変えていこうとする動きの一環として、この判決をとらえる必要がある。その動きが始まったのは90年代からではなかったか。
1937年に南京に入城した元日本兵士東史郎さんが90年代に日記を公表したが、元上官から訴えられた裁判を担当したことがあった。地裁では敗訴したが、高裁では尋問もあり逆転するのではないかと思っていた。一般的には高裁で尋問をやるということはひっくり返る可能性が大きいのだが、ところが、裁判官が3人とも入れ替わり、結果は地裁と同じく敗訴だった。今考えると明らかに政治的な意思が働いていたに違いない確信している。驚くべきことに、日本会議に会長職には元最高裁判事が2人もなっている。
社会は急激に変わる時がある。学会の通説であった天皇機関説が、たった2年間で不敬罪に問われた。その1930年代とは違って、まだ話せる自由が完全には封じられていない。綱引きと一緒で、力のバランスが崩れると、一気に進んでしまう。だからこそ、こうした裁判は重要だと思っている。