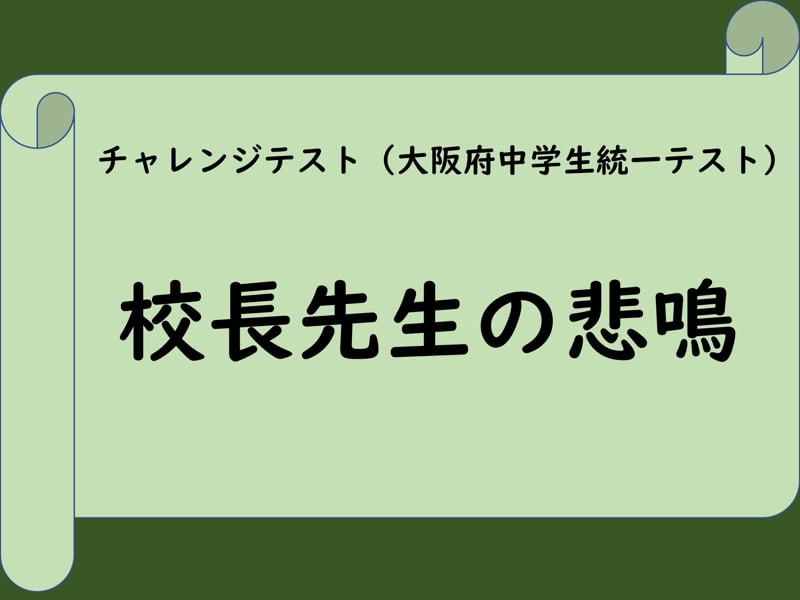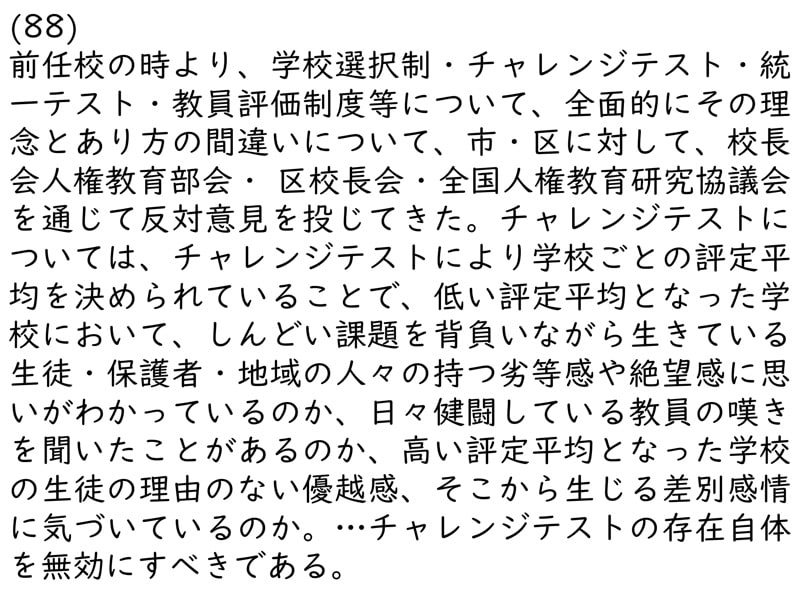「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分を撤回させる大阪ネットワークニュース第17号に寄稿しました。減給処分取り消し訴訟上告が棄却された後のたたかいについて述べたものです。お読みくだされば嬉しいです。
ポスト最高裁 辻谷博子
〈最高裁上告棄却〉
2018年4月18日、最高裁第2小法廷は、辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟上告棄却・上告申立不受理を決定しました。すでに1年が経ってしまいましたが、こちらの事務的なミスにより報告が遅れましたことをまずお詫びいたします。
2014年1月20日大阪地裁に訴状を提出して以来、一貫して訴えてきました「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」いわゆる「君が代」強制条例の違憲性について、司法は結局のところなんら審議をせずに判断を回避した結果と言えます。これが日本の司法の現実です。
〈連綿と続く「日の丸」「君が代」裁判〉
「日の丸」や「君が代」をどう取り扱うかについては、戦後まもなくから議論が起こります。とりわけ先の戦争でこれらが果たした役割、ましてそれらが教室で教えられたことを振り返るなら、それを戦後の学校で再び繰り返してはいけないというおおいなる抵抗がありました。政府や行政は、学校とりわけ儀式において「日の丸」を掲げ「君が代」を斉唱することを推進しようとしましたが、それに対して現場の多くの教員は、さまざまな立場、さまざまな考えの子どもたちが学ぶ学校において、「日の丸」「君が代」を強制することはあってはならないと主張し行動を起こしたわけです。
「日の丸」「君が代」裁判は1960年代から連綿と続きます。大阪、福岡、京都、沖縄、東京、鹿児島、広島・・ゆうに70件を越えます。
「日の丸」「君が代」の戦後史は、そのまま司法に対して憲法を問う歴史でもあったわけです。私が裁判に踏み切った理由は、そういった先達のたたかいを引き継ぎ、かつ、それを次代の子どもたちにも伝えていきたいと思ったからです。「君が代」裁判は今後もまだまだ続きます。そして、私自身、ポスト最高裁の今も、全国で唯一大阪だけにある「君が代」強制条例は明らかに憲法に違反しているという考えはまったく変わっていません。
〈「君が代」強制条例の違憲性〉
2011年6月3日、大阪維新の会が提案した「君が代」強制条例案は、わずか数時間の審議のみで、数の力の暴挙により可決成立に至りました。そしてその半年後の2012年3月23日には、今度はその処分条例ともいえる職員基本条例が可決成立しました。ここに大阪の公立学校のすべての教員に「君が代」起立斉唱職務命令を出し、それに抵抗すれば免職もあり得るとの“命令と恫喝”の全体主義の嵐が大阪の学校に吹き荒れ始めたといっても過言ではありません。
大阪地裁に提訴して以来、司法に一貫して求めてきたことは「君が代」強制条例・職員基本条例の違憲性でしたが、地裁判決(2016年7月6日内藤裕之裁判長)も高裁判決(2017年8月31日田中敦裁判長)もなんら審議は行いませんでした。特に高裁においては、西原博史意見書を提出し判断を迫りましたが、「西原意見書はにわかに採用できない」の一言で片付けられるという態様に、司法の最後の砦として最高裁に一縷の望みを託したわけです。しかし、ついに司法は「君が代」強制条例について憲法判断は行いませんでした。
昨年、ひとりの法学者が司法の現状を次のように言われました。「憲法判断を行わないのが司法のプロだという裁判官の意識が日本の司法の問題である」と。
「日の丸」「君が代」が国家のシンボルである以上、そしてそれらを為政者が「国民」を束ねる道具として利用しているからには、司法もそれに忖度するということなのでしょうか。しかし、司法が国や行政の過ちを判断しないでいったいだれがその危険性を指摘できるでしょうか。
〈「君が代」強制条例施行から8年〉
新年度が始まりました。4月入学式を前にして、またしても大阪の学校は、職務命令からスタートしました。2011年「君が代」強制条例が公布施行され8年目になります。学校現場は明らかに変わりました。条例下「君が代」起立斉唱“命令”体制は不当な人事評価制度ともあいまって、教職員が意見、特に政府や行政に対する批判的な意見を表明することさえ憚られる空気を生み出しました。もちろん、それは生徒にも即座に伝播します。子どもたちは、「上」のいうことを聞くのは当たり前、今ある社会を批判することもできず、格差社会を肯定し、何か問題があったとしても「自己責任論」に絡め取られているように見えます。これこそが為政者の狙いではなかったのかとさえ思うほどです。
〈ポスト最高裁〉
今、私は、司法が憲法を尊重しないなら、私たち市民が憲法を擁護していく他はないと考えています。「君が代」裁判はこれからも続くことでしょう。司法が憲法を取り戻すまでたたかいは続きます。それと同時に憲法は誰のために、何のためにあるのか、多くの人々と考え合い、語り合い、そして憲法を私たちの生活のなかで活かしていきたいと思います。4月1日の“新元号騒動”をみれば、それはこれまで以上に困難な道かもしれません。しかし、だからこそ私たちのやるべきことはより明確ともいえます。
これまで「君が代」不起立減給処分取消裁判を応援してくださったみなさま、心よりお礼申しあげます。そして、今こそポスト最高裁のこの困難な時代を、知恵を出し合いたたかい続けて行こうではありませんか、子どもたちの未来に向けて。それが私たちの責任であると同時に希望であると確信しています。憲法を次代に活かすために。