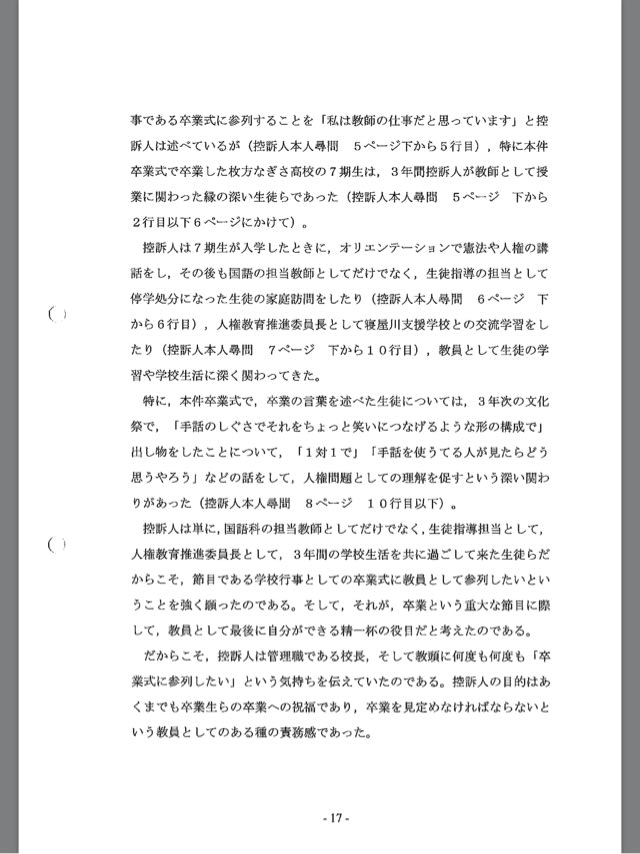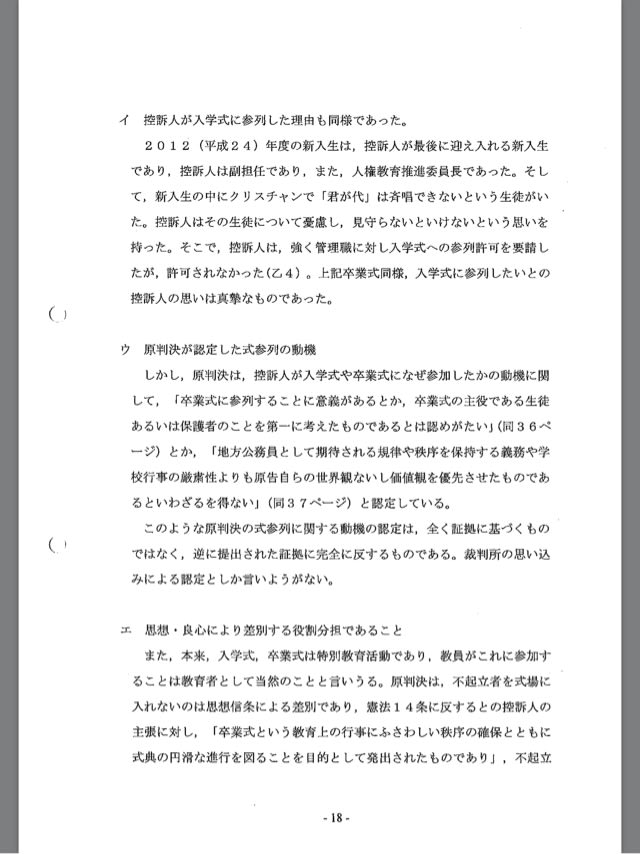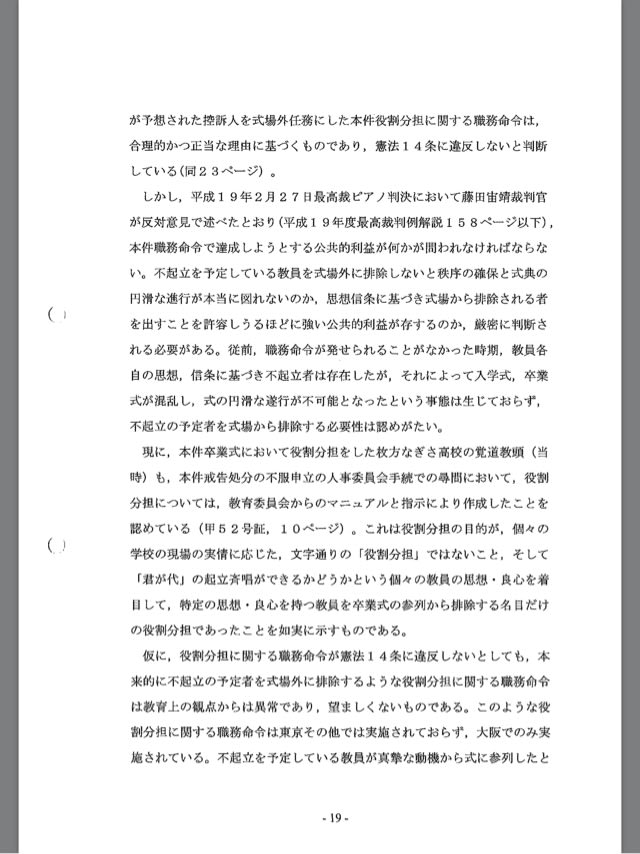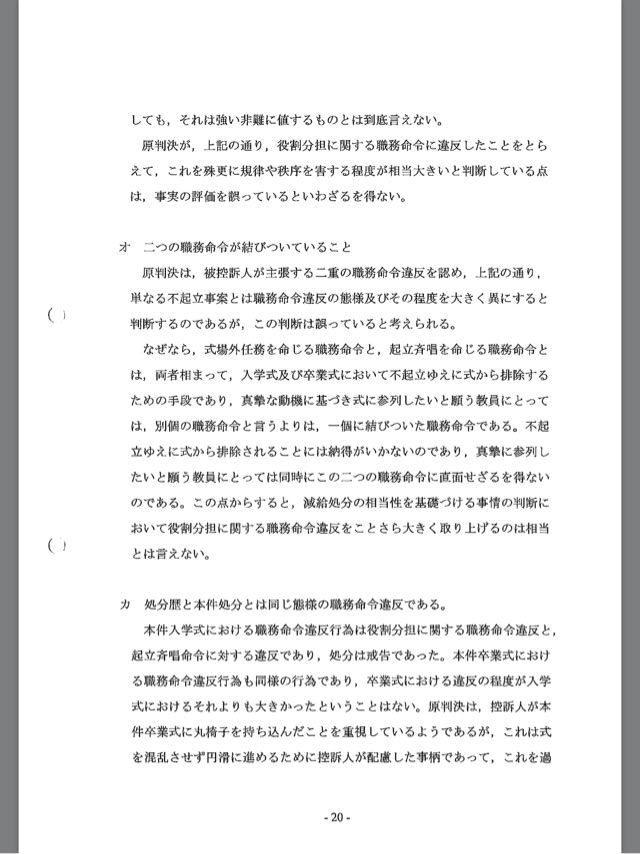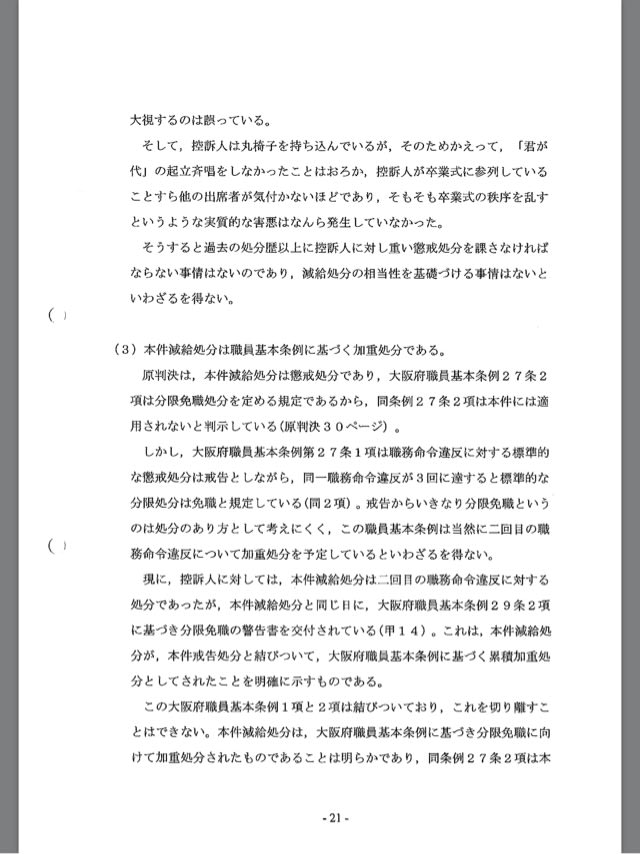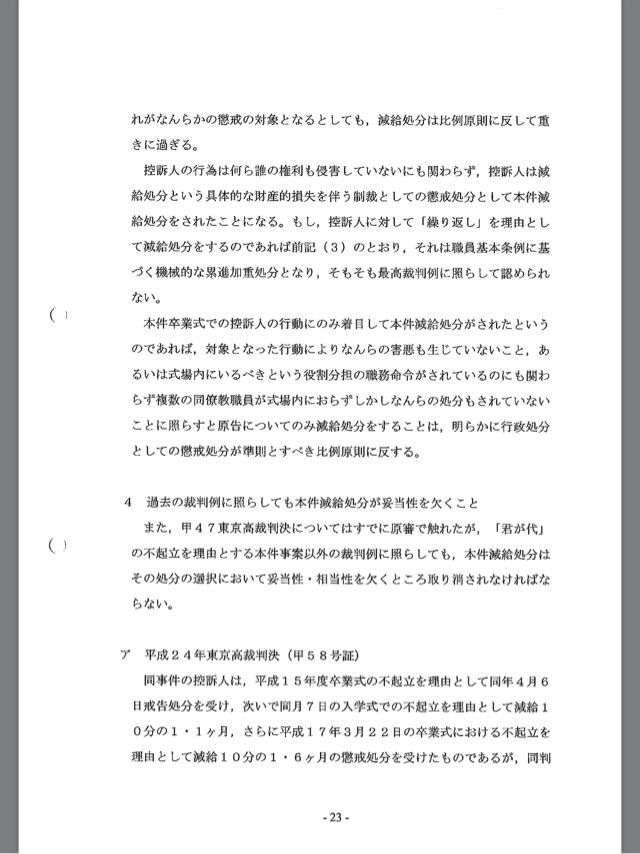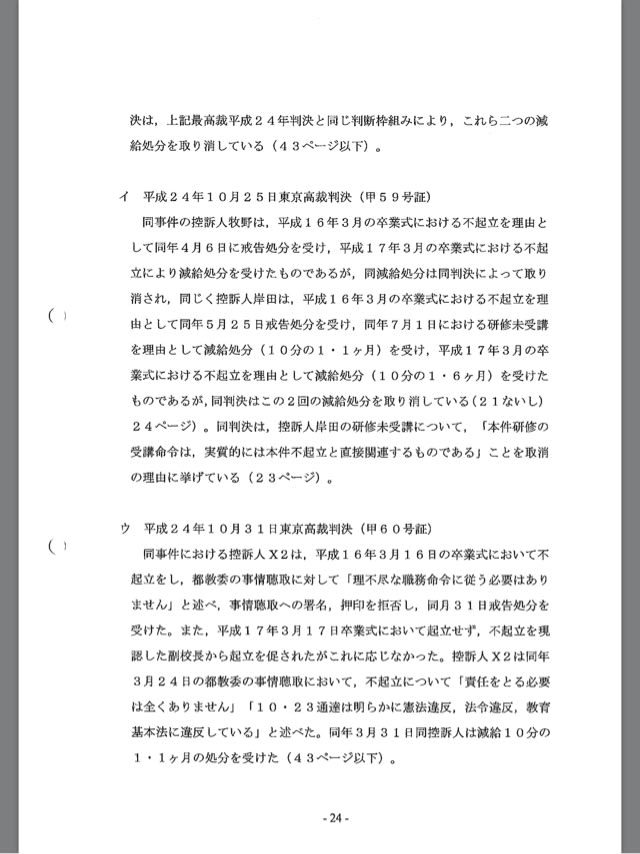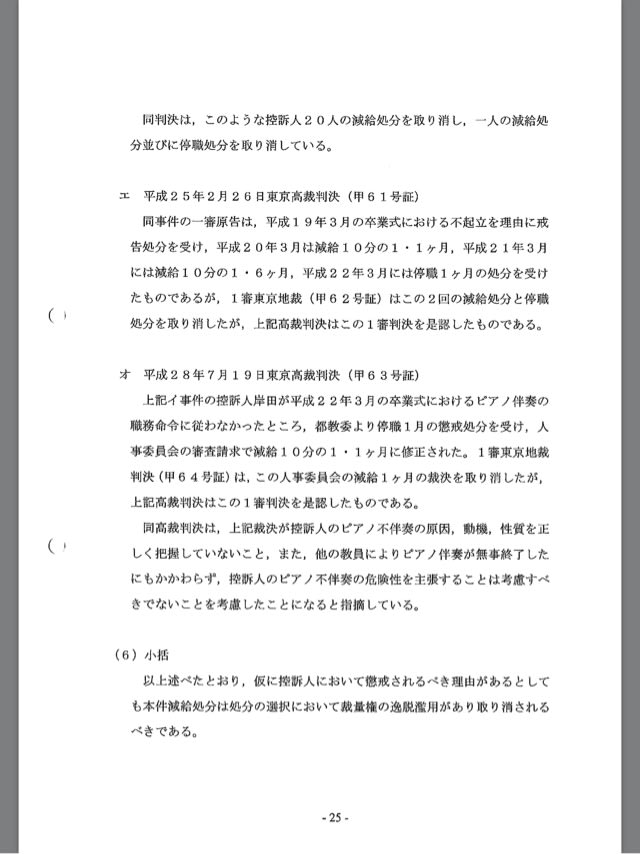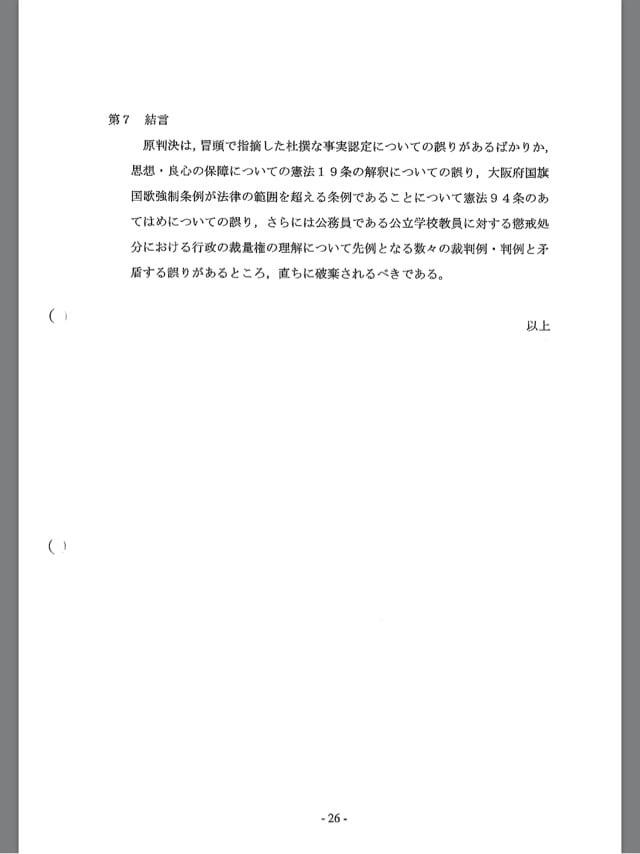はじめに
11月9日、驚くほどの差別発言を繰り返していたドナルド・トランプ氏が合衆国大統領に当選しました。政策以前の問題としてあれほどの人権侵害を、白昼しかも公的な場で行っていた人物が国民の支持を得て当選する現実はめまいを覚えるほどです。しかし、振り返ってみると、日本でも同じ現象が起こっているのではないでしょうか。安倍総理をはじめとする内閣のお歴々、鶴保沖縄担当相、稲田法相、、、そして、大阪の橋下徹元大阪府知事・市長、松井現大阪府知事、かれら政治家のヘイトスピーチさながらの発言が、実はそれを支持する人々に支えられながら、ますます差別と偏見が広がっていく悪循環は同じ構造であるように思います。
私は、今、大連で控訴審に向け準備をしながら、奥野さんの「君が代」不起立減給処分取消が高裁においても認められなかったこと、入れ墨アンケート拒否処分取消がついに最高裁でも認められなかったこと―これらの事実を前に、もう一度、人権について根源的なところから問い直し共有する必要性を感じています。政治が、司法が不当であればあるほど、私たちは声を出さなければならないのかもしれません。おそらく今多くの方がそう思われているのではないでしょうか。オラッショレイ♪オラッショレイ♪あきらめない!
さて、9月12日、大阪高裁に控訴理由書を提出しました。既に、ブログ「教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク」(Tネット)で全文を公開していますが、ここでは、その要点を紹介し、皆様方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
控訴理由書要約版
(1)事実認定における致命的な欠陥
原審判決では、減給処分取消を棄却する前提として人事委員会における戒告処分承認との裁決をあげているが、これは紛れもない事実認定の誤りである。(人事委員会の係属証明書を証拠として提出)
また、卒業式に参列した動機について、原審における供述、証言、証拠を何ら吟味もせず、「原告自らの世界観ないし価値観を優先させた」と認定している。
そもそも、憲法が保障する三権分立のもと、司法裁判所の判断が立法権・行政権に優越する判断とされているのは、裁判官が事実認定については証拠に基づいて客観的に認定するという判断過程の公正さがあってのことである。
ところが、原審判決はこのように証拠に基づかない事実認定を前提としている。これは、司法裁判所の判断に対する社会的信頼をも毀損するものである。このような大きな欠陥のある原審判決は直ちに破棄されるべきである。
(2)「君が代」起立斉唱は慣例上の儀礼的所作ではない
原審判決は、卒業式における「君が代」起立斉唱は、習俗的な「慣例上の儀礼的所作」であるゆえ、それが控訴人の思想・良心を直接に侵害するものではないとし、そもそも外部的にも思想・良心と衝突する問題とは認識されないという。しかし、本件卒業式時、そのような事実はない。
例えば、「君が代」は歌わないと言い卒業式を欠席した卒業生の存在、キリスト教の信仰を理由に「君が代」を歌わないという生徒の情報が中学から寄せられたこと、さらには、卒業式において「国歌斉唱」を省いた式次第を卒業生自らが作成したこと、またさらには、卒業式予行の折に学校長に対し「君が代」をなぜ歌わなければならないのかと質問したこと等々—控訴人が実際に体験しただけでもこれだけの事実が存在する。(これらは証拠として提出)
大阪府立高校において、卒業式において「君が代」起立斉唱が習俗的な慣例上の儀礼的な所作として行われていた事実はない。
(3)思想・良心の侵害
そもそも「君が代」起立斉唱を強制することは、絶対無制限なものとして憲法で保障されているところの控訴人の思想・良心を直接的に制約するものである。
控訴人が教員としてこれまでに行ってきた人権教育の観点から考えれば、控訴人は「君が代」起立斉唱はできない。なぜなら、国家のシンボルである「日の丸」「君が代」が「日本人」という多数派を形成し、少数者を排除することにつながりかねないものであることを、控訴人自身は人権教育を通して経験してきたからである。そこから控訴人は、集団同調圧力の強い日本社会では、学校において「日の丸」「君が代」というシンボルを用いて生徒らを一つに束ねることが少数者を排除することになりかねない危惧をも強く抱いてきた。
さらに、控訴人は人権教育の一環として行ってきた労働法教育から、権利を主張することの重要性や少数者が排除されがちな社会的において少数者自らが表現することの意味生徒らに教えもし、自らも考えてきた。おかしいと思いながら多数者価値観に従うことが、少数者を孤立させ差別を助長し、少数者の持つ人権を尊重しない社会につながると説いてきた控訴人にとって、自身の思想・良心に反して「君が代」を起立斉唱することは、まさに集団の価値観に無条件に従いおもねることであり、自らが行ってきた人権教育の実践と矛盾することであった。
本件卒業式においても、自身の「君が代」の思いを生徒らに伝えたのは、控訴人自身の人格の中核としての思想・良心にかかわる問題だからである。(証拠提出)
原審判決は、過去の最高裁判決を引用し、「君が代」起立斉唱は特定の思想を持つことを強制するものではなく、思想と異なる外部的行為を求められるに過ぎない、いわば思想・良心の間接的な強制に過ぎないという。しかし、思想・良心というのは、何らかの外部的行為を伴う表現によってのみしか、その内容を人に伝えることができない。それを考えると、「自身の思想と異なる外部的行為を求める」ことは、「思想・良心の直接の侵害」というほかはない。
外部的行為の領域における思想・良心の自由の意義については、憲法学者西原博史氏は、「思想・良心と外部的行為のつながりこそが、憲法保障にとって決定的なポイント」であると指摘する。「良心は、そしてよく考えれば思想は、心の中で固定的なものとして保有され言語的表現を支えるだけでなく、むしろ規範として個人の行為にとっての基準を提供し、自ら行うべき行為と行ってはならない行為の間の区別を行う」機能があるゆえ、「憲法19条は外部的行為の領域においても一定の意義を持ち、個人の思想・良心と根本的に相容れない外部的行為を法秩序が強制するような場合において、そうした法義務からの免除を求める意義を持つものと解釈され」ると述べ、思想・良心の自由はもっぱら内心に関わるものであるという古典的な理論を批判する。(証拠提出)
そもそも、原審判決が引用する最高裁判決の枠組みこそが少数者を排除する理論である。「君が代」起立斉唱が広く行われていたことをもって(控訴人は前述したようにその事実も争うが)、「君が代」の起立斉唱が習俗となり無意味化したという枠組みを形成し、その中で行われる起立斉唱という行為には、何ら思想・良心の自由を侵害するような積極的な意味はないと結論づける。しかし、それこそが多数派の価値観を既成事実として、社会全体の統一的かつ優先される基準とすることで、基準にそぐわない少数者を排除することにほかならない。
憲法学者奥野恒久氏は、最高裁多数意見の問題点について、「慣例上の儀礼的所作」として「儀式の強調」をすることは、「同調圧力」をともなうため、「抑圧性・強調性はいっそう際立ったものになる」との指摘があるという。
「『心ここにあらず』の「君が代」斉唱のススメ」だとしても、「儀式において特定の行動を取るよう、子どもたちに『刷り込む』ことになるのは間違いな」く、「『君が代』を拒む者の立場を多数派に想像させる契機を摘み取る」ということである。つまり、原判決は、「慣例上の儀礼的所作」という表現により、さも既成事実があるかのように装った多数者価値観のもと、「君が代」起立斉唱はできないという控訴人に思想・良心について、少数者であることを理由にそれが多数者の価値観に対して劣るとし譲ることを是認するものである。これこそまさに少数者排除の理論である。(証拠提出)
重ねて述べるが、思想・良心の自由は、単純な精神活動であるのみならず、社会で生きる個々人の行動や生活を自律的に規律する規範ともなるものであり、人格的存立の中心にある人権である。そうすると、思想・良心の自由とは、人間が人間として生きる限り、国、地域、時代を越えて保障される普遍的人権であるといえる。
2016年9月1日、合衆国ナショナルフットボールリーグの試合において、コリン・キャパニック選手は、「黒人や有色人種を抑圧するような国の国歌に敬意は払えない」との理由から国歌斉唱の折に起立しなかった。これは、キャパニック選手の思想・良心に基づく行為であり、かつ政治的な表明である。オバマ大統領は、キャパニック選手は憲法で保障されている意見表明の自由を行使しているだけだと彼を擁護した。
現に思想・良心の自由や意見表明に対する不干渉の自由は、国際人権規約(自由権規約)の第18条、第19条において、あらゆる人間の人権として確認されている。アメリカで保障される思想・良心の自由と日本で保障される思想・良心の自由の内容に差異があることに合理性はない。
(4)「君が代」条例は違憲
原審判決は、「君が代」条例の目的は、学校教育法及び国旗国歌法の趣旨に合致するかのようにいうが、誤りである。
「君が代」条例は、その目的を第1条で記載している。そしてその対象を「府民、とりわけ次代を担う子ども」とし、「君が代」についての特定の価値観を積極的に形成させることを『君が代』条例は、「次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」を実現することと並んで、教職員らに対しては選択の余地なく「君が代」の起立斉唱を義務づけている。
国旗国歌法制定時の立法経緯に照らせば、「君が代」あるいは「日の丸」と結びつけて、「愛国心」としての意味を持たせること、さらに外部的行為を強制することは、国旗国歌法が厳格に禁止しているところである。
ならば、教育基本法や学校教育法に、いわゆる「愛国心」についていかに記載されていようとも、それをことさらに「君が代」「日の丸」と結びつけ「愛国心」の意味を持たせること、さらには、それらについて外部的行為を強制することは、国旗国歌法が厳格に禁止している。そうすると、教職員に対して「君が代」起立斉唱を強制する大阪の「君が代」条例は、国旗国歌についてのあらゆる意味での強制を禁止する国旗国歌法の趣旨に逸脱するものであり、法律の範囲を超えた条例として憲法94条に違反する。
(5)裁量権の逸脱・濫用
最高裁(1977年12月20日判決)は、公務員に対する懲戒処分について、諸般の事情の総合考慮の上で、裁量権の逸脱・濫用が判断されるのであるから、一面だけを取り上げて判断してはならないという趣旨を含むと考えられる。
ところが、原審判決は、「裁量権の範囲の逸脱またはその濫用に関する検討」の中で、本件不起立の原因ないし動機、性質ないし態様、結果ないし影響等については全く考慮にいれておらず、行為の前後における役割分担についての職務命令違反と過去の処分歴しか考慮にいれていない。
しかも、「式場内の役割を与えられて式場内にいた教員が国歌斉唱時に不起立不斉唱であった事案とは職務命令違反の態様及びその程度が相当大きいものであると評価することができる」などと判示しているが、このような判断手法が、最高裁判決に反し、またその判断内容も誤っている。
そもそも役割分担職務命令は、文書によってなされたが、終了時期等は明示されていない。しかも同僚証言によれば、役割分担は緩やかなものでしかなく、従前は管理職からすべての教員に対し式への参列が呼びかけられていたことも明らかである。また、本件卒業式において式場内の役割分担を命じられていたが式に参列せず、そのため教員席が複数空席になっている事実も認められる。それらの教員が職務命令違反に問われた事実もない。この点から見ても、役割分担は緩やかなものであったと解される。これらから、本件職務命令が式の終了まで式場外警備を命じるものであったと明確には言えない。また、仮にそうであったとしても、その違反が、原審判決が認定するような減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情とすることはできない。
控訴人が卒業式に参列したのは、何よりも、それが自分の教員としての責務だと考えたからである。教科指導や生徒指導、そして人権教育推進委員長として7期生と深くかかわったことから、控訴人は管理職である校長や教頭に何度も何度も「卒業式に参列したい」旨を伝えている。控訴人の卒業式に参列した目的はあくまでも卒業生らへの祝福であり、卒業を見定めなければならないという教員としてのある種の責務感であった。
にもかかわらず、原審判決は、控訴人が卒業式や入学式になぜ参列したのか、その動機に関して、「卒業式に参列することに意義があるとか、卒業式の主役である生徒あるいは保護者のことを第一に考えたものであるとは認めがたい」とか、「地方公務員として期待される規律や秩序を保持する義務感や学校行事の厳粛性よりも原告自らの世界観ないし価値観を優先させたものであると言わざるを得ない」と認定しているが、これは全く証拠に基づくものではなく、逆に提出されている証拠に完全に反するものである。原審判決におけるこれらの認定は裁判所の思い込みによる認定としか言いようがない。
また、本来学習指導要領に記載されている教育課程の特別活動である入学式や卒業式に参列することは教員としては当然のことである。
原審判決は、「君が代」不起立である者を式場内に入れないのは思想信条による差別であり憲法に反するとの控訴人の主張に対し、「卒業式という教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図ることを目的として発出されたものであり」、不起立が予想された控訴人を式場外任務にした本件役割分担に関する職務命令は、合理的かつ正当な理由に基づくものであり、憲法14条に違反しないと判断している。
しかし、2007年最高裁ピアノ判決において藤田宙靖裁判官が反対意見を述べたとおり、本件職務命令で達成しようとする公共的利益が何かが問われなければならない。不起立を予定している教員を式場外に排除しないと秩序の確保と式典の円滑な進行が図れないのか、思想信条に基づき式場から排除される者を出すことを許容しうるほどの公共的利益が存するのか、厳密に判断する必要がある。従前より教員各自の思想、信条に基づき不起立は存在したが、それによって入学式、卒業式が混乱し、式の円滑な遂行が不可能になったという事態は生じておらず、不起立の予定者を式場から排除する必要性は認めがたい。
現に本件戒告処分不服申立て人事委員会承認尋問において、当時、そして本件卒業式時の教頭は役割分担については、教育委員会からのマニュアルと指示により作成したことを認めている。つまり役割分担とは学校それぞれが要した役割分担ではなく、「君が代」起立か否か、すなわち個々の教員の思想・良心に着目して特定の思想・良心を有する教員を卒業式から排除する名目だけの役割分担であったことを如実に示すものである。
仮に役割分担に関する職務命令が憲法14条に違反しないとしても、不起立の予定者を式場外に排除するような役割分担は教育上の観点からは異常であり、望ましくない。このような役割分担に関する職務命令は東京その他では実施されておらず、大阪でのみ実施されている。不起立を予定している教員が真摯な動機から式に参列したとしても、それは強い非難に値するものとは到底言えない。原審判決が、役割分担に関する職務命令に違反したことをとらえて、こえを殊更に起立や秩序を害する程度が相当大きいと判断している点は、事実の評価を誤っていると言わざるを得ない。
また、原審判決は、被控訴人が主張する二重の職務命令違反を認め、単なる不起立事案とは職務命令の態様及びその程度を大きく異にすると判断するが、誤っている。なぜなら、式場外任務を命じる役割分担と起立斉唱を命じる職務命令とは両者相まって、入学式及び卒業式において不起立ゆえに式から排除するための手段であり、真摯な動機に基づき式に参列したいと願う教員にとっては、別個の職務命令というよりは、一個に結びついた職務命令といえる。不起立なら式から排除されることには到底納得がいかず、真摯に参列したいと願う教員にとっては同時にこの二つの職務命令に直面せざるを得ない。この点を考えれば、減給処分の相当性を基礎づける事情の判断において役割分担に関する職務命令違反を殊更大きく取り上げるのは相当とは言えない。
入学式での「君が代」不起立も卒業式における「不起立」も控訴人にとっては同様の行為である。卒業式における違反の程度が入学式のそれに比して大きかったということはない。原審判決は、控訴人が卒業式に丸椅子を持ち込んだことを重視しているようであるが、これは式を混乱させず円滑に進めるために控訴人が配慮したためであり、このことを過大視するのは誤っている。しかも控訴人の行動により卒業式の秩序が乱れるようなことは一切なかったわけである。そうすると、過去の処分歴以上に控訴人に対して懲戒処分を課さなければならない事情はなく、減給処分の相当性を基礎づける事情はないと言わざるを得ない。
原審判決は、本件処分は懲戒処分であり、大阪府職員基本条例27条2項は分限免職処分を決める規定であるから、同条例27条2項は本件には適用されないと判示している。しかし、大阪府職員基本条例第27条1項は職務命令違反に対する標準的な懲戒処分は戒告としながら、同一職務命令違反がさ3回に達すると標準的な分限処分は免職と規定している。現に控訴人に対しては、本件減給処分は二回目の職務命令違反に対する処分であったが、同時に、大阪府職員基本条例29条2項に基づき分限免職の警告書を交付されている。これは本件減給処分が、本件戒告処分と結びついて、大阪府職員基本条例に基づく累積加重処分としてなされたことを明確に示すものである。この大阪府職員基本条例1項と2項は結びついており、これを切り離すことはできない。本件減給処分が大阪府基本条例に基づき分限免職に向けて加重処分されたものであることは明らかであり、同条例27条2項は本件に適用されないとする原審判決は明らかに誤っている。この条例の規定は、明らかに職務命令違反について機械的な累積加重処分を予定しており、地公法に反すると共に、減給処分以上の処分についてはその相当性を基礎づける事情が必要であるとする最高裁判決に枠組みにも明確に反するものである。
また、地公法27条2項は、この法律で定める事由による場合でなければ意に反して降任、免職されず、としている。大阪府職員基本条例27条2項は同一職務命令違反による分限免職を定めているが、これは懲戒処分の積み重ねの上での分限処分であり実質的には懲戒解雇の定めである。なお、「君が代」の不起立を理由として、教員の職を奪うことを迫ることについては、もはや教職員の身分を捨てるかどうかの二者択一を迫るものであり「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的あ侵害につながるものであ」るとする東京高裁判決もある。すなわち、大阪府職員基本条例は地公法によらない免職を定めているのであり、この点でも同条例は法律に違反し憲法94条に違反するものである。
そもそも役割分担の職務命令は強い拘束力を持つものではなかったこと、控訴人は役割分担を終えて例年通り卒業式に参列したこと、卒業式の進行の円滑を妨害したり秩序を乱すことも全くなかったことに照らすと、仮にそれが何らかの懲戒の対象になるとしても、減給処分は比例原則に反して重すぎる。これは最高裁判例に照らしても認められない。本件卒業式において控訴人のみ減給処分がされたというのであれば、役割分担職務命令にしたがっていない複数の同僚教員が何ら処分されていないことに照らすと、明らかに行政処分としての懲戒処分が準則とすべき比例原則に反する。
最後に、以下の判例に照らしても本件減給処分の妥当性を欠く。
ア 2012年東京高裁判決
イ 2012年10月25日東京高裁判決
ウ 2012年10月31日東京高裁判決
エ 2013年2月26日東京高裁判決
オ 2016年7月19日東京高裁判決
(6)結語
原審判決は、事実認定に誤りがある。さらに思想・良心の保障についての憲法19条の解釈についての誤り、大阪府国旗国歌条例が法律の範囲を超える条例であることについて憲法94条のあてはめの誤り、さらには行政の裁量権の理解について先例となる数々の裁判例・判例と矛盾する誤りがあるところ、直ちに破棄されるべきである。
11月9日、驚くほどの差別発言を繰り返していたドナルド・トランプ氏が合衆国大統領に当選しました。政策以前の問題としてあれほどの人権侵害を、白昼しかも公的な場で行っていた人物が国民の支持を得て当選する現実はめまいを覚えるほどです。しかし、振り返ってみると、日本でも同じ現象が起こっているのではないでしょうか。安倍総理をはじめとする内閣のお歴々、鶴保沖縄担当相、稲田法相、、、そして、大阪の橋下徹元大阪府知事・市長、松井現大阪府知事、かれら政治家のヘイトスピーチさながらの発言が、実はそれを支持する人々に支えられながら、ますます差別と偏見が広がっていく悪循環は同じ構造であるように思います。
私は、今、大連で控訴審に向け準備をしながら、奥野さんの「君が代」不起立減給処分取消が高裁においても認められなかったこと、入れ墨アンケート拒否処分取消がついに最高裁でも認められなかったこと―これらの事実を前に、もう一度、人権について根源的なところから問い直し共有する必要性を感じています。政治が、司法が不当であればあるほど、私たちは声を出さなければならないのかもしれません。おそらく今多くの方がそう思われているのではないでしょうか。オラッショレイ♪オラッショレイ♪あきらめない!
さて、9月12日、大阪高裁に控訴理由書を提出しました。既に、ブログ「教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク」(Tネット)で全文を公開していますが、ここでは、その要点を紹介し、皆様方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
控訴理由書要約版
(1)事実認定における致命的な欠陥
原審判決では、減給処分取消を棄却する前提として人事委員会における戒告処分承認との裁決をあげているが、これは紛れもない事実認定の誤りである。(人事委員会の係属証明書を証拠として提出)
また、卒業式に参列した動機について、原審における供述、証言、証拠を何ら吟味もせず、「原告自らの世界観ないし価値観を優先させた」と認定している。
そもそも、憲法が保障する三権分立のもと、司法裁判所の判断が立法権・行政権に優越する判断とされているのは、裁判官が事実認定については証拠に基づいて客観的に認定するという判断過程の公正さがあってのことである。
ところが、原審判決はこのように証拠に基づかない事実認定を前提としている。これは、司法裁判所の判断に対する社会的信頼をも毀損するものである。このような大きな欠陥のある原審判決は直ちに破棄されるべきである。
(2)「君が代」起立斉唱は慣例上の儀礼的所作ではない
原審判決は、卒業式における「君が代」起立斉唱は、習俗的な「慣例上の儀礼的所作」であるゆえ、それが控訴人の思想・良心を直接に侵害するものではないとし、そもそも外部的にも思想・良心と衝突する問題とは認識されないという。しかし、本件卒業式時、そのような事実はない。
例えば、「君が代」は歌わないと言い卒業式を欠席した卒業生の存在、キリスト教の信仰を理由に「君が代」を歌わないという生徒の情報が中学から寄せられたこと、さらには、卒業式において「国歌斉唱」を省いた式次第を卒業生自らが作成したこと、またさらには、卒業式予行の折に学校長に対し「君が代」をなぜ歌わなければならないのかと質問したこと等々—控訴人が実際に体験しただけでもこれだけの事実が存在する。(これらは証拠として提出)
大阪府立高校において、卒業式において「君が代」起立斉唱が習俗的な慣例上の儀礼的な所作として行われていた事実はない。
(3)思想・良心の侵害
そもそも「君が代」起立斉唱を強制することは、絶対無制限なものとして憲法で保障されているところの控訴人の思想・良心を直接的に制約するものである。
控訴人が教員としてこれまでに行ってきた人権教育の観点から考えれば、控訴人は「君が代」起立斉唱はできない。なぜなら、国家のシンボルである「日の丸」「君が代」が「日本人」という多数派を形成し、少数者を排除することにつながりかねないものであることを、控訴人自身は人権教育を通して経験してきたからである。そこから控訴人は、集団同調圧力の強い日本社会では、学校において「日の丸」「君が代」というシンボルを用いて生徒らを一つに束ねることが少数者を排除することになりかねない危惧をも強く抱いてきた。
さらに、控訴人は人権教育の一環として行ってきた労働法教育から、権利を主張することの重要性や少数者が排除されがちな社会的において少数者自らが表現することの意味生徒らに教えもし、自らも考えてきた。おかしいと思いながら多数者価値観に従うことが、少数者を孤立させ差別を助長し、少数者の持つ人権を尊重しない社会につながると説いてきた控訴人にとって、自身の思想・良心に反して「君が代」を起立斉唱することは、まさに集団の価値観に無条件に従いおもねることであり、自らが行ってきた人権教育の実践と矛盾することであった。
本件卒業式においても、自身の「君が代」の思いを生徒らに伝えたのは、控訴人自身の人格の中核としての思想・良心にかかわる問題だからである。(証拠提出)
原審判決は、過去の最高裁判決を引用し、「君が代」起立斉唱は特定の思想を持つことを強制するものではなく、思想と異なる外部的行為を求められるに過ぎない、いわば思想・良心の間接的な強制に過ぎないという。しかし、思想・良心というのは、何らかの外部的行為を伴う表現によってのみしか、その内容を人に伝えることができない。それを考えると、「自身の思想と異なる外部的行為を求める」ことは、「思想・良心の直接の侵害」というほかはない。
外部的行為の領域における思想・良心の自由の意義については、憲法学者西原博史氏は、「思想・良心と外部的行為のつながりこそが、憲法保障にとって決定的なポイント」であると指摘する。「良心は、そしてよく考えれば思想は、心の中で固定的なものとして保有され言語的表現を支えるだけでなく、むしろ規範として個人の行為にとっての基準を提供し、自ら行うべき行為と行ってはならない行為の間の区別を行う」機能があるゆえ、「憲法19条は外部的行為の領域においても一定の意義を持ち、個人の思想・良心と根本的に相容れない外部的行為を法秩序が強制するような場合において、そうした法義務からの免除を求める意義を持つものと解釈され」ると述べ、思想・良心の自由はもっぱら内心に関わるものであるという古典的な理論を批判する。(証拠提出)
そもそも、原審判決が引用する最高裁判決の枠組みこそが少数者を排除する理論である。「君が代」起立斉唱が広く行われていたことをもって(控訴人は前述したようにその事実も争うが)、「君が代」の起立斉唱が習俗となり無意味化したという枠組みを形成し、その中で行われる起立斉唱という行為には、何ら思想・良心の自由を侵害するような積極的な意味はないと結論づける。しかし、それこそが多数派の価値観を既成事実として、社会全体の統一的かつ優先される基準とすることで、基準にそぐわない少数者を排除することにほかならない。
憲法学者奥野恒久氏は、最高裁多数意見の問題点について、「慣例上の儀礼的所作」として「儀式の強調」をすることは、「同調圧力」をともなうため、「抑圧性・強調性はいっそう際立ったものになる」との指摘があるという。
「『心ここにあらず』の「君が代」斉唱のススメ」だとしても、「儀式において特定の行動を取るよう、子どもたちに『刷り込む』ことになるのは間違いな」く、「『君が代』を拒む者の立場を多数派に想像させる契機を摘み取る」ということである。つまり、原判決は、「慣例上の儀礼的所作」という表現により、さも既成事実があるかのように装った多数者価値観のもと、「君が代」起立斉唱はできないという控訴人に思想・良心について、少数者であることを理由にそれが多数者の価値観に対して劣るとし譲ることを是認するものである。これこそまさに少数者排除の理論である。(証拠提出)
重ねて述べるが、思想・良心の自由は、単純な精神活動であるのみならず、社会で生きる個々人の行動や生活を自律的に規律する規範ともなるものであり、人格的存立の中心にある人権である。そうすると、思想・良心の自由とは、人間が人間として生きる限り、国、地域、時代を越えて保障される普遍的人権であるといえる。
2016年9月1日、合衆国ナショナルフットボールリーグの試合において、コリン・キャパニック選手は、「黒人や有色人種を抑圧するような国の国歌に敬意は払えない」との理由から国歌斉唱の折に起立しなかった。これは、キャパニック選手の思想・良心に基づく行為であり、かつ政治的な表明である。オバマ大統領は、キャパニック選手は憲法で保障されている意見表明の自由を行使しているだけだと彼を擁護した。
現に思想・良心の自由や意見表明に対する不干渉の自由は、国際人権規約(自由権規約)の第18条、第19条において、あらゆる人間の人権として確認されている。アメリカで保障される思想・良心の自由と日本で保障される思想・良心の自由の内容に差異があることに合理性はない。
(4)「君が代」条例は違憲
原審判決は、「君が代」条例の目的は、学校教育法及び国旗国歌法の趣旨に合致するかのようにいうが、誤りである。
「君が代」条例は、その目的を第1条で記載している。そしてその対象を「府民、とりわけ次代を担う子ども」とし、「君が代」についての特定の価値観を積極的に形成させることを『君が代』条例は、「次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」を実現することと並んで、教職員らに対しては選択の余地なく「君が代」の起立斉唱を義務づけている。
国旗国歌法制定時の立法経緯に照らせば、「君が代」あるいは「日の丸」と結びつけて、「愛国心」としての意味を持たせること、さらに外部的行為を強制することは、国旗国歌法が厳格に禁止しているところである。
ならば、教育基本法や学校教育法に、いわゆる「愛国心」についていかに記載されていようとも、それをことさらに「君が代」「日の丸」と結びつけ「愛国心」の意味を持たせること、さらには、それらについて外部的行為を強制することは、国旗国歌法が厳格に禁止している。そうすると、教職員に対して「君が代」起立斉唱を強制する大阪の「君が代」条例は、国旗国歌についてのあらゆる意味での強制を禁止する国旗国歌法の趣旨に逸脱するものであり、法律の範囲を超えた条例として憲法94条に違反する。
(5)裁量権の逸脱・濫用
最高裁(1977年12月20日判決)は、公務員に対する懲戒処分について、諸般の事情の総合考慮の上で、裁量権の逸脱・濫用が判断されるのであるから、一面だけを取り上げて判断してはならないという趣旨を含むと考えられる。
ところが、原審判決は、「裁量権の範囲の逸脱またはその濫用に関する検討」の中で、本件不起立の原因ないし動機、性質ないし態様、結果ないし影響等については全く考慮にいれておらず、行為の前後における役割分担についての職務命令違反と過去の処分歴しか考慮にいれていない。
しかも、「式場内の役割を与えられて式場内にいた教員が国歌斉唱時に不起立不斉唱であった事案とは職務命令違反の態様及びその程度が相当大きいものであると評価することができる」などと判示しているが、このような判断手法が、最高裁判決に反し、またその判断内容も誤っている。
そもそも役割分担職務命令は、文書によってなされたが、終了時期等は明示されていない。しかも同僚証言によれば、役割分担は緩やかなものでしかなく、従前は管理職からすべての教員に対し式への参列が呼びかけられていたことも明らかである。また、本件卒業式において式場内の役割分担を命じられていたが式に参列せず、そのため教員席が複数空席になっている事実も認められる。それらの教員が職務命令違反に問われた事実もない。この点から見ても、役割分担は緩やかなものであったと解される。これらから、本件職務命令が式の終了まで式場外警備を命じるものであったと明確には言えない。また、仮にそうであったとしても、その違反が、原審判決が認定するような減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情とすることはできない。
控訴人が卒業式に参列したのは、何よりも、それが自分の教員としての責務だと考えたからである。教科指導や生徒指導、そして人権教育推進委員長として7期生と深くかかわったことから、控訴人は管理職である校長や教頭に何度も何度も「卒業式に参列したい」旨を伝えている。控訴人の卒業式に参列した目的はあくまでも卒業生らへの祝福であり、卒業を見定めなければならないという教員としてのある種の責務感であった。
にもかかわらず、原審判決は、控訴人が卒業式や入学式になぜ参列したのか、その動機に関して、「卒業式に参列することに意義があるとか、卒業式の主役である生徒あるいは保護者のことを第一に考えたものであるとは認めがたい」とか、「地方公務員として期待される規律や秩序を保持する義務感や学校行事の厳粛性よりも原告自らの世界観ないし価値観を優先させたものであると言わざるを得ない」と認定しているが、これは全く証拠に基づくものではなく、逆に提出されている証拠に完全に反するものである。原審判決におけるこれらの認定は裁判所の思い込みによる認定としか言いようがない。
また、本来学習指導要領に記載されている教育課程の特別活動である入学式や卒業式に参列することは教員としては当然のことである。
原審判決は、「君が代」不起立である者を式場内に入れないのは思想信条による差別であり憲法に反するとの控訴人の主張に対し、「卒業式という教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図ることを目的として発出されたものであり」、不起立が予想された控訴人を式場外任務にした本件役割分担に関する職務命令は、合理的かつ正当な理由に基づくものであり、憲法14条に違反しないと判断している。
しかし、2007年最高裁ピアノ判決において藤田宙靖裁判官が反対意見を述べたとおり、本件職務命令で達成しようとする公共的利益が何かが問われなければならない。不起立を予定している教員を式場外に排除しないと秩序の確保と式典の円滑な進行が図れないのか、思想信条に基づき式場から排除される者を出すことを許容しうるほどの公共的利益が存するのか、厳密に判断する必要がある。従前より教員各自の思想、信条に基づき不起立は存在したが、それによって入学式、卒業式が混乱し、式の円滑な遂行が不可能になったという事態は生じておらず、不起立の予定者を式場から排除する必要性は認めがたい。
現に本件戒告処分不服申立て人事委員会承認尋問において、当時、そして本件卒業式時の教頭は役割分担については、教育委員会からのマニュアルと指示により作成したことを認めている。つまり役割分担とは学校それぞれが要した役割分担ではなく、「君が代」起立か否か、すなわち個々の教員の思想・良心に着目して特定の思想・良心を有する教員を卒業式から排除する名目だけの役割分担であったことを如実に示すものである。
仮に役割分担に関する職務命令が憲法14条に違反しないとしても、不起立の予定者を式場外に排除するような役割分担は教育上の観点からは異常であり、望ましくない。このような役割分担に関する職務命令は東京その他では実施されておらず、大阪でのみ実施されている。不起立を予定している教員が真摯な動機から式に参列したとしても、それは強い非難に値するものとは到底言えない。原審判決が、役割分担に関する職務命令に違反したことをとらえて、こえを殊更に起立や秩序を害する程度が相当大きいと判断している点は、事実の評価を誤っていると言わざるを得ない。
また、原審判決は、被控訴人が主張する二重の職務命令違反を認め、単なる不起立事案とは職務命令の態様及びその程度を大きく異にすると判断するが、誤っている。なぜなら、式場外任務を命じる役割分担と起立斉唱を命じる職務命令とは両者相まって、入学式及び卒業式において不起立ゆえに式から排除するための手段であり、真摯な動機に基づき式に参列したいと願う教員にとっては、別個の職務命令というよりは、一個に結びついた職務命令といえる。不起立なら式から排除されることには到底納得がいかず、真摯に参列したいと願う教員にとっては同時にこの二つの職務命令に直面せざるを得ない。この点を考えれば、減給処分の相当性を基礎づける事情の判断において役割分担に関する職務命令違反を殊更大きく取り上げるのは相当とは言えない。
入学式での「君が代」不起立も卒業式における「不起立」も控訴人にとっては同様の行為である。卒業式における違反の程度が入学式のそれに比して大きかったということはない。原審判決は、控訴人が卒業式に丸椅子を持ち込んだことを重視しているようであるが、これは式を混乱させず円滑に進めるために控訴人が配慮したためであり、このことを過大視するのは誤っている。しかも控訴人の行動により卒業式の秩序が乱れるようなことは一切なかったわけである。そうすると、過去の処分歴以上に控訴人に対して懲戒処分を課さなければならない事情はなく、減給処分の相当性を基礎づける事情はないと言わざるを得ない。
原審判決は、本件処分は懲戒処分であり、大阪府職員基本条例27条2項は分限免職処分を決める規定であるから、同条例27条2項は本件には適用されないと判示している。しかし、大阪府職員基本条例第27条1項は職務命令違反に対する標準的な懲戒処分は戒告としながら、同一職務命令違反がさ3回に達すると標準的な分限処分は免職と規定している。現に控訴人に対しては、本件減給処分は二回目の職務命令違反に対する処分であったが、同時に、大阪府職員基本条例29条2項に基づき分限免職の警告書を交付されている。これは本件減給処分が、本件戒告処分と結びついて、大阪府職員基本条例に基づく累積加重処分としてなされたことを明確に示すものである。この大阪府職員基本条例1項と2項は結びついており、これを切り離すことはできない。本件減給処分が大阪府基本条例に基づき分限免職に向けて加重処分されたものであることは明らかであり、同条例27条2項は本件に適用されないとする原審判決は明らかに誤っている。この条例の規定は、明らかに職務命令違反について機械的な累積加重処分を予定しており、地公法に反すると共に、減給処分以上の処分についてはその相当性を基礎づける事情が必要であるとする最高裁判決に枠組みにも明確に反するものである。
また、地公法27条2項は、この法律で定める事由による場合でなければ意に反して降任、免職されず、としている。大阪府職員基本条例27条2項は同一職務命令違反による分限免職を定めているが、これは懲戒処分の積み重ねの上での分限処分であり実質的には懲戒解雇の定めである。なお、「君が代」の不起立を理由として、教員の職を奪うことを迫ることについては、もはや教職員の身分を捨てるかどうかの二者択一を迫るものであり「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的あ侵害につながるものであ」るとする東京高裁判決もある。すなわち、大阪府職員基本条例は地公法によらない免職を定めているのであり、この点でも同条例は法律に違反し憲法94条に違反するものである。
そもそも役割分担の職務命令は強い拘束力を持つものではなかったこと、控訴人は役割分担を終えて例年通り卒業式に参列したこと、卒業式の進行の円滑を妨害したり秩序を乱すことも全くなかったことに照らすと、仮にそれが何らかの懲戒の対象になるとしても、減給処分は比例原則に反して重すぎる。これは最高裁判例に照らしても認められない。本件卒業式において控訴人のみ減給処分がされたというのであれば、役割分担職務命令にしたがっていない複数の同僚教員が何ら処分されていないことに照らすと、明らかに行政処分としての懲戒処分が準則とすべき比例原則に反する。
最後に、以下の判例に照らしても本件減給処分の妥当性を欠く。
ア 2012年東京高裁判決
イ 2012年10月25日東京高裁判決
ウ 2012年10月31日東京高裁判決
エ 2013年2月26日東京高裁判決
オ 2016年7月19日東京高裁判決
(6)結語
原審判決は、事実認定に誤りがある。さらに思想・良心の保障についての憲法19条の解釈についての誤り、大阪府国旗国歌条例が法律の範囲を超える条例であることについて憲法94条のあてはめの誤り、さらには行政の裁量権の理解について先例となる数々の裁判例・判例と矛盾する誤りがあるところ、直ちに破棄されるべきである。