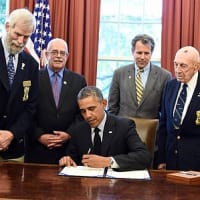武田 知弘著(評者:栗原 裕一郎)
祥伝社新書、780円(税別)
第一次世界大戦での敗戦により支払不能なほどの賠償金を負わされたドイツは、ハイパーインフレーションに見舞われ経済がほとんど崩壊しかけていた。一時、持ち直しかけたりしたものの、息つく間もなく今度は世界恐慌に襲われ壊滅的な打撃を受けてしまう。そんな大不況のなか、生活が破綻した中産階級や労働者、農民らの怒りを吸収して支持を伸ばしたヒトラーが政権を取る。
ナチスは、ドイツ経済に驚異的とも奇跡的ともいいうる復興をもたらす。失業問題をわずか数年で解決し、経済を安定させ、世界恐慌からいち早く抜け出すことに成功したのである。
ナチスというと暗黒の支配といったイメージが強いが、一方で、大胆な政策によって国を立て直し、国民を厚くケアした福祉国家という別の顔も持っていた。だからこそヒトラーは熱狂的な支持を集め続けたわけだ。
いったいどんなマジカルな政策をヒトラーは繰り出しのか? 本書は、経済政策という側面から、ヒトラーおよびナチスを探った、ちょっと珍しい一冊である。
ナチス政権誕生までのドイツ経済の足取りを簡単に振り返っておこう。
第一次大戦に敗戦したドイツはベルサイユ条約により植民地全部と領土の一部を取り上げられたうえ、1320億マルク(330億ドル)の賠償金を請求された。ドイツの当時の歳入20年分くらいの額であり、毎年の支払いは歳入の2分の1から3分の1に及んだ。
そんなもの払えるわけがない。札をガンガン刷ったドイツは、1922年から1923年にかけてハイパーインフレーションに見舞われてしまうことになる。どのくらいハイパーだったかというと、0.2~0.3マルクだった新聞が1923年11月には80億マルクに暴騰する勢いだったそうである(村瀬興雄『ナチズム』中公新書)。
ハイパーインフレによってもっとも打撃を受けたのは中産階級や労働者、農民だった。一方で、外貨でドイツの資産を買ったりしてボロ儲けする者もいたのだが、そのなかにはユダヤ人実業家が少なからず含まれていた。その怨みもユダヤ人迫害の一因となる。
このハイパーインフレを止めたのは、ヒャルマール・シャハトという銀行家である。ときの首相シュトレーゼマンにより通貨全権委員に任命されたシャハトは、兌換紙幣「レンテンマルク」を発行し、同時にデノミを実行してインフレを収束させることに成功、1926年ごろからドイツ経済は回復に向った。この「レンテンマルクの奇跡」により、シャハトはドイツ国民から英雄視されることとなった。
だが、好況も束の間、1929年10月、ウォール街暴落をきっかけに世界恐慌が起こり、アメリカからの投機マネーに依存していたドイツは深刻な不況におちいってしまうのである。
資本主義と社会主義のいいとこ取り
ヒトラーが政権を取るのは出口なしの大不況にあえぐ最中の1932年のこと。そのころドイツは、財政赤字を補うために不況下にもかかわらずデフレ政策を取って困窮する国民をさらに苦境に落とすという最悪の状態にあり、失業者は600万人に登っていた。全労働者数の3分の1にあたる数字だ。
ナチスは、この莫大な失業者をほんの3年ほどで恐慌以前の160万人にまで減らし、経済をみごとに回復させたのである。
その経済政策はひとことでいえば、〈資本主義と社会主義両方の長所を生かしつつ、欠点を修正する〉というものであった。
アウトバーン計画を筆頭に公共事業によって雇用を創出するというのがメインの政策で、初年度だけで20億マルクが計上されたという。
大不況のなか、どこからそんなカネが降ってわいてきたのかというと、国債を大量に発行したのである。そんな乱暴なことをしたらまたハイパーインフレになりそうなものだが、これが上手くいって、ナチス・ドイツは不況からあっさり脱出する。
この計画を主導したのはシャハト。先に見た「レンテンマルクの奇跡」の英雄である。ヒトラーはシャハトをかき口説き、ナチスの経済大臣に迎えていたのだ。
アウトバーン建設は、雇用を創出しただけに止まらず、大動脈としてドイツ産業の発展に大きく寄与した。さらに、大規模な事業計画を行なうと積極的にアナウンスすることで、人々に景気回復の期待を持たせるよう働きかけもした。景気が良くなるとみんなが思えばサイフの紐が緩んで本当に景気が良くなるのである。
その他、中高年を優先的に雇用する、大規模店の出店を制限して中小店を守る、中小企業への融資制度を整える、価格統制により物価を安定させる、農家を保護する、結婚を促進し少子化を予防するなどなど、国民と経済を保護することに関しては、およそ考えつくかぎりの手段を講じたのであった。
一方で、公共事業による景気回復で生じた利益を国庫に回収するシステムもつくりあげていた。企業に対しては「配当制限法」という法律を課し一定以上の利益が出た場合は公債を買うことを義務づけ、個人に対しては貯蓄を促す制度を準備したのである。
ここまでは政府が市場に積極的に介入するケインズ政策の亜種という印象であるが、ナチスは政権を取ると直ちに労働組合を解体し、ストライキを禁止していた。
このへんが社会主義的な要素で、そんなことをすれば労働者の地位が悪化しそうだけれど、ドイツという労働者の国の伝統が絶妙なバランスを実現させたのか、大きな破綻なく労働者の環境および待遇は向上していった。
労働組合に代わり、資本家も労働者も同胞であるとする「労働戦線」が組織されたのだが、これがよく考えられた仕組みで、理念だけではなく「国民労働統制法」という法律でも制御されており、労働者を管理しつつ不満を吸収できるシステムをつくりあげたのだ。
健康診断や有給休暇はもとより住宅にいたるまで労働環境も十分すぎるほどに整備されていたし、また、労働戦線に付随した「歓喜力行団」という組織により、労働者には、レジャーや娯楽までもがふんだんに提供されていた。
その延長線上で企画されたのがフォルクスワーゲンだった。のちにドイツの国民車となるフォルクスワーゲンは、庶民も自家用車が持てるようにしようとナチスが国家プロジェクトとして手掛けたものだったのである。
しかし、このプロジェクトをヒトラーは実現できなかった。ポーランド侵攻を機に第二次世界大戦へ突入していくナチスは、始動待ちの工場を軍需施設に切り替えたのであった……。
失業問題の解消と経済の安定という目標を達成したナチスは、1936年から次なる経済政策にシフトする。具体的には「自給自足」と「戦争できる国力」を目標に設定するのだが、ここから迷走が始まる。
ここまで見てきた夢のように充実した政策を敷いてきたのはシャハトだったわけだが、そのシャハトを切り、経済にはまるで素人のゲーリングに政策を任せてしまうのである。
当然のように自給自足計画にことごとく失敗したナチスは経済的に逼迫していく。
ナチスに残された道は勝利か滅亡しかない
近隣国への侵攻も、ナチスの認識としては「侵攻」ではなく、ベルサイユ条約によって奪われたかつての領土を「奪回」し「自給自足」を目指すための行動の一環だった。
〈植民地をたくさん持っている国は、ことさらに貿易をしないでもやっていける。/しかしベルサイユ条約で植民地を全部取られているドイツとしてはとてもやっていけない。貿易が縮小されれば、食料にさえ事を欠くようになってしまう。/そこで生活圏を得るために、第一次世界大戦以前に持っていた領土、植民地を奪還するというのが、ナチスの目標のひとつだった〉
ナチスの経済政策は結局は破綻してしまったわけだが、原因は何だったのだろうか。
著者は、中央銀行の独立性を、ヒトラーが犯してしまったことに主因を見ている。
軍備拡大に同意しなかったシャハトの首を切ったあと、ヒトラーはドイツ帝国銀行を国有化し、軍事費を捻出するために公債を乱発した。
「この戦争では勝利か滅亡しかない」
ヒトラーがそう叫んだのは、負けを認めれば、莫大に発行した国債がとてつもないインフレを引き起こすことがわかっていたからだと著者はいう。
〈ナチスは軍備のために莫大な借金を背負い、その借金のために崩壊したといえるのだ〉
そのほか、アメリカの第二次大戦参戦の本当の理由は、ナチスが準備しており、ケインズが絶賛したという「欧州新経済秩序」を阻止するのが目的だったのではないかといった説も披露されている。欧州新経済秩序とは、1940年に発表された現在のユーロを先取りしたような計画で、管理通貨制度に移行し、マルクを欧州全域で流通させようとしたものである。当時世界の金の7割を保有していたアメリカとしては、金の価値を守るために参戦する必要があったのではないかというわけだ。
さて著者は、ナチスの経済政策が〈現代、資本主義の過酷な競争社会に限界を感じているわれわれに、なんらかのヒントを与えるものではないだろうか?〉とまえがきに書いている。
金融資本主義が破綻したのでケインズ政策的な要素を取り込みたいというのはわからないではないけど……と考えつつ読んだのだが、ところどころでひやっとするフレーズに遭遇した。
〈徹底的に経済効率を高めることが、必ずしも心豊かな生活を営むこととイコールではないのではないか。ナチスの政策を見ていると、そういうことを考えさせられる〉
〈「独裁体制」は、人類が国家のシステムとして使いこなすには、まだ難しいということかもしれない〉
うーむ、著者の武田さんはもしかしたらわりと左寄りの思想をお持ちの方なのだろうか。まあ、それを割り引いても(割り引けばというか)、示唆に富んだ、教えられること大の一冊なのだが。
(文/栗原 裕一郎、企画・編集/須藤 輝&連結社)
2009年5月29日(金)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090528/195992/
どちらも最初は見下されていた~『ユダヤ人とダイヤモンド』
守 誠著(評者:朝山 実)
幻冬舎新書、800円(税別)
こどものころ、学研の「科学と学習」を売り込みに、業者(あれは町の本屋さんだったのか)が学校にやってくることがあった。
だいたい春先に、年間購読を募るのだが、希望者は申し込んでくださいというだけ。担任教師は、気乗りしない様子だった。
月刊誌本体の記憶はあやふやだが、付録の鉱石セットだけはケースの色形まではっきりおぼえている。花崗岩などの石ころに混じって、ルビーやエメラルドの原石が入っていた。
宝石=高価、それがオマケで付いてくる、すごい!! 大ニュースじゃないか。なんでこれが大騒ぎにならないのか、不思議だった。
「どうや、センセ、すごいやろ」と箱から、グリーンの石を差し出すと、担任は「よかったわね」と、しげしげと見て返してきた。うらやましそうではない。「大切にしなさいよ」といいながら、ハナで笑うような顔だった。それらは加工されてはじめて、宝石になるというのを知ったのは、だいぶ後のことだ。
そんなことをふいに思い出したのは、銀座にオープンしたフランスのジュエリーショップが、店頭で5000個のダイヤを無料プレゼントするというので、長い行列ができている、とニュースで取り上げていたからだ。
ホンモノのダイヤには違いなかろうが、落とせば失せてしまいそうな小粒の裸石。何万円か支払えば装飾品にしてくれるという。早朝から行列をつくっているのは、ジュエリーとは無縁そうな男性たちという光景。イメージ戦略としてヒットしているのかどうかわからないが、テレビカメラが集まったのを宣伝費として考えたなら、タダで配ってもおつりはくるってことなのか。
さて、本書は、価値があるんだかないんだかわからないダイヤモンドの歴史をひもとくものだ。著者は元商社マンで、ダイヤの輸入に関わり、調べていくうちにユダヤ人の歴史と深く結びついていくことを知ったという。発端は40年ちかく前のことだというから、研究はすでにライフワーク化している。
「三流の石」が「希少なもの」に
意外なのは、ほんの200~300年前まで、ダイヤモンドは硬すぎて加工しにくく、宝石としては「三流の石」扱いだったことだ。16世紀、いちばん高価だったルビーと比べたら1カラットあたりの価格は、8分の1に過ぎなかったとか。
もともと加工職人や仲買商には、ユダヤ人が多かった。それには、当時のヨーロッパでは、ユダヤ人に対して職業規制が課せられていたことが関係していた。ダイヤは儲けがうすい。だから、働き手は少なく、就労の規制もない。つまり、ほかの人たちがやりたがらなかったわけだ。
そんな日陰のダイヤが脚光を浴びるのは、17世紀になって、「ブリリアント・カット」なる研磨技術が開発されてからのことだ(開発者にあたる研磨工については諸説あって、特定されていない)。
しかし、ダイヤの価格は一定しない。19世紀に入って、南アフリカで鉱山が次々と発見されるや、供給過剰となり、価格の暴落を招いた。このとき巨大な資本を注入し、強引に鉱山を束ねて、市場を安定させたのが、ユダヤ人のロスチャイルド家だった。
そして、20世紀。「ダイヤモンド王」アーネスト・オッペンハイマーが登場する。1880年、ドイツのタバコ商人の子として生まれた彼は、17歳でロンドンのダイヤモンド・ブローカーに入社し、南アで原石の買い付け担当をしたのち、経緯はよくわからないが、金の採掘で得た資産を元手に、1920年、ダイヤモンド業界に舞い戻り、原石販売のカルテルを構築する。
彼が歴史に名を残せたのは、過剰となりつつあったダイヤを「希少なもの」に見せかけ、高価格で安定させることに成功したからだ。その手腕は「限りなく詐欺師に近いビジネスマン」ともいわれた。
オッペンハイマーがユダヤ人だったことから、「ダイヤとユダヤ人」のつながりを印象付けることにもなったといわれる。しかし、本書では、晩年のオッペンハイマーがユダヤ教からキリスト教に改宗したエピソードに触れながら、なぞの多いその真相に迫ろうともしている。
また、エピソードとして驚きなのは、ナチス・ドイツとダイヤの関係だ。
1939年、ドイツ軍のポーランド侵攻により第二次世界大戦は幕を開けた。そのポーランド占領後、ドイツが次の標的にしたのは、ベルギーとオランダだった。
なぜ、ベルギーとオランダだったのか。イギリス攻撃の拠点とする目的があったといわれているが、著者によれば、もうひとつの理由が隠されていたという。
当時、ベルギーのアントワープは、世界最大のダイヤモンド加工センターだった。2万5千人の研磨工がいて、ユダヤ人ダイヤモンド商たちで街は賑わいをみせていた。
〈戦争で勝利をおさめるためには膨大な資金が必要だ。ダイヤモンドは軽くて高価で略奪商品としては、もっとも換金しやすい。また軍需工場にとり不可欠な戦略物資である〉
ベルギー侵攻には、ユダヤ人から根こそぎダイヤモンドを奪い取る企みが隠されていた。著者は、戦後にアントワープのジャーナリストがまとめた小冊子をもとに、ナチス・ドイツがどれだけ綿密な計画を練っていたのか、詳細を明らかにしている。
一度はベルギーからフランスへと逃げ出したユダヤ人たちに、ナチスは、迫害を加えるどころか「微笑」を示した。ユダヤ人たちを安心させ、アントワープへと帰還させたのち、時間をかけ、さらに油断させるために、不満の聞き手にもなった。伝えられる迫害は、自分たちには及ばないものだと信じ込ませたのだ。
ユダヤ人をだましたナチスをだました男
計画を練ったのはドイツ経済省で、直接手を下したのが悪名高きゲシュタポ(国家秘密警察)である。占領から2年後、彼らは、ユダヤ人たちがこれまで扱ってきたダイヤの取引記録をあらいざらい申告させ、全容を把握した上で、一粒残らずダイヤを没収し、強制収容所へと送りこんだ。
しかも、作戦の中枢を担ったドイツ人の役人フレンゼルは、あのゲシュタポさえだまくらかして、発覚すれば処刑は確実の、ダイヤのネコババをやってのけた。二重の詐欺を働いた「ユダヤ人ダイヤモンド所持品の総括管理監督責任者」の悪行は、露見することなく戦争終結に至り、彼が横領したダイヤもどこかに消えたままだという。
ほかにも、本書は、ユダヤやダイヤに関する「知っていますか?」的なエピソードの宝庫である。
著者は、資料や文献を集めるだけでなく、イラク軍がクウェートに侵攻した湾岸戦争時に、テルアビブを訪れるなどしている。その際の記述は、臨場感あふれるものだ。
イラクのフセイン大統領がイエラエルに向けスカッド・ミサイルを発射するとぶち上げた直後とあって、「万一の場合に」と取材相手のダイヤモンド商から、いきなりガスマスクを差し出された。
大航海時代にインドからダイヤモンドの原石をヨーロッパにもたらしたのはユダヤ人だと落ち着き払って講義するのを、著者は、いまにものミサイルが……と話を聞くどころではない。危険を承知でわざわざ尋ねて行ったにもかかわらず、なんと著者は、取材を早々に切り上げ、翌日にはおおあわてでテルアビブを脱出している。
おかげで著者は貴重な取材相手と連絡をとれないままだという。しかし、わらうなんてことはできない。命あってのことだ。
残念なのは、そうしたナマミの著者が登場するのが、この一場面かぎりだということだ。オッペンハイマーやフレンゼルなどの、なぞめいた人物像への興味をかきたてられるいっぽうで、柱となる「ダイヤモンドとユダヤ人」の関係そのものは、学生時代、午後に睡魔と格闘しながらうけた授業のようなきまじめさで、個としてのユダヤ人の顔がなかなか見えてこないのは難点である。取材のしすぎで、歴史の整理に労をとられてしまったためかもしれないが。
(文/朝山 実、企画・編集/須藤 輝&連結社)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090603/196576/?P=1
祥伝社新書、780円(税別)
第一次世界大戦での敗戦により支払不能なほどの賠償金を負わされたドイツは、ハイパーインフレーションに見舞われ経済がほとんど崩壊しかけていた。一時、持ち直しかけたりしたものの、息つく間もなく今度は世界恐慌に襲われ壊滅的な打撃を受けてしまう。そんな大不況のなか、生活が破綻した中産階級や労働者、農民らの怒りを吸収して支持を伸ばしたヒトラーが政権を取る。
ナチスは、ドイツ経済に驚異的とも奇跡的ともいいうる復興をもたらす。失業問題をわずか数年で解決し、経済を安定させ、世界恐慌からいち早く抜け出すことに成功したのである。
ナチスというと暗黒の支配といったイメージが強いが、一方で、大胆な政策によって国を立て直し、国民を厚くケアした福祉国家という別の顔も持っていた。だからこそヒトラーは熱狂的な支持を集め続けたわけだ。
いったいどんなマジカルな政策をヒトラーは繰り出しのか? 本書は、経済政策という側面から、ヒトラーおよびナチスを探った、ちょっと珍しい一冊である。
ナチス政権誕生までのドイツ経済の足取りを簡単に振り返っておこう。
第一次大戦に敗戦したドイツはベルサイユ条約により植民地全部と領土の一部を取り上げられたうえ、1320億マルク(330億ドル)の賠償金を請求された。ドイツの当時の歳入20年分くらいの額であり、毎年の支払いは歳入の2分の1から3分の1に及んだ。
そんなもの払えるわけがない。札をガンガン刷ったドイツは、1922年から1923年にかけてハイパーインフレーションに見舞われてしまうことになる。どのくらいハイパーだったかというと、0.2~0.3マルクだった新聞が1923年11月には80億マルクに暴騰する勢いだったそうである(村瀬興雄『ナチズム』中公新書)。
ハイパーインフレによってもっとも打撃を受けたのは中産階級や労働者、農民だった。一方で、外貨でドイツの資産を買ったりしてボロ儲けする者もいたのだが、そのなかにはユダヤ人実業家が少なからず含まれていた。その怨みもユダヤ人迫害の一因となる。
このハイパーインフレを止めたのは、ヒャルマール・シャハトという銀行家である。ときの首相シュトレーゼマンにより通貨全権委員に任命されたシャハトは、兌換紙幣「レンテンマルク」を発行し、同時にデノミを実行してインフレを収束させることに成功、1926年ごろからドイツ経済は回復に向った。この「レンテンマルクの奇跡」により、シャハトはドイツ国民から英雄視されることとなった。
だが、好況も束の間、1929年10月、ウォール街暴落をきっかけに世界恐慌が起こり、アメリカからの投機マネーに依存していたドイツは深刻な不況におちいってしまうのである。
資本主義と社会主義のいいとこ取り
ヒトラーが政権を取るのは出口なしの大不況にあえぐ最中の1932年のこと。そのころドイツは、財政赤字を補うために不況下にもかかわらずデフレ政策を取って困窮する国民をさらに苦境に落とすという最悪の状態にあり、失業者は600万人に登っていた。全労働者数の3分の1にあたる数字だ。
ナチスは、この莫大な失業者をほんの3年ほどで恐慌以前の160万人にまで減らし、経済をみごとに回復させたのである。
その経済政策はひとことでいえば、〈資本主義と社会主義両方の長所を生かしつつ、欠点を修正する〉というものであった。
アウトバーン計画を筆頭に公共事業によって雇用を創出するというのがメインの政策で、初年度だけで20億マルクが計上されたという。
大不況のなか、どこからそんなカネが降ってわいてきたのかというと、国債を大量に発行したのである。そんな乱暴なことをしたらまたハイパーインフレになりそうなものだが、これが上手くいって、ナチス・ドイツは不況からあっさり脱出する。
この計画を主導したのはシャハト。先に見た「レンテンマルクの奇跡」の英雄である。ヒトラーはシャハトをかき口説き、ナチスの経済大臣に迎えていたのだ。
アウトバーン建設は、雇用を創出しただけに止まらず、大動脈としてドイツ産業の発展に大きく寄与した。さらに、大規模な事業計画を行なうと積極的にアナウンスすることで、人々に景気回復の期待を持たせるよう働きかけもした。景気が良くなるとみんなが思えばサイフの紐が緩んで本当に景気が良くなるのである。
その他、中高年を優先的に雇用する、大規模店の出店を制限して中小店を守る、中小企業への融資制度を整える、価格統制により物価を安定させる、農家を保護する、結婚を促進し少子化を予防するなどなど、国民と経済を保護することに関しては、およそ考えつくかぎりの手段を講じたのであった。
一方で、公共事業による景気回復で生じた利益を国庫に回収するシステムもつくりあげていた。企業に対しては「配当制限法」という法律を課し一定以上の利益が出た場合は公債を買うことを義務づけ、個人に対しては貯蓄を促す制度を準備したのである。
ここまでは政府が市場に積極的に介入するケインズ政策の亜種という印象であるが、ナチスは政権を取ると直ちに労働組合を解体し、ストライキを禁止していた。
このへんが社会主義的な要素で、そんなことをすれば労働者の地位が悪化しそうだけれど、ドイツという労働者の国の伝統が絶妙なバランスを実現させたのか、大きな破綻なく労働者の環境および待遇は向上していった。
労働組合に代わり、資本家も労働者も同胞であるとする「労働戦線」が組織されたのだが、これがよく考えられた仕組みで、理念だけではなく「国民労働統制法」という法律でも制御されており、労働者を管理しつつ不満を吸収できるシステムをつくりあげたのだ。
健康診断や有給休暇はもとより住宅にいたるまで労働環境も十分すぎるほどに整備されていたし、また、労働戦線に付随した「歓喜力行団」という組織により、労働者には、レジャーや娯楽までもがふんだんに提供されていた。
その延長線上で企画されたのがフォルクスワーゲンだった。のちにドイツの国民車となるフォルクスワーゲンは、庶民も自家用車が持てるようにしようとナチスが国家プロジェクトとして手掛けたものだったのである。
しかし、このプロジェクトをヒトラーは実現できなかった。ポーランド侵攻を機に第二次世界大戦へ突入していくナチスは、始動待ちの工場を軍需施設に切り替えたのであった……。
失業問題の解消と経済の安定という目標を達成したナチスは、1936年から次なる経済政策にシフトする。具体的には「自給自足」と「戦争できる国力」を目標に設定するのだが、ここから迷走が始まる。
ここまで見てきた夢のように充実した政策を敷いてきたのはシャハトだったわけだが、そのシャハトを切り、経済にはまるで素人のゲーリングに政策を任せてしまうのである。
当然のように自給自足計画にことごとく失敗したナチスは経済的に逼迫していく。
ナチスに残された道は勝利か滅亡しかない
近隣国への侵攻も、ナチスの認識としては「侵攻」ではなく、ベルサイユ条約によって奪われたかつての領土を「奪回」し「自給自足」を目指すための行動の一環だった。
〈植民地をたくさん持っている国は、ことさらに貿易をしないでもやっていける。/しかしベルサイユ条約で植民地を全部取られているドイツとしてはとてもやっていけない。貿易が縮小されれば、食料にさえ事を欠くようになってしまう。/そこで生活圏を得るために、第一次世界大戦以前に持っていた領土、植民地を奪還するというのが、ナチスの目標のひとつだった〉
ナチスの経済政策は結局は破綻してしまったわけだが、原因は何だったのだろうか。
著者は、中央銀行の独立性を、ヒトラーが犯してしまったことに主因を見ている。
軍備拡大に同意しなかったシャハトの首を切ったあと、ヒトラーはドイツ帝国銀行を国有化し、軍事費を捻出するために公債を乱発した。
「この戦争では勝利か滅亡しかない」
ヒトラーがそう叫んだのは、負けを認めれば、莫大に発行した国債がとてつもないインフレを引き起こすことがわかっていたからだと著者はいう。
〈ナチスは軍備のために莫大な借金を背負い、その借金のために崩壊したといえるのだ〉
そのほか、アメリカの第二次大戦参戦の本当の理由は、ナチスが準備しており、ケインズが絶賛したという「欧州新経済秩序」を阻止するのが目的だったのではないかといった説も披露されている。欧州新経済秩序とは、1940年に発表された現在のユーロを先取りしたような計画で、管理通貨制度に移行し、マルクを欧州全域で流通させようとしたものである。当時世界の金の7割を保有していたアメリカとしては、金の価値を守るために参戦する必要があったのではないかというわけだ。
さて著者は、ナチスの経済政策が〈現代、資本主義の過酷な競争社会に限界を感じているわれわれに、なんらかのヒントを与えるものではないだろうか?〉とまえがきに書いている。
金融資本主義が破綻したのでケインズ政策的な要素を取り込みたいというのはわからないではないけど……と考えつつ読んだのだが、ところどころでひやっとするフレーズに遭遇した。
〈徹底的に経済効率を高めることが、必ずしも心豊かな生活を営むこととイコールではないのではないか。ナチスの政策を見ていると、そういうことを考えさせられる〉
〈「独裁体制」は、人類が国家のシステムとして使いこなすには、まだ難しいということかもしれない〉
うーむ、著者の武田さんはもしかしたらわりと左寄りの思想をお持ちの方なのだろうか。まあ、それを割り引いても(割り引けばというか)、示唆に富んだ、教えられること大の一冊なのだが。
(文/栗原 裕一郎、企画・編集/須藤 輝&連結社)
2009年5月29日(金)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090528/195992/
どちらも最初は見下されていた~『ユダヤ人とダイヤモンド』
守 誠著(評者:朝山 実)
幻冬舎新書、800円(税別)
こどものころ、学研の「科学と学習」を売り込みに、業者(あれは町の本屋さんだったのか)が学校にやってくることがあった。
だいたい春先に、年間購読を募るのだが、希望者は申し込んでくださいというだけ。担任教師は、気乗りしない様子だった。
月刊誌本体の記憶はあやふやだが、付録の鉱石セットだけはケースの色形まではっきりおぼえている。花崗岩などの石ころに混じって、ルビーやエメラルドの原石が入っていた。
宝石=高価、それがオマケで付いてくる、すごい!! 大ニュースじゃないか。なんでこれが大騒ぎにならないのか、不思議だった。
「どうや、センセ、すごいやろ」と箱から、グリーンの石を差し出すと、担任は「よかったわね」と、しげしげと見て返してきた。うらやましそうではない。「大切にしなさいよ」といいながら、ハナで笑うような顔だった。それらは加工されてはじめて、宝石になるというのを知ったのは、だいぶ後のことだ。
そんなことをふいに思い出したのは、銀座にオープンしたフランスのジュエリーショップが、店頭で5000個のダイヤを無料プレゼントするというので、長い行列ができている、とニュースで取り上げていたからだ。
ホンモノのダイヤには違いなかろうが、落とせば失せてしまいそうな小粒の裸石。何万円か支払えば装飾品にしてくれるという。早朝から行列をつくっているのは、ジュエリーとは無縁そうな男性たちという光景。イメージ戦略としてヒットしているのかどうかわからないが、テレビカメラが集まったのを宣伝費として考えたなら、タダで配ってもおつりはくるってことなのか。
さて、本書は、価値があるんだかないんだかわからないダイヤモンドの歴史をひもとくものだ。著者は元商社マンで、ダイヤの輸入に関わり、調べていくうちにユダヤ人の歴史と深く結びついていくことを知ったという。発端は40年ちかく前のことだというから、研究はすでにライフワーク化している。
「三流の石」が「希少なもの」に
意外なのは、ほんの200~300年前まで、ダイヤモンドは硬すぎて加工しにくく、宝石としては「三流の石」扱いだったことだ。16世紀、いちばん高価だったルビーと比べたら1カラットあたりの価格は、8分の1に過ぎなかったとか。
もともと加工職人や仲買商には、ユダヤ人が多かった。それには、当時のヨーロッパでは、ユダヤ人に対して職業規制が課せられていたことが関係していた。ダイヤは儲けがうすい。だから、働き手は少なく、就労の規制もない。つまり、ほかの人たちがやりたがらなかったわけだ。
そんな日陰のダイヤが脚光を浴びるのは、17世紀になって、「ブリリアント・カット」なる研磨技術が開発されてからのことだ(開発者にあたる研磨工については諸説あって、特定されていない)。
しかし、ダイヤの価格は一定しない。19世紀に入って、南アフリカで鉱山が次々と発見されるや、供給過剰となり、価格の暴落を招いた。このとき巨大な資本を注入し、強引に鉱山を束ねて、市場を安定させたのが、ユダヤ人のロスチャイルド家だった。
そして、20世紀。「ダイヤモンド王」アーネスト・オッペンハイマーが登場する。1880年、ドイツのタバコ商人の子として生まれた彼は、17歳でロンドンのダイヤモンド・ブローカーに入社し、南アで原石の買い付け担当をしたのち、経緯はよくわからないが、金の採掘で得た資産を元手に、1920年、ダイヤモンド業界に舞い戻り、原石販売のカルテルを構築する。
彼が歴史に名を残せたのは、過剰となりつつあったダイヤを「希少なもの」に見せかけ、高価格で安定させることに成功したからだ。その手腕は「限りなく詐欺師に近いビジネスマン」ともいわれた。
オッペンハイマーがユダヤ人だったことから、「ダイヤとユダヤ人」のつながりを印象付けることにもなったといわれる。しかし、本書では、晩年のオッペンハイマーがユダヤ教からキリスト教に改宗したエピソードに触れながら、なぞの多いその真相に迫ろうともしている。
また、エピソードとして驚きなのは、ナチス・ドイツとダイヤの関係だ。
1939年、ドイツ軍のポーランド侵攻により第二次世界大戦は幕を開けた。そのポーランド占領後、ドイツが次の標的にしたのは、ベルギーとオランダだった。
なぜ、ベルギーとオランダだったのか。イギリス攻撃の拠点とする目的があったといわれているが、著者によれば、もうひとつの理由が隠されていたという。
当時、ベルギーのアントワープは、世界最大のダイヤモンド加工センターだった。2万5千人の研磨工がいて、ユダヤ人ダイヤモンド商たちで街は賑わいをみせていた。
〈戦争で勝利をおさめるためには膨大な資金が必要だ。ダイヤモンドは軽くて高価で略奪商品としては、もっとも換金しやすい。また軍需工場にとり不可欠な戦略物資である〉
ベルギー侵攻には、ユダヤ人から根こそぎダイヤモンドを奪い取る企みが隠されていた。著者は、戦後にアントワープのジャーナリストがまとめた小冊子をもとに、ナチス・ドイツがどれだけ綿密な計画を練っていたのか、詳細を明らかにしている。
一度はベルギーからフランスへと逃げ出したユダヤ人たちに、ナチスは、迫害を加えるどころか「微笑」を示した。ユダヤ人たちを安心させ、アントワープへと帰還させたのち、時間をかけ、さらに油断させるために、不満の聞き手にもなった。伝えられる迫害は、自分たちには及ばないものだと信じ込ませたのだ。
ユダヤ人をだましたナチスをだました男
計画を練ったのはドイツ経済省で、直接手を下したのが悪名高きゲシュタポ(国家秘密警察)である。占領から2年後、彼らは、ユダヤ人たちがこれまで扱ってきたダイヤの取引記録をあらいざらい申告させ、全容を把握した上で、一粒残らずダイヤを没収し、強制収容所へと送りこんだ。
しかも、作戦の中枢を担ったドイツ人の役人フレンゼルは、あのゲシュタポさえだまくらかして、発覚すれば処刑は確実の、ダイヤのネコババをやってのけた。二重の詐欺を働いた「ユダヤ人ダイヤモンド所持品の総括管理監督責任者」の悪行は、露見することなく戦争終結に至り、彼が横領したダイヤもどこかに消えたままだという。
ほかにも、本書は、ユダヤやダイヤに関する「知っていますか?」的なエピソードの宝庫である。
著者は、資料や文献を集めるだけでなく、イラク軍がクウェートに侵攻した湾岸戦争時に、テルアビブを訪れるなどしている。その際の記述は、臨場感あふれるものだ。
イラクのフセイン大統領がイエラエルに向けスカッド・ミサイルを発射するとぶち上げた直後とあって、「万一の場合に」と取材相手のダイヤモンド商から、いきなりガスマスクを差し出された。
大航海時代にインドからダイヤモンドの原石をヨーロッパにもたらしたのはユダヤ人だと落ち着き払って講義するのを、著者は、いまにものミサイルが……と話を聞くどころではない。危険を承知でわざわざ尋ねて行ったにもかかわらず、なんと著者は、取材を早々に切り上げ、翌日にはおおあわてでテルアビブを脱出している。
おかげで著者は貴重な取材相手と連絡をとれないままだという。しかし、わらうなんてことはできない。命あってのことだ。
残念なのは、そうしたナマミの著者が登場するのが、この一場面かぎりだということだ。オッペンハイマーやフレンゼルなどの、なぞめいた人物像への興味をかきたてられるいっぽうで、柱となる「ダイヤモンドとユダヤ人」の関係そのものは、学生時代、午後に睡魔と格闘しながらうけた授業のようなきまじめさで、個としてのユダヤ人の顔がなかなか見えてこないのは難点である。取材のしすぎで、歴史の整理に労をとられてしまったためかもしれないが。
(文/朝山 実、企画・編集/須藤 輝&連結社)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20090603/196576/?P=1