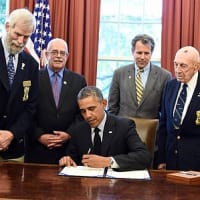【早読み/先読み アメリカ新刊】反ユダヤのルーズベルトの「化けの皮」を剥ぐ
2013.5.5 18:00

FDR and the Holocaust: A Breach of Faith
FDRとホロコースト:背信と裏切り
Rafael Medoff
Wyman Institute
■ リベラル派の英雄もひと皮剥けばユダヤ人嫌いだった
アメリカ第32代大統領、フランクリン・D・ルーズベルトといえば、1933年から45年まで12年間、大統領職にあった「民主党リベラル派の大政治家」。米政治史上、2期以上大統領職を務めた唯一の大統領である。(のちに憲法が改正され、大統領は2期までと定められた。)
リベラル派から見ると、ニューディール政策をはじめとする福祉国家的政策を導入し、アメリカを大恐慌から脱皮させ、外交面では日独の侵略を阻止するべく第2次大戦に参戦、戦後の国際秩序を確立させた「英雄」である。だが、「小さな政府」を提唱する保守派はニューディール政策に極めて否定的な評価をしている。外交面でもソ連のスターリンに対する容共的なスタンスをとり、ソ連の侵略行為を黙認していたといった批判がある。
日本人から見ると、ルーズベルトは日本軍が1941年12月8日、米ハワイの真珠湾を攻撃したときの大統領。
2011年に出た「Freedom Betrayed: Herbert Hoover’s Secret History of the Second World War and Its Aftermath」(George H.Nash)によれば、政敵・ハーバート・フーバー第31代大統領から「対ドイツ参戦の口実として、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』」と批判されている。
フーバーは、アメリカが対ドイツ戦に参戦する口実を作るために日本軍が真珠湾を攻撃することを事前に察知しながら放置していたと書き記していたというのだ。フーバーの遺族が保管していた関係文書からそうした記述が見つかったというのだ。
32年の大統領選に敗れたフーバーが、その後いかにしてそうした情報を入手したのか、単なる推測なのか、そのへんは定かではない。
■ 膨大なメモや書簡から探り当てたルーズベルトの本心
1冊の本がすでに出来上がっている政治家のイメージを一変させることがしばしばある。「リベラル派の旗手・ルーズベルト」も例外ではない。
「この男、かっこいいことを言っていたが、実は徹底したユダヤ人嫌いだった」
そう言い切ったのが、本書の著者、ラッファエル・メドッフ博士だ。オハイオ州立大学やニューヨーク州立大学で教鞭をとったのち、現在ワシントンにある「ディビッド・ワイマン・ホロコースト問題研究所」の所長を務めている。ホロコースト研究の一人者だ。
膨大な資料を基にメドッフは、ルーズベルトのユダヤ人嫌いを示す新たな証拠を以下のように列挙している。
1)ルーズベルトは1923年、ハーバード大学にはあまりに多くのユダヤ人が在籍しているとして、移民割り当て制度を導入させた。
2)ルーズベルトは38年、ポーランドにおける反ユダヤの風潮は、ユダヤ人がポーランド経済を牛耳っているからだと私的会合で述べていた。
3)ルーズベルトは41年の閣議の席上で、オレゴン州の連邦政府機関で働くユダヤ人は多すぎると言明。
4)ルーズベルトは43年、チャーチル英首相と会談した際に、ニューヨーク州知事当時、地元ハイドパーク各地区に4,5人ずつのユダヤ人を住ませたことで反ユダヤにはならなかったことを例に上げて、「ユダヤ人を世界中にばらばらに住ませるのがいい」と発言。
5)ルーズベルトは、「あなたの家計にはユダヤ人の血が流れているのか」との質問に「私の大動脈にはユダヤの血など一滴も流れていない」と力説。(ルーズベルト家は1650年前後にオランダからニューヨークに移住したクラース・ヴァン・ルーズベルトに始まるユダヤ系といわれている。)
こうした個人的なユダヤ人観を反映してか、政策面では33年6月、ベルリンに赴任するウィリアム・ドッド大使に、「ナチス・ドイツがドイツ在住のユダヤ人にひどい仕打ちをしているようだが、犠牲者がアメリカ国籍でない限り、アメリカ政府としては何も出来ない。ドイツへの対応は非公式、かつ個人的なレベルでの影響力を行使するのみだ」と指摘していた。
著者は、こうしたスタンスが、600万人を虐殺したホロコーストにつながったと厳しく指摘している。
■ 「ルーズベルトには限られた選択しかなかった」という反論も
本書が発売されるのとほぼ同時に、アメリカン大学の2人の歴史学者、リチャード・ブレイトマンとアラン・ラッチマンもルーズベルトのユダヤ政策を扱った本、「FDR and the Jew」を出版。この本の趣旨は、「米国内のユダヤ人に対するネガティブな風潮を反映してルーズベルトには限られた選択肢しかなかった」というもの。
これが発端となって、ロサンゼルス・タイムズの紙面では読者を巻き込んだ論争が繰り広げられている。
ワシントン・ポストのユダヤ系米人コラムニスト、リチャード・コーエン記者は、こう書いている。
「わが家ではナチスや軍国主義者を打ち破ったルーズベルトは神様的存在だった。ルーズベルトが死去した日、母親は神様がなくなられたと放心状態になった。…が、今、ルーズベルトもただの人間だったことを知った。彼もまた史上最大の犯罪に立ち向かう男ではなかったのだ」
最初に触れたフーバーの「ルーズベルト陰謀説」。そのフーバーが多額の寄付をしたスタンフォード大学フーバー研究所には、死後膨大なフーバー関連資料が眠っているという。ロシア革命に関する文献はロシア国内に保管されているものよりも歴史的価値の高いものもあるという。「ルーズベルトは日本軍の真珠湾攻撃を事前に知っていた」とするフーバーの指摘を裏付ける資料もあるのか、どうか。ぜひ全資料を公開してもらいたいものだ。
(高濱賛)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130505/amr13050518010002-n1.htm
ナチスドイツを支援していたアメリカ大物財界

オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史 より
「メディアが都合よく無視していたこと・・・ヒトラー政権の反ユダヤ主義が明らかになった後も、アメリカ経済界の大物達がナチスドイツを支援していたという事実」
F・ルーズベルトの犯罪 『フーバー回想録』の衝撃 稲村公望
2月 20th, 2012 by 月刊日本編集部.
中央大学客員教授 稲村公望
昨年十二月、日米開戦から七十周年を迎えた。その直前に一冊の回想録が刊行された。ジョージ・ナッシュ氏が編集したフーバー大統領の回想録『Freedom Betrayed(裏切られた自由)』だ。ここには、大東亜戦争の歴史の書き換えを迫る重大な記録が含まれている。千頁近くにも及ぶこの大著をいち早く読破し、その重要性を指摘している稲村公望氏に聞いた。
ルーズベルトが日本を戦争に引きずり込んだ
―― 『Freedom Betrayed』のどこに注目すべきか。
稲村 フーバー大統領死去から実に四十七年の歳月を経て刊行された同書は、フランクリン・ルーズベルト大統領を厳しく批判しており、同書の刊行はいわゆる「東京裁判史観」清算のきっかけになるほど重大な意味を持つ。例えば、フーバーは回想録の中で、次のように書いている。
「私は、ダグラス・マッカーサー大将と、(一九四六年)五月四日の夕方に三時間、五日の夕方に一時間、そして、六日の朝に一時間、サシで話した。(中略)
私が、日本との戦争の全てが、戦争に入りたいという狂人(ルーズベルト)の欲望であったと述べたところ、マッカーサーも同意して、また、一九四一年七月の金融制裁は、挑発的であったばかりではなく、その制裁が解除されなければ、自殺行為になったとしても戦争をせざるを得ない状態に日本を追い込んだ。制裁は、殺戮と破壊以外の全ての戦争行為を実行するものであり、いかなる国と雖も、品格を重んじる国であれば、我慢できることではなかったと述べた」
これまでも、チャールス・A・ビアード博士らが日米戦争の責任はルーズベルトにあると主張してきた。対日石油禁輸について、ルーズベルト大統領から意見を求められたスターク海軍作戦部長が「禁輸は日本のマレー、蘭印、フィリピンに対する攻撃を誘発し、直ちにアメリカを戦争に巻き込む結果になるだろう」と述べていた事実も明らかにされていた。しかし、ビアードらの主張は「修正主義」として、アメリカの歴史学界では無視されてきた。つまり、ルーズベルトの責任がフーバーの口から語られたことに、重大な意味があるのだ。
『フーバー回想録』には、対日経済制裁について次のように明確に書かれている。
「…ルーズベルトが犯した壮大な誤りは、一九四一年七月、つまり、スターリンとの隠然たる同盟関係となったその一カ月後に、日本に対して全面的な経済制裁を行ったことである。その経済制裁は、弾こそ撃っていなかったが本質的には戦争であった。ルーズベルトは、自分の腹心の部下からも再三にわたって、そんな挑発をすれば遅かれ早かれ(日本が)報復のための戦争を引き起こすことになると警告を受けていた」
天皇陛下の和平提案を退けたルーズベルト
―― まさに、ビアードらの主張を裏付けるものだ。ルーズベルトは日本を無理やり戦争に引きずり込もうとした。彼は真珠湾攻撃前から日本本土爆撃を計画していたともいう。
稲村 アラン・アームストロングは、『「幻」の日本爆撃計画―「真珠湾」に隠された真実』の中で、真珠湾攻撃の五カ月前にルーズベルトが日本爆撃計画を承認していたことを明らかにした。その計画は「JB─355」と呼ばれるもので、大量の爆撃機とパイロットを中国に送って、中国から日本本土を爆撃しようという計画だった。
『フーバー回想録』は、「スティムソンの日記が明らかにしたように、ルーズベルトとその幕僚は、日本側から目立った行動が取られるように挑発する方法を探していたのだ。だから、ハルは、馬鹿げた最後通牒を発出して、そして真珠湾で負けたのだ」と書き、ルーズベルトが近衛総理の和平提案受け入れを拒否したことについては、次のように批判している。
「近衛が提案した条件は、満州の返還を除く全てのアメリカの目的を達成するものであった。しかも、満州の返還ですら、交渉して議論する余地を残していた。皮肉に考える人は、ルーズベルトは、この重要ではない問題をきっかけにして自分の側でもっと大きな戦争を引き起こしたいと思い、しかも満州を共産ロシアに与えようとしたのではないかと考えることになるだろう」
徳富蘇峰は、「日本が七重の膝を八重に折って、提携を迫るも、昨年(昭和十六年)八月近衛首相が直接協商の為に洋上にて出会せんことを促しても、まじめに返事さへ呉れない程であった。而して米国、英国・蒋介石・蘭印など、いわゆるABCDの包囲陣を作って蜘蛛が網を張って蝶を絞殺するが如き態度を執った。而して、彼等の頑迷不霊の結果、遂に我をして已むに已まれずして立つに至らしめたのだ」(『東京日日新聞』一九四二年三月八日付)と書いていたが、七十年という歳月を経て、ようやく『フーバー回想録』によって、蘇峰の主張が裏付けられたのだ。
フーバーは、さらに重大な事実を記録している。
天皇陛下は、一九四一年十一月に駐日米国大使を通じて、「三カ月間のスタンドスティル(冷却期間)をおく」との提案をされたが、ルーズベルトはこの提案をも拒否したと書いている。アメリカの軍事担当も、冷却期間の提案を受け入れるべきであるとルーズベルト大統領に促していたのだ。
フーバーは、「日本は、ロシアが同盟関係にあったヒトラーを打倒する可能性を警戒していたのである。九十日の冷却期間があって、(戦端開始の)遅れがあれば、日本から〝全ての糊の部分〟を取り去ることになり、太平洋で戦争する必要をなくしたに違いない」とも書いている。
当時、アメリカでは戦争への介入に反対する孤立主義的な世論が強かった。ルーズベルトは欧州戦線に参戦するために、日本を挑発し戦争に引きずり込んだのである。日本国内にも日本を日米開戦に向かわせようとする工作員が入りこんでいた。実際、リヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が日本国内で諜報活動を行い、そのグループには近衛のブレーンだった尾崎秀実もいた。
―― ルーズベルト自身、反日的思想を持っていたとも言われる。
稲村 彼は日系人の強制収容を行い、「日本人の頭蓋骨は白人に比べ二千年遅れている」と周囲に語るなど、日本人への人種差別的な嫌悪感を強く持っていたとも指摘されている。
http://gekkan-nippon.com/?p=2969
【真珠湾攻撃70年】 「ルーズベルトは、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』」
日中戦争-戦争を望んだ中国 望まなかった日本
林 思雲, 北村 稔
「日中戦争は日本の侵略戦争だった」―この言説の呪縛から解き放たれるときがきた。戦争開始前後における知られざる「真実」を明らかにした画期的論考。
内容紹介
本書では、日中戦争研究の大前提となっている「侵略戦争を起こした日本と
侵略された中国」という枠組みは、取り払われている。
――冒頭からこう述べられているとおり、本書はこれまでの硬直した日中戦争観を
排したうえで歴史をとらえようと試みたものである。
本書では、これまで正面から論じられなかったが事実が明らかにされている。
その一つが、本書サブタイトルにあるように、「戦争を望んだ中国と望まなかった日本」
という構図である。また他にも、これまで論じられなかった事実が、
丁寧な検証をもとに提起されている。
中国近代史研究に定評のある二人の著者が送る渾身の論考。本書の読者は、
日中戦争に対する見方がこれまでいかに歪曲したものであったかがわかるだろう。
まさに日中の近現代史を変えるであろう一冊!
http://www.amazon.co.jp/dp/4569693008
(読者の声1)『日中戦争:戦争を望んだ中国、望まなかった日本』(北村稔・林思雲共著)(PHP)を全文英訳しました。
日中歴史共同研究日本側座長の北岡伸一・東大教授は、「日本の歴史学者で、日本が侵略していないとか、南京虐殺はなかったと言っている人はほとんどいない」と読売新聞に書いています。
ということは日本の歴史学者は、事実と無関係のウソもしくは空論をまじめに論じていることになります。なぜなら、日支事変の2大重要ポイントを完全に否定することになるからです。
第1ポイント:盧溝橋事件では、事件勃発4日後に結ばれた「現地停戦協定」第1条で「中国側に責任があり、責任者を処罰する」と書かれていたことを無視しています。
第2ポイント:本格的な戦争は盧溝橋から約1ヶ月後に起こった上海事変です。
当時、反日的であったニューヨークタイムズですら、「日本軍は事態の悪化を防ぐためにできる限りのことをした。だが中国軍によって文字通り衝突へと無理やり追い込まれてしまったのである」
と書いています。(1937年8月30日付)
広く信じられている「日本侵略者論」は、実は極めて怪しい論なのです。
実は当時、中国では日本と戦うべしという世論が圧倒的であり、それに対して日本は戦争を全く望んでいなかったというのが実情でした。
本書は、こうした事実、そして戦争下の中国社会の実態を豊富な資料に基づいて明らかにしている画期的な日中戦争論です。
いつまで架空の思いこみに囚われて「贖罪意識」の奴隷になっているのでしょう。
http://www.melma.com/backnumber_45206_5104882/
日中戦争はドイツが仕組んだ
ドイツ人は恋人にチョコレートも贈らないほどにケチだが、その本当の理由は?
日本の新幹線が時刻表通りに運行されることをドイツ人は信用しない
♪
川口マーン恵美『サービスできないドイツ人、主張できない日本人』(草思社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
秀逸な日独文化比較論である。
日本人とドイツ人の差違を平明に主婦の視点から、三人の娘の母親として(教育ママ?)の視点から、そして作家、エッセイストとしての文化的視点からの考察に加えて、本書の全編に愛国者の視点がある。
後者の視点がないとスタンスに一貫性が失われる。
一部は雑誌『MOKU』などに連載されていたので読んだ箇所もあるが、いつも叙述が変化に富んでいて、刺激的で面白くもあり哀しいほどにおかしい。生活に密着したところから議論が進むので、若い女性も飛びついて読む本だろう。
とても取っつきやすく、それでいて文章は陰陽と濃淡に彩られる。
観光地へ行っても土産を買わないドイツ人、どっさり買い込む日本人。駐車代金100円を節約するドイツ人は、しかし家具をコーディネートして豪華なセットをどんと買う。家をぴかぴかに磨く。ところが誕生パーティでは贈り物をしない。出席者は自作の詩を読んだりする。ピアノを弾く。嗚呼、そうか、生活の態度が最初から違うのだ。
こうなると恋人同士でも巨大な懸隔が日本人とドイツ人の男女交際の過程にも如実に現れる。
ラボホテルを楽しみ、高価なプレゼントを贈る日本人のカップル。百円ショップあたりで奇妙な雑貨を買って、それを平然と恋人におくるドイツ人。
時刻表通りにぴったりに運行する日本の新幹線。遅れてもお詫びもしないうえ、放送もしないドイツ。ゴミの仕分けが徹底しているドイツは家とその周囲は綺麗なのに、公道は汚染されている。
宅配便に時間指定ができる日本、いつくるかわからないドイツ。文句を言っても「それは私の所為じゃない」と責任を転嫁する癖は、なんだか中国人風。つまりドイツ人の潜在意識には『サービスをやるのは下人』という凄い階級意識が存在するという。
だから川口さんは「成田空港に着いた途端、ドイツでの日頃の緊張がストンと抜け落ちる」のも「日本社会では警戒心を持たなくてもよい」からだと力説される。
(嗚呼、良い国に生まれて良かった)
評者(宮崎)が一番驚かされたのは教育制度を論じた箇所である。
てっきりドイツにはマイスター制度がいまも脈々と存続し、技術者の子は熟練工に磨きをかける、だからドイツも日本同様のものづくり国家と固く信じてきたが、過去三十年ですっかり様変わりしているという。
伝統的に小学四年生で試験の結果、エリートと「そうでない」と人生のコースが別れるドイツは、はてしなき効率主義でもあった。
ところが、職業訓練をおこなう学校はいまや「落ちこぼれ、すね者、外国人」のたまり場となり、不良学校然として、エリートは避けるうえ、職人の親までが、そうした『落ちこぼれ学校』に子供を行かせなくなっているというではないか。
そのうえ、教育者にもドイツでは問題がある。
「子供を扱う術」をドイツでは「教師養成の過程であまり重視しない」。だから教師と生徒は対立関係おなり、敵視するのだというから穏やかではない。
子供がビールを飲もうが学校でタバコをすおうが、同級生同士がいきなり同棲しようが教師はまったく無関心。「ドイツの学校では、教師と生徒の繋がりはほとんどない。教師はその授業の時間にいるだけで、教師間の横の繋がりも希薄だ」という。
川口さんはこう言う。
「日本の学校で何より素晴らしいと思うのは、小学校で教師が生徒と一緒に給食をたべること、そして生徒が学校の掃除をすることだ。指導要領がどう変わろうが、教育委員会が右寄りになろうが左寄りになろうが、この二つだけは絶対に変えるべきではない」
さて本書の言語による文化比較の肯綮も、ドイツで三十年近くを暮らす川口さんらしい実体験から産まれている。
文学作品でもカフカやムラカミハルキをお互いがよみ、しかし言葉のニュアンスや翻訳不能の箇所があるので、終局的にその作品を理解できたとは言えないだろう。
日本語とドイツ語。それを使うときのマナー、身振りの差!
「使う言葉によって、なぜその人間の中身が変わるのか」と著者は設問する。たとえば、「着物を着たら動作が淑やかになって、言葉使いも柔らかくなり、性格が優しくなるのに、その同じ人間がビキニを着たら、胸を張って大股で歩き出し、動作と同じく性格も活発になるのと似ている」。
英語も中国語も敬語がなく、丁寧語は少ない。「わたくし」も「私」も「わらわ」も。「オレ」も「僕」も「ワシ」もない。中国語の一人称の主語は「我」であり英語は「I」だけ。
言葉に深みがあるのは、どうしても日本語の強み。
評者が中国へ行ってよく指摘されるのは「なぜ中国人社会では宮崎さんは、あれほど横柄なのか?」。自分では気がついていなかった。
英語を喋るとき、集中して論理を構築することに努力し、なぜか身振りも大げさになり、手を広げたりしている自分を発見するが、日本語で会話しているときは、むしろ敬語、相手への思いやりに気がいって、言葉を選ぶことに気を遣う。
中国では横柄な態度を意図的にやっているわけではなく、中国語が本来、尊敬語も丁寧語もない、貧しい語彙力の言語体系である以上、どうやって詭弁を弄するかにエネルギーが注がれる。
こうした言葉を使う側の姿勢にも、文化の本質があることを思い出した。本書は入念に、このことの検証を展開している。収穫が多く、旅行中、携行して読み切った。
http://www.melma.com/backnumber_45206_5105105/
白人はイルカ食べてもOKで日本人はNG 科学的根拠はない
2011.06.14 16:00
【書評】『白人はイルカを食べてもOKで日本人はNGの本当の理由』
吉岡逸夫著・講談社+α新書・880円(税込)
* * *
本書の表紙を開くと、鮮血に染まった海岸に横たわる多数のイルカがいきなり目に飛び込んでくる。イルカ漁で有名な和歌山県太地町の写真ではない。デンマーク自治領、フェロー諸島で行なわれている追い込み漁を写したものだ。
アカデミー賞を受賞した映画『ザ・コーヴ』で、太地町の人々は極悪人のように描かれたが、この映画にフェロー諸島のイルカ漁は一切出てこない。
〈今回のイルカ漁への非難、捕鯨への批判を見て、そこに白人たちの差別意識を感じるのは私だけだろうか〉
本書では、イルカ保護活動家らへインタビューを行ない、太地町とフェロー諸島の扱いの違いを比較し、彼らの傲慢さがどこから生まれてくるのかを検証していく。
シー・シェパード幹部のスコット・ウェスト氏はこう述べている。
〈イルカは牛などに比べて人間に近い。われわれと同じような複雑な頭脳と形態を持っている。彼らは文化的な共同体を持ち、自身の言葉や歴史を持っているから人間に近い。他の家畜とは違う〉
イルカは人間と同じだとする“イルカ教”のカルトも同然であり、科学的根拠はどこにもない。
著者は、白人はイルカ漁がOKで日本人はNGの理由として、差別や寄付金目的のほか、日本側のPR不足を挙げ、苦言も呈する。
東日本大震災の発生時、岩手県にいたウェスト氏らシー・シェパードのメンバーも被災し、住民や警察の支援で無事避難できたことが報道された。ウェスト氏は手記で「我々に向けられた親切と寛容さを、書きつくすことはできない」と述べている。寄付金集めが目的で日本叩きをしている連中でも、日本人は差別したりはしないのだ。
※SAPIO2011年6月15日号
http://www.news-postseven.com/archives/20110614_21772.html
日本の刺青と英国王室―明治期から第一次世界大戦まで [著]小山騰
[評者]平松洋子(エッセイスト)
[掲載]2011年2月6日
■「野蛮」に憧れた、奇妙な交流史
カバーの肖像写真に息をのんだ。笑みを浮かべた妙齢の英国女性が身にまとっているのは繊細なレース模様のドレスではなく、全身にほどこされた刺青なのだった。彼女は「刺青師の王様(キング)」と呼ばれた英国人G・バーチェットの妻。よく見ると、右上腕の一部に髪を結った日本女性の意匠が紛れこんでいる。
この本を読むまでまったく知らなかった。明治期、英国から日本の刺青にこれほど熱い視線が注がれていたとは。
刺青は文明開化まっさかりの日本で野蛮とみなされ禁止されたが、かたや「文明国」の英国王室や貴族階級にとっては憧憬(しょうけい)の対象だった。先鞭(せんべん)をつけたのは明治天皇にも面会したベレスフォード卿で、明治二年に来日したとき背中一面に狩猟の光景の刺青を入れた。十四年、のちのジョージ五世とアルバート王子は鶴と龍。英国の新聞記事は、わざわざ日本で彫る刺青は「大変な熱狂状態」と報じた。
皮肉なパラドクスである。日本はひたすら「文明国」を目指したが、その相手から見れば「野蛮」な刺青はひとの肌に咲く精密な芸術の華だった。羨望(せんぼう)は、英国王室が複雑な婚姻関係をもつヨーロッパ王室にまで広がってゆく。
著者は国会図書館や英国図書館を経て、現在ケンブリッジ大学図書館勤務。英国で発掘した資料や文献を精読し、まさに刺青をほどこすような丹念な手つきで日英間にひそむ奇妙な交流史を発掘してゆく。その過程で「刺青のシェークスピア」「エンペラー」と呼ばれてあまたの外国人顧客に刺青を彫った日本人、彫千代の存在も掘り起こし、興味をそそる。
明治四十三年発表、谷崎潤一郎『刺青』の冒頭を思いだす。
「其(そ)れはまだ人々が『愚』と云(い)う貴い徳を持って居て、世の中が今のように激しく軋(きし)み合わない時分であった」
鎖国下で独自に切磋琢磨(せっさたくま)、芸術的到達をみせた刺青の親善交流。それは明治の徒花(あだばな)などではなく、むしろ「貴い徳」の所産でもあったろうか。わたしは読むうち、ふしぎにのんびりとして微笑(ほほえ)ましい気分を抱いた。
◇
こやま・のぼる 48年生まれ。ケンブリッジ大学図書館日本部長。
http://book.asahi.com/review/TKY201102080162.html
日本の刺青と英国王室―明治期から第一次世界大戦まで: 小山 騰: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4894347784
〈時の回廊〉森浩一「古墳の発掘」 天皇陵の疑念 世に問う
森浩一さん=京都市中京区、滝沢美穂子撮影
「仁徳天皇陵」に葬られているのは、本当に仁徳天皇か。半世紀前、天皇陵を巡る疑問を初めて世に問いかけた一冊が、『古墳の発掘』だった。それ以降、書き続けた一般書は100冊を超す。多くの研究者や歴史教科書に影響を与えた考古学者は、80歳を超えてなお、日々の発見に心躍らせる。
◇
昭和30年代、僕は大阪府立高校に勤める傍ら、奈良県橿原市で古墳群の発掘を指揮していた。その最中の1964年春、東京大の井上光貞先生が、自身の著作『日本の歴史(1)神話から歴史へ』(中央公論社)の考古学担当に抜擢(ばってき)してくれました。
その夏、発掘が終わると、扇風機もない大阪の自宅で、氷柱を毎日2本バケツに入れて机の左右に立て、1週間ほど懸命に書いた。原稿を取りに来た中央公論の編集長から、「新書を1冊書きませんか」と誘いを受けたのが、『古墳の発掘』。「『天皇陵』にしたい」と言うと、「天皇陵をいきなり書き出しても分からない」。だから前半を古墳入門編とし、後半で「タブーの天皇陵」に力を注ぎました。
小学生の頃、電車通学する車窓から百舌鳥(もず)古墳群の巨大な古墳が見えた。その最大の古墳「仁徳陵」の被葬者が仁徳天皇かどうかを疑う人はいなかった。古墳群にあるもう一つの巨大な前方後円墳、ニサンザイ古墳は「陵墓参考地」で天皇陵ではない。天皇陵の指定が完璧なら、参考地というあいまいなものを残す必要はないのに、という疑念が子ども心にわいたんです。
天皇陵は墳丘内への立ち入りが禁止されており、江戸時代の図面や石室の観察記録を丹念に読んで、知識とするほかない。幸運だったのは『古墳の発掘』を書く前年、宮内庁「書陵部紀要」が発行され、幕末の「文久の修陵図」を見たこと。そこには、天皇陵を改変する前と後の様子が見事に描かれていた。荘厳な構築物を見せることで幕府が朝廷を尊崇していることを示そうとした実態もわかりました。
初版本で思い切って「天皇陵の所在地と墳形」の一覧表を作り、信頼性の度合いを示した。多くの天皇陵に「妥当なようだが、考古学的な決め手を欠く」として、●印を付けたんです。後の11版では表に手を加え、初版で「ほとんど疑問がない」と○印を付けた仁徳天皇陵を●印に落としました。
『古墳の発掘』は売れて28版までいったが、まだまだ不満やった。本では「仁徳陵」などと表記したが、その後、「仁徳陵古墳」を使い始めた。宮内庁が仁徳陵に指定している古墳、の意味だ。たった2文字があるかないかの違いだが、多くに影響を与えたようだ。宮内庁のある人から「法律で決まっている天皇陵に勝手に古墳名を付けるとはけしからん」と手紙も来た。
それでもなお、「仁徳」の人名が付くという問題が残る。それは奈良時代に創られた漢風の諡号(しごう)で、古墳時代にはなかった。そこで、古墳の所在地で呼ばれている地名を適用し、「大山(だいせん)古墳」とする私案を出したんです。
宮内庁は天皇陵をどう考えているのか。1年ほどかけて知恵を結集し、今の仁徳陵で問題がないなら、そう言明すればいいし、疑いがあると思うなら今後、計画的に発掘すればいい。素早い決断を望みたいですな。
最後に日本の、地域のすごさ、というのを書き上げたいと思います。80歳を超えて、「もし60歳で死んでたら、こんなん知らんと死んでたんやな」「得したなあ」と思うことがようけある。「感激のない人には学問はできん」と誰か言うてたけど、ほんまやね。(聞き手・大脇和明)
◇
もり・こういち 1928年生まれ。同志社大名誉教授(日本考古学)。13歳から遺跡探訪を始め、同志社大在学中に学会誌「古代学研究」創刊。「関東学」など地域学も提唱。
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201202020353.html
【書評】『維新・改革の正体 日本をダメにした真犯人を捜せ』藤井聡著
2012.11.25 11:06
「維新・改革の正体」
■「失われた二十年」の真実
ケインズ主義的公共投資、国土計画、整備新幹線などは、かつては高度経済成長を支えたかもしれないが、それも、もはや過去のものである。これからは、政府が経済を主導する時代ではなく、小さな政府、自由化、グローバル化の時代であり、インフラのようなハードではなく、情報や金融のようなソフトの時代である。このようなイメージが共有されている。多くの人が、時代の流れは単線的で、逆行しないものと思いこんでいる。
しかし、実は、リーマン・ショック以降、世界の有力な経済学者たちは、ケインズの復活を唱え、公共投資を主張するようになっているのだ。また、良心的な知識人たちは、1980年代以降の新自由主義が破綻したことを認め、60年代頃が資本主義の「黄金時代」であったと再評価し、それを取り戻そうと訴えている。時代は、単線的に進むわけではない。間違った道へと進んだのならば、方向を変え、場合によっては後戻りすることも必要なのだ。「後戻りはできない」とかたくなに思うのは、左翼的な進歩史観の悪弊である。
本書は、日本経済の「黄金時代」を築いた戦前生まれの3人、宍戸駿太郎、下河辺淳、小里貞利の証言の記録である。日本経済の成長を支えた彼らの歩んだ道は、決して平坦ではなかった。特に80年代以降、彼らが築いた成果を享受した後の世代は、先輩たちに感謝する代わりに、彼らを排除した。反成長主義の左派からも、新自由主義の右派からも攻撃された彼らは、理論やデータをもって戦い続けたが、劣勢はいかんともしがたかった。その結果が、「失われた二十年」であり、リーマン・ショックである。
3人の証言から、日本を没落させた犯人たちが実名で暴かれていく過程は、スリリングである。3人とも、高齢にもかかわらず、明晰(めいせき)な論理を語る。時勢に流されずに信念を貫き通すその姿は、感動的である。これが、真のエリートというものであろう。彼らの意志を継ごうという著者の気概が伝わってくる。日本の命運を決める総選挙の前に、必読の書である。(産経新聞出版・1365円)
評・中野剛志(評論家)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121125/bks12112511070015-n1.htm
維新・改革の正体を語る
http://www.youtube.com/watch?v=wLzxRPjr4S4
2013.5.5 18:00

FDR and the Holocaust: A Breach of Faith
FDRとホロコースト:背信と裏切り
Rafael Medoff
Wyman Institute
■ リベラル派の英雄もひと皮剥けばユダヤ人嫌いだった
アメリカ第32代大統領、フランクリン・D・ルーズベルトといえば、1933年から45年まで12年間、大統領職にあった「民主党リベラル派の大政治家」。米政治史上、2期以上大統領職を務めた唯一の大統領である。(のちに憲法が改正され、大統領は2期までと定められた。)
リベラル派から見ると、ニューディール政策をはじめとする福祉国家的政策を導入し、アメリカを大恐慌から脱皮させ、外交面では日独の侵略を阻止するべく第2次大戦に参戦、戦後の国際秩序を確立させた「英雄」である。だが、「小さな政府」を提唱する保守派はニューディール政策に極めて否定的な評価をしている。外交面でもソ連のスターリンに対する容共的なスタンスをとり、ソ連の侵略行為を黙認していたといった批判がある。
日本人から見ると、ルーズベルトは日本軍が1941年12月8日、米ハワイの真珠湾を攻撃したときの大統領。
2011年に出た「Freedom Betrayed: Herbert Hoover’s Secret History of the Second World War and Its Aftermath」(George H.Nash)によれば、政敵・ハーバート・フーバー第31代大統領から「対ドイツ参戦の口実として、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』」と批判されている。
フーバーは、アメリカが対ドイツ戦に参戦する口実を作るために日本軍が真珠湾を攻撃することを事前に察知しながら放置していたと書き記していたというのだ。フーバーの遺族が保管していた関係文書からそうした記述が見つかったというのだ。
32年の大統領選に敗れたフーバーが、その後いかにしてそうした情報を入手したのか、単なる推測なのか、そのへんは定かではない。
■ 膨大なメモや書簡から探り当てたルーズベルトの本心
1冊の本がすでに出来上がっている政治家のイメージを一変させることがしばしばある。「リベラル派の旗手・ルーズベルト」も例外ではない。
「この男、かっこいいことを言っていたが、実は徹底したユダヤ人嫌いだった」
そう言い切ったのが、本書の著者、ラッファエル・メドッフ博士だ。オハイオ州立大学やニューヨーク州立大学で教鞭をとったのち、現在ワシントンにある「ディビッド・ワイマン・ホロコースト問題研究所」の所長を務めている。ホロコースト研究の一人者だ。
膨大な資料を基にメドッフは、ルーズベルトのユダヤ人嫌いを示す新たな証拠を以下のように列挙している。
1)ルーズベルトは1923年、ハーバード大学にはあまりに多くのユダヤ人が在籍しているとして、移民割り当て制度を導入させた。
2)ルーズベルトは38年、ポーランドにおける反ユダヤの風潮は、ユダヤ人がポーランド経済を牛耳っているからだと私的会合で述べていた。
3)ルーズベルトは41年の閣議の席上で、オレゴン州の連邦政府機関で働くユダヤ人は多すぎると言明。
4)ルーズベルトは43年、チャーチル英首相と会談した際に、ニューヨーク州知事当時、地元ハイドパーク各地区に4,5人ずつのユダヤ人を住ませたことで反ユダヤにはならなかったことを例に上げて、「ユダヤ人を世界中にばらばらに住ませるのがいい」と発言。
5)ルーズベルトは、「あなたの家計にはユダヤ人の血が流れているのか」との質問に「私の大動脈にはユダヤの血など一滴も流れていない」と力説。(ルーズベルト家は1650年前後にオランダからニューヨークに移住したクラース・ヴァン・ルーズベルトに始まるユダヤ系といわれている。)
こうした個人的なユダヤ人観を反映してか、政策面では33年6月、ベルリンに赴任するウィリアム・ドッド大使に、「ナチス・ドイツがドイツ在住のユダヤ人にひどい仕打ちをしているようだが、犠牲者がアメリカ国籍でない限り、アメリカ政府としては何も出来ない。ドイツへの対応は非公式、かつ個人的なレベルでの影響力を行使するのみだ」と指摘していた。
著者は、こうしたスタンスが、600万人を虐殺したホロコーストにつながったと厳しく指摘している。
■ 「ルーズベルトには限られた選択しかなかった」という反論も
本書が発売されるのとほぼ同時に、アメリカン大学の2人の歴史学者、リチャード・ブレイトマンとアラン・ラッチマンもルーズベルトのユダヤ政策を扱った本、「FDR and the Jew」を出版。この本の趣旨は、「米国内のユダヤ人に対するネガティブな風潮を反映してルーズベルトには限られた選択肢しかなかった」というもの。
これが発端となって、ロサンゼルス・タイムズの紙面では読者を巻き込んだ論争が繰り広げられている。
ワシントン・ポストのユダヤ系米人コラムニスト、リチャード・コーエン記者は、こう書いている。
「わが家ではナチスや軍国主義者を打ち破ったルーズベルトは神様的存在だった。ルーズベルトが死去した日、母親は神様がなくなられたと放心状態になった。…が、今、ルーズベルトもただの人間だったことを知った。彼もまた史上最大の犯罪に立ち向かう男ではなかったのだ」
最初に触れたフーバーの「ルーズベルト陰謀説」。そのフーバーが多額の寄付をしたスタンフォード大学フーバー研究所には、死後膨大なフーバー関連資料が眠っているという。ロシア革命に関する文献はロシア国内に保管されているものよりも歴史的価値の高いものもあるという。「ルーズベルトは日本軍の真珠湾攻撃を事前に知っていた」とするフーバーの指摘を裏付ける資料もあるのか、どうか。ぜひ全資料を公開してもらいたいものだ。
(高濱賛)
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130505/amr13050518010002-n1.htm
ナチスドイツを支援していたアメリカ大物財界

オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史 より
「メディアが都合よく無視していたこと・・・ヒトラー政権の反ユダヤ主義が明らかになった後も、アメリカ経済界の大物達がナチスドイツを支援していたという事実」
F・ルーズベルトの犯罪 『フーバー回想録』の衝撃 稲村公望
2月 20th, 2012 by 月刊日本編集部.
中央大学客員教授 稲村公望
昨年十二月、日米開戦から七十周年を迎えた。その直前に一冊の回想録が刊行された。ジョージ・ナッシュ氏が編集したフーバー大統領の回想録『Freedom Betrayed(裏切られた自由)』だ。ここには、大東亜戦争の歴史の書き換えを迫る重大な記録が含まれている。千頁近くにも及ぶこの大著をいち早く読破し、その重要性を指摘している稲村公望氏に聞いた。
ルーズベルトが日本を戦争に引きずり込んだ
―― 『Freedom Betrayed』のどこに注目すべきか。
稲村 フーバー大統領死去から実に四十七年の歳月を経て刊行された同書は、フランクリン・ルーズベルト大統領を厳しく批判しており、同書の刊行はいわゆる「東京裁判史観」清算のきっかけになるほど重大な意味を持つ。例えば、フーバーは回想録の中で、次のように書いている。
「私は、ダグラス・マッカーサー大将と、(一九四六年)五月四日の夕方に三時間、五日の夕方に一時間、そして、六日の朝に一時間、サシで話した。(中略)
私が、日本との戦争の全てが、戦争に入りたいという狂人(ルーズベルト)の欲望であったと述べたところ、マッカーサーも同意して、また、一九四一年七月の金融制裁は、挑発的であったばかりではなく、その制裁が解除されなければ、自殺行為になったとしても戦争をせざるを得ない状態に日本を追い込んだ。制裁は、殺戮と破壊以外の全ての戦争行為を実行するものであり、いかなる国と雖も、品格を重んじる国であれば、我慢できることではなかったと述べた」
これまでも、チャールス・A・ビアード博士らが日米戦争の責任はルーズベルトにあると主張してきた。対日石油禁輸について、ルーズベルト大統領から意見を求められたスターク海軍作戦部長が「禁輸は日本のマレー、蘭印、フィリピンに対する攻撃を誘発し、直ちにアメリカを戦争に巻き込む結果になるだろう」と述べていた事実も明らかにされていた。しかし、ビアードらの主張は「修正主義」として、アメリカの歴史学界では無視されてきた。つまり、ルーズベルトの責任がフーバーの口から語られたことに、重大な意味があるのだ。
『フーバー回想録』には、対日経済制裁について次のように明確に書かれている。
「…ルーズベルトが犯した壮大な誤りは、一九四一年七月、つまり、スターリンとの隠然たる同盟関係となったその一カ月後に、日本に対して全面的な経済制裁を行ったことである。その経済制裁は、弾こそ撃っていなかったが本質的には戦争であった。ルーズベルトは、自分の腹心の部下からも再三にわたって、そんな挑発をすれば遅かれ早かれ(日本が)報復のための戦争を引き起こすことになると警告を受けていた」
天皇陛下の和平提案を退けたルーズベルト
―― まさに、ビアードらの主張を裏付けるものだ。ルーズベルトは日本を無理やり戦争に引きずり込もうとした。彼は真珠湾攻撃前から日本本土爆撃を計画していたともいう。
稲村 アラン・アームストロングは、『「幻」の日本爆撃計画―「真珠湾」に隠された真実』の中で、真珠湾攻撃の五カ月前にルーズベルトが日本爆撃計画を承認していたことを明らかにした。その計画は「JB─355」と呼ばれるもので、大量の爆撃機とパイロットを中国に送って、中国から日本本土を爆撃しようという計画だった。
『フーバー回想録』は、「スティムソンの日記が明らかにしたように、ルーズベルトとその幕僚は、日本側から目立った行動が取られるように挑発する方法を探していたのだ。だから、ハルは、馬鹿げた最後通牒を発出して、そして真珠湾で負けたのだ」と書き、ルーズベルトが近衛総理の和平提案受け入れを拒否したことについては、次のように批判している。
「近衛が提案した条件は、満州の返還を除く全てのアメリカの目的を達成するものであった。しかも、満州の返還ですら、交渉して議論する余地を残していた。皮肉に考える人は、ルーズベルトは、この重要ではない問題をきっかけにして自分の側でもっと大きな戦争を引き起こしたいと思い、しかも満州を共産ロシアに与えようとしたのではないかと考えることになるだろう」
徳富蘇峰は、「日本が七重の膝を八重に折って、提携を迫るも、昨年(昭和十六年)八月近衛首相が直接協商の為に洋上にて出会せんことを促しても、まじめに返事さへ呉れない程であった。而して米国、英国・蒋介石・蘭印など、いわゆるABCDの包囲陣を作って蜘蛛が網を張って蝶を絞殺するが如き態度を執った。而して、彼等の頑迷不霊の結果、遂に我をして已むに已まれずして立つに至らしめたのだ」(『東京日日新聞』一九四二年三月八日付)と書いていたが、七十年という歳月を経て、ようやく『フーバー回想録』によって、蘇峰の主張が裏付けられたのだ。
フーバーは、さらに重大な事実を記録している。
天皇陛下は、一九四一年十一月に駐日米国大使を通じて、「三カ月間のスタンドスティル(冷却期間)をおく」との提案をされたが、ルーズベルトはこの提案をも拒否したと書いている。アメリカの軍事担当も、冷却期間の提案を受け入れるべきであるとルーズベルト大統領に促していたのだ。
フーバーは、「日本は、ロシアが同盟関係にあったヒトラーを打倒する可能性を警戒していたのである。九十日の冷却期間があって、(戦端開始の)遅れがあれば、日本から〝全ての糊の部分〟を取り去ることになり、太平洋で戦争する必要をなくしたに違いない」とも書いている。
当時、アメリカでは戦争への介入に反対する孤立主義的な世論が強かった。ルーズベルトは欧州戦線に参戦するために、日本を挑発し戦争に引きずり込んだのである。日本国内にも日本を日米開戦に向かわせようとする工作員が入りこんでいた。実際、リヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が日本国内で諜報活動を行い、そのグループには近衛のブレーンだった尾崎秀実もいた。
―― ルーズベルト自身、反日的思想を持っていたとも言われる。
稲村 彼は日系人の強制収容を行い、「日本人の頭蓋骨は白人に比べ二千年遅れている」と周囲に語るなど、日本人への人種差別的な嫌悪感を強く持っていたとも指摘されている。
http://gekkan-nippon.com/?p=2969
【真珠湾攻撃70年】 「ルーズベルトは、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』」
日中戦争-戦争を望んだ中国 望まなかった日本
林 思雲, 北村 稔
「日中戦争は日本の侵略戦争だった」―この言説の呪縛から解き放たれるときがきた。戦争開始前後における知られざる「真実」を明らかにした画期的論考。
内容紹介
本書では、日中戦争研究の大前提となっている「侵略戦争を起こした日本と
侵略された中国」という枠組みは、取り払われている。
――冒頭からこう述べられているとおり、本書はこれまでの硬直した日中戦争観を
排したうえで歴史をとらえようと試みたものである。
本書では、これまで正面から論じられなかったが事実が明らかにされている。
その一つが、本書サブタイトルにあるように、「戦争を望んだ中国と望まなかった日本」
という構図である。また他にも、これまで論じられなかった事実が、
丁寧な検証をもとに提起されている。
中国近代史研究に定評のある二人の著者が送る渾身の論考。本書の読者は、
日中戦争に対する見方がこれまでいかに歪曲したものであったかがわかるだろう。
まさに日中の近現代史を変えるであろう一冊!
http://www.amazon.co.jp/dp/4569693008
(読者の声1)『日中戦争:戦争を望んだ中国、望まなかった日本』(北村稔・林思雲共著)(PHP)を全文英訳しました。
日中歴史共同研究日本側座長の北岡伸一・東大教授は、「日本の歴史学者で、日本が侵略していないとか、南京虐殺はなかったと言っている人はほとんどいない」と読売新聞に書いています。
ということは日本の歴史学者は、事実と無関係のウソもしくは空論をまじめに論じていることになります。なぜなら、日支事変の2大重要ポイントを完全に否定することになるからです。
第1ポイント:盧溝橋事件では、事件勃発4日後に結ばれた「現地停戦協定」第1条で「中国側に責任があり、責任者を処罰する」と書かれていたことを無視しています。
第2ポイント:本格的な戦争は盧溝橋から約1ヶ月後に起こった上海事変です。
当時、反日的であったニューヨークタイムズですら、「日本軍は事態の悪化を防ぐためにできる限りのことをした。だが中国軍によって文字通り衝突へと無理やり追い込まれてしまったのである」
と書いています。(1937年8月30日付)
広く信じられている「日本侵略者論」は、実は極めて怪しい論なのです。
実は当時、中国では日本と戦うべしという世論が圧倒的であり、それに対して日本は戦争を全く望んでいなかったというのが実情でした。
本書は、こうした事実、そして戦争下の中国社会の実態を豊富な資料に基づいて明らかにしている画期的な日中戦争論です。
いつまで架空の思いこみに囚われて「贖罪意識」の奴隷になっているのでしょう。
http://www.melma.com/backnumber_45206_5104882/
日中戦争はドイツが仕組んだ
ドイツ人は恋人にチョコレートも贈らないほどにケチだが、その本当の理由は?
日本の新幹線が時刻表通りに運行されることをドイツ人は信用しない
♪
川口マーン恵美『サービスできないドイツ人、主張できない日本人』(草思社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
秀逸な日独文化比較論である。
日本人とドイツ人の差違を平明に主婦の視点から、三人の娘の母親として(教育ママ?)の視点から、そして作家、エッセイストとしての文化的視点からの考察に加えて、本書の全編に愛国者の視点がある。
後者の視点がないとスタンスに一貫性が失われる。
一部は雑誌『MOKU』などに連載されていたので読んだ箇所もあるが、いつも叙述が変化に富んでいて、刺激的で面白くもあり哀しいほどにおかしい。生活に密着したところから議論が進むので、若い女性も飛びついて読む本だろう。
とても取っつきやすく、それでいて文章は陰陽と濃淡に彩られる。
観光地へ行っても土産を買わないドイツ人、どっさり買い込む日本人。駐車代金100円を節約するドイツ人は、しかし家具をコーディネートして豪華なセットをどんと買う。家をぴかぴかに磨く。ところが誕生パーティでは贈り物をしない。出席者は自作の詩を読んだりする。ピアノを弾く。嗚呼、そうか、生活の態度が最初から違うのだ。
こうなると恋人同士でも巨大な懸隔が日本人とドイツ人の男女交際の過程にも如実に現れる。
ラボホテルを楽しみ、高価なプレゼントを贈る日本人のカップル。百円ショップあたりで奇妙な雑貨を買って、それを平然と恋人におくるドイツ人。
時刻表通りにぴったりに運行する日本の新幹線。遅れてもお詫びもしないうえ、放送もしないドイツ。ゴミの仕分けが徹底しているドイツは家とその周囲は綺麗なのに、公道は汚染されている。
宅配便に時間指定ができる日本、いつくるかわからないドイツ。文句を言っても「それは私の所為じゃない」と責任を転嫁する癖は、なんだか中国人風。つまりドイツ人の潜在意識には『サービスをやるのは下人』という凄い階級意識が存在するという。
だから川口さんは「成田空港に着いた途端、ドイツでの日頃の緊張がストンと抜け落ちる」のも「日本社会では警戒心を持たなくてもよい」からだと力説される。
(嗚呼、良い国に生まれて良かった)
評者(宮崎)が一番驚かされたのは教育制度を論じた箇所である。
てっきりドイツにはマイスター制度がいまも脈々と存続し、技術者の子は熟練工に磨きをかける、だからドイツも日本同様のものづくり国家と固く信じてきたが、過去三十年ですっかり様変わりしているという。
伝統的に小学四年生で試験の結果、エリートと「そうでない」と人生のコースが別れるドイツは、はてしなき効率主義でもあった。
ところが、職業訓練をおこなう学校はいまや「落ちこぼれ、すね者、外国人」のたまり場となり、不良学校然として、エリートは避けるうえ、職人の親までが、そうした『落ちこぼれ学校』に子供を行かせなくなっているというではないか。
そのうえ、教育者にもドイツでは問題がある。
「子供を扱う術」をドイツでは「教師養成の過程であまり重視しない」。だから教師と生徒は対立関係おなり、敵視するのだというから穏やかではない。
子供がビールを飲もうが学校でタバコをすおうが、同級生同士がいきなり同棲しようが教師はまったく無関心。「ドイツの学校では、教師と生徒の繋がりはほとんどない。教師はその授業の時間にいるだけで、教師間の横の繋がりも希薄だ」という。
川口さんはこう言う。
「日本の学校で何より素晴らしいと思うのは、小学校で教師が生徒と一緒に給食をたべること、そして生徒が学校の掃除をすることだ。指導要領がどう変わろうが、教育委員会が右寄りになろうが左寄りになろうが、この二つだけは絶対に変えるべきではない」
さて本書の言語による文化比較の肯綮も、ドイツで三十年近くを暮らす川口さんらしい実体験から産まれている。
文学作品でもカフカやムラカミハルキをお互いがよみ、しかし言葉のニュアンスや翻訳不能の箇所があるので、終局的にその作品を理解できたとは言えないだろう。
日本語とドイツ語。それを使うときのマナー、身振りの差!
「使う言葉によって、なぜその人間の中身が変わるのか」と著者は設問する。たとえば、「着物を着たら動作が淑やかになって、言葉使いも柔らかくなり、性格が優しくなるのに、その同じ人間がビキニを着たら、胸を張って大股で歩き出し、動作と同じく性格も活発になるのと似ている」。
英語も中国語も敬語がなく、丁寧語は少ない。「わたくし」も「私」も「わらわ」も。「オレ」も「僕」も「ワシ」もない。中国語の一人称の主語は「我」であり英語は「I」だけ。
言葉に深みがあるのは、どうしても日本語の強み。
評者が中国へ行ってよく指摘されるのは「なぜ中国人社会では宮崎さんは、あれほど横柄なのか?」。自分では気がついていなかった。
英語を喋るとき、集中して論理を構築することに努力し、なぜか身振りも大げさになり、手を広げたりしている自分を発見するが、日本語で会話しているときは、むしろ敬語、相手への思いやりに気がいって、言葉を選ぶことに気を遣う。
中国では横柄な態度を意図的にやっているわけではなく、中国語が本来、尊敬語も丁寧語もない、貧しい語彙力の言語体系である以上、どうやって詭弁を弄するかにエネルギーが注がれる。
こうした言葉を使う側の姿勢にも、文化の本質があることを思い出した。本書は入念に、このことの検証を展開している。収穫が多く、旅行中、携行して読み切った。
http://www.melma.com/backnumber_45206_5105105/
白人はイルカ食べてもOKで日本人はNG 科学的根拠はない
2011.06.14 16:00
【書評】『白人はイルカを食べてもOKで日本人はNGの本当の理由』
吉岡逸夫著・講談社+α新書・880円(税込)
* * *
本書の表紙を開くと、鮮血に染まった海岸に横たわる多数のイルカがいきなり目に飛び込んでくる。イルカ漁で有名な和歌山県太地町の写真ではない。デンマーク自治領、フェロー諸島で行なわれている追い込み漁を写したものだ。
アカデミー賞を受賞した映画『ザ・コーヴ』で、太地町の人々は極悪人のように描かれたが、この映画にフェロー諸島のイルカ漁は一切出てこない。
〈今回のイルカ漁への非難、捕鯨への批判を見て、そこに白人たちの差別意識を感じるのは私だけだろうか〉
本書では、イルカ保護活動家らへインタビューを行ない、太地町とフェロー諸島の扱いの違いを比較し、彼らの傲慢さがどこから生まれてくるのかを検証していく。
シー・シェパード幹部のスコット・ウェスト氏はこう述べている。
〈イルカは牛などに比べて人間に近い。われわれと同じような複雑な頭脳と形態を持っている。彼らは文化的な共同体を持ち、自身の言葉や歴史を持っているから人間に近い。他の家畜とは違う〉
イルカは人間と同じだとする“イルカ教”のカルトも同然であり、科学的根拠はどこにもない。
著者は、白人はイルカ漁がOKで日本人はNGの理由として、差別や寄付金目的のほか、日本側のPR不足を挙げ、苦言も呈する。
東日本大震災の発生時、岩手県にいたウェスト氏らシー・シェパードのメンバーも被災し、住民や警察の支援で無事避難できたことが報道された。ウェスト氏は手記で「我々に向けられた親切と寛容さを、書きつくすことはできない」と述べている。寄付金集めが目的で日本叩きをしている連中でも、日本人は差別したりはしないのだ。
※SAPIO2011年6月15日号
http://www.news-postseven.com/archives/20110614_21772.html
日本の刺青と英国王室―明治期から第一次世界大戦まで [著]小山騰
[評者]平松洋子(エッセイスト)
[掲載]2011年2月6日
 著者:小山 騰 出版社:藤原書店 価格:¥ 3,780 著者:小山 騰 出版社:藤原書店 価格:¥ 3,780 |
■「野蛮」に憧れた、奇妙な交流史
カバーの肖像写真に息をのんだ。笑みを浮かべた妙齢の英国女性が身にまとっているのは繊細なレース模様のドレスではなく、全身にほどこされた刺青なのだった。彼女は「刺青師の王様(キング)」と呼ばれた英国人G・バーチェットの妻。よく見ると、右上腕の一部に髪を結った日本女性の意匠が紛れこんでいる。
この本を読むまでまったく知らなかった。明治期、英国から日本の刺青にこれほど熱い視線が注がれていたとは。
刺青は文明開化まっさかりの日本で野蛮とみなされ禁止されたが、かたや「文明国」の英国王室や貴族階級にとっては憧憬(しょうけい)の対象だった。先鞭(せんべん)をつけたのは明治天皇にも面会したベレスフォード卿で、明治二年に来日したとき背中一面に狩猟の光景の刺青を入れた。十四年、のちのジョージ五世とアルバート王子は鶴と龍。英国の新聞記事は、わざわざ日本で彫る刺青は「大変な熱狂状態」と報じた。
皮肉なパラドクスである。日本はひたすら「文明国」を目指したが、その相手から見れば「野蛮」な刺青はひとの肌に咲く精密な芸術の華だった。羨望(せんぼう)は、英国王室が複雑な婚姻関係をもつヨーロッパ王室にまで広がってゆく。
著者は国会図書館や英国図書館を経て、現在ケンブリッジ大学図書館勤務。英国で発掘した資料や文献を精読し、まさに刺青をほどこすような丹念な手つきで日英間にひそむ奇妙な交流史を発掘してゆく。その過程で「刺青のシェークスピア」「エンペラー」と呼ばれてあまたの外国人顧客に刺青を彫った日本人、彫千代の存在も掘り起こし、興味をそそる。
明治四十三年発表、谷崎潤一郎『刺青』の冒頭を思いだす。
「其(そ)れはまだ人々が『愚』と云(い)う貴い徳を持って居て、世の中が今のように激しく軋(きし)み合わない時分であった」
鎖国下で独自に切磋琢磨(せっさたくま)、芸術的到達をみせた刺青の親善交流。それは明治の徒花(あだばな)などではなく、むしろ「貴い徳」の所産でもあったろうか。わたしは読むうち、ふしぎにのんびりとして微笑(ほほえ)ましい気分を抱いた。
◇
こやま・のぼる 48年生まれ。ケンブリッジ大学図書館日本部長。
http://book.asahi.com/review/TKY201102080162.html
日本の刺青と英国王室―明治期から第一次世界大戦まで: 小山 騰: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4894347784
〈時の回廊〉森浩一「古墳の発掘」 天皇陵の疑念 世に問う
森浩一さん=京都市中京区、滝沢美穂子撮影
「仁徳天皇陵」に葬られているのは、本当に仁徳天皇か。半世紀前、天皇陵を巡る疑問を初めて世に問いかけた一冊が、『古墳の発掘』だった。それ以降、書き続けた一般書は100冊を超す。多くの研究者や歴史教科書に影響を与えた考古学者は、80歳を超えてなお、日々の発見に心躍らせる。
◇
昭和30年代、僕は大阪府立高校に勤める傍ら、奈良県橿原市で古墳群の発掘を指揮していた。その最中の1964年春、東京大の井上光貞先生が、自身の著作『日本の歴史(1)神話から歴史へ』(中央公論社)の考古学担当に抜擢(ばってき)してくれました。
その夏、発掘が終わると、扇風機もない大阪の自宅で、氷柱を毎日2本バケツに入れて机の左右に立て、1週間ほど懸命に書いた。原稿を取りに来た中央公論の編集長から、「新書を1冊書きませんか」と誘いを受けたのが、『古墳の発掘』。「『天皇陵』にしたい」と言うと、「天皇陵をいきなり書き出しても分からない」。だから前半を古墳入門編とし、後半で「タブーの天皇陵」に力を注ぎました。
小学生の頃、電車通学する車窓から百舌鳥(もず)古墳群の巨大な古墳が見えた。その最大の古墳「仁徳陵」の被葬者が仁徳天皇かどうかを疑う人はいなかった。古墳群にあるもう一つの巨大な前方後円墳、ニサンザイ古墳は「陵墓参考地」で天皇陵ではない。天皇陵の指定が完璧なら、参考地というあいまいなものを残す必要はないのに、という疑念が子ども心にわいたんです。
天皇陵は墳丘内への立ち入りが禁止されており、江戸時代の図面や石室の観察記録を丹念に読んで、知識とするほかない。幸運だったのは『古墳の発掘』を書く前年、宮内庁「書陵部紀要」が発行され、幕末の「文久の修陵図」を見たこと。そこには、天皇陵を改変する前と後の様子が見事に描かれていた。荘厳な構築物を見せることで幕府が朝廷を尊崇していることを示そうとした実態もわかりました。
初版本で思い切って「天皇陵の所在地と墳形」の一覧表を作り、信頼性の度合いを示した。多くの天皇陵に「妥当なようだが、考古学的な決め手を欠く」として、●印を付けたんです。後の11版では表に手を加え、初版で「ほとんど疑問がない」と○印を付けた仁徳天皇陵を●印に落としました。
『古墳の発掘』は売れて28版までいったが、まだまだ不満やった。本では「仁徳陵」などと表記したが、その後、「仁徳陵古墳」を使い始めた。宮内庁が仁徳陵に指定している古墳、の意味だ。たった2文字があるかないかの違いだが、多くに影響を与えたようだ。宮内庁のある人から「法律で決まっている天皇陵に勝手に古墳名を付けるとはけしからん」と手紙も来た。
それでもなお、「仁徳」の人名が付くという問題が残る。それは奈良時代に創られた漢風の諡号(しごう)で、古墳時代にはなかった。そこで、古墳の所在地で呼ばれている地名を適用し、「大山(だいせん)古墳」とする私案を出したんです。
宮内庁は天皇陵をどう考えているのか。1年ほどかけて知恵を結集し、今の仁徳陵で問題がないなら、そう言明すればいいし、疑いがあると思うなら今後、計画的に発掘すればいい。素早い決断を望みたいですな。
最後に日本の、地域のすごさ、というのを書き上げたいと思います。80歳を超えて、「もし60歳で死んでたら、こんなん知らんと死んでたんやな」「得したなあ」と思うことがようけある。「感激のない人には学問はできん」と誰か言うてたけど、ほんまやね。(聞き手・大脇和明)
◇
もり・こういち 1928年生まれ。同志社大名誉教授(日本考古学)。13歳から遺跡探訪を始め、同志社大在学中に学会誌「古代学研究」創刊。「関東学」など地域学も提唱。
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201202020353.html
【書評】『維新・改革の正体 日本をダメにした真犯人を捜せ』藤井聡著
2012.11.25 11:06
「維新・改革の正体」
■「失われた二十年」の真実
ケインズ主義的公共投資、国土計画、整備新幹線などは、かつては高度経済成長を支えたかもしれないが、それも、もはや過去のものである。これからは、政府が経済を主導する時代ではなく、小さな政府、自由化、グローバル化の時代であり、インフラのようなハードではなく、情報や金融のようなソフトの時代である。このようなイメージが共有されている。多くの人が、時代の流れは単線的で、逆行しないものと思いこんでいる。
しかし、実は、リーマン・ショック以降、世界の有力な経済学者たちは、ケインズの復活を唱え、公共投資を主張するようになっているのだ。また、良心的な知識人たちは、1980年代以降の新自由主義が破綻したことを認め、60年代頃が資本主義の「黄金時代」であったと再評価し、それを取り戻そうと訴えている。時代は、単線的に進むわけではない。間違った道へと進んだのならば、方向を変え、場合によっては後戻りすることも必要なのだ。「後戻りはできない」とかたくなに思うのは、左翼的な進歩史観の悪弊である。
本書は、日本経済の「黄金時代」を築いた戦前生まれの3人、宍戸駿太郎、下河辺淳、小里貞利の証言の記録である。日本経済の成長を支えた彼らの歩んだ道は、決して平坦ではなかった。特に80年代以降、彼らが築いた成果を享受した後の世代は、先輩たちに感謝する代わりに、彼らを排除した。反成長主義の左派からも、新自由主義の右派からも攻撃された彼らは、理論やデータをもって戦い続けたが、劣勢はいかんともしがたかった。その結果が、「失われた二十年」であり、リーマン・ショックである。
3人の証言から、日本を没落させた犯人たちが実名で暴かれていく過程は、スリリングである。3人とも、高齢にもかかわらず、明晰(めいせき)な論理を語る。時勢に流されずに信念を貫き通すその姿は、感動的である。これが、真のエリートというものであろう。彼らの意志を継ごうという著者の気概が伝わってくる。日本の命運を決める総選挙の前に、必読の書である。(産経新聞出版・1365円)
評・中野剛志(評論家)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121125/bks12112511070015-n1.htm
維新・改革の正体を語る
http://www.youtube.com/watch?v=wLzxRPjr4S4