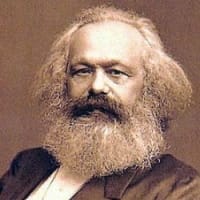新古典派・現代正統派の利子率理論はどのようなものだったか。資金の需給は利子率という資金の価格によってバランスする(はずである)。つまり不況局面においては投資が減退し資金需要も減退するから利子率は下がる。それもただ下がるだけではなく資金需要が復活するところまで下がるはずである。不況局面において投資は減退するが、利子率の低下によって投資は復活し景気は反転していく。これが新古典派・現代正統派の景気循環理論である。いわゆるリフレ派はこの理論のもっとも純粋な(素朴な?)表現である。
しかしケインズ一般理論では利子率は資金の需給バランスでは決定されず、資本家が自らの貯蓄のうちいくらを流動性として確保しておくか、という流動性選好の度合いによって決定される。この流動性選好は不況局面では高まることはあっても下がることはない。流動性選好が高まれば利子率も下がることはなく利子率の低下による投資の復活も望めないだろう。これがケインズの見立てである。
ケインズは金融市場において日々ポートフォリオを組み替える資本家の行動を想定する。もちろん強気の人から弱気の人、はたまた労働者の多くのように人任せにしている人々まで様々だが、多様な人々が従わなければいけない金融市場の単純な法則がある。それはより収益性の高い方に高い方にと乗り換えなければならないということである。
以下のケインズの所論を追うには、いったん通貨当局の公開市場操作により利子率が低く抑えられるという前提を外す必要がある。公開市場操作がいまだ一般的ではなかった時代である。
利子率の変化と流動性選好の変化について興味深い分析を行っている。先ほどの「金融市場の単純な法則」である。ほとんどの人が誤読していると思われるので注を付した。
利子率のどのような低下も非流動性の期間収益――これは資本勘定上の損失の危険を相殺するための、一種の保険プレミアムとなる――を減少させ(*1)、その減少幅は旧利子率と新利子率のそれぞれの平方の差に等しい(*2)。
たとえば、長期債権の利子率が4パーセントだとするとさまざまな確率を勘案したうえで、長期利子率の年上昇率がその4パーセントすなわち0.16パーセントを超えるおそれはないと思われるかぎり、流動性を手放したほうが有利である。(*3)けれども利子率がすでに2パーセントにまで低下していたら、期間収益が相殺しうる利子率の上昇は年率わずか0.04パーセントにすぎない。実際このようなことが主因となって、おそらく利子率はあまり低い水準にまでは下がらないのである。将来起こることは過去に起こったこととは違うと信じるに足るだけの理由がないかぎり(たとえば)2パーセントの長期利子率では、希望よりは怖れが優勢となり、しかもこの利子率では、期間収益は怖れのごく一部分を相殺するだけである(*4)。
*1:「期間収益(the current earnings from illiquidity)を減少させ」非流動性(債権)のことであるから、現に保有している債権の期間収益は減少しない。債券価格を上昇させるが…。流動性を手放そうとするかどうか、の問題であるから債券価格の上昇により、流通している(売りに出ている)債権の現在時点での将来収益を減少させる。との意味である。流動性の保有者から見た話なのだ。
*2:平方の差に等しい???旧利子率と新利子率を債券価格に割り戻して考えるとこうはならない。なにか深遠な数式でも隠れていそうだが、たとえば、利子4%分だけを再投資しようと考えた場合、利子が4%以上に上昇するならばその債券を売って乗り換えたほうがいい。つまり4%×4%=0.16%が限界ということである。債券は年間4%の収益であって複利にはならない。逆にこれ以下なら、保有し続ければいいし、もっと上がれば元本割れということもありうる。だから売って再投資することになる。その境界が4%×4%=0.16%である。
*3:4%の4%、ここが重要。債券の収益の再投資の話である。ここは「流動性を手放した方が有利」要は債券は「買い」だと言っている。0.16%を超える期待があるなら「売り」となる。
*4:利子率が低下すると、相殺しうる利子率の変動幅は小さくなり投資家は過敏になる。不況の時ほど金融の不安定性は増す。
ここまでは前ふりで、不況になるほど流動性選好が高まり状況をさらに悪化させるということを踏まえておけばいい。この章の白眉は、だからこそだが、次に出てくる公開市場操作について言及しているところである。
このように見て来ると、利子率が高度に心理的現象であることは明白である。たしかに、第5篇で見るように、均衡利子率は完全雇用利子率を下回る水準にはありえない。なぜなら、このような水準では真性インフレーション状態が生み出され(*1)、その結果、M1はどんどん増え続ける現金量を片っ端から吸収してしまうであろうから。
*1:完全雇用にあるとき、さらに金利を下げれば火に油を注ぐことになる。M1とは取引動機による貨幣保有。片っ端からモノに変わっていく。だからあり得ないと言っている。
このように見てくると、というのは「2パーセントの長期利子率では、希望よりは怖れが優勢となり、しかもこの利子率では、期間収益は怖れのごく一部分を相殺するだけである」を受けている。ケインズは心理的を高度に慣習的と言い換えて、利子率を放っておけばいつまでも完全雇用は達成されないことを指摘する。将来への不安が亢進したとき、流動性選好は高まる。利子率の一般理論では利子率は流動性を手放すことへの報酬であった。流動性選好が高まった時、利子率は上昇する。ないしはこれ以上下がらない水準に貼りつく。
ケインズは、そのような時に、通貨当局が取るべき方策を提言している公開市場操作である。かなり長いが引用する。今日では常識である(だった?)。
有効需要を完全雇用を与えるに足る高水準に維持しようとするさいに立ちはだかる困難―慣習的でかなり安定的な長期利子率と気まぐれで高度に不安定な資本の限界効率との結びつきによって生じる困難は以上で読者には明白になったことと思う。
だから利子率を操作することが完全雇用達成にとって重要なのだ。
ケインズによる「公開市場操作」の提案
以上のことは次の命題に要約することができる。期待の状態がどのようなものであれ、大衆は取引動機や予備的動機のために必要とされる量を超えて現金を保有しようとする潜在的可能性をもっており、その可能性は実際に現金保有となって実現するが、その程度がどれくらいかということは通貨当局が現金を創造しようとするさいの条件にかかっている。流動性関数L2に要約されるのはこの潜在的可能性にほかならない。
それゆえ他の条件に変わりがなければ、通貨当局の創造する貨幣量に応じて一つの利子率、もっと正確に言うと、満期の異なるさまざまな債権の利子率複合体が決まる。もっとも同様のことは、経済体系における貨幣以外のどのような要因をとってみても、それを他から切り離すかぎり、言えることである。したがってこの特殊な分析に有用性と意味があるとすれば、それは貨幣量の変化と利子率の変化とのあいだにとりわけ直接的あるいは因果的な連関がある場合だけである。われわれは両者のあいだにことさらの連関があると考えるが、その理由は、銀行体系と通貨当局は、大まかな言い方をすれば、貨幣と債権のディーラーであって、〔実物〕資産や消費財のディーラーとは違うということである。
通貨当局がありとあらゆる満期日の債権を、条件を指定し、売り買い双方向で取引することにやぶさかでなければ、利子率複合体と貨幣量との関係は直接的となるだろう。危険の程度がさまざまに異なる債権でも進んで取引しようとする場合には、なおさらである。このときには、利子率複合体は単に銀行体系が債権を取得あるいは手放すさいの条件を表すだけのものとなり、そして〔需要される〕貨幣量は、関連事項をすべて勘案したすえに、市場利子率に示された条件であれば流動現金を債権と交換に手放すよりはむしろそれに対する支配権をもつにしかずと考えて、人々が彼らの手許におく量だとことになろう。短期手形に対する単一の銀行割引率しかなかったところへ、中央銀行があらゆる満期日の金縁〔優良〕債券を指定した価格で複合的に売買するようになったことは、おそらく、通貨管理技術の考えられる改良の中でも実務上最も重要なるものである。
(*筆者注:日銀はフル活用している)