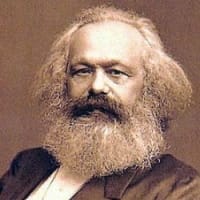第3章 有効需要の原理
経済学の不在
45年前、経済学部に籍を置いていたころ、マクロ経済学は空白であった。ケインズを講ずるわけでもなく、さりとてフリードマンもまだ猛威を振るってはいなかった。その頃、マルクスもケインズも「過去の人」扱いであり、彼らが提起した問題は「解決済み」とされていた。それどころかマルクスやケインズは「成長神話」を前提にしているとすら言われていたのである。
焦点は原油価格革命、貿易摩擦であり、ドルショックであった。世界貿易、国際金融だったのである。ケインズもマルクスも対象とするのは一国の閉鎖経済である。それゆえ、物事を深く考えない人は、世界貿易、国際金融の分野ではケインズもマルクスもあてにならない、と考えてしまったのである。
ではケインズが原理的に提起した完全雇用不可能性命題はどうなったか。
解決したのだろうか?
一般理論の科学性
この章ですでに「われわれが生活している経済社会が完全雇用を与えることができない」理由が説明されている。それは、⊿総供給価格/⊿雇用量が徐々に増加していくために総供給曲線が下に凸の曲線となるのに対して、⊿総需要価格/⊿雇用量は徐々に減少していき総需要曲線は上に凸の曲線となるからである。そうなる理由は、総供給価格は収穫逓減の法則に従い、総需要価格は限界消費性向低下の法則に従うからである。そのため総供給曲線(関数)と総需要曲線(関数)は必ず交わり、それ以上総供給(≒雇用量)が増えることはない。この交点のことを有効需要と呼ぶ。
このとき有効需要は達成されるが、そのときに同時に完全雇用が達成されている保証はどこにもないのである。詳しくは「第16章 資本の性質に関するくさぐさの考察」参照
収穫逓減の法則に従えば単位雇用量当たりの生産量は徐々に減るが、価格の上昇で総所得の上昇速度は上がる。よって下に凸となる。もちろんこの前提を捨てて、直線としても、上に凸としても構わない。限界消費性向が所得が増すほど下がればいいだけである。
限界消費性向低下は、一つは古今東西を問わない人間の心理法則として説明され、低下した消費を補うだけの投資がない限り有効需要は低下し完全雇用水準から離れていくのだと説明される。この章では、有効需要=消費+投資と定義されており、もっぱら限界消費性向の低下から説明されている。
従って、一般理論を根底から覆すためには限界消費性向低下の法則を否定すればよく
- 「人は豊かになればなるほど消費性向が上昇する」という事実を示すだけでよい。
- あるいは「低下した消費性向の分だけ必ず投資が増える」という事実を示すだけでよいのである。
一般理論の命題には、反証可能性があり極めて科学的である。
古典派、現代正統派の共通点
では「リカードが完膚無きまでの勝利」を得たのはなぜだろうか?ケインズは以下の5点を挙げる。
- 知的威信:無学な庶民の考えるところとは、はるかかけ離れた結論に到達していること
- 徳性:実践に移されると禁欲的となり、多くの場合、苦みさえともなったこと
- 美:壮大で首尾一貫した論理的上部構造をもつように仕立て上げられていること
- 権力の覚えめでたきもの:進歩を旨とする体制では数々の社会的不正義も無慈悲と見えるものもそれらはなべて必要悪にほかならず、これらを変革しようとする試みはつまるところ善よりはむしろいっそうの悪をなすと説明して見せたこと
- 権力の背後にいる支配的社会勢力の支持を引きつけた:資本家個人の自由な活動を正当化する方便を提供したこと
新自由主義は「痛みを分かち合うという徳性」を持っていることは、いやになるほど経験してきた。しかも人々が「お前も不幸になれ」とそれに熱狂することも。
こういうイデオロギー批判は今や流行らなくなってしまったが、新自由主義と言われる現代正統派にもそっくり当てはまるのは言うまでもない。
そして経済学は科学であることを止め体制擁護のイデオロギーとなったのである。