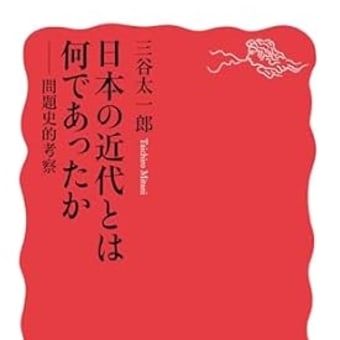日本では仏教伝来以前からそれぞれの豪族の祖先の霊や農業神が結びついて氏神などとして崇拝されてきた。そこにもたらされたのが仏教であり、元来アニミズムであった土着の氏神様とは要素の異なる対立するものとして入ってきたとも考えられる。しかし実際には両者はお互い補い合うように受け入れられ、実際仏教も中国と朝鮮半島を経由することとあわせてインドの仏教とは異なる姿となった。そもそもインドにおける仏教でさえ多様であり、オリジナルの形から新派、大乗仏教、密教と変容している。日本での仏教の特徴は「諸法実相」、つまり、森羅万象が真実の姿、実相であると捉えた。眼前に見える樹木や岩、人間の身体こそがそのままで真実の姿であると。自然崇拝の神道形態と似ているとも思える。
日本仏教における、諸法、実相に空、仏性というキーワードを加えて、解説する。諸法とは日常生活の場としての世界、実相とは世界の中の全ては真実の姿であること、空とは世界の中のものが恒常不変の実態として存在するのではないこと、仏性とは人間や生命あるものに本来備わるべき仏としての潜在的本性である。インド仏教では、1.物質的存在、2.それらを人が感じること、3.それを認識すること、4.それらに対する人の行動、5.判断 この5つを五蘊と考え、一人の人間が自分の感覚器官で把握したデータにより再構成した周囲世界のことを指していると考えた。日本仏教ではこうした人間感覚の対象となる物質世界が、人間の心的世界にどのような価値を持つのかを問題とした。認識主体の重要性よりも、眼前に見える花や岩という存在がわれわれにどのような意味、価値、力を投げかけてくるのかを重要視したのが日本仏教である。
日本仏教が考えた命題は、諸法は空なのか、諸法は実相であるのか、衆生には仏性が存するのか。インド仏教では「一切の衆生に悉く仏性有り」という如来蔵思想があるが、日本仏教では衆生とは命あるものすべて、「山川草木悉皆成仏」とした。日本では自然に命が宿る神道の考え方を取り込んだものと考えられる。さらに人間には本来仏性が備わるが、それを覆い隠すのが煩悩であり、煩悩などの汚れを取り除くことで仏性が顕わになってくるというもの。如来蔵思想を説いた勝鬘経に注釈を施したのが聖徳太子であり十七条憲法はこの経典に基づく。空海や最澄が生涯をかけて目指したことは諸法実相という思想をあらためてみずからの理想として構築し直すことだった。「諸法は空である」という仏教の一つの伝統が中心的な理想原理として承認されるようになるのが、平安初期の空海と最澄の時代だった。
空海も最澄も、諸法実相といえるのは、厳しい自己否定に裏打ちされた修行の後であるとした。しかし平安後期に現れた本覚思想や密教も生類のみではなく山川草木、森羅万象に仏性あるいは生命を見る。古来のアニミズムと仏教寺院による地域支配という経済的要因が合わさり、神仏習合が盛んに行われた結果である。本覚思想では仏性が重視され、衆生には仏性が存する、という日本的理解が進んだ。更に時代が進み、鎌倉仏教では、世界に対する考察をひとまずおいて、世界と空との関係にも関わらず、阿彌陀佛という人格神への関わりの中で空を体験することを追求。道元は、禅を実践することで、諸法は仏性なりと捉えられることを主張した。
室町時代になると諸法実相、煩悩即菩提、色即是空、といった仏教の伝家の宝刀を不幸な使い方により、空海や最澄の戒め、つまり厳しい修行のあとにのみ言えることを、誰でもがとなえることができるとした。室町時代には「諸法実相」「色即是空」が芸能、絵画などの文化的表現として追求された。江戸時代には寺請制度により仏教徒数は増えたが、仏教の教えが広まったかは疑問である。明治以降は新たな状況下、仏教が自らの理論と実践の表現を変えざるを得なくなる。人間の認識とは別として、世界の実存を認めざるを得なくなったのである。本書内容は以上。