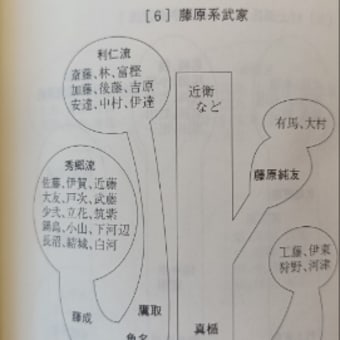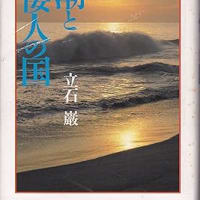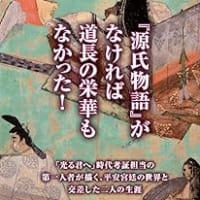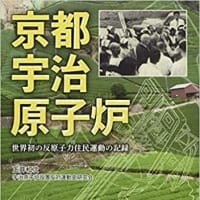この酸素濃度はカンブリア紀以降でも5回劇的に低下しており、現在の酸素濃度21%を大きく上回る時期もあった。その劇的に減少したボトムの時期と5回の生物大絶滅が同期しているという。酸素濃度の低下時期には多様性が増加して様々な基本的デザインが試され、そしてその後には酸素濃度の上昇があり、生き残った生物の多様性が増加する。カンブリア大爆発と言われるカンブリア紀の多種類生物の出現はカンブリア紀の最初に起きた酸素濃度の劇的低下の反動であるというのがその仮説。
そしてカンブリア紀に発生した生物の一つの特徴として体節の繰り返しがあった。そのデザインは鰓という呼吸器官の効率化であり、繰り返すことで鰓の表面積が増え、表面の水流により効率よく水が鰓に取り入れられたため生き残りに有利に働いた。軟体動物がその体に殻をつけたのは、ポンプ式呼吸システムの不可欠な仕組みであったという。
シルル紀からデボン紀にかけて水中から陸上に進出した生物は鰓呼吸から肺呼吸に移行した。水生生物の中では海綿、刺胞、腕足動物、コケムシ、棘皮動物のなかで陸上進出に成功した例はない。進出成功組は節足動物、軟体動物、環形動物、脊索動物であり、この中では節足動物の成功が一番約束されていた。なぜならその外骨格の箱が乾燥からの保護に適していたから。具体的にはクモ、サソリ類である。
石炭紀からペルム紀に始まった卵胎生も酸素濃度の高さがもたらした。産卵においても湿度は保たれなければならないので、卵の殻は固くて丈夫である必要があるが、あまりに水の透過性が低ければ卵は酸素を取り入れることができない。高酸素状態こそが卵胎生の前提条件であったという。ペルム紀最後の酸素濃度低下は古生代の終わりを告げる大絶滅をもたらした。その時に、心臓の4室化の進化が起こり、それは低酸素環境での呼吸効率向上をもたらした。3室心臓を持つのは両生類と爬虫類、4室心臓は哺乳類と鳥類である。恐竜が変温動物か恒温動物なのかは結論が出ていないが、中生代に繁栄した恐竜が鳥類の先祖であったとすれば、この繁栄も心臓の4室構造、つまり朝おきたらすぐに活動できて餌をすぐに取りに行けるという優位性が繁栄をもたらしたのではないかという仮説が成り立つ。
三畳紀の最後にも大絶滅があったが、二足歩行した恐竜のボディデザインはこの低酸素環境に適応し、4足歩行による呼吸への制約を取り払い、前足により獲物を捕獲するという新たな働きをももたらしたという。三畳紀の低酸素環境は四肢類の恐竜の一部が海で生活する様式を再進化させる圧力をもたらした。実際、三畳紀からジュラ紀にかけては海生恐竜の多様性が増加している。
もともとの本の名前は”Out of Thin Air”である。こちらの方が内容にあっている気もするが、主張のメインは恐竜から鳥類への進化であるような気もする。カンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、ペルム紀という古生代、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀という中生代、このあたりに関心が深い方にはぜひオススメ。