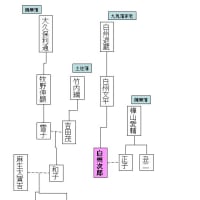本書は2012年に発刊された「銃・病原菌・鉄」の筆者ジャレド・ダイアモンドの最新作。「銃・病原菌・鉄」では、人類が発展してきた中で、一部の文明が繁栄し、それ以外が廃れてしまった理由について分析した。スペインが南アメリカ大陸の征服をした時に表題となった銃、病原菌、鉄が大きな役割を果たした。生物の進化や人類学などだけではなく、遺伝子工学、環境生物学、言語学などを組み合わせて考察すると、ここまでのことが推測できるという内容で、一部の専門分野だけからの考察では成し得ない学際的な分析と、大きなテーマに立ち向かう姿勢が本書にも発揮されていると思う。
続く「文明崩壊」では、いろいろな社会が発展してきた後に滅びてしまった理由について考察した。イースター島、北アメリカ大陸、古代マヤ、江戸時代の日本も取り上げられた。江戸時代の日本では町中での文化的な暮らしや林業の活用などが紹介され、ルワンダや配置とドミニカ、中国、オーストラリアなども題材にされた。
本書「昨日までの世界」では600万年前にチンパンジーやゴリラなどの他の類人猿たちと進化のたもとをわかった人類が何をしてきたのか、そしてその名残が現代社会にどのように残っているのか、先進国と言われる国に住む人類が忘れてしまったより良い暮らしと、進化に伴い淘汰された良くない生活、そしてそこに忘れられたそれぞれの理由などについて考察されている。600万年といえば非常に長い時間だが、狩猟生活から農耕生活に切り替わってきたのはわずか11000年前、金属器が開発されたのが7000年前、国家が初めて成立し、文字が出現したのが5400年前、この国家システムが文字の活用を広げ、食料生産の分業を進め、司法や警察、軍隊が成立し、私達人類が「歴史」として習ってきたことがらが起こり始める。しかし、この1万年とその前にも流れていた599万年の世界はどのくらい違っていたのだろうか。
四大文明が発生しその後欧州やアジア、アメリカ大陸で発展してきた各文明と、そうした文明と隔絶されて暮らしてきたアマゾン奥地やニューギニア高地人たちの違いは一体何であろうか。西洋社会をまるで知らなかったアマゾン奥地やニューギニア高地に住む人たちは599万年の人類の歴史を色濃く残しているはずである。これが「昨日までの世界」、昨日までの世界とは人類の伝統的社会であり、人類の脳と認知が形作られた進化適応の歴史の片鱗が残っているという。こうした伝統的社会で形成されている人間関係の考え方、紛争解決の知恵、子育て、高齢者対策、宗教、病気への対応、政治の考え方の中には現代社会が失ってしまって、実はおおいに役立つものがある。もちろん、多くの呪術的な行いや不衛生な生活は現代社会のほうが好ましい。ノスタルジックに昨日の世界に回帰すべき、という主張では決してない。伝統的社会から現代社会で暮らす私達は何を学べるか、これが本書のポイントである。
ダイヤモンドは現代社会をWEIRDと表現する。Western西洋的、Educated教育が普及、Industrial産業化されている、Rich豊か、Democratic民主的、Weirdつまり風変わり、伝統的社会での暮らしと比べれば風変わりなのである。国家成立以前には首長国家、部族社会があり、数百から多くても数万人のグループで暮らしていた。そしてその前の小規模血縁集団では数十人規模のグループでの暮らしがあり、リーダーや長老とともに狩猟を中心とした生活があった。小グループでの暮らしでは構成員のすべてが自分のための食料手配や身の回りの始末をすることになる。当たり前であるが、WEIRDの世界ではそうではない。警察や司法、農業従事者や宗教化、音楽科、役者までいる。本書ではアフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、アメリカ大陸、そして日本ではアイヌ、伝統的社会がもっとも色濃く残っているというニューギニアと世界の各地でのフィールドワークから集めた情報を元に人間関係、紛争解決、子育て、高齢者対策、宗教、病気への対応、政治と各話題についてまとめている。
WEIRD社会に住む私達は町で他人とすれ違っても殺されるかもしれないとか敵かどうかを確認することは通常はしない。国家があり住民や旅行者でも法律に従っているはずだという信頼感があり、それは警察力や社会信頼から成り立っている。しかし伝統的社会ではそうではない。見知らぬ他人は敵か有益な通商者、会ったことはない血縁者、もしくは友好的他集団の他人である。WEIRD人が伝統的社会の人たちと初めて接触するときには、友好的集団の他人だと認識されなければ殺されてしまうこともある。これは土地の利用が伝統的社会では仲間以外とは排他的に行われることが普通だからである。狩猟にしても農業にしても他人と土地を共有することは自分達のグループにとってプラスはない。そこで、土地を巡る争いは仲間と考えられる他の部族とも協力しながら敵と奪い合いを繰り返すことになる。狩猟も農業もしない通商目的の商人は他の地方の珍しいものや自分の土地では手にはいらない物をもたらしてくれるので有益である。白人を初めてみた伝統的社会の人たちは白人を何と認識したのだろうか。自分たちの土地を侵害する敵か、有益な商人か。ある場合には敵である収奪者であり、ある場合には有益な商人であったが、銃を持っているためかなわない相手であった。
紛争の解決では、WEIRD社会では司法による裁判が通常行われるが、伝統的社会では、血縁集団を巻き込んだ話し合いが行われ、それが不調に終われば限りなく続く報復合戦になる。別の部族の子供に対して不慮の事故で怪我をさせてしまった、または殺してしまった時の解決方法は、本人が直接行わず、血縁者や長老が仲立ちをする。そして相手の部族の代表が事故に対する賠償ともいえる価値の評価について交渉する。その結果、部族が財産だとみなせる豚やその他の物資により賠償が行われ、限りない報復に陥らないための努力が重ねられ穏便な解決が目指される。そうした交渉を通じて、当人は相手の子供の親との面談も行い、詫びる気持ちを伝える。これがなければ一生続く血縁関係や人間関係のなかで恨みが続いてしまうからである。WEIRD社会の裁判制度の不備な点はここではないかという指摘である。
子育てでは、離乳と出産の間隔や授乳、大人との触れ合い、父親代わりの大人、異なる年齢との遊びなどが紹介される。移動する集団に属する母親は、乳児を連れて移動するのは乳児が一人なら対応できるが二人もいるとできないため、子供が一人で移動できる年齢にならなければ次の子供は産もうとしない。双子の片方の乳児殺しを容認するのはこれが理由となる。決まった時間に授乳するのではなく欲しがるときに授乳するのも赤ちゃんにとっては大変ありがたい。WEIRD社会では子供は乳母車に乗せて運ぶ。乳児は母親の方を向いて横になって運ばれるが、それでは運動神経が発達しないという。伝統的社会では赤ちゃんは大人がだっこする。歩くときの視線は大人と共有できるため小さい時から大人の身のこなしを同じ目線で経験できるため運動神経がよく発達するという。子供の自立性に任せ、異なる年代の子どもたちの集団で遊ぶことで社会の成り立ちを小さい時から学ぶことができる。 こう書かれてみると、昭和の日本ではこうした伝統的社会での子育てが行われていたことに気づく。幼児殺しを除けばまさに伝統的社会での子育ての利点が生かされていたのである。
高齢者への対応では、高齢者の価値について考察される。ひと世代前以前に起きた災害の記憶、両親が狩猟に出かけている間の子育てが期待される。しかし激しい体力の消耗が求められる長距離の移動では高齢者は置いて行かれてしまうこともある。危険に対する対応では「健全な妄想」が求められるという。倒れてくるかもしれない大木の下では寝ない、地面に突き刺さった枝から推測するその理由、時として犯すリスクとその可能性などWEIRD社会では忘れてしまったような危険予知の能力が必要とされているという。現代でもラッキーな人と不運な人がいるが、ラッキーな人は危険の察知をすることに長けていて、チャンスの萌芽を見逃さないこうした伝統的社会での動きができているのかもしれない。
病気への対応では、非感染症による死亡が殆ど無いことが説明される。WEIRD社会では感染症の多くは克服されているが死因の上位は高血圧にともなう心臓病、糖尿病、ガン、肥満に伴う様々な生活習慣病である。伝統的社会ではこのような人は見られないが、急激にWEIRD化する伝統的社会では急激な肥満などのWEIRD社会特有の症状の増大が見られ、一方感染症は減少する状況がある。飢餓への備えでは、599万年の間人類は常に飢餓の備えが最優先されてきたため倹約遺伝子とも言えるDNA配列の人たちが生き残ってきたと考えられている。日本人もその例にもれないが、欧米人には糖尿病発病者がそれ以外の人種に比べると少ないと言われている。ダイヤモンドはこの理由を推測し、中世以降の飢餓消滅を上げているが、この点は説得力にかける。その他災害による食糧不足には食料の分散保管、まずいものでも食べるという食習慣の拡大で対応する。
多くの伝統的社会では部族が異なれば言語も異なるため、多くの人達は数種類の言語を話すという。世界には7000の言語が今でも存在するが、その多くは伝統的社会である。WEIRD社会には1000程度しか残っていない。伝統的社会では老人の痴呆症状が見られないため、複数言語を話すことでアルツハイマー予防になるのではないかと主張する。方言と言語の違いについても述べているが、ここは定かではない。イタリア語とギリシャ語、スペイン語には共通性があり、相互に理解可能な場合も多いというが、異なる言語である。しかし、同じ英語でもスコットランドやウェールスとイングランドでは通じないことも多い。日本の中でも青森や秋田、鹿児島、そして沖縄では単語までが異なるためお互いには通じない。しかしテレビの発達は標準語の理解という意味では片方向の理解は進んだ。バイリンガルの効用はWEIRD社会でも通じる。
塩については、伝統的社会では自然からの摂取しかしない。WEIRD社会ではテーブルの上に塩がおいてあるため好きなだけかけて食べてしまう。これが高血圧につながり生活習慣病になる。糖分も同様である。
本書の読者のほとんどはWEIRD社会のメンバーであり、人類の多様性からみればほんの一部にしか過ぎない。その一部の人達が世界の多くの社会を占めていることは、生産性が高く、栽培しやすい植物や動物を手に入れ育てられる地域に住んでいる、その御蔭で早くから農業を発展させることができたためである。その結果失ったと思われる伝統的社会の良い点、子育て、高齢者の処遇、紛争解決の知恵、非感染症疾患の回避、これらから現代社会は多くのことを学ぶことができそうである。なぜ人類は発達してきて、このような人種や国家間の差ができているのか、なぜいま紛争が相次いているのか、WEIRD社会の格差はなぜこのように広がってしまったのか、考えてみたい方には読んで見る価値の高い本だと思う。