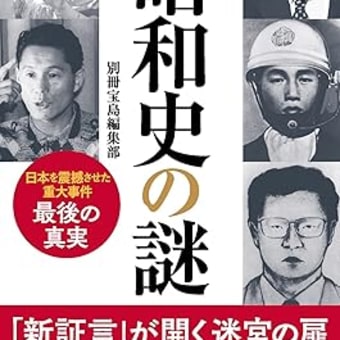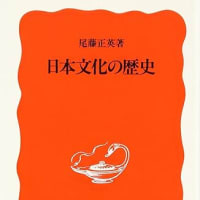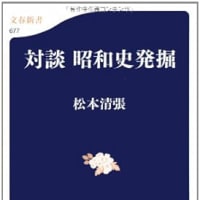サンカは地方によりその呼び方が異なる。関東ではミナオシ、テンバ、中部ではポン、ノアイ、中部から近畿、中国四国ではオゲ、中部近畿中国のサンカ、九州のミツクイドン、ミツクリカンジンなどである。いずれも箕を作る、直す、という職業や「坂の者(さかのもん)」から転訛したものとされている。職業は箕直し以外にも川魚漁や竹細工、棕櫚箒など様々であった。三角がサンカの全国組織がある、と主張している事実はあり得ない、というのが筆者の主張である。
中世歴史学者の網野善彦はその著書「無縁・公界・楽」で山や川に住む漂泊の民がいたことを指摘しているがサンカという言葉は使っていない。民族学者の柳田国男には「イタカおよびサンカ」という著書がある。また柳田による同様の民を解説した「木地屋物語」では「諸国の木地屋(ろくろ師)は数多くの珍しい見聞を持っているに違いないが、袖にボタンがあるような服を着た我々にはそうした話を語ってはくれないだろう。木地屋にも一人くらいは歴史家があってもよさそうなものではないか」と書いている。フィールド研究で木地屋などの人たちを研究するには限界があると諦めたような記述である。
三角の研究に協力したミナオシの民はなぜ手伝ったのか、それは金が欲しかったから、三角は彼らに金を渡して写真(映像)を手に入れたというのが筆者の主張である。サンカは奈良もしくは京都で生まれた言葉であり、そこから各地に広がった。被差別民はそうした人たち「坂の者」の末裔であり、、とも呼ばれ視された人たちであったと筆者はいう。
西日本には多く存在するが東日本、北日本にはあまりない、もしくは意識されていないことは両地域で職業に対する歴史的・文化的違いがあるからなのだろうか。まだまだわからないことが多い分野である。
サンカの真実 三角寛の虚構 (文春新書)