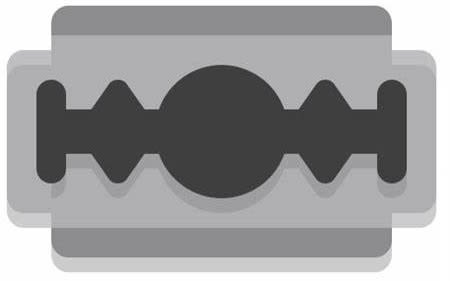ロックやJ-POP、映画やSFに明け暮れていると思われがちな管理人ですが、実はオジサンはオジサンらしく、時代小説が(も)大好きなのです。司馬遼太郎や山田風太郎はかなり読んでいると思いますし、山本周五郎、藤沢周平あたりも結構。池波正太郎の「剣客商売」シリーズは全巻読破。ちょっと変わったところでは峰隆一郎の「人斬り弥介」シリーズは(多分)全巻読破。有名作家で一番「読んでない」のは柴田練三郎ですかね。あ、「眠狂四郎無頼控」はある程度読みましたが。SF、時代物両方を扱う豊田有恒なんかもいいですね。
峰隆一郎という人は荒唐無稽でいてなぜか現実的というか、理論的なところがある人で、刃と刃がぶつかれば名刀といえども刃こぼれする、血糊の所為でそう何人も切れるものではない、骨と骨の間を薙げば胴体だって両断できるなど、日本刀について色々勉強させていただきました。
管理人、決してアブナイ人間ではありませんが、刃物は大好き。アーミーナイフや切り出し、肥後の守など持っています。便利なのでカッターナイフはよく使いますが、あれはあくまで道具。刃物ではありません。一度だけ、ただ一度だけ、真剣を手にした事があります。親戚のおじさんがどういう伝で手に入れたか、美術刀ではなく、また刃引きもしていない、まさに本物。中学校の頃でしたので、その圧倒的質感と、美しさを通り越したまがまがしさに感銘(ショック?)を受けたのを今でもはっきり覚えています。おっかなびっくり持たせてもらいましたが、あれは重い。とても片手で振り回せる代物ではありませんでした。この刃物好きがどうも時代物、特に剣豪もの好きへと繋がっているようです。
 さて、新鋭作家の荒山徹氏の「柳生薔薇(そうび)剣」、最近時代物は読んでいなかったので、久しぶりに手にしました。本の帯には「司馬遼太郎の透徹した歴史観と山田風太郎の奇想天外な構成力、さらに柴田練三郎の波乱万丈の物語展開を受け継ぐ時代小説作家」とありますが、そこまで買いかぶるのはいかがか‥‥良いところ取りという感じが否めません。その分「深み」に欠けるような。
さて、新鋭作家の荒山徹氏の「柳生薔薇(そうび)剣」、最近時代物は読んでいなかったので、久しぶりに手にしました。本の帯には「司馬遼太郎の透徹した歴史観と山田風太郎の奇想天外な構成力、さらに柴田練三郎の波乱万丈の物語展開を受け継ぐ時代小説作家」とありますが、そこまで買いかぶるのはいかがか‥‥良いところ取りという感じが否めません。その分「深み」に欠けるような。
ま、評論家然としたゴタクはさておき、文句なしに楽しめる一冊。主人公の一人である美貌の女性うねが中年の女性だという設定も面白い。朝鮮人である彼女が祖国を捨て日本人として生きる覚悟をする。彼女を強制帰国させようとする日本と地朝鮮。別段重要人物というわけでもなく、多分になりゆきと双方の国の意地のぶつかり合い。追っ手の手を逃れるため駆け込み寺として有名な東慶寺に逃げ込もうとする。自害するとかいう手段をとらず、あくまで権威に逆らっていく。
「案ずるな、うね。わしはもう充分当家のため奉公いたした。いや、先代さまの御他界で奉公は終わっていたのやも知れぬ。武士を辞めることに悔いはない。されど、お前の夫たるは、フフ、死ぬまで罷(や)めること相叶わぬわ」
「忠に非ず、孝に非ず、和 - 夫婦の和によって、わしはそなたの戦に助勢つかまつるぞ」
涙腺ほとばしるシーン。結局夫である主馬と3人の息子は彼女を東慶寺に送り込むため、深い愛情と、愛するもののために死ぬ、その歓喜のうちに敵と戦い死んで行く。
東慶寺に逃げ込んだうねを護るのが柳生但馬守の長女、矩香(のりか)。女剣士というだけで充分カッコイイのですが、やたら強い。多勢と戦っても刃と刃の触れる音さえさせず、案山子を切るように敵を倒す。ウン、確かに峰隆一郎が書いている通り、刃こぼれすれするからなあ。切り込んできた敵の刀を片手でもぎ取り、返す手で峰撃ちするシーンがありますが、果たして剣豪といえども女性の片手で可能なのか?そこで実際に真剣を手にした感覚を思い出し、あれほどの重量のある日本刀、振り下ろした刀を止めるには相当の力が必要。刀の慣性と押し戻そうとする力がつりあい、一瞬の力の空白というものが出来るはず、その一瞬につけ入れば、可能かも、なんて考えたりしますね。
これに加え姉の前ではまったく形無し、シスコンぶり爆発の柳生十兵衛とか、人物設定はなかなかのものですが、ネタ割れになるので詳しくは申し上げないにせよ、物語の後半は飛ばしすぎ、終わり方も何かあっけない。管理人とすれば前半の主馬とうね、息子達の夫婦愛、家族愛と矩香のカッコよさが印象に残った作品。出世作の「高麗秘帖」もそのうち読んでみようと思います。
峰隆一郎という人は荒唐無稽でいてなぜか現実的というか、理論的なところがある人で、刃と刃がぶつかれば名刀といえども刃こぼれする、血糊の所為でそう何人も切れるものではない、骨と骨の間を薙げば胴体だって両断できるなど、日本刀について色々勉強させていただきました。
管理人、決してアブナイ人間ではありませんが、刃物は大好き。アーミーナイフや切り出し、肥後の守など持っています。便利なのでカッターナイフはよく使いますが、あれはあくまで道具。刃物ではありません。一度だけ、ただ一度だけ、真剣を手にした事があります。親戚のおじさんがどういう伝で手に入れたか、美術刀ではなく、また刃引きもしていない、まさに本物。中学校の頃でしたので、その圧倒的質感と、美しさを通り越したまがまがしさに感銘(ショック?)を受けたのを今でもはっきり覚えています。おっかなびっくり持たせてもらいましたが、あれは重い。とても片手で振り回せる代物ではありませんでした。この刃物好きがどうも時代物、特に剣豪もの好きへと繋がっているようです。
 さて、新鋭作家の荒山徹氏の「柳生薔薇(そうび)剣」、最近時代物は読んでいなかったので、久しぶりに手にしました。本の帯には「司馬遼太郎の透徹した歴史観と山田風太郎の奇想天外な構成力、さらに柴田練三郎の波乱万丈の物語展開を受け継ぐ時代小説作家」とありますが、そこまで買いかぶるのはいかがか‥‥良いところ取りという感じが否めません。その分「深み」に欠けるような。
さて、新鋭作家の荒山徹氏の「柳生薔薇(そうび)剣」、最近時代物は読んでいなかったので、久しぶりに手にしました。本の帯には「司馬遼太郎の透徹した歴史観と山田風太郎の奇想天外な構成力、さらに柴田練三郎の波乱万丈の物語展開を受け継ぐ時代小説作家」とありますが、そこまで買いかぶるのはいかがか‥‥良いところ取りという感じが否めません。その分「深み」に欠けるような。 ま、評論家然としたゴタクはさておき、文句なしに楽しめる一冊。主人公の一人である美貌の女性うねが中年の女性だという設定も面白い。朝鮮人である彼女が祖国を捨て日本人として生きる覚悟をする。彼女を強制帰国させようとする日本と地朝鮮。別段重要人物というわけでもなく、多分になりゆきと双方の国の意地のぶつかり合い。追っ手の手を逃れるため駆け込み寺として有名な東慶寺に逃げ込もうとする。自害するとかいう手段をとらず、あくまで権威に逆らっていく。
「案ずるな、うね。わしはもう充分当家のため奉公いたした。いや、先代さまの御他界で奉公は終わっていたのやも知れぬ。武士を辞めることに悔いはない。されど、お前の夫たるは、フフ、死ぬまで罷(や)めること相叶わぬわ」
「忠に非ず、孝に非ず、和 - 夫婦の和によって、わしはそなたの戦に助勢つかまつるぞ」
涙腺ほとばしるシーン。結局夫である主馬と3人の息子は彼女を東慶寺に送り込むため、深い愛情と、愛するもののために死ぬ、その歓喜のうちに敵と戦い死んで行く。
東慶寺に逃げ込んだうねを護るのが柳生但馬守の長女、矩香(のりか)。女剣士というだけで充分カッコイイのですが、やたら強い。多勢と戦っても刃と刃の触れる音さえさせず、案山子を切るように敵を倒す。ウン、確かに峰隆一郎が書いている通り、刃こぼれすれするからなあ。切り込んできた敵の刀を片手でもぎ取り、返す手で峰撃ちするシーンがありますが、果たして剣豪といえども女性の片手で可能なのか?そこで実際に真剣を手にした感覚を思い出し、あれほどの重量のある日本刀、振り下ろした刀を止めるには相当の力が必要。刀の慣性と押し戻そうとする力がつりあい、一瞬の力の空白というものが出来るはず、その一瞬につけ入れば、可能かも、なんて考えたりしますね。
これに加え姉の前ではまったく形無し、シスコンぶり爆発の柳生十兵衛とか、人物設定はなかなかのものですが、ネタ割れになるので詳しくは申し上げないにせよ、物語の後半は飛ばしすぎ、終わり方も何かあっけない。管理人とすれば前半の主馬とうね、息子達の夫婦愛、家族愛と矩香のカッコよさが印象に残った作品。出世作の「高麗秘帖」もそのうち読んでみようと思います。