
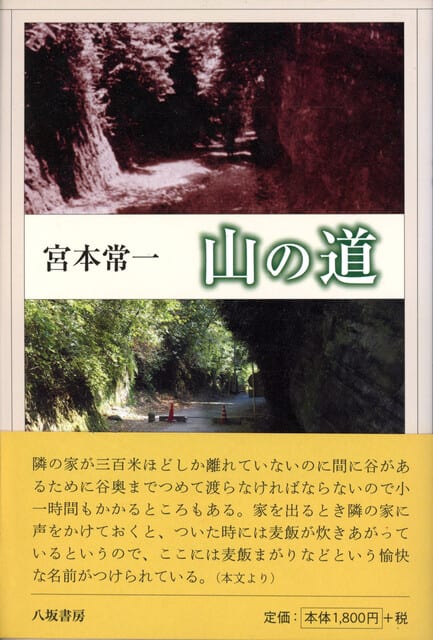
いずれにしても山中には里人には知れないきびしい生活があり、また殺戮がおこなわれていたことはここにあげた例ばかりでなく、実はもっともっと多かったのである。そして山中の居住は決して夢多く平和なものではなかった。
にもかかわらず、里人は山の彼方に幸福の世界を夢みていた。」

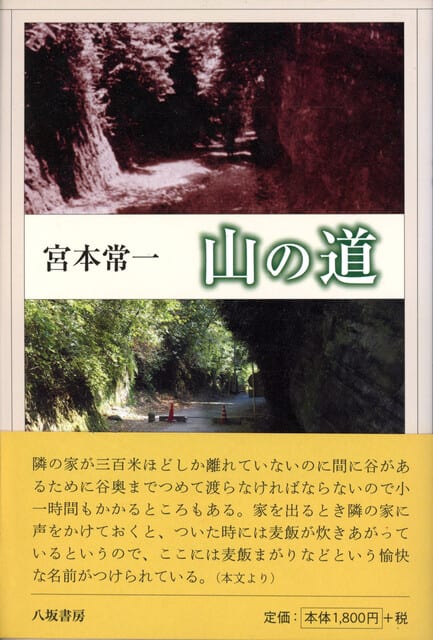

8日朝、八幡山展望台からの富士山

安倍奥(遠景)も白くなってきた

今日向かう松風閣は遠景(高草山)右端の小さな突起・虚空蔵山の場所にある
2/8、昨年暮れに脊髄腫瘍で亡くなった友人Suyの四十九日法要を宗傳寺で、その後、お膳上げを焼津・松風閣で行った。
昨年秋に母親を亡くしたSyoに身寄りはなく、友人葬とでもいったところ。地元在住の友人4人(とその家族)、東京から足を運んできた大学時代の友人、ShyとTumとは40年ぶり近くの再会となろうか。こうして旧交を温められたのも、まめな付き合いをしていたSyoのおかげだ。それぞれが彼の思い出を語り、彼の好きだった芸をして小さいながら良い供養の宴だった。

松風閣窓越しの富士山

Ryoも一緒に供養してくれた

9日帰宅後、伊太まで散歩、梅がチラホラと咲き始めた

伊太八幡神社
新年も10日になって間の抜けたことだが、本年も穏やかな年でありますように。
仕事納めの28日になって、15年程も使っていたPCが逝ってしまった。暮れの仕事が片付くまで持ったのは彼なりの意地だったのだろうか。後生大事に使い続けたのは仕事に使うソフトのバージョンが古いからで、今は何もかもサブスクリプションの方式になってしまって必要もない機能に無駄に金がかかってしまう。買取済みのソフトを活かせる方法をネットで検索したり、帰省中の息子に尋ねたりしたが、そんな都合の良いことはもはや無かった。あと何年仕事ができるか分からないが、取り敢えず年明けの仕事再開に間に合わせるために、中古(整備品)の新しいPCを手配し、正月中かけてソフトのインストール、周辺機器の接続、データの移動などに追われ、何とか再構築することができた。で、ブログも再開できる運びとなった。
温暖な当地では風もなく穏やかな正月を迎えることができた。

波田の立石稲荷に参詣し、いつものように八幡山のパノラマ台に上がった。

初富士と志太平野・駿河湾の向こうに伊豆半島

初山行は5日、精進湖北の三方分山へ。前夜のものかうっすらと白いものが。

精進諏訪神社の境内には国天然記念物の大杉(樹齢1200年、目通り10.2m、高さ40m)

旧中道往還を登り切った阿難坂(女坂)峠の石仏

パノラマ台からの富士山

精進湖


12/15、粟ヶ岳の後の忘年会で新型コロナに感染、熱は2、3日で平熱に戻ったが胃腸の不調が今も続く。忘年会参加者の約半分が感染というクラスター状態でやれやれのことだ。幸い家族への感染は無し。
12/24、旧い友人(高校の同級生)のSが亡くなった。末期ガンで年は越せないと告げられていたが、前週には蓮華寺の畔に連れ出してもらい、そばを啜って、ビールを舐めて、好きな煙草も吸った。前年、年老いた母親を亡くした後は彼に身内はなく、数人の友人だけでの静かな見送りとなった。寂しさが押し寄せる。

12/28、末っ子が十山のウィスキー「Flora 2024」を届けてくれる。噂には聞いていた南アルプスの貴重な酒は職場忘年会で引き当てた由。旨い!

粟ヶ岳山頂からの富士山
2024年最後の会山行は、我がランドマーク「粟ヶ岳」へ東側の大鉄・日切駅から目指した。馴染みの粟ヶ岳へは、東山いっぷく処、西側の倉真温泉、そして本年8月には南側の西山から登っているが、日切からは初めてのこと。昔々に(中学の遠足?)金谷から登ったような記憶が微かにあるが、ここからだったのかは定かでない。

志戸呂の坂途中からの富士山

台地の上の行人塚

近づいてくる粟ヶ岳の「茶」文字
志戸呂の坂を登って台地の上に出ると行人塚が建つ。1603年(慶長年間)、大井川の氾濫で島田宿が消失し山側の元島田(島田市医療センター南側))に移転し、島田市大鳥、大井川渡河、牛尾山、島田市(金谷町)志戸呂谷北という中世のルートが復活、1614年まで約10年間、仮の東海道とされた。ここはその一部で碑には「正徳二年巳八月二日 帰真 満願院全行得道上座霊位」と彫られている。数10メートル先には摩滅が進み判読困難となった石の道標があって、古くからの街道であったことが窺われる。直進すると小鮒川・日坂へと下っていく慶長の仮東海道のルートとなる。今回は右折し安田(あんだ)へと向かう。進むに従い粟ヶ岳の「茶」の字が随分と大きくなり、茶畑を前景に存在感のある山容が望まれる。途中には国営農業水利事業(平成9年度完了)の大きな調整水槽がいくつもあって、大井川の川口取水工から水路橋を経て大代の牧之原揚水機場から揚げられた水が溜められている。


安田の大ジイ
粟ヶ岳北東中腹の集落・安田(あんだ)には、県指定天然記念物のスダジイの巨樹があって神仏をその懐に抱えて悠然と立っている。樹高は27メートルとそれほど高くはないが、枝張りは東西26メートル、南北23メートルにも及び、八俣の大蛇(やまたのおろち)のように八方の天空に枝を張りくねらせ、一樹なのに一つの森のような風貌を持っている。ところで[安田/あんだ]という地名だが、[あだ]とルビが振られていることもある。『民俗地名語彙事典』(ちくま学芸文庫)によれば「アダ ①オク(奥)に対する里がアダ ②日あたりのよい土地」とされている。金谷安田の場所を見てみると、粟ヶ岳北東に位置し、東側が開けた菊川上流部の小さな谷であるから、「①オク(粟ヶ岳)に対する里 ②日あたりのよい土地」の語意を充たしていると思われる。

名残の紅葉
安田から奥貝戸を経て東山からのハイキングコースに合流すると、ひと登りで山頂の阿波々神社に到着、本年の山登りの無事を感謝し参拝後、眺望の効くかっぽしテラスで暫し富士山や伊豆半島(やや霞みがちであったが)、そして眼下の大井川とわが町の景観を楽しんだ。山頂には「かっぽし(刈干し)」で作られた来年の干支・蛇が飾られ、多くのハイカーで賑わっていた。

粟ヶ岳山頂の大蛇

大代のジャンボ干支
下山は岳山との鞍部から小尾根を大代に下って、山頂のそれに比べてジャンボな二匹の大蛇が飾られた「大代ジャンボ干支」会場に、予定時刻の11時半に到着した。こちらも大賑わいであったが、大蛇をバックに参加者全員で集合写真を撮って、本年最後の定例山行を終了した。その後は迎えのマイクロバスに乗車し川根温泉へ移動、忘年会を楽しんだ。