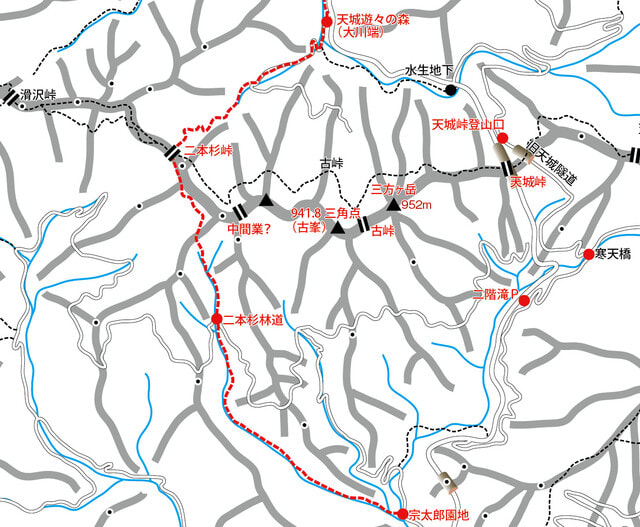芋穴所[いもあなど]のマルカシ
11月10日、所属会の「おはようハイキング」は、藤枝・高根山へ出かける。生憎の天気と思いきや、昼前の解散時までもってくれて、山頂ではそこそこの展望も得られた。午前中の一時の山歩きが心地よい。

高根山頂からの眺望
高根山は東海自然歩道の本コースとなっているが、中学の時、同級生二人とここから家山までを歩いたのが、私が自分自身で計画した山歩きの最初だった。身成川の谷に出た後の8km余の林道歩きが長く疲れ、家山駅に着く頃はすっかり日暮れていたと覚えている。東海自然歩道の全区間完成が1974年、東京高尾の「明治の森」から大阪箕面の「明治の森」までを結び、つまりは「明治百年」の昂揚の一環だった側面もあるだろう。それから50年が経って「昭和百年」はもう間近のこととなった。

高根山中腹には、1188年、加賀白山より勧請された高根白山神社が鎮座する。
* * *
【2019年7月記】

洋上から望む加賀白山
誰がいつ決めたのかは知らないが、「日本三名山」は富士山、立山、白山を指す。ところが、これが「四名山」となると白山が抜けて木曽御嶽山、伯耆大山が加わるというのだからややこしい。いずれが“名山”であるかはさておいて、この五山の共通点は、いずれも古くから山岳信仰の対象の霊山ということだ。そうした霊山は、里からはっきりと見上げられる独立峰であることが多い。加賀、美濃、越前の三国境に位置する白山も、平野部や日本海からその姿を仰ぎ見ることができる。山頂部は一年の半分以上を雪で覆われ、まさに〝白き山〟の姿となる白山への信仰がいつ頃始まったのかは定かでないが、農のための水の源の神として、また海上交通の目印として航海と漁労の守護神でもあったのだろう。白山信仰の広がりを示すものに全国の白山神社の分布がある。大正年間の神社明細帳によれば42都府県にまたがって2716社があるとされ、白山の隣接地を中心にして東国へと広がっている。また、加賀白山は奈良、京都など古代の政治や仏教界の中心地域に近く、その存在は「越のしらやま」として早くから知られていたことから、単なる土着的な信仰対象ではなく、全国的規模(あるいは東アジア的な)の信仰対象となっていったと思われる。

山岳信仰の発展とともに麓から眺め拝むだけではなく、御山に登り修行する人々が出てくるようになる。白山主峰群の一角、大汝峰[おおなんじみね](2684m)は、立山の大汝山と同様に阿弥陀如来が姿を変えて現れた、大己貴[おおなむち]権現(大国主)を祀る「おおなむち―おおなんじ」峰である。仏教の阿弥陀如来が出雲系の大己貴権現に姿を変えて出現するというのは、日本の神道と朝鮮渡来の仏教を習合させるための本地垂迹説で、養老元年(717)に泰澄[たいちょう]大師が白山に最初に登り開山したという伝説は、土着の信仰が中央仏教界の流行に組み込まれた時点と考えられる。白山そのものを祀る白山比咩[しらやまひめ]神社の存在から、昔は「はくさん」ではなく「しらやま」がその名であり、常に白雪をかぶった美しい山の姿から、白山神=白山姫が作り出されたのだろう。また、白山には朝鮮半島からの新羅[しらぎ]明神信仰(白の信仰)が入り込んでいる。古代の陶器窯跡と各地域の白山神社の位置が重なることは、白山信仰が朝鮮渡来の技術者と何らかの関わりがあると考えられる。日本海文化における海上交通路の目標としての白き山の価値も高かったはずだ。

全国に広がった白山信仰の痕跡は、我が地でも見ることができる。上図はグーグルマップで検索した島田近隣の白山神社の分布で、意外と多くの社があることが分かる(図には載らないが、藤枝高根山も白山神社)。この内、一番の馴染みは何と言っても相賀にある高山白山神社だろう。『島田風土記 ふるさと大長伊久美』によれば「白山神社は、1191(建久二)年平安末期、石田氏が加賀国から勧請し、高山(標高566.7m)の中腹に高山権現社として永く奉祀してきたとされる。そして室町時代、応永年間(1394~1428)に加賀国(石川県)白山神社社僧が当山に移り住み、以後白山神(加賀白山比咩神社)を併せ祀り高山白山権現社と改称したと言伝えられている。」(2010年7月の当会のグループ山行「白山」には、現宮司のIK氏(kazさん夫君*故人)もゲストメンバーとして参加している。)また、浜岡、菊川、掛川などでは、塩の道(秋葉街道)沿いに白山神社が散在するのも、古来から続く北陸地方との交流が窺えて興味深い。(以下略)
(『やまびこ』No.267「白山信仰と越前禅定道」より)