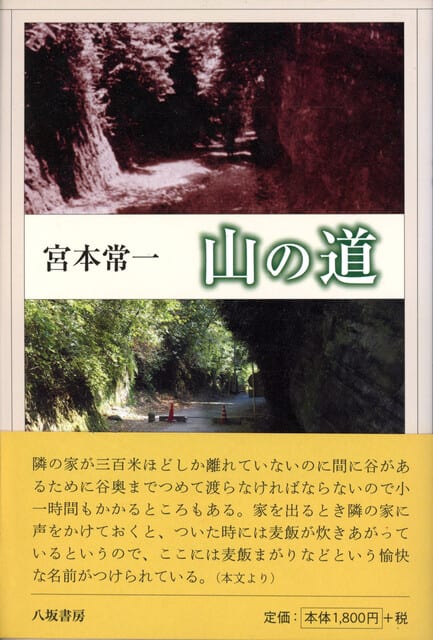会の仲間が奥三河の夏焼城ヶ山(豊田市)に行ってきた。
夏焼城ケ山
夏焼城ケ山2025年4月29日参加者 4名■コース中央公園6:35=大井平公園8:40-9:03…大井...
島田ハイキングⅣ
報告に「夏焼という名前が気にかかり」とあるが、夏作の焼畑地に由来するのは確かだろう。
夏焼村の沿革 | 地名の由来 | 株式会社葵エンジニアリング
地勢 城ケ山の北西麓に位置する。地名は焼畑にちなむ。地名の変遷 江戸期~明治22年:三河国加茂郡夏焼村。江戸前期からは設楽に編入。明治11年北設楽郡に所属。同22年稲橋...
株式会社葵エンジニアリング
因みに地理院地図で「夏焼」を地名検索すると青森、秋田、静岡、愛知、岐阜、富山、徳島、山口の各県でヒットした。この内、静岡(水窪・飯田線大嵐駅の南)から富山(南砺市・五箇山の北)の中部4県での分布を見ると、民俗学でいう「中のボカシの地帯」に沿っていて興味深いところだ。
青旗の場所に「夏焼」地名
豊田市の夏焼は南朝所縁の尹良親王伝承の場所でもあり、木地師系の集落だったのだろう。伊那根羽村との国境の峠(旧三州街道)となる杣路峠にも興味が湧いた。
ところで「夏焼」地名で一番有名なのは静岡水窪・佐久間湖畔の廃村のようだ。
夏焼集落の歴史 - 集落の成り立ちと暮らしについて解説 - historica
今回は夏焼集落の歴史について解説していく。夏焼集落は静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家の山間に位置する廃村である。廃村になった時期は2015年と最近までは居住者がいたこ...
historica
この水窪の夏焼開郷に係わる天龍村坂部の熊谷家については、宮本常一が『山の道』の中で触れている。
「天竜川中流、長野県の南端に坂部という所がある。飯田線の車窓から天竜川を距てた急斜面の上日本のちょっぴり集落が見える。ここが坂部である。坂部は今から六〇〇年あまり前に熊谷直実の子孫の住みついたところである。この家は『熊谷家伝記』という比較的確実な記録を残しているので、いわゆる落人伝説を持つ家がどのように山中に住みついたかを知るのに大変教えられるところがある。」
「多くの平家谷の伝説を持つ村々も平野地方で戦に敗れた人たちが熊谷家のように山中深く入り開墾定住し、同類の者と婚姻圏を形成することによりそれ以外の村々とは比較的接触が少ないままに今日にいたったものもあり、また木地屋や狩猟などを主業としつつ、一般農民とはやや違った生活をしていたために、その人たちとは出自を異にする者と見られて来、山人もまた蔑視を避けるためその出自を誇示しようとする意図を持っており、それをまた裏付けようとする遊行聖たちが居て、これらの伝承が、まことしやかなものになっていったのではないかと思う。
いずれにしても山中には里人には知れないきびしい生活があり、また殺戮がおこなわれていたことはここにあげた例ばかりでなく、実はもっともっと多かったのである。そして山中の居住は決して夢多く平和なものではなかった。
にもかかわらず、里人は山の彼方に幸福の世界を夢みていた。」