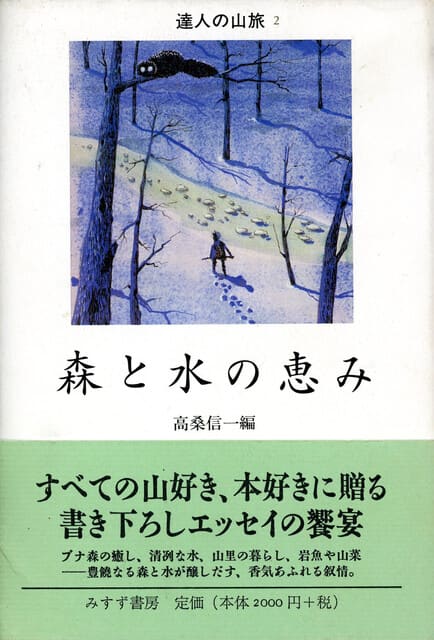金谷牧の原鳥瞰図を眺める
コロナ禍の最中にあって、近隣歩きのネタを求めた『古地図で楽しむ駿河・遠江』(加藤理文編著・2018年 風媒社)の冒頭に、吉田初三郎の鳥瞰図がいくつか掲げられていた。吉田初三郎という鳥瞰図絵師の名を聞いたのは、『やまびこ』245号(2017年9月)「地図は物語る」と題したS・Mさんの巻頭エッセイで、その時、大いに興味を覚えた。
――描かれている情報は、その場所に人を誘う目的でデェフォルメされており、ある物語を伝えてくれている感さえある。――
全ての任意の地点が、どの方角からも同様に同等に、すなわち等距離に描かれる地形図とは全く逆に、鳥瞰図には主観的な視点(目的)が存在するから、図の中心にはその視線の先、すなわち目的の核心が描かれることになる。そこから眺められるストーリー性が面白いのである。

金谷牧の原鳥瞰図 *詳細は下記WEB「吉田初三郎式鳥瞰図データベース」より閲覧可能
掲図の主題となっている牧ノ原茶園といえば、中條景昭など旧徳川家臣団や大井川川越人足による開拓が知られているが、全国ブランドの名を得るには、さらに昭和までの年月を要したことが編著者の加藤氏の解説から窺われる。この鳥瞰図作成の目的は、そうした牧ノ原茶のPRであることは明白だが、実際の依頼主はどうも製茶機メーカーの川崎鐵工所のようで、絵図の左右の中心に八木式製茶機工場と川崎製茶研究園が大きく描かれ、かつ自社関連施設は赤の名称標示で強調されている。牧ノ原茶のPRでは、やはり吉田初三郎の「牧野原茶園を中心とせる静岡県鳥瞰図」(1927年)があって、こちらは静岡県茶業組合の制作依頼によるものだ。
牧ノ原茶園の背景として富士山が描かれるのは当然として、その左、大井川の上流に[南アルプス連峰]とあるのは嬉しい。西に目をやれば[夜泣石]、[小夜ノ中山]、[久延寺]とあり、ここは外せない名所だったのだろうか。旧国一の[大井川橋]を渡った先に[島田]がある。このザックリ感はさすがに少し寂しい気がするが、[藤枝][焼津]のまるで農村、漁村感よりはましか。また中心があれば辺境もあるわけで、右上には[東京]の先に[青森][函館]、さらに遠く[桑港](サンフランシスコ)まであるのは、そこが牧ノ原茶の輸出先であったゆえであろうか? やはり左上には[大阪]の先に[門司]さらに[釜山]まで記される拡がり方に時代性が感じられる。
左側中程上の「大」の字には[淡々山](あわわやま?)とあり「粟ヶ岳」(あわんたけ)だと思い至るが、おや?「茶」の字ではないではないか。粟ヶ岳の「茶」の字の由来は、掛川観光協会のHP『掛川観光情報』によると
粟ヶ岳山腹の巨大な「茶」の字は、昭和7年頃、東山のお茶のPRのために、茶業組合や村民が力を合わせ、粟ヶ岳の急斜面に松の樹を植え付けたのが始まりだそう。茶の字の形を決めるために、白い紙を付けた縄を持って並び、それを向いの山から遠望して、手旗で合図して調整を繰り返したとのこと。その後、初代の松の木がマツクイムシの害にあい、檜に植え替えられたそうですが、今でも定期的にメンテナンスを行い、美しく雄大な茶文字が保たれています。
とのこと。この絵図の制作が1931年(昭和6)で、「茶」の字が完成した昭和7年の一年前であることから、あるいは吉田は植栽途中のものを見て「大文字」と勘違いしたのだろうか。でも鳥瞰図制作の目的が牧ノ原茶(同時に川崎の製茶機)の振興なのだから、「あれは茶の字になるんですよ」くらいの話が川崎の人から出なかったのかなぁと不思議に思った。
 金谷・元「金河座」
金谷・元「金河座」
ところで、私の亡母は金谷田町の八百屋の生まれで、小さい頃、大衆芝居好きの母の祖母に連れられ芝居見物に通ったことをよく話していたが、それが[八木式製茶機工場]の南に描かれる[金河座]だったのだろう。金谷の街並の代表的な建物として絵図に載るのだから、当時の金谷の文化の殿堂といった存在だったのかも知れない。絵図を眺めていると、金谷という町はこじんまりとしているが、街並と寺社さらに茶園とその工場がうまく配置された、一寸お洒落感のある町に見えてくる。かつての母の話の端々には、そんな金谷自慢の雰囲気があったことを思い出した。いずれにせよ、お茶が地域発展の大きな力となっていた頃の話である。

(2022年2月記)
*2024年7月7日まで府中市美術館にて「Beautiful Japan 吉田初三郎の世界」展を開催中