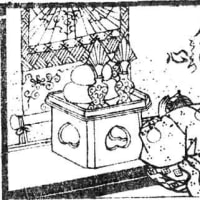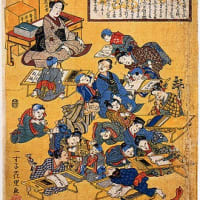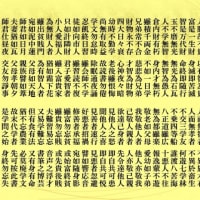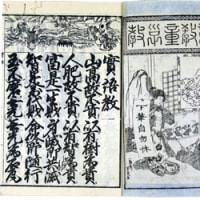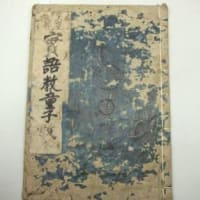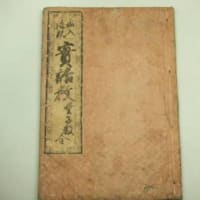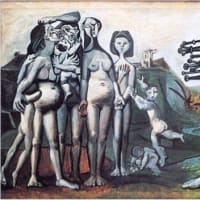殉国七士
「殉国七士」と尊称されている人々は、先の東京裁判で、日本を背負って絞首刑となった七人であります。
土肥原賢二

松井石根

東条英機

武藤章

板垣征四郎

広田弘毅

木村兵太郎

当時の国際法を無視し、大量殺戮兵器を用い、無差別虐殺を行うことによって血塗られた勝利を、大東亜戦争において収めたアメリカを中心とした十一ヵ国による日本処分が東京裁判です。
戦争犯罪によって得た自らの勝利に基づいて、敗者を戦争犯罪者として裁くという、まさしくそれは勝てば官軍と言う言葉が当てはまります。
人間としての誇りを一片なりとも持っていれば行うことができないような裁判によって七名は裁かれました。
東京裁判によって犯罪者とされ昭和二三年十二月二三日未明に処刑された七人は火葬に付されました。
*十二月二三日は今上天皇ご出生日です。
彼らの遺骨が、GHQの目を掠めて採取された状況は、塩田道夫氏が詳しく書かれているので引用します。
全部の遺体が焼けたのは、一時間半ほど経ってからだった。窯の扉が火夫によって開けられ、長い鉄のカキ棒で白骨が取り出されると、火葬場長の飛田は、七人の遺骨の一部を七つの骨壷に入れて他の場所に隠した。
ところが、この隠した骨壷は、誰かがA級戦犯を憐れんだのか、線香を供えたために、香り煙のために監視の米兵に見つかってしまった。このため骨壷は米兵の手もとへ移った。米兵は、鉄製の鉢の中へ遺骨を入れると、鉄棒のような物で上から突いて、骨を細かく砕きはじめた。それはまさに死者にムチを振る惨い行為であった。
米軍がA級戦犯の骨を砕いて、空から東京湾へ撒くという噂があった。それは日本人が英雄崇拝の対象になるのを恐れて海にばら撒くというのである。遺骨を隠すことに失敗した飛田は、内心穏やかでないあせりがあった。
骨を砕き終えた米兵は、黒い箱を七つ出して、砕いた骨を入れた。そして箱の上に1から7までの番号を書き入れた。この遺骨の入った箱は、A級戦犯の遺体を巣鴨から運んでんきた米兵が持ち去った。台の上に灰と一緒に残っていた小さな骨は、米兵の監視つきで火葬場にある共同骨捨て場に捨てるように命じられたのである。
A級戦犯の遺骨を奪う計画は。小磯国昭大将の弁護人だった三文字正平によって進められていた。三文字弁護士は、米人弁護士のブルウェットに相談し、彼を通じてGHQに処刑されたA級戦犯の遺骨を遺族たちに渡せるように嘆願していたのである。ところが、マ元帥は一向に首を振らなかったため実現はしなかった。
そこで三文字弁護士は、巣鴨プリズンにおいて処刑されたA級戦犯が、久保山で火葬されることを探りあてた。三文字は火葬場のすぐ上にある興禅寺を訪ねて住職の市川伊雄と会った。市川住職は東京裁判にも傍聴に行き、裁判の不公平さに怒りを抱く一人であった。三文字弁護士が市川住職に協力を求める説明にも熱が入った。
このA級戦犯の遺骨が米軍の手から戻されないと、国民が不公平だった東京裁判の結果を認めたことになる。彼らの命令で戦場に駆り出された三百万の英霊さえ、辱めを受けて浮かばれなくなる。市川住職も日本人として耐えがたいことだったので、三文字に協力することを引き受けた。市川住職は、火葬場長の飛田を三文字に紹介したのである。
久保山火葬場の内部に働く人の協力で、はじめはA級戦犯の遺骨を分けて隠すことができたのが、米兵の監視に見つかり失敗した。今度は、火葬場の共同骨捨て場に捨てられているA級戦犯の骨を持ち出さなくてはならない。次の新しい骨が捨てられるまでは、一応、少しは他の骨も混ざってしまったとはいえ、七人の遺骨は残っている。
これを盗み出すのは十二月二十五日の夜と決めた。米軍の監視がクリスマスで気がゆるんでいる隙に実行しようというのである。暗くなり、頃合を見計らって、三文字弁護士と市川住職は勝手知ったる飛田火葬場長の案内で火葬場の骨捨て場に忍び込んだ。
三人は米軍の監視に見つからぬように、闇夜の中で外套を頭からかぶり、身をかがめながら作業を始めた。三人は暗がりの中で音を立てないように、根気よく手探りで遺骨を探し集めた。七人の遺骨は全体の一部でありながら、大きな骨壷に一杯分を集めることができた。
火葬場から盗み取ってきた遺骨は、湿気をとるために再度焼かれた。遺骨のことが世間に漏れては米軍の咎めを受けることになる。そこで三文字の甥で、上海の戦線で戦死した三文字正輔の名前を骨壷に書いた。これを興禅寺に預けて供養することになったのが、A級戦犯として処刑された七名の秘められた供養であった。
以上、「天皇と東条英機の苦悩」(塩田道夫著)より
このようにして集められた遺骨は、翌昭和二四年五月にはまだGHQの勢力下に日本があったため、伊豆山中の興亜観音に隠されるように葬られました。
しかし昭和三三年に入ると、他の場所に移してお祀りしようという話が持ち上がり、昭和三五年八月十八日に三ヶ根山(愛知県幡豆郡幡豆町)の山頂付近に移されることになりました。
三ヶ根山には殉国七士廟が設けられ、その中の殉国七士の墓に遺骨が分骨されて安置され、今に至ります。



最後に七名の辞世の句、詩を紹介します
土肥原賢二
「わが事もすべて了りぬいざさらば ここらでさらばいざ左様なら」
「天かけりのぼりゆくらん魂は 君が代千代に護るならべし」
「踏み出せば狭きも広く変わるなり 二河白道もかくやありなん」
松井石根
「天地も人もうらみずひとすじに 無畏を念じて安らけく逝く」
「いきにえに尽くる命は惜かれど 国に捧げて残りし身なればく」
「世の人にのこさばやと思ふ言の葉は 自他平等に誠の心」
東条英機
「我ゆくもまたこの土地にかへり来ん 国に報ゆることの足らねば」
「さらばなり苔の下にてわれ待たん 大和島根に花薫るとき」
「散る花も落つる木の実も心なき さそうはただに嵐のみかは」
「今ははや心にかかる雲もなし 心豊かに西へぞ急ぐ」
武藤章
「霜の夜を 思い切ったる門出かな」
「散る紅葉 吹かるるままの行方哉」
板垣征四郎
「ポツダムの宣のまにまにとこしえの 平和のために命捧ぐる」
「とこしえの平和のために身を捨てて 糞土を黄金にかえる嬉しさ」
「大神の御魂の前にひれふして ひたすら深き罪を乞うなり」
「今はただ妙法蓮華と唱えつつ 鷲の峰へといさみたつなり」
「さすらいの身の浮き雲も散りはてて 真如の月を仰ぐうれしさ」
「懐かしき唐国人よ今もなほ 東亜のほかに東亜あるべき」
広田弘毅
広田弘毅さんはは辞世の句を断ったそうです。
広田弘毅さんの名句を紹介します
風車風の吹くまで昼寝かな
(意味)
夏、青畳の上に大の字になる昼寝は実に気持ちのいいものだ。風車が静かに回り、風鈴がチリン、チリンと小さく鳴ったりするのを聞きながらする昼寝は、昼寝の醍醐味である。だが残念ながら風が吹かず風鈴は鳴らない。風が吹くまで待つこ
とにしょう。
木村兵太郎
「現身はとはの平和の人柱 七たび生まれ国に報いむ」
「平和なる国の弥栄祈るかな 嬉しき便り待たん浄土に」
「うつし世はあとひとときのわれながら 生死を越えし法のみ光り」
「殉国七士」と尊称されている人々は、先の東京裁判で、日本を背負って絞首刑となった七人であります。
土肥原賢二

松井石根

東条英機

武藤章

板垣征四郎

広田弘毅

木村兵太郎

当時の国際法を無視し、大量殺戮兵器を用い、無差別虐殺を行うことによって血塗られた勝利を、大東亜戦争において収めたアメリカを中心とした十一ヵ国による日本処分が東京裁判です。
戦争犯罪によって得た自らの勝利に基づいて、敗者を戦争犯罪者として裁くという、まさしくそれは勝てば官軍と言う言葉が当てはまります。
人間としての誇りを一片なりとも持っていれば行うことができないような裁判によって七名は裁かれました。
東京裁判によって犯罪者とされ昭和二三年十二月二三日未明に処刑された七人は火葬に付されました。
*十二月二三日は今上天皇ご出生日です。
彼らの遺骨が、GHQの目を掠めて採取された状況は、塩田道夫氏が詳しく書かれているので引用します。
全部の遺体が焼けたのは、一時間半ほど経ってからだった。窯の扉が火夫によって開けられ、長い鉄のカキ棒で白骨が取り出されると、火葬場長の飛田は、七人の遺骨の一部を七つの骨壷に入れて他の場所に隠した。
ところが、この隠した骨壷は、誰かがA級戦犯を憐れんだのか、線香を供えたために、香り煙のために監視の米兵に見つかってしまった。このため骨壷は米兵の手もとへ移った。米兵は、鉄製の鉢の中へ遺骨を入れると、鉄棒のような物で上から突いて、骨を細かく砕きはじめた。それはまさに死者にムチを振る惨い行為であった。
米軍がA級戦犯の骨を砕いて、空から東京湾へ撒くという噂があった。それは日本人が英雄崇拝の対象になるのを恐れて海にばら撒くというのである。遺骨を隠すことに失敗した飛田は、内心穏やかでないあせりがあった。
骨を砕き終えた米兵は、黒い箱を七つ出して、砕いた骨を入れた。そして箱の上に1から7までの番号を書き入れた。この遺骨の入った箱は、A級戦犯の遺体を巣鴨から運んでんきた米兵が持ち去った。台の上に灰と一緒に残っていた小さな骨は、米兵の監視つきで火葬場にある共同骨捨て場に捨てるように命じられたのである。
A級戦犯の遺骨を奪う計画は。小磯国昭大将の弁護人だった三文字正平によって進められていた。三文字弁護士は、米人弁護士のブルウェットに相談し、彼を通じてGHQに処刑されたA級戦犯の遺骨を遺族たちに渡せるように嘆願していたのである。ところが、マ元帥は一向に首を振らなかったため実現はしなかった。
そこで三文字弁護士は、巣鴨プリズンにおいて処刑されたA級戦犯が、久保山で火葬されることを探りあてた。三文字は火葬場のすぐ上にある興禅寺を訪ねて住職の市川伊雄と会った。市川住職は東京裁判にも傍聴に行き、裁判の不公平さに怒りを抱く一人であった。三文字弁護士が市川住職に協力を求める説明にも熱が入った。
このA級戦犯の遺骨が米軍の手から戻されないと、国民が不公平だった東京裁判の結果を認めたことになる。彼らの命令で戦場に駆り出された三百万の英霊さえ、辱めを受けて浮かばれなくなる。市川住職も日本人として耐えがたいことだったので、三文字に協力することを引き受けた。市川住職は、火葬場長の飛田を三文字に紹介したのである。
久保山火葬場の内部に働く人の協力で、はじめはA級戦犯の遺骨を分けて隠すことができたのが、米兵の監視に見つかり失敗した。今度は、火葬場の共同骨捨て場に捨てられているA級戦犯の骨を持ち出さなくてはならない。次の新しい骨が捨てられるまでは、一応、少しは他の骨も混ざってしまったとはいえ、七人の遺骨は残っている。
これを盗み出すのは十二月二十五日の夜と決めた。米軍の監視がクリスマスで気がゆるんでいる隙に実行しようというのである。暗くなり、頃合を見計らって、三文字弁護士と市川住職は勝手知ったる飛田火葬場長の案内で火葬場の骨捨て場に忍び込んだ。
三人は米軍の監視に見つからぬように、闇夜の中で外套を頭からかぶり、身をかがめながら作業を始めた。三人は暗がりの中で音を立てないように、根気よく手探りで遺骨を探し集めた。七人の遺骨は全体の一部でありながら、大きな骨壷に一杯分を集めることができた。
火葬場から盗み取ってきた遺骨は、湿気をとるために再度焼かれた。遺骨のことが世間に漏れては米軍の咎めを受けることになる。そこで三文字の甥で、上海の戦線で戦死した三文字正輔の名前を骨壷に書いた。これを興禅寺に預けて供養することになったのが、A級戦犯として処刑された七名の秘められた供養であった。
以上、「天皇と東条英機の苦悩」(塩田道夫著)より
このようにして集められた遺骨は、翌昭和二四年五月にはまだGHQの勢力下に日本があったため、伊豆山中の興亜観音に隠されるように葬られました。
しかし昭和三三年に入ると、他の場所に移してお祀りしようという話が持ち上がり、昭和三五年八月十八日に三ヶ根山(愛知県幡豆郡幡豆町)の山頂付近に移されることになりました。
三ヶ根山には殉国七士廟が設けられ、その中の殉国七士の墓に遺骨が分骨されて安置され、今に至ります。



最後に七名の辞世の句、詩を紹介します
土肥原賢二
「わが事もすべて了りぬいざさらば ここらでさらばいざ左様なら」
「天かけりのぼりゆくらん魂は 君が代千代に護るならべし」
「踏み出せば狭きも広く変わるなり 二河白道もかくやありなん」
松井石根
「天地も人もうらみずひとすじに 無畏を念じて安らけく逝く」
「いきにえに尽くる命は惜かれど 国に捧げて残りし身なればく」
「世の人にのこさばやと思ふ言の葉は 自他平等に誠の心」
東条英機
「我ゆくもまたこの土地にかへり来ん 国に報ゆることの足らねば」
「さらばなり苔の下にてわれ待たん 大和島根に花薫るとき」
「散る花も落つる木の実も心なき さそうはただに嵐のみかは」
「今ははや心にかかる雲もなし 心豊かに西へぞ急ぐ」
武藤章
「霜の夜を 思い切ったる門出かな」
「散る紅葉 吹かるるままの行方哉」
板垣征四郎
「ポツダムの宣のまにまにとこしえの 平和のために命捧ぐる」
「とこしえの平和のために身を捨てて 糞土を黄金にかえる嬉しさ」
「大神の御魂の前にひれふして ひたすら深き罪を乞うなり」
「今はただ妙法蓮華と唱えつつ 鷲の峰へといさみたつなり」
「さすらいの身の浮き雲も散りはてて 真如の月を仰ぐうれしさ」
「懐かしき唐国人よ今もなほ 東亜のほかに東亜あるべき」
広田弘毅
広田弘毅さんはは辞世の句を断ったそうです。
広田弘毅さんの名句を紹介します
風車風の吹くまで昼寝かな
(意味)
夏、青畳の上に大の字になる昼寝は実に気持ちのいいものだ。風車が静かに回り、風鈴がチリン、チリンと小さく鳴ったりするのを聞きながらする昼寝は、昼寝の醍醐味である。だが残念ながら風が吹かず風鈴は鳴らない。風が吹くまで待つこ
とにしょう。
木村兵太郎
「現身はとはの平和の人柱 七たび生まれ国に報いむ」
「平和なる国の弥栄祈るかな 嬉しき便り待たん浄土に」
「うつし世はあとひとときのわれながら 生死を越えし法のみ光り」