小規模発電システムの欠点をまとめると、常時一定電力が供給できないことになる。
・太陽電池:夜はだめ。雨天や曇りも・・・。
・小規模水力発電:季節要因がある。
・風力発電:風が吹かないときもある。
夜、渇水、無風となると電力供給が無くなるという不安は事実。だが、これらの自然なエネルギーを電力へ変換する試みは悪くない。
今の大規模発電システムの火力、水力、原子力は季節要因を限りなく無くしたシステムになっている。真夏の真昼をピークとしたときの供給能力を中心に考えられているから、太陽電池発電システムを追加すると少しだけ大規模発電システムを減らすことができるだろう。
小規模発電システムの発電コストが下がって今の大規模発電システムと同等になったら、火力発電や原子力発電の追加及び置き換え(建て替え)が不要になるが、最低限の安定電力維持源(バッファー)として存在する必要がある。
このバッファーは前述の大規模発電システムに頼るか、充電池システムに頼ることになる。
充電池システムにはいうらかの考え方がある。
・化学系蓄電池:リチウムイオン、ニッカド、鉛・・・。
・電荷保持系:巨大コンデンサ。(電荷を貯めるシステム)
・Kinetic系:フライホイールで電気エネルギーを運動エネルギーに変換。
揚水発電も近い考え方
・化学変換系:水の電気分解などで水素を作って保持。
<水素で燃料電池だけじゃなく、燃焼火力発電も可能>
Kinetic系以外のシステムは化学系電源である。これらはDC(直流)である。
となる、DC電源システムの構築も必要となる。
交流(AC)電源が当たり前とされているが、AC/DC変換(ヘビーメタルバンドみたいだ)も多い。
回路系技術者ではないので詳細はよくわからない(わかっていない)のだが、オーディオの世界ではDC電源信奉を聞く。
AC/DC変換の基礎は交流電源の入力線の途上にダイオードを直列に入れると山だけが流れるパルス(脈流)となる。ダイオードの後ろにコンデンサを並列にかますとパルス電源が流れていない間にコンデンサが放電することで擬似的に直流を作る。と言うところから来ている。
DC電源信奉ではこのコンデンサの放電による直流がわずかに震えるからそれが音に効くとか。
半導体回路(IC/LSI)がDC駆動であることから家庭内はDCでも良いのかもしれない。
こんな事を書いてるとどこかのDCエコハウスみたいだが・・・。
新規システムとして、既存の火力/原子力/水力発電の上に追加することになるのだろう。
火力の場合、石油は燃やすよりも化学製品の基にする方がよい。燃やすのはプラスチックにしてからでも良いと思うしね。
いずれにせよエコ発電というか、小規模発電は不安定だからバッファーが必要だ。
バッファーを既存電力系を使うのか、新たに蓄電・充電システムを構築するのか。
前者は比較的コストダウンになるが、後者はコストアップになる。
旧来発電システム建て替えが不要であればコストはほぼ同等なのかもしれない。
・太陽電池:夜はだめ。雨天や曇りも・・・。
・小規模水力発電:季節要因がある。
・風力発電:風が吹かないときもある。
夜、渇水、無風となると電力供給が無くなるという不安は事実。だが、これらの自然なエネルギーを電力へ変換する試みは悪くない。
今の大規模発電システムの火力、水力、原子力は季節要因を限りなく無くしたシステムになっている。真夏の真昼をピークとしたときの供給能力を中心に考えられているから、太陽電池発電システムを追加すると少しだけ大規模発電システムを減らすことができるだろう。
小規模発電システムの発電コストが下がって今の大規模発電システムと同等になったら、火力発電や原子力発電の追加及び置き換え(建て替え)が不要になるが、最低限の安定電力維持源(バッファー)として存在する必要がある。
このバッファーは前述の大規模発電システムに頼るか、充電池システムに頼ることになる。
充電池システムにはいうらかの考え方がある。
・化学系蓄電池:リチウムイオン、ニッカド、鉛・・・。
・電荷保持系:巨大コンデンサ。(電荷を貯めるシステム)
・Kinetic系:フライホイールで電気エネルギーを運動エネルギーに変換。
揚水発電も近い考え方
・化学変換系:水の電気分解などで水素を作って保持。
<水素で燃料電池だけじゃなく、燃焼火力発電も可能>
Kinetic系以外のシステムは化学系電源である。これらはDC(直流)である。
となる、DC電源システムの構築も必要となる。
交流(AC)電源が当たり前とされているが、AC/DC変換(ヘビーメタルバンドみたいだ)も多い。
回路系技術者ではないので詳細はよくわからない(わかっていない)のだが、オーディオの世界ではDC電源信奉を聞く。
AC/DC変換の基礎は交流電源の入力線の途上にダイオードを直列に入れると山だけが流れるパルス(脈流)となる。ダイオードの後ろにコンデンサを並列にかますとパルス電源が流れていない間にコンデンサが放電することで擬似的に直流を作る。と言うところから来ている。
DC電源信奉ではこのコンデンサの放電による直流がわずかに震えるからそれが音に効くとか。
半導体回路(IC/LSI)がDC駆動であることから家庭内はDCでも良いのかもしれない。
こんな事を書いてるとどこかのDCエコハウスみたいだが・・・。
新規システムとして、既存の火力/原子力/水力発電の上に追加することになるのだろう。
火力の場合、石油は燃やすよりも化学製品の基にする方がよい。燃やすのはプラスチックにしてからでも良いと思うしね。
いずれにせよエコ発電というか、小規模発電は不安定だからバッファーが必要だ。
バッファーを既存電力系を使うのか、新たに蓄電・充電システムを構築するのか。
前者は比較的コストダウンになるが、後者はコストアップになる。
旧来発電システム建て替えが不要であればコストはほぼ同等なのかもしれない。














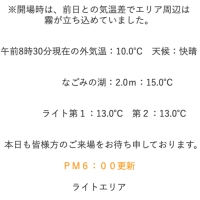





それによると、その宇宙人は地球人にちょとした警告(アドバイス)を与える目的で地球を訪れたとされ、以下のように言ったそうです。
「あんたたちは電子の使い方が間違っているよ」
それを読んだ僕の感想は「もしかしたらそんな気がする(直感的に)」でした。
今あのときの感想を振り返りますと「とにかく電子をさんざん使ってコンピューターだとかにまで応用し、そこそこに成功してはいるようだが、どこか何か非効率。もしかすると事の本質が見えてないのかも知れない」といった感じ。
更に少し突っ込んで書けば「コンピューターのように情報処理としての電子はまだしも、動力や熱としての電子の使い方は何かまずい。内燃機関ほどでないにせよ、ムダな部分があってそれが環境中にダダ漏れっぽい」といった感じ。
で、動力系についてはたとえば反重力みたいなことの研究をもっとしなければと思ったのでした。
今でも思います。電気自動車になったとて、ゴムのタイヤで地面を転がって移動とはなぁと。
身近な処で冷蔵庫とエアコンと給湯器。放熱と加熱を断熱された熱媒体を介すると熱拡散を防ぐ、エントロピーを増やさないシステムになると思ってます。生体に近づきます。
熱効率の点から再計算は必要ですが感覚的に冷水より温水の方が温め安いです。
ここに加圧による態変化をってヒートポンプですね。
恐らく、電子を巧く使えば良い断熱材になると思います。
電子の振動が熱ですから。
オカルトの波動と同一視されそうですが。
熱伝対、電子クーラー、この辺りが鍵でしょう。
太陽の黒点が無い等、とんでもないことになりそうですが、パラダイムシフトの前触れかもしれません。