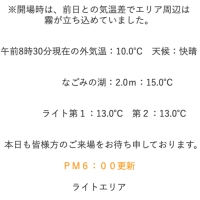リザーバーでのフライフィッシングでは、鱒が沈んでいる時がある。そういう時の攻略法を考えてみる。
状況を思い出してみよう。
天気は晴れでたまに陰る程度。風は無風かもしくは弱く、キャストの邪魔にならない。
暫く雨が降らない等で水は澄んでいる。水面には落ち葉等も殆ど無い。
時間帯は9時から15時頃迄の明るい時間帯。風光明媚な状況。
放流から2週間以上経過して、鱒は若干野生を取り戻している。
ライズリングはあるが、頻度は低い。鱒は深場からの急浮上/急潜航。
偏光サングラスを通して水面を逆光、順光のどちらから眺めても魚が全く見えないかたまに見える程度。
逆光では水面に何らかの虫が飛んでいる事が確認できるが、これは年がら年中ミッジがいるからなんとも。
前回、スプーンやバイブレーティングブレイドのボトムポンピングに魚は出た(私ではなくルアー使い)。
ルアーはフライよりも底を取りやすい。先の「中層」ではなく、もっと深い所に魚が居たわけだ。このような深場はフライではなかなか狙いにくい。狙うなら次の方法になるだろう。
じゃ、なぜ、魚は深い所に居るのだろう。
光 と考えています。
水中での光の減衰はLambert-Beerの法則により次の式で表される。SAUCE
だそうだ。よくわからないだろうが、ま、大体透明度の2倍から2.6倍とみなせるようですね。
透明度が1mになると
なぜ、魚が浮いてくるか。魚には瞳孔が無いから明るいと眩しいという説は簡単だが、明順応と暗順応があるし、浅くて透明度の高いNZ南島の快晴の浅瀬でライズする事からも特に眩しい訳ではないだろう。しかし、リザーバーではどうか。明け方から徐々に明るくなってくるが、ある時刻になると急に山麓から日が射す。魚は明順応するよりも今迄の明るさの所に移動し、徐々に沈んでいく。その方が楽だからだろう。そし深場から水面を見るとピューパがクネクネ登っていくのが見えるとそれを喰らおうと追いかける。
ここで、魚とピューパと太陽の位置関係が重要になりそうだ。逆光だと見えないが順光だとよく見えるので追いかけるのではないだろうか。
となればあとはティペットの位置が問題になりそうだ。
徐々に解明できそうな気がする。
状況を思い出してみよう。
天気は晴れでたまに陰る程度。風は無風かもしくは弱く、キャストの邪魔にならない。
暫く雨が降らない等で水は澄んでいる。水面には落ち葉等も殆ど無い。
時間帯は9時から15時頃迄の明るい時間帯。風光明媚な状況。
放流から2週間以上経過して、鱒は若干野生を取り戻している。
ライズリングはあるが、頻度は低い。鱒は深場からの急浮上/急潜航。
偏光サングラスを通して水面を逆光、順光のどちらから眺めても魚が全く見えないかたまに見える程度。
逆光では水面に何らかの虫が飛んでいる事が確認できるが、これは年がら年中ミッジがいるからなんとも。
2009年夏の考察
だから、中層のミッジ・リトリーブ(ピューパ、またはソフトハックル)が有効という考え。概ね正しいと考えているが、もう少し検証してみる。深みにいる魚にすると底から浮上するミッジピューパが目前を横切る。魚(捕食者)はダッシュしてそれを追う。ミッジピューパでない何かの生物であっても「捕食者」に追われると逃げる。逃げるとそれを喰らうのが捕食者の本能。
前回、スプーンやバイブレーティングブレイドのボトムポンピングに魚は出た(私ではなくルアー使い)。
ルアーはフライよりも底を取りやすい。先の「中層」ではなく、もっと深い所に魚が居たわけだ。このような深場はフライではなかなか狙いにくい。狙うなら次の方法になるだろう。
1) Long Leader Nymphing
フローティングラインの先に5ftでも9ftでも良いけどテーパードリーダーをつけ、その先のテイペットを長く(4mとか)取る。フライは重たいビーズヘッドのMSCとか、ハーズイヤー、エッグ、オクトパスボム、ビーズヘッドピューパ、スカッドなど。重く沈めばなんでも良い(ストリーマ系はトラウトガムとか、マツーカとか水中でボワッとならないまっすぐなやつがよいみたい。マツーカはこの釣り方であまり使った事無いけど・・・)
なるべく遠くに投げて、と言いたい所ですが、リーダーが長く、フライが重いのでワイドループっぽく投げるかスリークォーターっぽく
フライラインがクロスしない様に投げる必要があります。ダブルハンドフライロッドが結構有効ですね。
さて、キャスト後はフライが沈んでいくのを数を数えて待ちます。カウントダウンですね。リーダーが沈んで、フライラインの先端も徐々に沈んでいきます。ポリリーダー等のシンキングリーダーを使って沈めるのも一つの手です。
いずれにせよ、フライラインのテンションが生じたり無くなったりする時は鱒がフライを吸ったり吐いたりしているようなので、そのうちフライラインが急に伸びてヒットします。しかし結構フライを呑まれるみたいです。
フライを深く沈めるのはルースニングでも可能なんだけど、インジケーター等を工夫する必要があります。
なるべく遠くに投げて、と言いたい所ですが、リーダーが長く、フライが重いのでワイドループっぽく投げるかスリークォーターっぽく
フライラインがクロスしない様に投げる必要があります。ダブルハンドフライロッドが結構有効ですね。
さて、キャスト後はフライが沈んでいくのを数を数えて待ちます。カウントダウンですね。リーダーが沈んで、フライラインの先端も徐々に沈んでいきます。ポリリーダー等のシンキングリーダーを使って沈めるのも一つの手です。
いずれにせよ、フライラインのテンションが生じたり無くなったりする時は鱒がフライを吸ったり吐いたりしているようなので、そのうちフライラインが急に伸びてヒットします。しかし結構フライを呑まれるみたいです。
フライを深く沈めるのはルースニングでも可能なんだけど、インジケーター等を工夫する必要があります。
2) Deep Loothning
ティペットはL. L. Nymphingと同じくやはり長くなります。インジケーターを遊動式にする人もいますし、繊維系にすることでガイドに引っかからない様にする人もいます。狙ったタナがハッキリしています。フライは沈むタイプならなんでも。
杉坂(弟)氏のタマちゃんの様なフライだと、沈みきった所でティペットのよりで回転する事もあるとか。
杉坂(弟)氏のタマちゃんの様なフライだと、沈みきった所でティペットのよりで回転する事もあるとか。
3) チップシンク(ニンフチップ?)
シンキングリーダーと同じだけど、チップシンクは汎用性がないのであまり使わない。シンクレートを切り変えられるシンキングリーダーを使うか、マルチヘッド(チップ)を使っています。
4) SInking Line リトリーブ
ついついストリーマを引っ張りたくなります。これも色々あって
一方、魚が比較的浅そう!と思った時はフローティングラインにシンキングリーダーを足して引っ張る事もありますが、フライのトレースラインが手前程浮いてくる傾向があります。極スローならフライのトレースラインは一定値を維持できますが、今回のお題目の様に深い時はインタミの方が良い様です。
インタミを含んだシンキングラインはリトリーブ中も徐々に沈んでいきますのでトレースラインはカウントダウン(つまり引き始めの位置)とリトリーブ速度に依存します。ただ、ミッジは結構速い動きでピッピッと動かした方が良いみたいです。
・フルライン
・シューティングヘッド
・シンキングリーダープラス
となります。私はインタミにシンキングリーダーをプラスしています。理由はシューティングヘッドよりも扱いやすいこと、フルラインと違ってシンクレートをシンキングリーダーで調節しやすいからです。タイプIIよりも重いフルラインにシンキングリーダーをつけると、沈み過ぎの様な気がしています。・シューティングヘッド
・シンキングリーダープラス
一方、魚が比較的浅そう!と思った時はフローティングラインにシンキングリーダーを足して引っ張る事もありますが、フライのトレースラインが手前程浮いてくる傾向があります。極スローならフライのトレースラインは一定値を維持できますが、今回のお題目の様に深い時はインタミの方が良い様です。
インタミを含んだシンキングラインはリトリーブ中も徐々に沈んでいきますのでトレースラインはカウントダウン(つまり引き始めの位置)とリトリーブ速度に依存します。ただ、ミッジは結構速い動きでピッピッと動かした方が良いみたいです。
じゃ、なぜ、魚は深い所に居るのだろう。
光 と考えています。
水中での光の減衰はLambert-Beerの法則により次の式で表される。SAUCE
Iz = I0exp[-kZ]
Iz: 水深Z mの光量。
I0表水面での光量
kは減衰係数(m-1)
表水面の光量の1%が届く水深を生産層の深さ(Zem)としているがZe=4.6/kが得られるので、生産層の深さが1mの時のkの値は4.6となる。I0表水面での光量
kは減衰係数(m-1)
だそうだ。よくわからないだろうが、ま、大体透明度の2倍から2.6倍とみなせるようですね。
夏の日中の直射: 100,000lx
冬の日向: 50,000lx
冬の曇天: 20,000lx
晴天の日陰: 10,000lx
冬の雨天: 5,000lx
雷雨、降雪:2,000lx
最近のなごみの湖の透明度が感覚的に3m程度はあるので、水深6~8mで500lx。冬の日向: 50,000lx
冬の曇天: 20,000lx
晴天の日陰: 10,000lx
冬の雨天: 5,000lx
雷雨、降雪:2,000lx
0m: 50,000lx
1m: 23,208lx
2m:10,772lx
3m: 5,000lx
4m: 2,321lx
5m: 1,077lx
6m: 500lx
という感じだ。ま、水深3mで1/10になると言う感じかな。1m: 23,208lx
2m:10,772lx
3m: 5,000lx
4m: 2,321lx
5m: 1,077lx
6m: 500lx
透明度が1mになると
0m: 50,000lx
1m: 10,772lx
2m: 2,321lx
3m: 500lx
という感じだ。水深3mで1/100になる。だから、薄濁りが入ると魚が浮いてきて釣りやすくなる。これは夕方になると魚が浮いてくるのも同じ理由であろう。1m: 10,772lx
2m: 2,321lx
3m: 500lx
なぜ、魚が浮いてくるか。魚には瞳孔が無いから明るいと眩しいという説は簡単だが、明順応と暗順応があるし、浅くて透明度の高いNZ南島の快晴の浅瀬でライズする事からも特に眩しい訳ではないだろう。しかし、リザーバーではどうか。明け方から徐々に明るくなってくるが、ある時刻になると急に山麓から日が射す。魚は明順応するよりも今迄の明るさの所に移動し、徐々に沈んでいく。その方が楽だからだろう。そし深場から水面を見るとピューパがクネクネ登っていくのが見えるとそれを喰らおうと追いかける。
ここで、魚とピューパと太陽の位置関係が重要になりそうだ。逆光だと見えないが順光だとよく見えるので追いかけるのではないだろうか。
となればあとはティペットの位置が問題になりそうだ。
徐々に解明できそうな気がする。