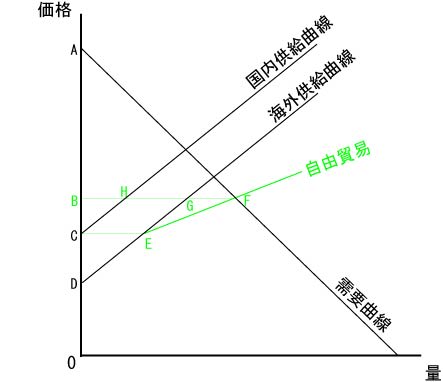先日の新聞記事で「ベーシックインカム」という言葉を知ったが、よい仕組みだと思う。働いているかどうかにかかわらず、すべての人に定額の所得を保証するというもので、究極のバラマキ政策といってもよい。一般のイメージとは違って、バラマキ政策は公平で効率的な優れた福祉政策だと私は思っている。最近の日本の政策では、給付付き税額控除、定額給付金、子供手当てなどが類似の政策と考えられる。
ベーシックインカムは「負の所得税」とほぼ同じ制度といってよいだろう。負の所得税は所得に応じて給付され、ベーシックインカムは所得と無関係に給付されるが、どうせ所得税があるのだから、ベーシックインカムと所得税を併せた結果は税率次第で負の所得税と同じである。
ベーシックインカムと間接税だけにして、所得税を廃止するという案もあるようだが、それも負の所得税を極端な税率カーブで設定した場合と同等だ。税制が劇的に簡素化する面白い案だが、高額所得層への課税累進率が緩くなりすぎるので無理だろう。
ベーシックインカムについてはウィキペディアのページが大変わかりやすい。ここに挙げられている問題点について考えてみた。
財源
当然かなりの財源が必要になるが、代わりに年金、扶養控除、失業保険、生活保護などを一部代替できるのだから、おおまかに言って財源的には中立のはずだ。所得を再配分するなら、どのような方法にしても、結局財源が必要なのであるから、問題はどのような方法が最も効果的かということだ。
なお、高齢者への年金や障害者への保障も一部ベーシックインカムで代替できるだろうが、全額を代替することはできない。ベーシックインカムは若い健康な人、つまり本来は働ける人のための保障であるから、働くことが困難な人への給付よりかなり低くするのが当然だろう。
皆が働かなくなる
所得の再配分には常にこの問題がついて回る。勤労意欲の低下を完全に避けることはできない。しかし同程度の所得再配分をする前提なら、ベーシックインカムや負の所得税は、現在の制度ほどは勤労意欲を低下させないように思える。現行制度では「130万円の壁」に代表されるように、働いても手取りが増えなかったり、さらにはかえって減ってしまう場合すらある。失業保険や生活保護にも同様の構造があって働く意欲を阻害している。生活保護では、節約して貯金することが許されないというおかしなことになっている。
ただ、現在の生活保護は比較的金額が多い(健康な壮年独身でも月12万円ほど貰える)けれども、「仕事が見つからない理由」を何度も聞かれたりするので、そこまでして貰おうという健常者の数は抑えられていると思われる。ベーシックインカムではそのような「後ろめたさ」がなくなるので、誰にとっても働かないという選択が簡単になり、働かない人が増える可能性はあるだろう。対策を考えないとおそらく、ズルズルと「最低保障生活」に安住してしまう人も出てくる。私も危ない(笑)。だから、高齢、障害、子育て、介護等の理由がなく差し引きで税金を貰い続けるには、その条件として、学習でも生活指導でも職業訓練でも何でもよいから、何らかの授業や社会参加を求めたほうがよいのではないか。昨今の「貧困問題」を見ていると、本当に仕事がないというよりは、本人の意欲や生活規則、精神状態、お金の使い方のほうが問題なように思える。
不正受給
給付付き税額控除には納税者番号制が必須だと言われる。ベーシックインカムは所得に関係なく給付されるが、ベーシックインカムと所得税の合算で考えると、給付付き税額控除と同様、所得を隠して不正に税金を貰う人が出てくることが懸念される。しかし、そもそも正確な納税は現行制度でも同じように重要であることが忘れられているのではなかろうか。
本来払うべき税金を払わないのも、本来貰えないはずの税金を貰うのも、不正にお金を得る点では変わりなく、国家財政や福祉に与える打撃は同じである。だから罪の重さも大差ない。
企業がベーシックインカムを当てにして給与を減らす
そのような影響はあるかもしれないが、問題は何もないはずだ。少しくらい給料が減ってもベーシックインカムがそれ以上に増えるのだから個々人にとっては十分だし、皆が同じ影響を蒙るのだから不公平でもない。そもそも現在の累進課税制度にも同様の給与を減らす効果があるはずだが、これを理由として累進率を緩和してほしいという意見はほとんど聞かない。
環境破壊
消費性向の高い低所得層にお金を配ると、今より多くのお金が使われ、景気がよくなると同時に環境破壊も進む可能性がある。だがこれはベーシックインカムとは本質的に別の問題だ。環境をよくするには、再配分をやめるより環境税のほうがずっと効果的だし、景気の過熱が心配なら公共工事を減らせばよい。早く景気過熱を心配できるほどになりたいものである。
移民にも給付するのか
ベーシックインカムの有無にかかわらず、豊かな先進国が門戸を広げれば、移民は殺到する。そうした人々の社会保障の負担をどうするか、といった問題は世界各国で昔から問題になっていることで、これも基本的にベーシックインカムとは別の話である。
移民に好かれないように自国の社会保障を削ろうという本末転倒な話は聞いたことがない。豊かな先進国ほど移民には魅力的だが、移民をどこまで受け入れるか、彼らにどこまで社会保障を適用するかは、別の政策問題だ。
給付が外国製品に使われてしまう
これもまったく別問題である。低所得層のほうが外国製品を好むという根拠はなく、むしろ高額所得層のほうが舶来品を好むかもしれない。だったら外国製品の流入を減らすために高額所得層からもっと税金を徴収すべきだろうか。
いずれにせよ、貿易収支を改善するために自国民を貧しくするというのは本末転倒だし、再配分と貿易収支はさらに無関係だ。そのうえ、そもそも日本は昔から貿易黒字で困っている(最近はそうでもないが)。
生きがいの喪失
働かなくても生きていけると何をしたらよいかわからなくなる人が増えるという意見だが、これは豊かになってかえって不幸になったとか、原始時代のほうがスリル満点で生き生きしていたのではないか、という話と同じようなもので、そういう面もあろうが、だからといって本気で貧しくなりたい人はまずいない。
安心して犯罪に参加できる
前科があってもベーシックインカムを貰えるなら、それを保険と考えて大胆な犯行に及ぶことができる、という面白い意見だが、それなら重大な前科がある人は給付を減らすことも考えられる。それは行き過ぎとしても、刑務所に入っている期間は給付しないことにするだけでも、犯罪のコストはむしろ今より高くなるだろう。
ベーシックインカムや負の所得税には、悪いところがあまりないように思える。制度が簡素化されるために官庁の仕事が減るので官僚がいやがるかもしれないが、公平で簡素な制度によって無駄が減り、福祉レベルが向上し、日本全体が豊かになるだろう。
関連:年金、失業保険、生活保護、所得税の統合
ベーシックインカムは「負の所得税」とほぼ同じ制度といってよいだろう。負の所得税は所得に応じて給付され、ベーシックインカムは所得と無関係に給付されるが、どうせ所得税があるのだから、ベーシックインカムと所得税を併せた結果は税率次第で負の所得税と同じである。
ベーシックインカムと間接税だけにして、所得税を廃止するという案もあるようだが、それも負の所得税を極端な税率カーブで設定した場合と同等だ。税制が劇的に簡素化する面白い案だが、高額所得層への課税累進率が緩くなりすぎるので無理だろう。
ベーシックインカムについてはウィキペディアのページが大変わかりやすい。ここに挙げられている問題点について考えてみた。
財源
当然かなりの財源が必要になるが、代わりに年金、扶養控除、失業保険、生活保護などを一部代替できるのだから、おおまかに言って財源的には中立のはずだ。所得を再配分するなら、どのような方法にしても、結局財源が必要なのであるから、問題はどのような方法が最も効果的かということだ。
なお、高齢者への年金や障害者への保障も一部ベーシックインカムで代替できるだろうが、全額を代替することはできない。ベーシックインカムは若い健康な人、つまり本来は働ける人のための保障であるから、働くことが困難な人への給付よりかなり低くするのが当然だろう。
皆が働かなくなる
所得の再配分には常にこの問題がついて回る。勤労意欲の低下を完全に避けることはできない。しかし同程度の所得再配分をする前提なら、ベーシックインカムや負の所得税は、現在の制度ほどは勤労意欲を低下させないように思える。現行制度では「130万円の壁」に代表されるように、働いても手取りが増えなかったり、さらにはかえって減ってしまう場合すらある。失業保険や生活保護にも同様の構造があって働く意欲を阻害している。生活保護では、節約して貯金することが許されないというおかしなことになっている。
ただ、現在の生活保護は比較的金額が多い(健康な壮年独身でも月12万円ほど貰える)けれども、「仕事が見つからない理由」を何度も聞かれたりするので、そこまでして貰おうという健常者の数は抑えられていると思われる。ベーシックインカムではそのような「後ろめたさ」がなくなるので、誰にとっても働かないという選択が簡単になり、働かない人が増える可能性はあるだろう。対策を考えないとおそらく、ズルズルと「最低保障生活」に安住してしまう人も出てくる。私も危ない(笑)。だから、高齢、障害、子育て、介護等の理由がなく差し引きで税金を貰い続けるには、その条件として、学習でも生活指導でも職業訓練でも何でもよいから、何らかの授業や社会参加を求めたほうがよいのではないか。昨今の「貧困問題」を見ていると、本当に仕事がないというよりは、本人の意欲や生活規則、精神状態、お金の使い方のほうが問題なように思える。
不正受給
給付付き税額控除には納税者番号制が必須だと言われる。ベーシックインカムは所得に関係なく給付されるが、ベーシックインカムと所得税の合算で考えると、給付付き税額控除と同様、所得を隠して不正に税金を貰う人が出てくることが懸念される。しかし、そもそも正確な納税は現行制度でも同じように重要であることが忘れられているのではなかろうか。
本来払うべき税金を払わないのも、本来貰えないはずの税金を貰うのも、不正にお金を得る点では変わりなく、国家財政や福祉に与える打撃は同じである。だから罪の重さも大差ない。
企業がベーシックインカムを当てにして給与を減らす
そのような影響はあるかもしれないが、問題は何もないはずだ。少しくらい給料が減ってもベーシックインカムがそれ以上に増えるのだから個々人にとっては十分だし、皆が同じ影響を蒙るのだから不公平でもない。そもそも現在の累進課税制度にも同様の給与を減らす効果があるはずだが、これを理由として累進率を緩和してほしいという意見はほとんど聞かない。
環境破壊
消費性向の高い低所得層にお金を配ると、今より多くのお金が使われ、景気がよくなると同時に環境破壊も進む可能性がある。だがこれはベーシックインカムとは本質的に別の問題だ。環境をよくするには、再配分をやめるより環境税のほうがずっと効果的だし、景気の過熱が心配なら公共工事を減らせばよい。早く景気過熱を心配できるほどになりたいものである。
移民にも給付するのか
ベーシックインカムの有無にかかわらず、豊かな先進国が門戸を広げれば、移民は殺到する。そうした人々の社会保障の負担をどうするか、といった問題は世界各国で昔から問題になっていることで、これも基本的にベーシックインカムとは別の話である。
移民に好かれないように自国の社会保障を削ろうという本末転倒な話は聞いたことがない。豊かな先進国ほど移民には魅力的だが、移民をどこまで受け入れるか、彼らにどこまで社会保障を適用するかは、別の政策問題だ。
給付が外国製品に使われてしまう
これもまったく別問題である。低所得層のほうが外国製品を好むという根拠はなく、むしろ高額所得層のほうが舶来品を好むかもしれない。だったら外国製品の流入を減らすために高額所得層からもっと税金を徴収すべきだろうか。
いずれにせよ、貿易収支を改善するために自国民を貧しくするというのは本末転倒だし、再配分と貿易収支はさらに無関係だ。そのうえ、そもそも日本は昔から貿易黒字で困っている(最近はそうでもないが)。
生きがいの喪失
働かなくても生きていけると何をしたらよいかわからなくなる人が増えるという意見だが、これは豊かになってかえって不幸になったとか、原始時代のほうがスリル満点で生き生きしていたのではないか、という話と同じようなもので、そういう面もあろうが、だからといって本気で貧しくなりたい人はまずいない。
安心して犯罪に参加できる
前科があってもベーシックインカムを貰えるなら、それを保険と考えて大胆な犯行に及ぶことができる、という面白い意見だが、それなら重大な前科がある人は給付を減らすことも考えられる。それは行き過ぎとしても、刑務所に入っている期間は給付しないことにするだけでも、犯罪のコストはむしろ今より高くなるだろう。
ベーシックインカムや負の所得税には、悪いところがあまりないように思える。制度が簡素化されるために官庁の仕事が減るので官僚がいやがるかもしれないが、公平で簡素な制度によって無駄が減り、福祉レベルが向上し、日本全体が豊かになるだろう。
関連:年金、失業保険、生活保護、所得税の統合