
昨年9月から蜻蛉日記を講読してます。
上巻は作者道綱の母の、女の嘆きの繰りごとが、ちょっと辟易、気味でしたが、中巻に入ると、記事の内容に興味も湧いてきます。
いきなり、中巻の66段からです。
西の宮の左の大臣(おとど)流され給ふ
源高明が、藤原氏の陰謀ともいわれる、立皇太子をめぐる謀反の密告によって配流された、安和の変である。
その前の段で
ちょっと険悪なところもあった作者と時姫両家の仲直りを兼ねた
小弓の遊びを予定していた安和2年3月25日、
いかなる咎まさりたりけむ
天下(てんげ)の人々流るることののしること出てで来て
大騒ぎになり小弓は中止になった、と記しています。
作者にとって、源高明は、兼家の異腹の妹愛宮の婿にあたり、
残された愛宮の出家に際しては、哀惜に満ちた長歌を送っています(第69段)。
あはれ今は かくいふかひも なけれども
思ひしことは 春のすゑ 花なむ散る
歌人で名高い作者、この高明を惜しむ長歌(この頃までが長歌の全峰盛期)の差出人を、
なぜか、愛宮の同腹の実兄としたのでした。なにを憚ったのでしょう?
悲しみの共感をあからさまには、述べない、という美意識なのか、
あるいは、単に身分差を憚ったということでしょうか?
でもなぜこの兄?多武峰少将物語のその人に?
このころを前後して、作者はなんというのでもない病に臥して(今でいえばうつ病?)すっかり弱気になって悲痛な遺書を書くのですね(第68段)
そこでは、15にもなる道綱のことを見捨てないで、あまり強く叱らないで、と
兼家にすがるように訴えるのです。
兼家の息子、道綱はいろいろしでかすことが多かった、ということか!
才色兼備の作者の思うようにいかないこと、夫兼家のほか
もう一つの頭痛の種、ひとり息子のこと、
古今東西、母の泣きどころ、なのでした。
上巻は作者道綱の母の、女の嘆きの繰りごとが、ちょっと辟易、気味でしたが、中巻に入ると、記事の内容に興味も湧いてきます。
いきなり、中巻の66段からです。
西の宮の左の大臣(おとど)流され給ふ
源高明が、藤原氏の陰謀ともいわれる、立皇太子をめぐる謀反の密告によって配流された、安和の変である。
その前の段で
ちょっと険悪なところもあった作者と時姫両家の仲直りを兼ねた
小弓の遊びを予定していた安和2年3月25日、
いかなる咎まさりたりけむ
天下(てんげ)の人々流るることののしること出てで来て
大騒ぎになり小弓は中止になった、と記しています。
作者にとって、源高明は、兼家の異腹の妹愛宮の婿にあたり、
残された愛宮の出家に際しては、哀惜に満ちた長歌を送っています(第69段)。
あはれ今は かくいふかひも なけれども
思ひしことは 春のすゑ 花なむ散る
歌人で名高い作者、この高明を惜しむ長歌(この頃までが長歌の全峰盛期)の差出人を、
なぜか、愛宮の同腹の実兄としたのでした。なにを憚ったのでしょう?
悲しみの共感をあからさまには、述べない、という美意識なのか、
あるいは、単に身分差を憚ったということでしょうか?
でもなぜこの兄?多武峰少将物語のその人に?
このころを前後して、作者はなんというのでもない病に臥して(今でいえばうつ病?)すっかり弱気になって悲痛な遺書を書くのですね(第68段)
そこでは、15にもなる道綱のことを見捨てないで、あまり強く叱らないで、と
兼家にすがるように訴えるのです。
兼家の息子、道綱はいろいろしでかすことが多かった、ということか!
才色兼備の作者の思うようにいかないこと、夫兼家のほか
もう一つの頭痛の種、ひとり息子のこと、
古今東西、母の泣きどころ、なのでした。












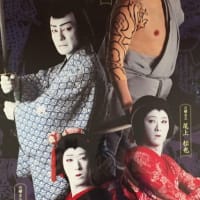



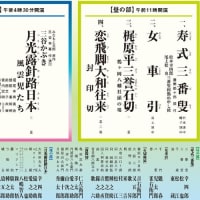

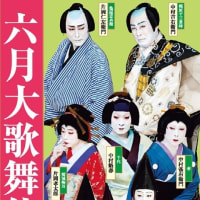








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます