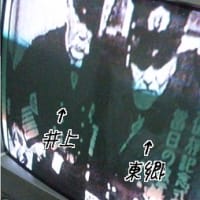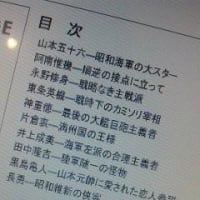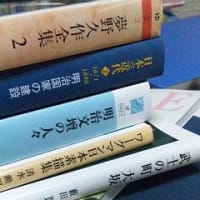2回目の更新です。
■■■ 広瀬武夫の柔道開始時期 2
前回までのまとめ
***
1) 『軍神広瀬中佐詳伝』 より
・講道館で柔道を始めたのは明治16年末
・恩師山縣小太郎の勧めによる。山縣は嘉納の姉婿と知り合い
2) 『嘉納治五郎』 他 講道館関係資料 より
・広瀬が講道館に通い始めたのは富士見町時代 即ち 明治19年3月~20年夏頃
・講道館入門は明治20年11月13日
3) 『嘉納先生伝』 より
・広瀬は攻玉社時代に起倒流を習っていた 明治16年末~ 明治18年9月
***
とまあ、こういった感じですけれども。
結論から言いますと、講道館に通い始めた時期、柔道を始めた時期は
①明治16年末ではなく(詳伝) ②明治19年3月以降(講道館資料) が妥当と思われます。
何故かと言いますに、↓を見て頂くと…
明治16年末というと、講道館は上二番町にあった頃になります。
富士見町ではない。
更に講道館は設立が明治15年5月なのですが、16年末と言うとまだ1年半程しか経っていない。
実は、その頃の講道館は修業者が殆どがいない状況で、門人を集めるのが大変だった。
門人第1号であった富田常次郎が回顧しているのですが、
・道場の経費は嘉納が一切負担。修業者に種々の便宜を与え月謝をとらない
・入門者は甚少、明治15年には僅かに9人、翌年は8人、19年には98人。
ここで漸く光が見えたが世間ではまだ柔道の名を知る者は少なく柔術を呼ばれていた。
明治16年の門人8人ですよ。笑。
講道館にやって来る人数が僅かなだけに、この頃門を叩いた人の名前も残っているのですが、その中に広瀬の名前は出てきていません。
これがひとつめ。
さらに、富田は広瀬と書簡のやりとりをしています。
広瀬は海軍部内の柔道関係者の窓口であったようなんですよね。広瀬がロシアに駐在している時にも手紙のやりとりをしている。
そう言う事もあって、明治16年末に広瀬が講道館に来たとするなら、こうした関係の富田が広瀬について回顧談で触れていないというのは不自然に思います。
これがふたつめ。
■■■
とまあ、入門時期、開始時期はこんな感じなのですが、なぜ柔道を始めたんでしょうねえ…
切欠がいまいち分からない。
それらしき事を記しているのは 『軍神広瀬中佐詳伝』 のみになります。
ただこちらの伝記には誤りが散見されるので、そのまま鵜呑みにできない所もあります。
第1回目で紹介した文章、柔道を始めた時期についてもソースが分からない事ですし、それを考えると『詳伝』の記載には疑問が残る事も確かです。
しかし広瀬が講道館に入門したのは、恩師山縣小太郎が嘉納治五郎の姉婿と知り合いで、その繋がりがあったため というのは、無碍に否定できない説得力がある。
その辺りをどう見るのかが難しい所ですなー…
講道館の関係資料からの推測しますと、
明治16年に8人、19年に98人であった講道館入門者も、20年には292人、21年378人、22年605人と急増します。

そして広瀬といえば、攻玉社時代に起倒流柔術を習い、海軍兵学校に入学。
海兵に入ってからも起倒流を続けていたかは不明ですが、
海兵在校中に急拡大しつつあった講道館の話を聞いて興味を持ち、仲間と訪れることになった。
という流れだったのではないか。
講道館を訪れた年代から考えると、こちらの方が『詳伝』の既述よりも自然な気がします。
さらに推測になりますが、
広瀬が山縣に柔術を習っている事を話していたならば、山縣が広瀬に嘉納や講道館について話したこともあったかもしれません。
この辺り、もう少し考える材料が欲しい所ですがこれ以上はなかなか難しい。
幾つか資料を見比べての結論は、
明治16年10月 上京し、山縣小太郎宅に奇寓。12月に攻玉社に入塾し、その生徒時代に起倒流柔術を習う
明治18年12月 海軍兵学校入学。
明治19年 3月 ~20年 この頃に講道館に通い始める
明治20年 夏頃 兵学校で仲間との乱取りを兵学校長が目撃する
明治20年11月 講道館入門
・海兵在校中に急拡大しつつあった講道館の話を聞いて興味を持ち、仲間と訪れることになった
・嘉納治五郎の姉婿と交流のあった恩師から、嘉納や講道館の話を聞いたが可能性もある
こんな感じかな?と
最新の画像[もっと見る]