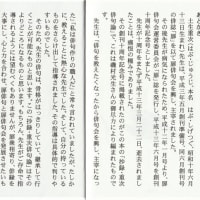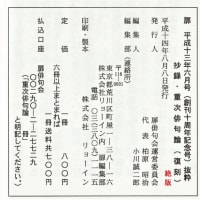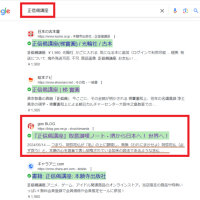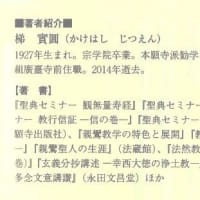十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図
前田秀一 プロフィール
<本論要旨>は こちらから
2.五畿内におけるキリシタンの受容(表-3)7~11、17~21)

拡大詳細は、こちらから
1)五畿内におけるキリスト教布教 -足掛かり
(1)フランシスコ・ザビエルの野望と挫折
フランシスコ・ザビエルは日本において以下4項の企画をもっていた2)(p30)。
①都にのぼって天皇に拝謁し、全日本で自由に布教する許可を得、さらに、天皇はシナの皇帝と友好関係にあると聞いたので、勘合符を入手してシナ伝道に備える
②日本の大学を歴訪してヨーロッパへくわしい情報をおくり、後続する有能な同志が宗論において日本の諸宗派を論破できる道を開く
③日本‐インド間の定期航路をひらき、堺にポルトガル貿易商館を設置して、布教の財政的な基礎をかためる
④日本人をキリスト教世界に派遣する
1550年10月末(天文19年10月末)、平戸を出港して、山口(12月17日発)、厳島(12月下旬発)を経由し1551年1月上旬(天文19年12月上旬)に堺港に到着した。1月中旬に都に入ったが、応仁・文明の乱による都の荒廃の中、乱の影響で幕府や守護大名の衰退が加速化し、頼るべき政権(第14代将軍足利義輝:在位1546~1565年)が近江朽木に逃れていて拝謁することができず、デウスの種をまくべき状況にないと判断しわずか11日の滞在で都を離れた。
1551年2月上旬(天文20年1月上旬)ザビエルが堺港を発ってから2)(p33)、永禄2年(1559)9月18日、後継者ガスパル・ビレラが堺に到着するまで約8年半の歳月が流れた。
フロイスは、ザビエルが堺に向かう途次、立ち寄った港で一人の身分の高い男に堺に住んでいる友人宛の紹介状をもらい、堺に上陸した際に一行が日比屋了珪の家に泊まったと書いた17)(p17)。しかし、『フロイス日本史』翻訳者・松田毅一氏は、その後、ガスパル・ヴィレラが堺に上陸した際に日比屋了珪の家に泊まらなかったことを事例として挙げ、ロドリーゲスが『日本教会史』に記載した「ザビエルは宿泊するところがなかったので、住吉の大明神(宿院御旅所)の松林に赴き、そこの一本松の木の根元に、拾ってきた数枚の古いござで小屋を作り、その中で寝泊まりした」とする説をとり17)(p22)、フロイスが『日本史』を執筆する際に日比屋家に対する配慮から脚色した疑いがあると解説している2)(p38)。
(2)ガスパル・ヴィレラの再挑戦
永禄2年(1559)10月18日、「ガスパル・ヴィレラ(日本滞在:1556~1570年)が政権の状況調査を目的に再び都をめざして堺に到着した。堺には知り合いもないので航海中にヴィレラの説教を聴聞して受洗したウルスラという女性の紹介で、ソウゼンと言う人の家に泊めてもらった。
翌日、司祭(ヴィレラ)が伴侶の人たちとともに町を見物していた時、たまたま、パウロ・イエサンと称する山口出身の身分ある五十過ぎのキリシタンの医師に出会い、国主・大内義隆(1507~1551年)の死に際して自分も放遂されて来たと事情を打ち明けられた。彼は(司祭たちに)どこへ行くのかと訊ねたので、彼らは、比叡山に赴き、そこで許可を得て五畿内で教えを説くつもりだ、と答えると、パウロは御身らが(使命として)帯びたことは重要であり難しい企てだと言い、彼はヴィレラらを別の家に連れて行き優遇した。
堺ではさっそく新奇を求めて数名の人が説教を聞きたいと申し出た。しかし司祭は、比叡山の主な僧侶の一人である西楽院に宛てた山口の国主の書状を携えており、寺院が建っている十六名の上長たち、およびかの大学の学問所を訪ねたく思ったし、自らの使命につき(修道会員として、上長からの)命令に服従して、それを速やかに実行したいと考えたので堺には3日しか滞在しただけだった。」17)(p44)
「堺を発って、大阪で一泊して淀川を遡り逢坂関を経て大津に至り、三井寺を訪ね、1559年10月22日に坂本のディオゴの家に赴いた。10月23日日本人修道士・ロレンソがまず比叡山に赴き、門弟の大泉坊を訪ねたが体よく断られ、翌24日ヴィレラ自ら比叡山に再訪したが、比叡山での交渉にヴィレラは絶望した。比叡山の許可なくして都へ入ることの無謀さに伴侶たちから止められたが、ヴィレラはたとえ(入京)の当日に殺されても自分の使命を果たすまでは豊後へは帰らないと単身でも都へ入ることを決意した。かの年老いた尼僧の一人は、伴天連に同情し、彼に言った。「御身は異国の方であり、それゆえ、都には多分一人としてお知り合いはおられますまい。私が、あそこにいる知人に宛てて、皆さんを泊めてあげてくださいと手紙を書きましょう」と。そして彼女はそのとおりにした。」17)(p60)
「都では、説教を聞きに来る人々の殺到ぶりは日増しに高まっていった。時には学識僧との激しい宗論となり都の町の仏僧たちは激昂し始めた。そのような中、全五畿内で最も主だった(寺院の)一つである紫の僧院(大徳寺)から、数人の禅宗の僧侶が、公家を装って訪ねて来たが、彼らは(司祭たちの説教を)聞いただけで、一言も話さなかった。」17)(p86)
「かくて家主たちは、人から悪口を言われ、仏僧たちの圧迫に恐れをなし、さっそく司祭に、もうこれ以上家を貸しておけぬから出ていってほしいと通報した。・・・というのは、僧侶、親族、友人、隣人たちは、(伴天連)を追い出し、自分のみや妻子に神仏の罪がふりかからぬようにせよ、とひどくせき立てたからであった。」17)(p92)
「そこへ禅宗の紫の僧院(大徳寺)から、もう八十歳近い老僧が訪ねて来た。彼は齢を重ねていたのと、気分がすぐれぬために、都に自分用に一軒の家を構えていた。生来親切な人で博愛と慈悲の業に心を傾けていた。彼はあの(司祭の)貧しい家に来ると、たいていの人々と同じように、ありふれた好奇心から出た質問を始めた。・・・司祭はその質問に満足な回答をした後に、自分がここで説いている(キリシタンの)教えについて少しぐらい聞きたいと思わぬかと訊ねた。それを聞くと老僧は微笑み、自分はすでに解脱のことは心得ており、インドとヨーロッパの珍しいことを知りたいだけだと言った。
それはあたかも、(自分が奉ずる)禅宗は、霊魂の不滅とか宇宙の第一原因、至福なる(天国での)果報とか来世(で)の懲罰(といったキリシタンの教え)を否定し、千六百の公案というものが(禅宗に)あって、人々はそれによってあらゆる良心の呵責をなくそうと努めるものである。だから(いまさら)自分たちの職分に大いに反する教えを携えて道を外す必要はない、と言おうとしているかのようであった。
ところで彼は司祭に同情していたので、他日また戻って来て、少しばかりの食物を持参したが、それは非常に清潔で、上手に料理してあった。・・・司祭は彼の贈物に対して謝意を表すことに決め、さっそく(老僧)に、デウスのことや、理性を備えた(人間の)霊魂(が)不滅であることや、来世のことを話すよう、適当な機会を探し求めた。果たして彼は説教を聞き始め、大いに興味を持つようになり、我らの(教えの)ことに非常に感動し、驚嘆の念を抱いた。そしてその善良な老人は、引き続き説教を聞いた後に聖なる洗礼を受け、その際、ファビアン・メイゾンと名づけられた。
冬の厳寒の折であるが、ミサを聞きに来て、ダミアンを傍に呼んで言うことには、私は伴天連様がミサを捧げられる時に、毎朝なにもかぶらずに、あんなに長い間立っておられるのを見ると、本当にお気の毒に思う。それにまた、銀の盃から冷酒を召しあがるのを見ると、お身体に障りはしまいかと、いっそうそのように感じる。どうか、私の家には、小さい銅の炉がついた非常にきれいな茶の湯の釜がありますことを、彼にあなたからお伝えください。もしお望みならば、それを彼に贈りましょう。」17)(p94~95)
「教会は嵐の後、静謐な歩みを保っていた。・・・1559年(永禄2年)11月初め、司祭は公方(第14代将軍足利義輝)様を訪問して、自分の名誉を回復させたり、(先に)下付された允許状を保証して恩恵を示されたことに謝意を述べようとしたところ、公方様はその点、いくらか難色を示し、当地の民衆は挙げて伴天連に反対して騒いでおり、僧侶もまた激しい憎しみを抱いている。したがって予が御身を優遇し、訪問を受けるのを人々が次々と見たならば、かならずや予にも不慮の出来事が起きることであろう。それゆえ、予を訪ねてこないようにと言った。」17)(p138)
(3)商都・堺での捲土重来 - 日比屋了珪の献身
「司祭(ヴィレラ)は、都においては布教がさしあたってなんら進展しないことが判ったが、(生来)霊魂の救済ということに大いなる熱意を抱いていたので、キリシタンの数が増えぬままでいることには、胸中もはや堪えられなくなった。・・・そして彼には、都以外としては、日本のヴェネツィア(とも言うべき)堺の市街以上に重要な場所はなかろうと思われた。すなわち、その市街は大きく、富裕であり、盛んに商取引が行われるのみならず、あらゆる国々の共通の市場のようで、絶えず各地から人々が参集するところである。
司祭は、堺には(自分のための)家も知人もないという事情が最初困難として自分の身に起こり得ようと考えたが、その時、我らの主なるデウスは、この市街のはなはだ名望があり、広く親族を有するフクダ日比屋了珪(生没不詳)なる一市民の心を動かし給うた。彼は伴天連がもし同所(堺)に来るならば、自分の邸に泊まってもらいたいと考えて、伴天連を知っていた日向殿(三好日向守長逸)という貴人に宛てて、もし(伴天連)が堺に来ることがあれば拙宅に住まわれるよう説得してほしいと書き送った。」17)(p140)
1561年(永禄4年)8月、「(司祭)が都から18里距たった堺に来た時に、日比屋了珪はその来訪を非常に喜び、あとう限り歓待した。そして彼がそこで我らの聖なる信仰について説き始めたところ、新奇なことであったので数名の者が説教を聞きに訪れた。これらの人の中には幾人かの学識ある人々もおり、彼らはいくつかの論拠から、いかなる結論を出すべきかを洞察したが、当時それを実行しはしなかった。なぜならば、同市(堺)の住民の自尊心と不遜なことは非常なもので、彼らは貪欲、暴利、奢侈、逸楽をほしいままにしており、加うるに悪魔は滑稽さと奸計によって、キリシタンになることは彼らにとり堕落を意味し、恥辱であると思い込ませていたからである。そのために多くの者は、同国人からのそうした辱めを恐れ、真理を認めながら受け入れず、大勢の人々が司祭に対して、世間の思惑や評判が、自分たちがデウスの教えの心理に従うことを躊躇させるのだと告白した。
それにもかかわらず、了珪の数人の子どもと親族たちがキリシタンとなり、それから2年後(1563年)には(了珪)も洗礼を受け、自らの生活および行為によって人々を大いに感化し、つねに当市のキリシタンの柱石となり生活の亀鑑であった。そして堺にはまだ我々の同僚たちの家がなく、司祭(ヴィレラ)たちがキリシタンの世話をしたり、布教のために他の用件を片付けようとしてその地に赴いた十八ヶ年以上もの間、彼の家は昼夜とも教会の役目を果たし、彼のものであった二階を司祭たちは居室とし、そこでミサを献げ、告白を聴き、キリシタンたちに他の秘跡を授けたりした。」17)(p140)
「都や堺の人々は、現地の人の中からキリシタンになる者は少なかったが、他の国から(そこへ)来る人々の(中)で、(キリシタンの教え)を聴いて洗礼を受ける者は、いつも後を断たなかった。」20)(p11)
SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから