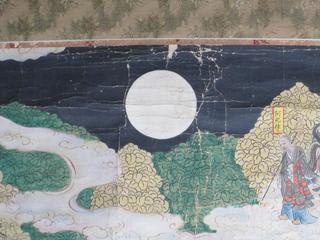立春も過ぎ、いよいよ春の訪れを感じます。
春夏秋冬、時は一時も立ち止まることなく過ぎていきます。
時だけでなく、すべてのものが常に移り変わっているのです。
先日まで大きかった雪の塊が、どんどん小さくなっていきます。
「氷」がとけたら何になる?とある先生が尋ねたそうです。
「水になる」と、生徒は答えたそうですが、
そのうちのひとりは「春が来る」と答えたそうです。
では、私たちの「安心」に至る道は、どんな道でしょう?
ミニバラのミス・ピーチヒメが芽吹き始めました。
もうすぐ薔薇の季節です。
春夏秋冬、時は一時も立ち止まることなく過ぎていきます。
時だけでなく、すべてのものが常に移り変わっているのです。
先日まで大きかった雪の塊が、どんどん小さくなっていきます。
「氷」がとけたら何になる?とある先生が尋ねたそうです。
「水になる」と、生徒は答えたそうですが、
そのうちのひとりは「春が来る」と答えたそうです。
では、私たちの「安心」に至る道は、どんな道でしょう?
ミニバラのミス・ピーチヒメが芽吹き始めました。
もうすぐ薔薇の季節です。