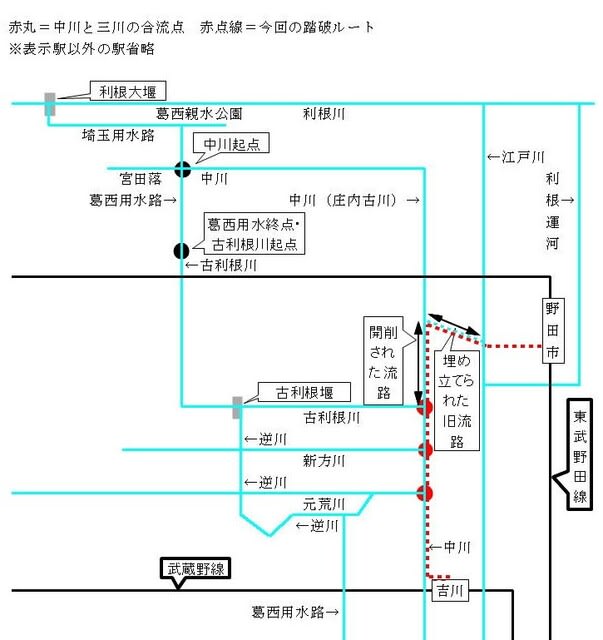ブラタモリが始まった頃(15年前)の録画を見る。最近復活して放送された3回のナレーターが草彅剛氏でないことに不満の声が寄せられていたが、そもそも最初の頃は戸田恵子だった。さらに、第1回の前に放送されたパイロット版では池田昌子だった。池田昌子と言えばメーテルである。なお、タモリさんと一緒にブラブラするアナウンサーは、パイロット版から3年間は久保田祐佳アナウンサーだった。
クラシック・ファンは、NHKのアナウンサーのうち、東京芸大出身の林田アナウンサー(この人も、いっときブラタモリのアナウンサーだった)に肩入れする人が多いようだが、それを言うなら久保田アナだってなかなかのものである。ご幼少のみぎり、かの鈴木雅明率いるBCJのマタイ受難曲に「子供の合唱」で参加されているのである。
録画の再生が終わり、現在放送中の番組の画面に切り替わったら、たった今録画で聴いていた声が聞こえてきた。房総半島の空撮を紹介する番組のナレーターが久保田アナであった。15年の時を経て、いろいろな人生経験をお積みになったかどうかは存じ上げないが声は変わってないなー、と思った。
それを言うなら、録画の終わりの方に当時の番宣がちらっと入っていて、それが「坂の上の雲」であった。ちょうど、今、再放送していて、その再放送の番宣をつい最近聞いたところである。同じドラマの番宣を15年後に再びするNHKと、それを同時に視聴する私、という構図である。
そんな案配だから、昔と今がごっちゃになり、録画中にニュース速報が入るとどきっとするが、それは15年前の出来事であって、あー良かった、とほっとする私なのである。
録画の冒頭には、当時のニュースの末尾がちらっと入っていて、1ドルが80円台。この15年で、円の価値は半分に下がった。単純に考えれば、同じお金を出しても外国製品は当時の半分しか買えないということだ。110円あたりで落ち着いていれば良かったのに。何事も、ほどほどというわけにはいかないようである。
なお、ブラタモリは、放送開始から3年経って数年休止し、再開したときもパイロット版が放送されたのだが、そのときのアナウンサーは、いま、朝ドラの前の番組を仕切っている首藤奈知子アナである。首藤さんでずっと行くのかな、と思ったら首藤さんは一回だけ。レギュラー回のアナウンサーは知らない人だった。その人は大出生した。以後、アナウンサーが代わるたびにその繰り返し。なかには「世界の某(故人)」のお身内になられた方もいる……ん?クラシック・ファンがそのアナウンサーのことを話題にするのを聞いたことがない。そのアナウンサー自身のことではないせいか。それとも、「世界の某」がファンの間では実はそれほど「世界」でないせいか。なお、当該「世界の某」は「世界の王」のことではない。
おっと、アナウンサーの話ばかりしてると、今回のジャンルを「地理」にしたことの当否に疑問が生じてしまう。もちろん、15年前のブラタモリもたいそう面白かった。番組で紹介した場所のそこかしこを訪ねてみる気まんまんである。例えば、本郷台地は本ブログの台地シリーズでも何度かとりあげたが、録画を見て、是非、菊坂に行ってお店屋さんでコロッケを買いたいと思った。台地と言えば、三田台地は敵(KO大学)の陣地であるから迂闊には近寄れないでいたが、15年前のブラタモリで紹介された急坂がたいそう気になったところ、そこら辺りに再開発の波が襲ってきて、番組のときはまだあった坂下の銭湯が今はもうないという。では坂はどうなった?すぐにでも、その生存確認に出向きたいのだが現在痛風闘病中である。また無理をしてぶり返しては元も子もないからしばらく我慢して、完治したら早速見に行きたいと思っている。
15年前は、タモリさんはまだ「笑っていいとも」をやっていたから、ブラブラするのは首都圏に限られていた。首都圏に住む者としては、おかげで、訪ねてみたい場所が身近にたくさんできた、というわけである。今はもう存在しない池も垂涎の的である。浅草にあった「ひょうたん池」だとか、新宿にあった「十二社池」の跡などは、是非訪ねてみたいと思っている(ひょうたん池の跡地がWINDS(昔の場外馬券売り場)であることはつかんでいる。だからと言って馬券を買いに行くのではない(きょうび、馬券はネットで買える(だが、絶対はずれるから買わない(えーと、閉じ括弧の数はいくつ要るんだっけ))))。