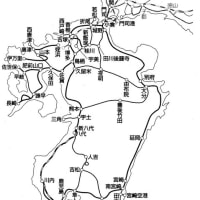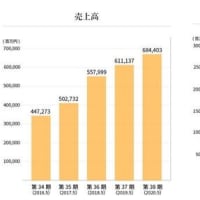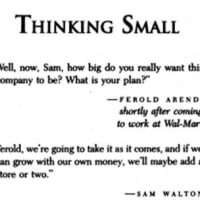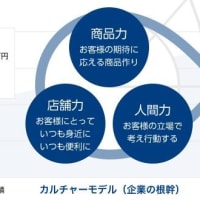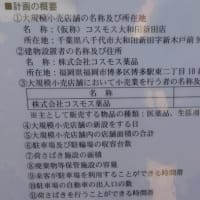『安楽死を遂げた日本人』宮下洋一著は,スイス、オランダ、ベルギー、アメリカ、スペイン、日本。世界6カ国の医師、患者、家族のもとを訪ね、死の「瞬間」にまで立ち会ったルポルタージュである。
自死,安楽死に関連して,昨年,多摩川で入水自殺を遂げた評論家・西部邁氏が思い起こされる。『安楽死を遂げた日本人』でも,西部氏の自殺を取り上げている。
◇ 安楽死を望む小島氏 -西部邁氏の自殺についての見解-(P31~P32)
「自殺」と「自死」には、大きな違いがあるという。小島*は、後者の定義を好んだ。自分で自分を殺すことは嫌いだと主張し、評論家・西部邁の例を出した。
西部は2018年1月、多摩川で入水自殺を遂げた。現場に西部を運んだ知人男性とテレビ局元社員は、前述の刑法202条にて、自殺封助の罪に問われていた(知人男性は懲役2年執行猶予3年の判決で確定、テレビ局元社員は18年9月に東京地裁から懲役2年執行猶予3年を言い渡された)。
「西部邁さんは自裁死という言葉を造語したんですね。最初それはすごくいい言葉だと思ったんです。なぜなら、自分の裁量で死を選ぶ。そう解釈できます。ところが、元々、自裁という言葉はあり、西部さんはそこに死という文字をつけて自裁死としたんですが、自裁という言葉も自殺という意味なんですよ。だとすれば、私は、その言葉も嫌いなんですよ」
死を願いつつも、「自殺した」とは言われたくないのだろう。
海外でもここ最近、「自殺幇助助」 という名称を極力避け、「自死幇助」という用語に切り替えている団体が多い。自ら死を選び、死期を早めるという行為は同じでも、そこに宿る精神によって、名称は異なってくるということだ。
もちろん、安楽死に反対する国や宗教団体からの圧力を避けたいという側面もある。たとえばカトリック教会では自殺が禁じられているため、そのワードを使わないことで乱轢を少なくしようというわけだ。
*小島氏)スイスでの安楽死を望み,宮下氏にコンタクトしてきた女性。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西部邁氏は,『私の死亡記事』文藝春秋刊 2000年10月発行 で,自らの死亡記事を寄稿している。この文中,"自死" "自裁"という用語がT使われている。
◇自殺できて安堵しております 西部邁(にしべ すすむ著) -『私の死亡記事』P146~147-
私儀、今から丁度一年前に死去致しました。死因は薬物による自殺であります。銃器を使用するのが念願だったのですが、当てにしていた二人の人間とも、一人は投身自殺、もう一人は胃痛で亡くなり、やむなく薬物にしました。
自殺を選んだ理由は、自分の精神がもうじき甚だしい機能低下を示してしまう、と確実に見通されたということであります。それは自分が単なる生命体に化すことであり、単なる生命体である自分が他の生命体を食して生き長らえているという状態を想像しますと、そういう状態にしか向かえない自分の生が無意味に思われました。ましてや、自分の単なる延命のために長年連れ添ってきた妻に介護の労苦を強いるのは想像するだにおぞましいことでした。
つまり、虚無の温床である生命それ自体にケリをつける、それが自分の生にかろうじて意味をみつける最後の手立てになった次第であります。そう考えそう行うことの妥当性については、かねてからの話し合いにより、妻子はよく理解してくれておりました。
かかる説明をあえてなすのは、今の世間が自死の意義をあまりよく理解しておらず、で、私の自裁が判明したあとで、妻子に世間から批難が寄せられるかもしれないと思料されるからにすぎません。自裁の直後に自己死亡通知を出さなかったのも同じ理由からであります。そして一年後にそれを出すのは、一年も経てば私の自殺が世間に生なましい印象を与えずに済むであろうと予想されたからです。また、あいつはどこに姿を消したのだ、との問い合わせが妻子のところにそろそろきているようですので、ここに死亡通知を出させていただくわけです。
ともかく私は、公のために死を選ぶという機会には恵まれませんでしたので、秘かに死ぬほかありませんでした。生前にわたしをひらくのに、つまり公を招き寄せるのに、一応の努力はしたのですが、やはり、能力の不足も然り乍ら、努力が足りなかったということなのでしょう。このような私にお付き合い下さった方々には、遅ればせではありますが、心から感謝致します。方々との理解と誤解の入り混じった交際がなければ私の生命に乗っかっていた小さな精神の機構つまり脳は、もつと早々と腐蝕していたに違いありません。思えば、まったく有り難い交際でありました。
この死亡通知をたまたま読まれて、お前はそも何者だと尋ねたくなる読者も多いことでしょう。私の履歴を簡単に述べておくのがこういう際の作法だとは承知しているのですが、すでに生前において、自分のやったことについては忘れゆくばかりでした。ニーチェを真似るわけではないのですが、何冊か本を書いたような気がする、としかいえません。このことからも、「精神」は活きていてこその代物だと、いわゆる彼岸にいるものとして、つくづく感じ入っております。左様なら。
 |
私の死亡記事 (文春文庫) |
|
『私の死亡記事』は,類をみないネクロロジー(死亡記事、
|
|
| 文藝春秋刊 |
>>>NHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」
https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/46/2586161/index.html
去年、一人の日本人女性が、スイスで安楽死を行った。女性は重い神経難病を患い、自分らしさを保ったまま亡くなりたいと願っていた。患者の死期を積極的に早める安楽死は日本では認められていない。そんな中で、民間の安楽死団体が、海外からも希望者を受け入れているスイスで安楽死することを希望する日本人が出始めている。この死を選んだ女性と、彼女の選択と向き合い続けた家族の姿は、私たちに何を問いかけるのか見つめる。
 |
安楽死を遂げた日本人 |
| 宮下 洋一 | |
| 小学館 |
『安楽死を遂げた日本人』は欧州を拠点とし活躍するジャーナリスト,宮下洋一氏が自殺幇助団体の代表であるスイスの女性医師と出会い,欧米の安楽死事情を取材し,「理想の死」を問うノンフィクションである。
 |
安楽死を遂げるまで |
| 宮下 洋一 | |
| 小学館 |
 |
安楽死を遂げた日本人 |
| 宮下 洋一 | |
| 小学館 |
内容紹介 ”講談社ノンフィクション賞受賞作品!”
安楽死,それはスイス,オランダ,ベルギー,ルクセンブルク,アメリカの一部の州,カナダで認められる医療行為である。超高齢社会を迎えた日本でも,昨今,容認論が高まりつつある。しかし,実態が伝えられることは少ない。
安らかに死ぬ――。本当に字義通りの逝き方なのか。患者たちはどのような痛みや苦しみを抱え,自ら死を選ぶのか。遺された家族はどう思うか。
79歳の認知症男性や難病を背負う12歳少女,49歳の躁鬱病男性。彼らが死に至った「過程」を辿りつつ,スイスの自殺幇助団体に登録する日本人や,「安楽死事件」で罪に問われた日本人医師を訪ねた。当初,安楽死に懐疑的だった筆者は,どのような「理想の死」を見つけ出すか。第40回講談社ノンフィクション賞を受賞した渾身ルポルタージュ。