
ずしがめってご存知ですか?
漢字で書けば厨子甕。
沖縄方言表記だと「じーしがーみー」…で、合ってますか??
亡くなった方の骨を収める、いわゆる骨壷です。
この厨子甕の変遷や美術工芸としての特徴などを解説した企画展が、
沖縄県立博物館で開催中でした。
古来から奄美から先島諸島まで連なる琉球弧、
その先の台湾や中国福建省地域、そして朝鮮半島では洗骨という習俗がありました。
これは亡くなって数年経った遺骨を洗い清める儀礼で、
洗骨された遺骨が納められた納骨器が厨子甕なのです。
墓の中に安置されて人目に触れることも無く、
また遺族感情というデリケートな部分もあり、最近まで研究も進んでいなかったそうですが、
ここに沖縄の人達の死者に対する想いや宗教的思想が凝縮されているとも言え、
今回の企画展は非常に興味深く、是非足を運んでみたいと思っていました。
少々専門的なお話ですが、少しの間お付き合いくださいね。
現在確認されている最古の厨子甕は、
15世紀末頃の今帰仁百按司墓から見つかっている長方形の箱に四つの足がついた板厨子。
つまり、その頃には風葬・洗骨の習俗が成立していたようです。
ちなみに同じ洗骨を行う地域の中でも沖縄だけが風葬で、
他の地域は一度土葬した上で、3年ほど経過したのち掘り返すのだとか。
この違いが何処から来るのかについての言及は、残念ながらありませんでした。
その後、材質が16世紀半ばには石、17世紀後半からは陶器へと変わっていき、
それに伴い装飾が大きく複雑化、
屋根が重層になり、シャチホコ・獅子・龍などが飾られた姿は、
まるで首里城正殿を写したかのようで、御殿(うどぅん)型と呼ばれています。
又、蓋や側面には銘書(みがち)という故人の姓名・屋号・あざな・死亡や洗骨年月日・経歴など、
その人物の人となりが記されてあり、貴重な文献史料としての価値も高いとされます。
以上、駆け足で厨子甕のことを紹介しましたが、
何故沖縄地域のみで厨子甕が発達したのかといった部分がよくわからないなどは、
これからさらに調査・研究・考察が進められることでしょう。
非常に充実した貴重な体験でした。
漢字で書けば厨子甕。
沖縄方言表記だと「じーしがーみー」…で、合ってますか??
亡くなった方の骨を収める、いわゆる骨壷です。
この厨子甕の変遷や美術工芸としての特徴などを解説した企画展が、
沖縄県立博物館で開催中でした。
古来から奄美から先島諸島まで連なる琉球弧、
その先の台湾や中国福建省地域、そして朝鮮半島では洗骨という習俗がありました。
これは亡くなって数年経った遺骨を洗い清める儀礼で、
洗骨された遺骨が納められた納骨器が厨子甕なのです。
墓の中に安置されて人目に触れることも無く、
また遺族感情というデリケートな部分もあり、最近まで研究も進んでいなかったそうですが、
ここに沖縄の人達の死者に対する想いや宗教的思想が凝縮されているとも言え、
今回の企画展は非常に興味深く、是非足を運んでみたいと思っていました。
少々専門的なお話ですが、少しの間お付き合いくださいね。
現在確認されている最古の厨子甕は、
15世紀末頃の今帰仁百按司墓から見つかっている長方形の箱に四つの足がついた板厨子。
つまり、その頃には風葬・洗骨の習俗が成立していたようです。
ちなみに同じ洗骨を行う地域の中でも沖縄だけが風葬で、
他の地域は一度土葬した上で、3年ほど経過したのち掘り返すのだとか。
この違いが何処から来るのかについての言及は、残念ながらありませんでした。
その後、材質が16世紀半ばには石、17世紀後半からは陶器へと変わっていき、
それに伴い装飾が大きく複雑化、
屋根が重層になり、シャチホコ・獅子・龍などが飾られた姿は、
まるで首里城正殿を写したかのようで、御殿(うどぅん)型と呼ばれています。
又、蓋や側面には銘書(みがち)という故人の姓名・屋号・あざな・死亡や洗骨年月日・経歴など、
その人物の人となりが記されてあり、貴重な文献史料としての価値も高いとされます。
以上、駆け足で厨子甕のことを紹介しましたが、
何故沖縄地域のみで厨子甕が発達したのかといった部分がよくわからないなどは、
これからさらに調査・研究・考察が進められることでしょう。
非常に充実した貴重な体験でした。













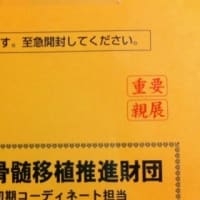






このよぉな記事、とても引き込まれます♪
音楽も泡盛も食生活も…
まだまだ奥が深いなぁ~と想います。
さすが、きしの屋さん!
良い勉強になりました♪
何度足を運んでも、新しい発見がある島ですよね。
私は本島とその周辺しか行ったことが無いんです。
宮古や八重山には、もっといろんな発見が待っているんでしょう。
それらも見てまわる為には、
一生掛かっても、まだ足りないような気がします