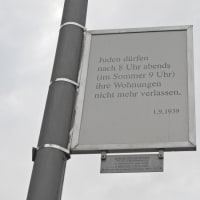8月30日(金)弦楽とピアノの室内楽/パノハSQとクァルテット・エクセルシオ
草津音楽の森国際コンサートホール
【曲目】
1. 西村 朗/弦楽四重奏曲 第2番「光の波」
2.フンメル/ピアノ五重奏曲 変ホ短調 Op.87
3.メンデルスゾーン/弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20

【アンコール】
3.メンデルスゾーン/弦楽八重奏曲 ~スケルツォ
【演 奏】
パノハ弦楽四重奏団/クァルテット・エクセルシオ/CB:クラウス・シュトール/Pf:/岡田博美
関先生のお供をさせて頂いてゲネプロで今日の曲目をひととおり前もって聴くことができた。ゲネプロで特に面白かったのは西村朗の曲をやったとき。作曲者が演奏に立ち合っていろいろ指示が伝えられながら進む様子は現代曲ならでは。その西村の弦楽四重奏曲は1992年の作品で、新作初演を中心とした斬新な活動で知られるアルディッティ四重奏団の委嘱作品。「演奏の難しい曲を」という注文で書かれた曲とのことだが、曲は単に超絶技巧をひけらかすのではなく、アグレシブでパッションに満ち、厳しさが主流である一方でファンタジーも感じる音楽。
クァルテット・エクセルシオはゲネプロから妥協のない火花が飛び散る白熱した演奏を聴かせ、思わず身を乗り出して聞き入った。とても楽しみな気持ちで臨んだ本番は、ゲネプロに比べてスケールがちょっと縮んでしまったように感じた。お客が入ってホールの鳴りが少し悪くなったせいもあるかも知れないが、アグレシブに迫ってきたのはゲネプロの方だった。いずれにしてもこれは前向きの優れた作品で、機会を見つけてまた聴きたい。
続いては音楽がガラリと変わってフンメルのクィンテット。この曲は第2楽章などには弦の聴かせ所もあるが、殆どピアノが主役。岡田博美のピアノは淀みなく流麗で、アンサンブルのなかを鮮やかに縫っていく感じ。無駄なところが全くなく、淡々と自分のパートを弾き進んで行き、他の奏者への働きかけみたいなものも感じられない。ピアノが主役だが、ピアノと弦楽アンサンブルとの能動的なやり取りや駆け引きがないとアンサンブルとしての面白味は出ない。弦のアンサンブルはよくまとまっていたし、エクセルシオのメンバーの大友のチェロや吉田のヴィオラなどいい歌を聴かせていたが、ピアノとの対話にまでは至らない。コントラバスのシュトールが、躍動する動きで両者の間を一生懸命取り持っているようにも聞こえたが、ピアノがもう少しアンサンブルに仕掛けてこないとつまらない。
アンサンブルの醍醐味を味わえたのは最後のメンデルスゾーン。パノハとエクセルシオという性格も向かう方向もかなり異なるカルテットが共演してどんな演奏になるかと思ったが、ゲネプロで既に感じさせた特徴が本番でも花開いた。両サイドはパノハのメンバー、中央のセカンドバイオリンとチェロはエクセルシオのメンバーが1番のパートを受け持つという混合編成で臨んだが、第1楽章から音色や感触はパノハの特徴である柔らかく奥ゆかしい音で語りかけてきた。その極めつけは第2楽章。くすみ加減の哀愁を帯びた音色は香り高く、詩情に溢れた歌が心の琴線を震わして、懐かしさが込み上げてきた。
この感触がパノハの色だとすると、フィナーレの若々しい能動性からはエクセルシオの息づかいが感じられた。一人の奏者が他の奏者に働きかけると、それに下の句を付けて返してくる、といったやり取りが集積して、最後のトゥッティでの劇的なたたみかけ・盛り上がりが築かれて、トリハダがビンビン立った。2つのカルテットのいいところが合わさった上に、更にパワーと深みを増したような素晴らしい演奏だった。
マスタークラス(マリオ・アンチロッティ)
コンサートの前、この日の午前中は関先生にくっついてアンチロッティのフルートのマスタークラスを聴き、午後はコンサートのゲネプロを聴いた。ゲネプロについては上述したので、マスタークラスを聴かせて頂いた感想を簡単に…
2人の生徒がモーツァルトのニ長調のコンチェルトを、もう1人は無伴奏の現代曲を演奏するときに居合わせた。モーツァルトでは、ヴィヴラートやブレスなど、テクニック面での細かいアドバイスと、ニュアンスの対比のつけ方や感じ方といった、音楽的な指導の両面から行われた。殆ど同じフレーズを繰り返す冒頭をいかに吹き分けるか、といったポイントひとつとってもなるほどと思えることばかりで、模範で演奏したアンチロッティのフルートは、頼もしく存在感も大きかった。昨日のコンサートの感想ではあまりいいことを書いていなかったが、改めて聴き直してみたい気分になった。アンチロッティがポイントを指摘すると、生徒はそれを的確にくみ取って自分の演奏に反映させていた。
現代曲の方は誰の曲かわからなかった。「特にこういう曲では、演奏者が聴き手に視覚的に与える印象も大切」というワンポイントレッスンが施されていた。
草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル2013(8/29)
草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル2012
草津音楽の森国際コンサートホール
【曲目】
1. 西村 朗/弦楽四重奏曲 第2番「光の波」

2.フンメル/ピアノ五重奏曲 変ホ短調 Op.87
3.メンデルスゾーン/弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20


【アンコール】
3.メンデルスゾーン/弦楽八重奏曲 ~スケルツォ
【演 奏】
パノハ弦楽四重奏団/クァルテット・エクセルシオ/CB:クラウス・シュトール/Pf:/岡田博美
関先生のお供をさせて頂いてゲネプロで今日の曲目をひととおり前もって聴くことができた。ゲネプロで特に面白かったのは西村朗の曲をやったとき。作曲者が演奏に立ち合っていろいろ指示が伝えられながら進む様子は現代曲ならでは。その西村の弦楽四重奏曲は1992年の作品で、新作初演を中心とした斬新な活動で知られるアルディッティ四重奏団の委嘱作品。「演奏の難しい曲を」という注文で書かれた曲とのことだが、曲は単に超絶技巧をひけらかすのではなく、アグレシブでパッションに満ち、厳しさが主流である一方でファンタジーも感じる音楽。
クァルテット・エクセルシオはゲネプロから妥協のない火花が飛び散る白熱した演奏を聴かせ、思わず身を乗り出して聞き入った。とても楽しみな気持ちで臨んだ本番は、ゲネプロに比べてスケールがちょっと縮んでしまったように感じた。お客が入ってホールの鳴りが少し悪くなったせいもあるかも知れないが、アグレシブに迫ってきたのはゲネプロの方だった。いずれにしてもこれは前向きの優れた作品で、機会を見つけてまた聴きたい。
続いては音楽がガラリと変わってフンメルのクィンテット。この曲は第2楽章などには弦の聴かせ所もあるが、殆どピアノが主役。岡田博美のピアノは淀みなく流麗で、アンサンブルのなかを鮮やかに縫っていく感じ。無駄なところが全くなく、淡々と自分のパートを弾き進んで行き、他の奏者への働きかけみたいなものも感じられない。ピアノが主役だが、ピアノと弦楽アンサンブルとの能動的なやり取りや駆け引きがないとアンサンブルとしての面白味は出ない。弦のアンサンブルはよくまとまっていたし、エクセルシオのメンバーの大友のチェロや吉田のヴィオラなどいい歌を聴かせていたが、ピアノとの対話にまでは至らない。コントラバスのシュトールが、躍動する動きで両者の間を一生懸命取り持っているようにも聞こえたが、ピアノがもう少しアンサンブルに仕掛けてこないとつまらない。
アンサンブルの醍醐味を味わえたのは最後のメンデルスゾーン。パノハとエクセルシオという性格も向かう方向もかなり異なるカルテットが共演してどんな演奏になるかと思ったが、ゲネプロで既に感じさせた特徴が本番でも花開いた。両サイドはパノハのメンバー、中央のセカンドバイオリンとチェロはエクセルシオのメンバーが1番のパートを受け持つという混合編成で臨んだが、第1楽章から音色や感触はパノハの特徴である柔らかく奥ゆかしい音で語りかけてきた。その極めつけは第2楽章。くすみ加減の哀愁を帯びた音色は香り高く、詩情に溢れた歌が心の琴線を震わして、懐かしさが込み上げてきた。
この感触がパノハの色だとすると、フィナーレの若々しい能動性からはエクセルシオの息づかいが感じられた。一人の奏者が他の奏者に働きかけると、それに下の句を付けて返してくる、といったやり取りが集積して、最後のトゥッティでの劇的なたたみかけ・盛り上がりが築かれて、トリハダがビンビン立った。2つのカルテットのいいところが合わさった上に、更にパワーと深みを増したような素晴らしい演奏だった。
マスタークラス(マリオ・アンチロッティ)
コンサートの前、この日の午前中は関先生にくっついてアンチロッティのフルートのマスタークラスを聴き、午後はコンサートのゲネプロを聴いた。ゲネプロについては上述したので、マスタークラスを聴かせて頂いた感想を簡単に…
2人の生徒がモーツァルトのニ長調のコンチェルトを、もう1人は無伴奏の現代曲を演奏するときに居合わせた。モーツァルトでは、ヴィヴラートやブレスなど、テクニック面での細かいアドバイスと、ニュアンスの対比のつけ方や感じ方といった、音楽的な指導の両面から行われた。殆ど同じフレーズを繰り返す冒頭をいかに吹き分けるか、といったポイントひとつとってもなるほどと思えることばかりで、模範で演奏したアンチロッティのフルートは、頼もしく存在感も大きかった。昨日のコンサートの感想ではあまりいいことを書いていなかったが、改めて聴き直してみたい気分になった。アンチロッティがポイントを指摘すると、生徒はそれを的確にくみ取って自分の演奏に反映させていた。
現代曲の方は誰の曲かわからなかった。「特にこういう曲では、演奏者が聴き手に視覚的に与える印象も大切」というワンポイントレッスンが施されていた。
草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル2013(8/29)
草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル2012