「熱狂の日」音楽祭2013 【パリ、至福の時】 東京国際フォーラム 「パリ、至福の時」と題し、19世紀後半から現代までパリを彩ったフランスとスペインの作曲家たちに焦点を当てた 今年のラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン。出演者の目玉は何と言っても18年ぶりの来日となる現代音楽の精鋭、アンサンブル・アンテルコンタンポランだろう 。設立者ブーレーズの作品もやるし、いつもとはひと味違った刺激的な体験が期待できる。それに、この音楽祭の常連だったミシェル・コルボが3年ぶりに登場するのも楽しみ。フランスが発祥のラ・フォル・ジュルネがフランス物で勝負する今回は、一層の充実した祭典になりそう。 中日の4日に絞って7公演を選び、メンバーの先行抽選で5公演のチケットをゲット、抽選に漏れた2公演分はちけぴの店頭発売日に並んでゲット。希望の公演チケットをすべて押さえた。以下、その7つの公演の感想を演奏順に紹介する。 |  |
~5月4日(土)~
 Vc:宮田 大/イプ・ウィンシー指揮 香港シンフォニエッタ
Vc:宮田 大/イプ・ウィンシー指揮 香港シンフォニエッタホールC(プルースト)
【曲目】
1.ラヴェル/クープランの墓
2.フォーレ/エレジー op.24

3. サン=サーンス/チェロ協奏曲第1番 イ短調 op.33


【アンコール】
サン=サーンス/白鳥

大ちゃんファンの奥さんと聴いた。このコンサートの主役はチェロの宮田大だが、最初はオーケストラだけのステージ。中国出身の若い女性指揮者、イブ・ウィンシーが指揮する香港シンフォニエッタによる「クープランの墓」は、とても瑞々しくて流麗。木管の音がちょっとストレート過ぎると感じることが時々あったが、ソロパートの積極的な姿勢も好ましく、柔らかさとメリハリのどちらも備えた楽しめる演奏だった。
宮田大のチェロは室内楽では何度か聴いているが、完全なソロで聴くのは初めて。あまり響かない大きなホールの3階席だったが、チェロの音が弱音でもふわっとホールいっぱいに広がってとてもよく聴こえてくるのに驚いた。音が柔らかく膨らんで、無理なく広がっていく。ふくよかな音は色合いを様々に変化させ、溢れる歌心を伝えてきた。フォーレのエレジーでの切なさを包む抒情、サン=サーンスでの熱い吐息で突き進むエネルギー、どちらにしても宮田さんのチェロはいくらでも水分を吸収する海綿のように瑞々しくて包容力があり、聴いていてとても満たされた。無伴奏で聴かせてくれたアンコールの「白鳥」は、温かく、どこか切なく、白鳥の羽根の末端まで細やかな神経が行き届いたデリケートな演奏にジーンときた。
 “聖なるパリ”
“聖なるパリ”ヤーン=エイク・トゥルヴェ指揮 ヴォックス・クラマンティス

ホールB5(ミシア・セール)
【曲目】
♪デュリュフレ/グレゴリオ聖歌による4つのモテット op.10
♪ギョーム・ド・マショー/ノートルダム・レー
♪プーランク/悔悟節のための4つのモテット
♪メシアン/おお聖なる饗宴
♪グレゴリオ聖歌より
【アンコール】
♪デュリュフレ/グレゴリオ聖歌による4つのモテット op.10~第1曲、第2曲
中世と現代の作品を得意とする声楽・器楽アンサンブルのヴォックス・クラマンティス、去年のLFJでは勅使川原三郎のダンス入りの公演のインパクトが強く残っている。今回は12人のヴォーカリストによるアカペラによる演奏会。
単旋律のグレゴリオ聖歌が演奏されたあと、同じ歌詞と旋律をベースに作曲された近・現代のフランスの作曲家による多声部作品を演奏し、これを繰り返すパターン。歌詞やベースとなる旋律が同じでも、千年の時を隔てて中世の音楽と近・現代の曲が交互に並ぶと毛色の違いが目立つと思いきや、実際に聴いてみると不思議ととてもしっくりくる。古くから信仰されている宗教のある種の普遍性を思わずにはいられない。どんなに時代が異なり、手段は違えど、キリスト教が人に伝えようとするメッセージは変わらないのだろう。
ヴォックス・クラマンティスの優しく清澄な響きと滑らかな歌いまわしによって生まれる歌の世界は、グレゴリオ聖歌では、単旋律の持つ豊かな表現力に未来への可能性を感じさせてくれ、多声部の現代の作品が、逆に人の心の根源的なものに立ち返らせる力を持っていることを教えてくれた。そして、時代を越えて共鳴し、人の心に届くものがあることを教えてくれた。
 “20世紀パリ:音楽の冒険(Cプロ)”
“20世紀パリ:音楽の冒険(Cプロ)”スザンナ・マルッキ指揮 アンサンブル・アンテルコンタンポラン
ホールC(プルースト)
【曲目】
1.ブーレーズ/デリーヴ1(6つの器楽のための)

2. ドビュッシー/フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ

3. ミュライユ/セレンディブ(22人の音楽家のための)


ブーレーズが設立し、常に現代音楽の最先端を歩んでいるアンサンブル・アンテルコンタンポランが、LFJに出演するために18年ぶりに来日した。今回のLFJはこれを聴けるだけで価値がある。
このアンサンブルの設立者ブーレーズの作品は、6つの楽器が織り成す響きの世界。それぞれの楽器からふわっと放たれ、空中を漂う音たちを、空気をつかむように両手でそっとつかみ取り、そこで心地よさそうに戯れている音たちを眺めているような感覚。各奏者の奏でる研ぎ澄まされた音同志が、アンサンブルとしてこのように調和するところがさすが。
続くドビュッシーも、ふわりと放たれる音の表情のニュアンスが素晴らしい。3色の水彩絵具が、水に溶けていって、水のなかで色が交ざったかと思うと、またそれぞれの色が現れる美しいマジックを見ているよう。なかなかこれほどの演奏に出逢えることはない。
ミュライユの「セレンディブ」は22人のメンバーが登場して室内オーケストラ並みの編成に。もしかして総出演?ちょった得した気分になったが、曲も演奏も素晴らしかった。オーケストラのプレイヤーがみんなソロをやっているかのようにオケの音が多彩な極彩色に輝き、光輝く森の中で呼び交わす無数の野鳥の声を聴いているよう。これぞ音の饗宴!カンジンスキーの音楽をモチーフにした絵画が目に浮かぶ。演奏は、複雑で速いモチーフもピタリと合わせ(ているように聴こえる)、実に鮮やかでエキサイティング。ミュライユの音楽はこれまで殆ど意識していなかったが、いろいろ聴いてみたくなった。でもこんな気分を味わえるのもEICの演奏あればこそかも。
 仲道郁代&アンヌ・ケフェレック
仲道郁代&アンヌ・ケフェレックよみうりホール(ロルカ)
【曲目】
♪ドビュッシー/「子供の領分」~グラドゥス・アド・パルナッスム博士、人形のセレナーデ、ゴリウォーグのケークウォーク
♪ドビュッシー/前奏曲集第1巻~アナカプリの丘
♪ドビュッシー/喜びの島


Pf:仲道郁代
♪ラヴェル/「鏡」~蛾、悲しげな鳥たち、海原の小舟

Pf:アンヌ・ケフェレック
♪ラヴェル/「マ・メール・ロワ」~眠れる森の美女のパヴァーヌ、美女と野獣の対話、妖精の園
Pf:アンヌ・ケフェレック&仲道郁代
今回のLFJで唯一親子3人で聴くコンサートをこれにしたのは、2月に息子と発表会で連弾した曲が入っているフォーレの「ドリー」をやるから。それなのに来てみたら、「ドリー」ももうひとつ発表されていた「小組曲」もやらず、おまけにそれぞれのソロのステージがデュオを押しやって、デュオは「マ・メール・ロア」から3曲だけ。仲道さんもケフェレックも、もちろんソロは素晴らしいが、今日はデュオを楽しみにしていたのでとても残念。
とは言え、演奏のほうはどれもよかった。仲道さんのピアノは柔軟で自然。ドビュッシーの曲の、モチーフやディナミークやリズムなどで現れるいろいろなアイディアが、完全に自分の中で消化され、熟成されて浮かび上がってくる。作為的なものが微塵もなく、音楽のなかで自分の居場所を見つけて輝いていた。「喜びの島」は半年前にも聴いたが、小柄な仲道さんが大きな翼を広げて大空へ羽ばたくようなスケールは素晴らしい。
ケフェレックの「鏡」は、硬質で透明感のあるラヴェルのピアノ音楽の特徴がよく出ていた。また、暗闇の中でスポットライトを浴びているような モノローグ的な語りかけの妙もケフェレックならではの世界。
二人の連弾では、終曲の終盤の盛り上がりが、伸び伸びとしてかつダイナミックにスウィングして心を揺さぶったが、これで終わりではやっぱり物足りない。せめてアンコールで最初に発表していた曲から何かやってくれるかと思ったが、何もなかった。。
 “聖なるパリ”
“聖なるパリ”ミシェル・コルボ指揮 ローザンヌ声楽アンサンブル/ローザンヌ器楽アンサンブル
S:アンヌ・モンタンドン/MS:セシル・マシュー/T:マティアス・ロイサー/Bar:ジャン=リュック・ウォーブル
ホールC(プルースト)
【曲目】
1.デュリュフレ/グレゴリオ聖歌による4つのモテット Op.10

2.グノー/レクイエム ハ長調(1893年版)
【アンコール】
♪?
コルボが3年ぶりにLFJに帰ってきた!これまでコルボの指揮で何度忘れ得ぬ幸せな体験をしてきたことか。今回はオケ、合唱ともにコルボ長年の主兵であるローザンヌのアンサンブルを率いての公演。フォーレのレクイエムはもちろん素晴らしいだろうが、今回は新たな発見と感動を味わうために、聴いたことがなかったグノーのレクイエムの公演を選んだ。グノーのミサ・ソレムニスは歌に溢れた甘美な名作なので、レクイエムも大いに期待した。
まずはアカペラで演奏したデュリュフレのモテット。これまでに体験したコルボの演奏の感動が甦る、デリケートで瑞々しい合唱にうっとり。天上の世界はこういうところに違いないと思うような清らかで平安に満ちた世界が目の前に広がった。
そしていよいよグノーのレクイエム。オケ付きとはいっても弦楽五重奏にポジティブオルガンが入るごく簡素な器楽伴奏で歌われたレクイエムは、期待に反して退屈な音楽だった。グノーが最晩年の75歳で書いたこのレクイエムは、ミサソレムニスで施されていた装飾的なものは一切排されているだけでなく、瑞々しさや活力も失われ、かといって死の悲しみや畏れがひしひしと伝わってくるわけでもない。現世を超越した天上界での安息を音楽で表現したと言えばそうなのかも知れないが、フォーレのレクイエムのような清澄で心が洗われる世界を感じるわけでもなく、振幅の少ない単調なフレーズとハーモニーの連続では、せっかくの演奏も魅力を発揮できず仕舞いだった。オケも付け足しのようなことしかやらず、なんとももどかしい。
グノーも老境に至って楽想が枯れてしまったとしか思えない音楽に、やっぱりフォーレクにしておけばよかったと後悔が。でも会場は楽員が引き上げたあともコルボを呼び出す拍手とブラボーが続き、出口に歩く途中、後ろを歩いていた人は「75歳の老人が書いた音楽だなんて考えられない」と絶賛していた。感じ方は人それぞれとはこのこと。コルボが選んだ曲だろうし、感動できるに越したことはないのだが…
 “20世紀パリ:音楽の冒険(Dプロ)”
“20世紀パリ:音楽の冒険(Dプロ)”アンサンブル・アンテルコンタンポラン
Vn:ジャン=マリー・コンケル/Fl:ソフィー・シェリエ/Ob:ディディエ・パトー/Cl:ジェローム・コンテ/Pf:永野英樹
ホールG409(アポリネール)
【曲目】
1.プーランク/オーボエ・ソナタ
2. ブーレーズ/フルート・ソナチネ


3. マヌリ/ミシガン・トリオ(クラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための)


アンサンブル・アンテルコンタンポランの2度目のコンサート。最初のプーランクは表情に乏しく物足りない。プーランクはもっと楽しげな気分が欲しい。それに、せっかくEICが来たのだから、プーランクみたいな「マトモ」な音楽ではなく、もっとハチャメチャな曲をやってほしい。この期待に応えてくれたのがそのあとの2曲。
フルート・ソナチネは、ブーレーズ初期の意欲的な作品。ハチャメチャではなくきちんとした構成感のある曲だが、その中身は激しく挑戦的。フラッターを多用したフルートはあらゆる方向に放射していき、ピアノと手に汗握るアクロバットを展開する。プーランクでは大人しくオーボエに従っていたピアノの永野英樹が、ここでは水を得た魚のごとくピチピチと跳ね回り、シェリエの機関銃のように撃ち込んでくるアグレッシブなフルートとの綱渡り的な白熱のやり取りに、前衛音楽全盛期の気概がガンガン伝わってきた。
続くマヌリの曲がまた凄かった。ピアノの反響板の下に譜面が置かれ、何が始まるのかと思ったら、クラリネットがビアノの内部に向かって吹き、弦に音を共鳴させた。この曲はビアノの内部の共鳴音を巧みに用い、クラ、ヴァイオリン、ピアノが連係して不思議な響きを作っていく。この特徴ある響きを活かして、3人が繰り広げるバトルは何が起きるか一時も目を離せないほどスリリングでエキサイティング。その集中力は焦げ臭さを感じるほどで、これぞEICここにあり、という演奏で圧倒した。久々に骨のある現代曲を堪能した。
現代曲というのはやはりこうした優れた演奏があってこそ真価が発揮されるものが多いし、音がまさに生まれ出る場に立ち合えるライブで体験するのが何よりと実感。
 Vn:オーギュスタン・デュメイ/Pf:児玉桃
Vn:オーギュスタン・デュメイ/Pf:児玉桃ホールB7(ヴェルレーヌ)
【曲目】
1.ドビュッシー/ヴァイオリン・ソナタ


2. フランク/ヴァイオリン・ソナタ イ長調



大幅な縮小開催となった震災の年も来てくれたデュメイは、LFJには欠かせない顔だ。今回は児玉桃をピアニストに迎えてソナタを2曲。児玉桃のピアノは実にデリケート。スタインウェイのピアノからプレイエルのような繊細で柔らかな音色を引き出す。陰影に富んだ表情はいつもどことなく洒落ていてデュメイと大人の会話を楽しんでいる雰囲気。
デュメイのヴァイオリンは変わらずに脂が乗り、充実の極みを聴かせた。デュメイは、自分が手掛ける作品を完全に自家薬籠中のものとして聴かせる。その演奏は、まさしく音楽に命を吹き込む行為に他ならないということを有無を言わせず納得させる。デュメイの手で音楽が鼓動を始め、血液が駆け巡り、熱く脈を打つ。音楽の中に蓄えられたエネルギーが、あるときは穏やかに滲み出し、またあるときは熱く烈しく噴き上げてくる。
音楽の強弱、緩急、濃淡といったものの意味を的確に見極め、ここにどのくらいのエネルギーをどのくらいの勢いでつぎ込むかを迷うことなく鮮やかに実演してみせる。甘いささやきから、朗々とした詠唱、ここぞというときの全エネルギーが一点に注ぎ込まれて勢いよく放たれる叫びまで、音楽はデュメイの心のままに全身全霊で命の営みを繰り広げる。その姿にはただ感服するのみ。
ドビュッシーの変化に富んだ曲想のすべてがその意味を明らかにし、循環形式で書かれたフランクのソナタの各部が、どんな役割を持ち、他の部分とどう関わっているかが、理屈抜きで伝わってくる。どんな時も全身で語りかけ、体当たりしてくるデュメイのヴァイオリンにただ身を任せ、感動に導かれた。
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2012
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2011
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2010
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2009



















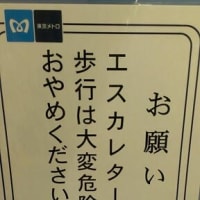






お聴きになられたプログラム、羨ましい限りです。特に、アンテルコンポランタンが。
ところでpocknさん、「春琴抄」観る予定あります?