各地の教育委員会は、4月からの制度移行に向けて首長の教育権限を強める新教育制度改革を具体化し始めています。これからの2ヶ月が教育の独立性と自立性を守り抜くための重要な局面を迎えます。2014年6月、通常国会で首長の教育行政への介入を強化する「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され(以下、「改正法」)、戦後一貫して教育の独立性を重視してきた教育委員会制度が根本的に改悪されました。他方では、法案審議の過程で首長の教育権限を強めることに教育関係者や世論から強い危惧が表明されました。そこで教育委員会は執行機関として存続し、その職務権限もかろうじて変更されませんでした。教育の独立性との関わりで首長の教育権限をどこまで抑制することができるか、これからの運動にかかっています。
教育委員会で始まってる新教育委員会制度の具体化~首長の教育介入を進める3つの危険性~
◆首長が策定する教育施策の「大綱」(教育目標)を通じた政治介入
「改正法」では、首長に対して教育予算の編成権に加えて、新たに教育施策の目標や根本となる方針についての「大綱」を決定する権限を与えました。このことによって首長は、教育目標や方針を通じて教育行政全体に絶大な影響力を持つことが考えられます。「改正法」は、「大綱」に記載する内容を「地方公共団体の長の有する権限に係る事項」(文科省通知)とし、首長の職務権限を越えた内容にまで踏み込んではならないと一定の歯止めを設けはしました。しかし、最終的に何を「大綱」に記載するかは、各自治体の判断となっており、今後「大綱」への記載事項が拡大解釈され首長がより深く教育政策に介入する危険性があります。
◆首長が主宰する「総合教育会議」を通じた政治介入
「改正法」では、新たに首長が「総合教育会議」を主宰することになりました。これまでは教育施策を審議する場は教育委員会であり、そこに首長が直接介入しないことで教育行政の独立性がどうにか保たれてきました。「改正法」では、「総合教育会議」について「首長及び教育委員会は相互の役割・権限を尊重しつつ、十分に協議を行い、調整を図ること」と附帯決議を付けたが、「総合教育会議」に関してほとんど具体的な規定がないため、首長が教育要求を教育委員会に押しつける場となる可能性があります。「総合教育会議」の協議題から教育委員会の権限事項を明確に外すように要求することが重要です。
◆首長が「新教育長」を任免する権限を握ることを通じた政治介入
これまでは、事務局の責任者である教育長と教育委員会のまとめ役である教育委員長は教育委員による互選で選ばれてきました。しかし、「改正法」では、教育長と教育委員長の果たしてきた役割を「新教育長」に統合し、教育施策の提案から審議、決定、執行に至るまで大きな権限を与えています。首長は、その「新教育長」を直接任命し罷免できることにより、教育委員会に大きな影響力を行使する危険性が強まります。首長-「新教育長」を通じた教育支配がいかに危険かは、松井大阪府知事-中原教育長による大阪府の教育を見れば一目瞭然です。
総合教育会議を先取りして市長の政治介入が進む大阪市
2014年度から大阪市では、教育条例を根拠として「市長と教育委員との協議」が開催されています。今年度すでに5回協議が行われており、特定の子どもを学校から排除する「個別指導教室」、職員会議と校内人事での校長権限強化、部活の外部委託、「平成27年度教育施策・予算の基本方針」など、市長の職務権限をはるかに超えた内容の協議が行われています。「市長と教育委員との協議」は事実上の決定機関として機能しており、教育委員会議は形式的な承認機関と化しています。
昨年11月の「市長と教育委員の協議」では、橋下市長と大森教育委員長の意向により、4月からの総合教育会議で校長の人事異動方針、教員の人事異動方針、教職員評価・育成システムの評価分布や運用のあり方まで協議することを決めました。新教育委員会制度の枠組みさえ踏みこえる政治介入の制度化です。橋下市長は、教員評価育成システムの下位評価が少ないことを批判し、「組織の人事評価としては全然機能していない。」「教員評価システムについて、この(市長と教育委員との)協議や総合教育会議の中で、人事室もフル回転させて対応する。」と宣言したのでした。
4月までが最初の正念場!教育行政への首長の介入に反対する声を!
首長の教育権限の強化は、今年の中学校教科書採択に重大な影響を与えます。首長が直接、教科書採択方針に介入できるだけでなく、首長が策定する「大綱」がそのまま教科書採択方針、教科書調査研究の観点にスライドする危険性もあります。首長に任命された絶大な権限を持つ「新教育長」が首長の意向を反映して教科書採択を行う危険性も十分にあります。
「つくる会」系グループは、首長に対して「大綱」に教科書採択方針を書き込ませること、教育委員に対して「大綱」に沿って教科書採択を行うことを働きかけています。2014年6月には安倍政権のバックアップのもとで教育再生首長会議が結成され、現在82名の首長が参加して首長の権限強化に向けて連携を強めています。首長の政治介入に反対する取り組みは、まさに2015年中学校教科書闘争の前哨戦です。各地の教育委員会に対して首長の教育権限強化に反対の声を届けましょう。全国の最先頭をきって首長の介入を強める大阪市に対して批判を集中しましょう。
教育委員会で始まってる新教育委員会制度の具体化~首長の教育介入を進める3つの危険性~
◆首長が策定する教育施策の「大綱」(教育目標)を通じた政治介入
「改正法」では、首長に対して教育予算の編成権に加えて、新たに教育施策の目標や根本となる方針についての「大綱」を決定する権限を与えました。このことによって首長は、教育目標や方針を通じて教育行政全体に絶大な影響力を持つことが考えられます。「改正法」は、「大綱」に記載する内容を「地方公共団体の長の有する権限に係る事項」(文科省通知)とし、首長の職務権限を越えた内容にまで踏み込んではならないと一定の歯止めを設けはしました。しかし、最終的に何を「大綱」に記載するかは、各自治体の判断となっており、今後「大綱」への記載事項が拡大解釈され首長がより深く教育政策に介入する危険性があります。
◆首長が主宰する「総合教育会議」を通じた政治介入
「改正法」では、新たに首長が「総合教育会議」を主宰することになりました。これまでは教育施策を審議する場は教育委員会であり、そこに首長が直接介入しないことで教育行政の独立性がどうにか保たれてきました。「改正法」では、「総合教育会議」について「首長及び教育委員会は相互の役割・権限を尊重しつつ、十分に協議を行い、調整を図ること」と附帯決議を付けたが、「総合教育会議」に関してほとんど具体的な規定がないため、首長が教育要求を教育委員会に押しつける場となる可能性があります。「総合教育会議」の協議題から教育委員会の権限事項を明確に外すように要求することが重要です。
◆首長が「新教育長」を任免する権限を握ることを通じた政治介入
これまでは、事務局の責任者である教育長と教育委員会のまとめ役である教育委員長は教育委員による互選で選ばれてきました。しかし、「改正法」では、教育長と教育委員長の果たしてきた役割を「新教育長」に統合し、教育施策の提案から審議、決定、執行に至るまで大きな権限を与えています。首長は、その「新教育長」を直接任命し罷免できることにより、教育委員会に大きな影響力を行使する危険性が強まります。首長-「新教育長」を通じた教育支配がいかに危険かは、松井大阪府知事-中原教育長による大阪府の教育を見れば一目瞭然です。
総合教育会議を先取りして市長の政治介入が進む大阪市
2014年度から大阪市では、教育条例を根拠として「市長と教育委員との協議」が開催されています。今年度すでに5回協議が行われており、特定の子どもを学校から排除する「個別指導教室」、職員会議と校内人事での校長権限強化、部活の外部委託、「平成27年度教育施策・予算の基本方針」など、市長の職務権限をはるかに超えた内容の協議が行われています。「市長と教育委員との協議」は事実上の決定機関として機能しており、教育委員会議は形式的な承認機関と化しています。
昨年11月の「市長と教育委員の協議」では、橋下市長と大森教育委員長の意向により、4月からの総合教育会議で校長の人事異動方針、教員の人事異動方針、教職員評価・育成システムの評価分布や運用のあり方まで協議することを決めました。新教育委員会制度の枠組みさえ踏みこえる政治介入の制度化です。橋下市長は、教員評価育成システムの下位評価が少ないことを批判し、「組織の人事評価としては全然機能していない。」「教員評価システムについて、この(市長と教育委員との)協議や総合教育会議の中で、人事室もフル回転させて対応する。」と宣言したのでした。
4月までが最初の正念場!教育行政への首長の介入に反対する声を!
首長の教育権限の強化は、今年の中学校教科書採択に重大な影響を与えます。首長が直接、教科書採択方針に介入できるだけでなく、首長が策定する「大綱」がそのまま教科書採択方針、教科書調査研究の観点にスライドする危険性もあります。首長に任命された絶大な権限を持つ「新教育長」が首長の意向を反映して教科書採択を行う危険性も十分にあります。
「つくる会」系グループは、首長に対して「大綱」に教科書採択方針を書き込ませること、教育委員に対して「大綱」に沿って教科書採択を行うことを働きかけています。2014年6月には安倍政権のバックアップのもとで教育再生首長会議が結成され、現在82名の首長が参加して首長の権限強化に向けて連携を強めています。首長の政治介入に反対する取り組みは、まさに2015年中学校教科書闘争の前哨戦です。各地の教育委員会に対して首長の教育権限強化に反対の声を届けましょう。全国の最先頭をきって首長の介入を強める大阪市に対して批判を集中しましょう。










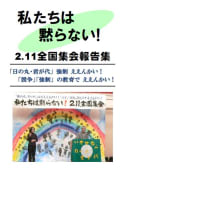
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます