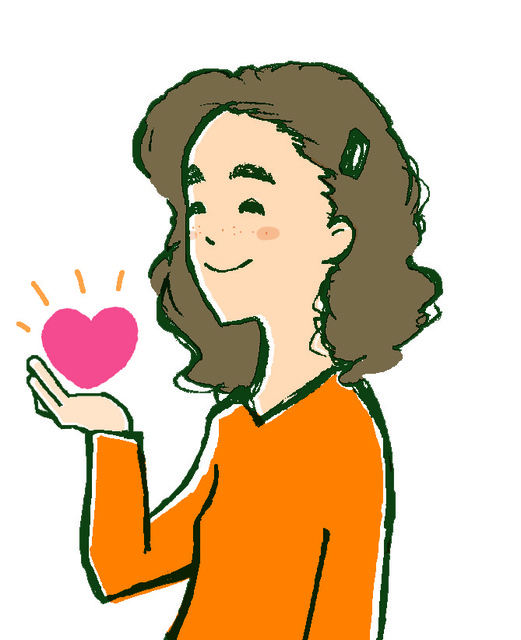■自由の哲学14章01~02段落
「すべての人は、自由になる素質を備えている」。
そう言う時、次のような反論が予想される。
人は人種や家族、男女など、
さまざまな自然発生的な集団の一人として生きており、
国や教会や会社などの集団の中で働く。
人は自分の属する集団の性質を帯びているし、
自分の行動もその集団の中での立ち位置によって決まる。
それでも、「一人であること」
=自由であること、がで . . . 本文を読む
調和のとれた成熟した人は、自分の値を自分で決める。
自然や神から快を受け取ろうと努力するのでもない。
禁欲生活に入って外の正しさを義務として果たすのでもない。
ただ、自分のしたいようにする。
その人自身の精神の悟りに基づいて。
その人がしたいことを実現していくことが、
その人の生き甲斐になり、
生きることを心底楽しいと感じる。
その人の欲と実現との関係が、その人の人生の値を決める。
自分の欲の . . . 本文を読む
こう述べると、誤解されやすいだろう。
調和のとれた人ではなく、中途半端な人は、
自分のやりたいことが人のすべてだ、と見なしがちだ。
自分が認めない考えはすべてはねつけて、
自分の思い通りに行動したがるだろう。
調和のとれた人について語った50段落までのことが、
成長途中の中途半端な人には
当てはまらないのは明らかだろう。
自分の高い欲が、
低い欲の殻を破って出てくるまでの人に
調和のとれた . . . 本文を読む
■自由の哲学13章50段落
悲観論的な倫理学では、
「人の精神には理想を仕立てる力がない」という前提で、
快を感じるために人は欲するのだ、と決める。
自分で理想を思い描けない人は、
人から与えてもらわなければならない。
また、おなかがすいたの暑いの寒いのという
低次元の欲は、物理的な自然が満たしてくれる。
しかし、人がまるごとで求めるものには、
精神的な欲求も含まれている。
それを知らないか . . . 本文を読む
人が欲を満たすことを快と思うのは、
欲が人間から出てくるものだからだ。
そして、欲を実現することに値打ちがあるのは、
自分がそれを欲したからだ。
人の欲することに値打ちがないというなら、
値打ちのあるものを、
人が欲しないところから、
もらってこないといけなくなる。
※
う~む、なんか人をバカにした話です。
「アンタの望んでること、値打ちないから
代わりにこれやっときなさい」
って人が教え . . . 本文を読む
「自分の欲を求めてはいけない」と言う者は、
まず、人を奴隷にしなければならない。
「したいからする」人ではなく、
「命令されるからする」人に。
そもそも、欲を満たすことは喜びだ。
「善」とは、誰かに言われてしなきゃいけない事ではなく、
自分が本当の自分になりゆきつつ、
そうしたいと思うことが善になる。
それを認めない者は、
まず、人の欲をその人の中から叩き出して、
これを欲するべきだ、これが善 . . . 本文を読む
尊く、大いなる理想に向かって努力する者は、
それが、その人の中にあるからだ。
その人の中にあるものを外の世界で実現していくのは、
その人の楽しみなのだ。
その楽しみに比べたら、
日常のアレコレの快を、その時の気分で満たすなんてことは、
小さなことだ。
理想主義者たちは、理想を現実にしながら、
精神的な贅沢を味っている。
※
とばしてますね~。
もうすぐこの章も終わりです。
ここはわかりやすい . . . 本文を読む
人が行為する時、理想的なのは
「道徳のファンタジー」から行動することだ。
「道徳のファンタジー」を実現するには、
その人に、
苦しみや痛みを乗り越えるほど強い欲求があるか
にかかっている。
それは、人が高いところから悟ったものであり、
人の精神のピンとした張りつめである。
人は、それを実現したいと思うものだ。
なぜなら、それこそ人がもっとも素晴らしいと感じるからだ。
倫理が人に「欲を無くしな . . . 本文を読む
ここからはトークショーをお届けします。
悲観論者:
「快を求めるな。快なんてものにはありつけない。
一人ひとり自分の課題の実現に向けて努力しろ」。
シュタイナー:
「人って、もともと、誰かに強制されなくても
自分の課題を実現しようと努力するものじゃないですか?
人が利己的に自分のシアワセばっかり求めてる、
なんてのは、哲学者が勝手に言ってるだけでしょう?」。
悲観論者:
「いや、快なんて求 . . . 本文を読む
悲観論者は「いくら快を求めても不快の方がもっと大きいんだから、
自分の欲なんか捨てて、みんなの幸せに尽くしなさい」と言うが、
人は、自分のやりたいこと=目標、に向かう時、
別に、快や不快の大きさなんかに左右されない
ということを忘れている。
人は、あらゆる困難を乗り越えてなお、やりたいと思う。
その充実感を求めて動く。
その「やりたい」という気持ちが、人の行動を決める。
人一人の仕事も、文化への . . . 本文を読む
(前半=
「快と不快のどっちが多いかなんて計算できない」
と言って、悲観論者を論破してみる人もいるけど、
快と不快、どちらが大きいかは、実感としてわかる。)
ただ、その結果から、
「何かをしたい時に、人は快と不快の大きさで決める」
と言うのは間違いだ。
私たちが何をしようかと決める前に、
「快・不快どっちが大きいかな」と思い巡らせるのは、
結局、どうでもいい時だけだ。
仕事の後、軽く息抜きを . . . 本文を読む
悲観論を論破しようとした側は
「快と不快のどっちが多いかなんて計算できない」
と言ってきた。
「どっちが多いか計算できる」というからには、
互いに同じ土俵で比べられるということだ。
さて、どんな快・不快にもそれなりに
決まった大きさや強さがある。
きっちり数字でどのくらいとは言えないにしても、
「おいしい料理」や「イケてるジョーク」が
快であること、楽しいことを知っている。
それぞれの快・ . . . 本文を読む
悲観論の人が言うように、
世界は快よりも不快が多かったとしても、
それが、私たちが欲を持つことに何も影響はない。
生き物は、快感を求めるだろうから。
苦しみが喜びより大きい、と
実験か何かで裏付けられたとしても、
そのことは、
「快の方が大きいから人生は生きるに値する」という
幸福論の人をお先真っ暗にするには役立つだろうけど、
欲を持つことが非理性的だと言うには役立たない。
そもそも、欲が繰り . . . 本文を読む
欲を満たすことで招く快と不快について
理性的な哲学がどう言おうと、
生きることにおいては、次のように言える。
たとえば、りんごをいくつか買おうとしている時。
もう店をしまいたい店主が
「安くしとくからこっちも一緒に持っていってくれ」、
と、悪いりんごを2倍ほど押しつけようとする。
私は、良いリンゴの値段に加えて
悪いりんごを持っていく労力を見積もって、
安いと思えたら、悪いりんごも喜んで持って . . . 本文を読む
■自由の哲学13章41段落_1
40段落で言ったことが正しいということは、
次のことからもわかる。
快の値は、棚からボタ餅的に得た時よりも、
苦労して得た時の方が大きい。
「もうこんなにしんどいんだったら止める」と、
欲がどんどん減っていきながらも、
なんとか続けてみてやっと得られた時は、
かろうじて残っていた欲との比で見るから
快の値はとても大きくなる。
また、次のことからもわかる。
. . . 本文を読む