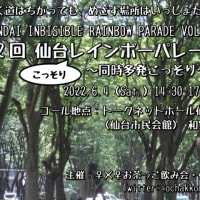2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催した参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」。
展示企画のひとつとして実施したのが「ご意見募集!フセンでコメント」。
パートナー制度について、事前にSNS等で寄せられた意見をホワイトボードに展示したほか、来場者にもその場で意見を書いてもらい、あわせ展示しました。当日展示した意見全60件をご紹介します!
今回の企画に先立ち2021年(令和3年)2-3月にインターネット上で実施した意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」に寄せられた意見もあわせご覧ください!
<男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」「ご意見募集!フセンでコメント」展示意見一覧(全60件、順不同)>
・法律婚できない代わりに養子縁組してるカップルやポリアモリーを「公序良俗に反する」とか言って蔑視し切り捨てるのダメ絶対。
・異性婚者から一言
当時大使館がなく配偶者ビザを取るため双方の国で婚姻届が必要で、渡航費翻訳費諸々で100万はかかった。現在帰化申請中で、まだ家内は戸籍に入っていない。
異性婚は紙っぺら一枚でタダ。はウソ。
社会的信用が欲しいなら責任がついて回るのです。
・「法的効力がなく、自分にとってメリットがなく、アウティングのデメリットがある」
から申請しなかった場合。
「制度を使ってないから、あなたたちの関係は本物ではない。真剣ではない」
と見なされるかもしれない点。
例えば「市営住宅への入居可」という「特典」などは、市営住宅に入りたくない人にとってはメリットでも何でもない。
デメリットのアウティングとは。
申請すれば、担当課の人にばれます。利用者名簿が保存されるはずなので、異動の度毎にバレる人が増える。
利用者が公務員なら、同じ職場の人です。
職場で、ゲイを笑うような会話がなされてるような自治体でも(最近は「あ、LGBT差別ダメだった、ハハハ」と最後に付く)
そんな制度を使ってないからといって、
「制度があるのに使わないことを選択している。だからあなたたちは真剣ではないのだ」
などと見なされるなら、制度がないほうがましだといえます。
・たとえ意味の無いパートナーシップ制度でも、使いたくない当事者は使わなければいいだけ、と言われるかもしれないが。
それでは済まない面もある。
意味の無い施策が、現代的レイシズムにも繋がるひとつの原因になる、という点です。
つまりは、マジョリティから見れば、
パートナーシップ含む様々な施策はLGBTの人に有用なのだろう、と見える。
それなのに、当事者は、せっかく作ってあげたその制度を使いもしなければ、文句ばかり言っている。
こんなに税金を使って多くの施策をしてるのに、LGBTはわがままで自分勝手だ、と見える。
実際には、
法的効果がないパートナーシップ制度、
根拠の無い知識を正しいとする啓発、
有害でしかないレインボートイレ、
どれも当事者には何の役にもたっていないのに。
得するのは、良いことしてますアピールできる自治体と、委託された団体や業者。
そして被害を受けるのは当事者。
・例えば、パートナー制度絡みでよく「パートナー証明ないと病院で家族扱いしてもらえなくて云々」みたいな話出てきますが、そんなことないですからね。
例えば仙台市立病院。「市立病院におきましては、同性パートナーとの関係を確認し、妥当と判断した場合に診療情報の提供を行うこととしております。」って、仙台市議会平成29年第4回定例会で明言されてます。証明書なんかなくたってこういう取り組みちゃんと進んでるんです。
差別的な対応する施設も、もちろん皆無ではないだろうけど、でもそれはパートナー証明の有無とは無関係に改善されるべきもの。パートナー証明の有無で利用できるサービスに差がつけられてしまうことは、あってはならないことだと思います。
パートナー制度ができたとしても、いろんな事情で制度を使えないカップルだっている。そんな状況で「同性カップル?じゃあパートナー証明持ってきてください!え?ない?じゃあ認められません!」なんて話になって、これまで利用できてたサービスから門前払いされるようになったりしたら、本末転倒なわけです。
パートナー証明もらうことで、「説明がラクになる」というメリットはあるだろうし、全く無意味だとは言いません。でも、パートナー制度推進運動の中で、パートナー証明なくたってすでに可能になってることがあたかもパートナー証明がないと不可能であるかのように宣伝されちゃってる例が見受けられるのは、非常にマズいと思っています。
制度推進するならなおさら、「アレもコレもパートナー証明なくたって利用OKです!いろいろ事情あってパートナー証明もらえない人たちもだから安心してください!」ってしっかりアナウンスする必要あると思います。
・“婚姻相当”などと言いながら現代日本の婚姻制度のキモである「貞操義務」「セックスに応じる義務」には触れずスルーするパートナー制度など欺瞞である。
・よく同性婚やパートナー制度絡みで「愛し合う2人を認めて!」みたいな言説見かけますが、そもそも現代日本の婚姻システムに愛って関係ないですよね。「愛を公的に認めてもらう手段=婚姻orパートナー制度」というのは筋違いなのでは。
そもそも「愛=素晴らしいもの、だから承認されて当然」みたいな恋愛至上主義的思想は人権や平等を謳うスタンスとは相容れないというか。単身者や非モテの蔑視に繋がるし。
「愛=素晴らしい」と無批判に持て囃す姿勢は愛の名のもとに振るわれる暴力の誘発・肯定に繋がりかねない。DVとか虐待とか性暴力とか、愛の名のもとに行われているケースのなんと多いことか。
人権や平等のためにパートナー制度というなら、そういった面にも徹底した配慮が必要ではないでしょうか。
・一部の同性婚法制化推進派が「愛し合ってるんだから良いじゃないか!」などと言っていたりするが冗談じゃない。「愛」を言い訳に自説を正当化する行為は「愛」の名のもとに振るわれる暴力まで正当化しかねない。
愛してるから殴っていい。
愛してるから犯していい。
愛してるから、
冗談じゃない。
・結局、「結婚=愛の承認」みたいな誤解が生まれがちなのって、日本人のほとんどが婚姻制度家族制度についてちゃんと教わっていない、学んでいないからではないでしょうか。子供はもちろん、大人だってろくに知らない。知らないまま結婚して、後でトラブルになったりしている。同性婚だパートナー制度だ云々言う前にまずは「現代日本における婚姻とは何か」しっかり知る必要があると思います。
・パートナー制度といえば、最近では兵庫県明石市等が導入している子供を巻き込んだいわゆる「ファミリーシップ制度」が話題ですが、明石市の要綱見て気になるのが「子供に拒否権がない」こと。
子供のためと言いながら、正直子供が蔑ろにされてる風に感じてしまいます。
日常生活でパートナーの子供との関係性を具体的に示したいってことなら、子供の親と2者間でのパートナー証明だけでも対応可能なのでは?拒否権奪ってまで子供をムリヤリ巻き込まなきゃならないんでしょうか?子供巻き込むならもっと丁寧にやっていただきたいと思います。
・もう6年も前の話なので、10代20代の若い人や最近興味持った人は知らないかもしれませんが、例えばパートナー制度第1号自治体のひとつである渋谷区では制度導入過程の問題点がいろいろ指摘されてました。「良いことやってるんだから大目に見てあげようよ!」で済む話ではありません。人権のため、平等のため、差別解消のためと言うならばこそ、なおさらきちんとやらないといけない。
ブーム化したパートナー制度に関しては全国各地でヒトモノカネがいろいろ動くようになってます。ブラックボックスの中でよく分からないまま制度がつくられるようなことはあってはならないと思います。制度制定過程や運用過程で不正があってはかえって差別偏見が助長されてしまいます。徹底した情報公開としっかりした議論が必要だと思います。
・東日本大震災関連では被災者支援NPO法人の公金横領事件があって警察沙汰にまでなっていたりする。「自分達は正しい」「自分達のやっていることは良いことだ」「目的のためなら手段は正当化される」なんて思い込んで、やって良いことと悪いことの区別がつかなくなってはマズい。
・LGBTブームが女性の人権をむしり取るような風潮、公的機関までがそれを助長するような風潮が昨今感じられなくもないのも非常に気になっているところです。
女性の人権、男女平等ないがしろにしてLGBTだけ生きやすくなるとかあり得ない。男女差別や男女格差にもしっかりと目を向けること。目を背けないこと。絶対に外してはならない視点です。
・他の方も指摘してらっしゃるけど、うちんとこは導入したはいいものの、はっきりと「二人のうちどちらかがセクマイであること」が条件なんですよね。別姓希望や友人同士には開かれていないのはどうなんだろうと思います
・パートナー制度、法律婚できない代わりに養子縁組したカップルについては、すでに制度利用を明確に認めている自治体が複数あるので、これからはコレが主流になっていくのかなあと思っています。
社会承認的な意味で自治体パートナー証明もらいつつ養子縁組も併用して法律的な保障も得る、というのが現状一番お金もテマヒマもかからず同性パートナーとの関係を安定させる方法ではないでしょうか。「公序良俗に反する」等の蔑視的な言葉を使わないのは当然として、さらに踏み込んでパートナー制度の枠組みの中で養子縁組の活用法なんかも積極的にアピールしてもらうのもアリなんじゃないかなあ。
・「直系姻族間の婚姻禁止規定」についてももっと議論して欲しいなと。「姑と婿(あるいは舅と嫁)は一生結婚できない」なんておかしくない?
要するに「配偶者の親は実の親と一緒」って価値観なんだろうけどイマドキそれってどうよ。それでいて相続権はないし。
こういう「現行家族制度婚姻制度のおかしさ」を揺さぶる議論、パートナー制度をきっかけにガンガンやったら良いと思います。LGBTセクマイだけじゃない、すべての人が当事者。
・しかしなんだかんだ言って“第1号”っていうのはやっぱり大変ですよね。前例も何もない中でイチから築き上げなきゃならない。第1号の渋谷や世田谷は、それは問題もすごく大きかったし、制度も穴だらけだったけど、でもやっぱり、すごかったんだなあと思います。
そういう意味では、後続組はラクができる。でも、だからこそ、先達の良いところも悪いところもしっかり学んで、より良い制度にしていかなきゃいけない。それは後続組の責任でしょう。自分のところの自治体でも!と言うなら、自治体の担当者の方には、既存の要綱とか条例とかあるだけ全部チェックして、入念に分析していただきたいです。単なるコピペのまねっこじゃしょうがない。
・パートナー制度、同性カップルだけでなく男女の事実婚カップルも使えるようにしている自治体が複数出てきているので、今後はコレが主流になっていくのかなと思っています。
大半のLGBTは「LGBTのための特別な制度」を求めているわけじゃないと思うんですよね。平等言うなら、異性カップルも同性カップルもまったく同じように使える制度の方が良くないですか?
もちろん「そもそも本丸の法律婚が同性カップルを排除してるじゃないか!」というのはその通りです。でも、だからって、それの向こうを張ってパートナー制度を「同性カップル限定」にする必要はないんじゃないか。
法律婚に関しては、今話題の嫡出推定に関する規定など、同性カップルと異性カップルを同等に扱うのには無理があると思われるテーマもあります。でも自治体パートナー制度レベルだったら、そういうのも特にないような気がするし。「LGBTの方々のために特別な制度をつくってさしあげました!」って特別枠でレインボーな証明書もらうより、カップル友達の異性カップルと同性カップルが一緒に同じ証明書もらって、おたがいお祝いする、とかの方が楽しくないですか?
・パートナー要綱お茶っこ試案は「友達同士OK」になっています。これは利用者の幅を広げるためももちろんありますが、「同性カップルがカミングアウトせずに制度利用できるようになる」ことも大きなポイントです。「カップル限定」にしてしまうと「制度利用=同性愛カミングアウト」になってしまう。「友達同士OK」だったらそれが回避できます。
・パートナー制度に限らずですが、セクマイ系施策に取り組もうとしている公的機関の方々にお願いしたいのが、「当事者からこういう意見があったから」というフレーズで責任逃れをしないでいただきたい、ということです。
セクマイ当事者も多様で、ひとりひとりさまざまな意見があります。当事者の意見にしっかりと耳を傾けることはもちろん重要なことですが、自分にとって都合の良い一部の意見だけを取り上げ「だって当事者がこう言ってるから!」などと言い張って施策を正当化するのは、公的機関の責任逃れ、当事者への責任の押しつけです。
典型的なのがいわゆるLGBTトイレ問題でしょう。LGBT当事者の要望で盛んに設置され、そして、LGBT当事者の要望により撤去されました。設置を求めたのも撤去を求めたのも当事者。そんなふうに当事者の意見も分かれているなかで、じゃあ公的機関としてどうするのか。それは様々な要素を踏まえた上で公的機関として責任を持って判断すべきことでしょう。
パートナー制度についても、セクマイ当事者の間でも意見は分かれています。当事者の意見を聞くことはもちろん重要なことで、そこは丁寧にやっていただきたい。多様な当事者の意見に耳を傾けていただきたい。そしてその上で、てんでバラバラな多様な意見を踏まえて、当事者の意見以外の様々な要素も踏まえて、公的機関として、より良いと思われる施策を責任をもって実施していただきたい。そう願います。
セクマイ当事者に多数決取れば良いってものでもないですからね。そもそもクローゼットの多いセクマイ業界で多数決取るなんてのがほぼ不可能だし、それ以前にマイノリティの問題なのに多数決でなんとかしようっていうのが矛盾なわけで。
・私は党派を問わずに同性婚の法整備を求める意見書の採択を求めて陳情を繰り返していますが
そのときに「パートナー制度があるので同性婚は必要ない」という回答を党派を問わずに投げられています
バラ色のように導入される今のパートナー制度は同性婚の法整備の大切さを間違いなく毀損しています
・自治体として“婚姻相当”の同性カップルがしっかり公的・法的保障得られるようにしてあげよう!というなら、実効性のほぼないパートナー証明出すだけでお茶を濁すより、例えば「公正証書作成支援」、渋谷区等が始めたような、公正証書作成費用助成や、無料法律相談などに取り組んだ方が理に適っているのでは。
・実効性のほぼないパートナー証明だけで“婚姻相当”と主張するのはいろいろと無理があるわけで。その程度の手続きで示せるのはせいぜいが“緊急連絡先”レベルといったところではないでしょうか。
もちろん、“緊急連絡先”だってすごく大事です。でも、“婚姻相当”とは違うよね、と。
ていうか“緊急連絡先”だったら別に「1対1限定」「恋愛関係・性愛関係限定」にする必要なんかない。友達同士だって良い。複数人を“緊急連絡先”にしたって良い。性別だって関係ない。
単身者激増の現代日本社会、“ガチの家族”でも“赤の他人”でもない、そのあいだのゆるい人間関係というものが非常に重要になってきていると思います。そういうゆるい人間関係をゆるく証明してあげる、そんな路線のパートナー制度もアリではないでしょうか。意外と現実的だと思います。
・ていうか、実効性のほぼないパートナー制度について「実効性はないが啓発効果がある!」っていう主張、よく聞きますが、啓発のために実際上は役に立たない制度をつくる、っていうのには正直違和感があります。そういうのっていろいろと誤解招くし、制度化するならするでちゃんと実効性のある、役に立つ制度つくった方が良いのではないでしょうか。啓発は啓発で別に取り組んだ方が良いのではないでしょうか。
・恋愛してるからって偉いわけじゃない。セックスしてるからって偉いわけじゃない。恋愛関係や性愛関係を特別視してもてはやすのはやめてほしい。そういう価値観にパートナー制度が加担するのはとても困ります。人権だ平等だ言うなら本当に気をつけて欲しいです。恋愛しない・したくない・できない人もいる。セックスしない・したくない・できない人もいる。優劣をつけるような話じゃない。
・同性パートナー制度に関連して「職場で同性カップルにも結婚祝い金支給!」なんてのもありますが、そもそもなんで職場で婚姻カップルに祝い金出さないといけないのか?なんでそんな風に婚姻カップルを優遇しなければならないのか?平等と言うならそういった根本からしっかり考え直して公平な視点で見直して欲しいものです。
職場の結婚祝い金っていろんなパターンありますが多くの場合、結婚しない人・できない人から取り立てた金を結婚した人・できた人に流しているわけでしょう。それが本当に人権や平等に配慮したとりくみなんですかね?平等と言うなら性別問わず“婚姻特権”の徹底排除が筋ではないでしょうか。
「同性婚カップルにも結婚祝い金支給させることで同性婚カップルが可視化され社会の理解がすすむので戦略として有効!」みたいな価値観もあるようだけどその戦略の下で踏みにじられている存在のことは忘れないでいただきたいなあと思います。
・昨今流行りのパートナー制度、報道では「婚姻相当」なんて言葉が安直に使われちゃってるけど、各自治体の制度の条文具体的に読んでみるとそんな風には読み取れないケースが実際には多いんですよね。
例えば今夏導入の佐賀県。パートナーシップとは「お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した(中略)二人の者の関係をいう」とのこと。
…コレ読んで「婚姻相当」だって思います?
「かけがえのないパートナーであって、相互に協力しあいながら継続的に共同生活を営んでおり、なおかつ夫婦(婚姻カップル)でない」なんて関係、いくらでもあるでしょう。
「かけがえのないパートナー」みたいなふんわりした意味分かるようで分からない表現が多用されるのは何でなんでしょうね。正直、自治体の責任逃れのように感じるし、こういうのを「婚姻相当」なんて安直に報道しちゃうメディア、ハッキリ言って誤報レベルでは。
・誠にですね。こういう、法律とか人権の問題を精神論というか道徳の問題にしてしまうのはよくないですね。
・だいたい、パートナー、っていう横文字カタカナ言葉が馴染めないのだ。日本語で言って欲しいのだ。
・パートナー制度で「パートナー証明もらえばカップルで市営住宅に入居できます!」みたいなのウリにしてる自治体多いけど、そもそもそんな証明とか同性カップルとか婚姻相当とか関係なく、戸籍上赤の他人同士でも同居認めれば良いだけの話じゃないんですかね。
「他人同士の同居は基本NG、同性カップルは例外的にOK」じゃ、入居=カミングアウト強制になるし、むしろ困るってカップルも多いのでは。
そもそも、友達同士で助け合って暮らしちゃ、なんでダメなの?
友達同士を認めないから結果的に同性カップルもNGになっちゃってるわけでしょ?同性カップルもOKにしろとか限定して言ってないでフツーに友達同士の入居認めるんじゃダメなんですかね? いろいろとよく分からないです。
ていうかセクマイのためって言うならむしろ単身者が安く安全に暮らせる物件もっと増やして欲しいです。
親と絶縁してて保証人確保できないとか親と折り合い悪くなったからすぐにでも実家出たいとかそういう事情抱えてる単身セクマイも多いと思うし。そういう人のためにこそ公営住宅が必要なのでは?
・「同性婚法制化推進してる人が必ずしも自治体パートナー制度推してるわけじゃない」ってことはしっかり認識しておく必要あると思う。夫婦別姓についても同じことが言える。
同性カップルの人と、別姓事実婚の人、それぞれから同じ意見聞いたことがあって。
「自分は本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるので、そんなマガイモノのパートナー制度なんか要らないしむしろ迷惑。自分の住む自治体で導入されても絶対利用しない」
自治体パートナー制度導入が同性婚法制化の推進力になる、っていう意見も根強いけど、それって証明できるものじゃないし。「法制化のためにはむしろ逆効果」っていう意見もあって、それはそれで一理あるわけで。
「本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるからこそ、そんなマガイモノは要らない。バカにするな」っていう意見ももっともだと思う。「同性婚法制化目指してるなら、当然自治体パートナー制度も推してるよね!導入されたら嬉しいよね!」なんて決めつけちゃダメ。
・「同性婚法制化のために自治体として何かするって言うなら“議会で同性婚の法整備を求める意見書を採択する”方が筋が通っているし有効」という意見もある。「パートナー制度ありき」「パートナー制度一択」じゃない。いろんなやり方がありそれぞれにメリットデメリットがある。しっかり比較検討すべき。
・パートナー制度のネーミングですが、個人的には「ネーミングライツ」もアリなんじゃないかなと思ってます。
【メリット】
・収益を関連事業に充てることができ、税金支出を抑えられる。
【デメリット】
・営利企業を関与させることに対する違和感。
・ライバル会社の社員が制度を使いづらくなるのでは。
・自治体パートナー制度絡みでは、推進派の議員が自治体をオセロの駒に例えて「オセロゲームのように、黒だったところを白というか、レインボーに変えていきたい」なんて発言してる記事を見たことがありますが、正直愉快ではなかったですね。
人のまちを、私のまちを運動のための手駒扱いするなと。利用するなと。発言した方に悪気はなかったんでしょうけど。
このまちの制度は、まず第一に、このまちを良くするためにつくるものなんじゃないんですかね。それが結果的に国全体を良くすることに繋がるんだったらもちろんそれはそれで結構なことですが、それはあくまで結果的な話であって。ハナっから運動の手駒扱いされるいわれはない。
・「生涯を共にしたい異性のパートナーいるけど、結婚はイヤ、別の選択肢も欲しい」というニーズは、日本でも自治体パートナー制度の普及の中で可視化されてきています。「性別不問」のパートナー制度導入する自治体も増えてる。仙台でも制度導入議論するなら必須のテーマ。
モノアモリー(単数恋愛)で性別違和のない異性愛者だって、いろいろ多様なわけで。異性間パートナーシップのあり方が多様化していけば、同性カップルなどセクマイの多様性もより肯定されるようになっていくのではないでしょうか。
そういう意味では、パートナー制度を「性別不問」にすることは、同性カップルにもいろいろメリットがあるような気がします。
・各地の自治体パートナー制度、あっちもこっちも必死で「セックス(性行為)」を隠蔽してますよね。それでいて近親者排除したりしてるから矛盾がモリモリ出てくる。
婚姻が「公認セックス契約」だからこそ、多くの人がこんなにも苦しんでるんじゃないか。
セックスの強要。セックスの拒否。セックスの不一致。
夫婦が揉める原因のかなりの割合、セックスでしょ?
だいたい、「婚姻=公認セックス契約」だからこそ、「自分は同性愛者だから同性と結婚したい!」っていう主張が成り立つわけであって。ソコ無視するって、全然同性愛者尊重してないし。
多様な性のあり方、同性婚、婚姻制度、家族制度、「セックス」抜きに語れるわけがない。ものすごく重いテーマなのに、真摯に向き合わず、流行りに乗ってコピペのパートナー制度つくって、「やってます感」出したいだけと言われても仕方ないんじゃないですか。
・最近の自治体パートナー制度、利用条件が「カップルの戸籍上の性別組み合わせは問わない(戸籍上異性カップルでもOK)、だがカップルの一方または双方がセクマイであることを求める」というのが増えてるんですよね。
軽くバイっ気あったり軽~い性別違和がありさえすれば条件満たすから、実質ほぼすべてのカップルが戸籍上の性別問わず使えるかたち。だったら性別不問って言い切っちゃっても良い気がするけど…どうしてもセクマイ強調したいんですかね??なんか不思議ですね、こういう規定。既に「性別不問」のパートナー制度の前例も複数ある中でこのような条件を付与するのは正直違和感を拭えないです。
「バイの男女カップル」は制度利用できて「ノンケの男女カップル」は利用できない、という条件設定に、合理的な説明がつくものでしょうか?
「あなたはバイだから異性の恋人と制度利用OK!でもお友達のノンケカップルはNG!あなたたちセクマイのために作って差し上げた制度ですから~!」なんて言われて、バイ当事者が喜ぶとでも思ってるんですかね。少なくともバイ当事者の私は、そんなこと言われたら物凄く不愉快ですね。
バイ当事者の1人として、これって超ありがちな「LGBTのB無視」の一環のような気がしてしまう。ヒガミかもしれないけど。でも、Bのことまともに考えてくれてたら、こんな雑な制度にならないんじゃない?
・家父長制を強化するパートナー制度は要りません!
・そもそも、現代日本の婚姻制度が排除しているのは「戸籍上同性カップル」。自認は関係なく、あくまで戸籍上の性別の問題なわけでしょう。自認を言い出すなら、既にこの日本に「法律婚してる(自認上)同性カップル」なんかいくらでもいるわけで。
一部自治体のパートナー制度が、性別違和の当事者への配慮などと称して「戸籍上の性別組み合わせは問わない、ただしセクマイであること」といった利用条件を設定していることには、だから違和感がぬぐえない。
パートナー制度、「セクマイ尊重」「性自認尊重」の名のもとに、なんかいろんなことブレまくってない?っていう疑問がすごくある。それ本当に「セクマイ尊重」になってます?むしろ蔑ろにしてません?安易に前例コピペじゃなく根本的なところからしっかり考えて欲しい。
・青森県弘前市でのパートナー制度導入にあたり実施されたパブリックコメント見ると、「前例もあることだし弘前市でもノンケ事実婚OKの制度にして欲しい!」という意見が複数寄せられており、それに対し市が「事実婚については、婚姻に準ずる一定の関係性が認められるなど、性的マイノリティの方とは事情も異なるものと考えており、本制度の対象とはしないものです。」と突っぱねていることが分かります。
ニーズが明らかにあるのに、事実婚の人たちの生き辛さだってあるのに、なぜここまでしてスルーするのか、よく分からない…
・嫌で嫌で拒否したくても難しい、弱い立場の子供の名前を敢えて証明書に書き込むファミリーシップ制度には懐疑的です。親たちのパートナー関係を証明するだけでも、子供に対する地位はある程度示せると思うし。
・特に今考慮すべきなのが、「2022年4月1日に成人年齢が18才となることに伴い、16・17才女子が婚姻できなくなる」事態ではないでしょうか。
これまで婚姻できていた10代後半層が婚姻不可となる。子供がいるケースも多いでしょう。この層に自治体パートナー制度で目配りするのもアリではないでしょうか。
・一部自治体の「自認する性が同性であれば戸籍上異性でもOK!」っていう同性パートナー制度設計、Xジェンダーを標榜する当事者の私としては非常にモヤッとしますね。かなり「排除されてる感」が強い。なんだかなあ。
・ていうか、そもそも日本って単身者でも未成年者を養子に迎えることができる国なわけで(原則家裁の許可いるけど)。
真剣に法律上も同性パートナーの子供の親になりたいなら養子縁組目指した方が良い気がするし、自治体が当事者のためというなら実効性のほぼないファミリーシップ証明なんか出すよりそういうのサポートしてあげた方が良いのでは?
「養子縁組すると実親の親権がなくなる!」っていう問題点は確かにありますが…でもそれ言ったら事実婚で子供もうけて育ててる男女カップルだってどっちかの単独親権だしなあ。実親との親子関係が切れるわけでもないし。
子育て同性カップルで「実親の親権がなくなることを恐れて育ての親と養子縁組しない」ってケース、実際のところどれだけあるんでしょう??
・「きちんと議会通して条例にしないと意味ない!」っていう意見もありますが…どうせ実効性ないんだし一時の流行りモノだしお手軽に要綱で済ましちゃうくらいが程々なのかも??
・パートナー制度導入初日に自治体お膳立てでメディア入れまくって証明書交付式やっておめでとうございまーす!なんて華々しく報道させたりするのも定番ですが、人権や平等のための制度というならやっぱりそういうのにも違和感があります。第1号だからって特別なわけじゃないし、そもそもパートナーいるからって特別扱いされて当然、単身者より偉い、というわけでもないでしょう。証明書交付イベントがLGBTビジネス起業家の売名に使われたと言われても仕方ないようなケースもありましたし。
もちろん、私的にお祝いすること自体は全く否定しませんが、公的機関がやるのには違和感があります。もっとフラットにやっていただきたいものです。実際、神奈川県横須賀市ではあえて証明書交付式はやらなかったとか。他自治体もぜひ参考にしていただきたいものです。
ていうかコレ、男女の法律婚に関しても言えることですけどね。いま生涯未婚率急上昇してるから、あちこちの自治体で婚姻届出した人に窓口で特別祝福サービスしちゃうような流行りがあって、まあ過疎化の現実とか考えると全面否定し難いところもあるのですが…個人的には正直「うわあ…」ってかんじです…
・同性婚に関して言えば。例えば女性同士のカップルが友人男性から精子提供受けて妊娠出産して3人で協力して子供育てる、なんてのは広い意味での複数婚的関係でしょう。そういう家族、すでに現実に存在してるわけで。いわゆるポリアモリーじゃなくても、“3人以上でのパートナーシップ”の話はだから重要なんです。
・パートナー制度導入自治体第1号のひとつ東京都世田谷区、2015年の導入当初は「独身であること」の証明書類一切確認してなかったんですよね。だから「既婚でもイケるじゃん!」とか言われてた。後になってマズイと思ったのか、2019年に「資料提示を求める」って制度改正してましたが。
でも、「証拠なんか要りません!あなたを信じます!」というのもそれはそれでアリだとは思いますけどね。どうせ実効性ない証明なんだし。だったら性善説貫いたって良いんじゃない?申請者の負担減らせるし。
・同性婚法制化推進派の方々が「同性婚できないとパートナーの手術の同意書にサインできなくて困る!入院時の身元保証人になれなくて困る!だから同性婚法制化必要!」なんて主張してるのをいまだに散見するわけですが、正直悪手だと思います。一昔前ならともかく、今となってはもう時代遅れ。
これだけ単身者が増えた現代日本、法律上の家族に依存せずとも医療が受けられる仕組みづくりが急務だし、実際実務上もそういう方向に進んできてる。逆に同性婚ムーブメントが「病人の面倒は家族がみるのが当たり前!」みたいな価値観揺り戻しちゃうのは私も単身者の1人として本当に困ります。
・手術の同意書にしろ、家の賃貸にしろ、制度そのものが根本的に大きな問題を抱えているのに、同性婚論議やパートナーシップ制度論議がそれを隠蔽するようなことになっては困る。そうなりかねない風潮がすごく気になっている。
・必要な医療を受けることを家族が妨げるなんてのは珍しいことじゃない。医療ネグレクトというやつだ。
「出産でもないのに婦人科に行くなんてふしだらだ!」
「身内が精神科にかかるなんて一族の恥だ!」
「身体にメスなんか入れたら醜くなるだろうが!許さない!」
たとえば虐待親が、DV配偶者が、本人の生殺与奪の権利を握ってしまう。生かすも殺すもかれら次第だ。
それって結局、誰のための制度なのか?
万一の場合の責任を回避したい医療者か?
家族の生き死にを管理したい家族か?
その中で、患者本人は尊重されているのか?
家族の同意なしには手術できない、家族の同意なしに手術したら医療者が責任を問われてしまう、そんな医療制度の問題こそなんとかすべきなんじゃないのかと思う。
死ぬときに家族がついていてくれる人ばかりじゃない。
適切な医療判断をしてくれる家族がいる人ばかりじゃない。
・家を借りる保証人も家族じゃないと。手術の同意書のサインも家族じゃないと。家族家族家族。なんだってこんなにも「家族」にいろいろなすりつけるんだろう。「家族」の持ち合わせがない人はどうすれば良いというのか。「家族」がなくてもまっとうな人間として生きられる社会であってほしい。
・お茶っこ試案の良いところは、純粋に「パートナーシップを証明する制度」であることに尽きると思います。
申請した二人の関係を証明するものであり、それ以上でもそれ以下でもない点が良いと思いました。
この証明をもって、法的な婚姻制度と同等の権利や義務が生じるか否かではなく、行政が「申請者二人が合意し、パートナーシップを宣誓した」ということを証明する制度にとどめていることです。
逆に言えば、この証明書がどれほどの効力を持つかは未知数です。
民間のサービスは、サービスの提供者の判断に委ねられますし、税的な優遇や相続権が適用されるのかどうかは、また別の議論・判断が必要になるのではないかと思います。
・パートナーシップ制度を「重病時の面会」や「相続」のために必要だと訴えている方々を目にしますが、たとえ制度的に認められたとしても、家族や周囲の認知が無い場合は、結局揉めることが目に見えています。(婚姻関係にあっても、同じことが起きています)
「国際間のパートナーの永住権」に関わる議論では、権利で守られる人たちがいる一方で、「偽装結婚」の問題が出てくることが想定されます。
この結果、「本当にパートナーシップにあるのか?」というパートナーシップの内容の精査が行われるようになってしまっては、多様なパートナーシップを証明する制度とは程遠くなるのではないでしょうか。
制度の導入ですべてが解決できるわけではなく、制度は一つのツールにすぎないことを念頭に議論が進むことを期待しています。
・お茶っこ試案、有効期限については面白い発想だなと思いました。
結婚記念日にお祝いをする夫婦と似たような関係性がある人達は、更新申請もある意味ライフイベントであり、双方の意思確認(継続性の確認)になるでしょうが、「空気のような存在」としてパートナーシップを結んでいる2人にとっては更新を忘れたり、意思確認がおっくうだったりしそうですね。
※そういう2人は、別の制度(養子縁組など)を使えば良いので、いろいろな制度があって「選択できる」というのは良いことだと思います。
・来年2022年4月1日から民法上の成人年齢が18歳になります。つまり、これまでの導入例では「成人であること」が求められてきた自治体パートナー制度も、18歳以上なら使えるようになるということです。
婚姻よりはるかにライトなパートナー制度、しかもノンケ男女カップルも使える自治体が増えています。たとえば、結婚はまだ早いと感じている10代後半~20代前半のカップルや学生カップルが利用するケースも今後増えてくるのではないでしょうか。
「結婚しちゃう?それともパートナー制度にしとく?」ノンケの若者カップルの間でそんな会話が増えるかもしれませんね。
ノンケの人たちにも「可哀相なセクマイのための救済制度」として見るんじゃなく「自分たちにも直接関わりのある制度」として考えていただきたいです。
・手をつなぐ間柄なら誰にでも適用される制度があってもいいなぁ
・いまの宮城に求めていることは、まずパートナーシップ制度は絶対。そのうえで婚姻制度と同等の医療制度と福利厚生を約束する。それがないとセクマイカップルは安心して宮城にはすめない。
・Xジェンダー自認でアロマンティック・アセクシャルだけど、色々と都合がいいから同様に恋愛しなくていい相手といずれはパートナー関係になりたいと思っている私。
でも、戸籍上の異性と結婚して「結婚したんだから愛し合ってるに違いない」と思われるのも嫌だし、戸籍上の同性と現在の不完全で理解を得てないパートナーシップを結んで「あの人って同性愛者なんだ…」って変に後ろ指さされるのも嫌。
愛の多様な形が認められるなら、「愛さない」も一つの形として認められてもいいじゃないですか。
「なんの力もないけど、二人の愛を多数派の私達が認めて祝福してあげる制度」なんて私には無意味なんです。
「お互いに合意した権利を必要とする人達が当然の権利を受け取れる、それだけのための制度」でいいと思います。そこに性別の確認も愛の確認も必要ない。
・自分の出身地でパートナーシップ制度が導入されたのですが、概要を見ると“戸籍上の性別不問/どちらかがセクマイのカップル”となっていて、真っ先に「バイ同士の異性カップルでもいいのか…?」と思いました(実際どうかは知らないけど、個人的にはイイと思う)。
婚姻にせよパートナー制度にせよ、公権力が個人のセックスのことを決める(貞操ギム)は気持ち悪い。ロマンチックラブの強調も。みんな公正証書つくってふたりのことはふたりで(3人でも4人でも)きめたらいいと思います。
展示企画のひとつとして実施したのが「ご意見募集!フセンでコメント」。
パートナー制度について、事前にSNS等で寄せられた意見をホワイトボードに展示したほか、来場者にもその場で意見を書いてもらい、あわせ展示しました。当日展示した意見全60件をご紹介します!
今回の企画に先立ち2021年(令和3年)2-3月にインターネット上で実施した意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」に寄せられた意見もあわせご覧ください!
<男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」「ご意見募集!フセンでコメント」展示意見一覧(全60件、順不同)>
・法律婚できない代わりに養子縁組してるカップルやポリアモリーを「公序良俗に反する」とか言って蔑視し切り捨てるのダメ絶対。
・異性婚者から一言
当時大使館がなく配偶者ビザを取るため双方の国で婚姻届が必要で、渡航費翻訳費諸々で100万はかかった。現在帰化申請中で、まだ家内は戸籍に入っていない。
異性婚は紙っぺら一枚でタダ。はウソ。
社会的信用が欲しいなら責任がついて回るのです。
・「法的効力がなく、自分にとってメリットがなく、アウティングのデメリットがある」
から申請しなかった場合。
「制度を使ってないから、あなたたちの関係は本物ではない。真剣ではない」
と見なされるかもしれない点。
例えば「市営住宅への入居可」という「特典」などは、市営住宅に入りたくない人にとってはメリットでも何でもない。
デメリットのアウティングとは。
申請すれば、担当課の人にばれます。利用者名簿が保存されるはずなので、異動の度毎にバレる人が増える。
利用者が公務員なら、同じ職場の人です。
職場で、ゲイを笑うような会話がなされてるような自治体でも(最近は「あ、LGBT差別ダメだった、ハハハ」と最後に付く)
そんな制度を使ってないからといって、
「制度があるのに使わないことを選択している。だからあなたたちは真剣ではないのだ」
などと見なされるなら、制度がないほうがましだといえます。
・たとえ意味の無いパートナーシップ制度でも、使いたくない当事者は使わなければいいだけ、と言われるかもしれないが。
それでは済まない面もある。
意味の無い施策が、現代的レイシズムにも繋がるひとつの原因になる、という点です。
つまりは、マジョリティから見れば、
パートナーシップ含む様々な施策はLGBTの人に有用なのだろう、と見える。
それなのに、当事者は、せっかく作ってあげたその制度を使いもしなければ、文句ばかり言っている。
こんなに税金を使って多くの施策をしてるのに、LGBTはわがままで自分勝手だ、と見える。
実際には、
法的効果がないパートナーシップ制度、
根拠の無い知識を正しいとする啓発、
有害でしかないレインボートイレ、
どれも当事者には何の役にもたっていないのに。
得するのは、良いことしてますアピールできる自治体と、委託された団体や業者。
そして被害を受けるのは当事者。
・例えば、パートナー制度絡みでよく「パートナー証明ないと病院で家族扱いしてもらえなくて云々」みたいな話出てきますが、そんなことないですからね。
例えば仙台市立病院。「市立病院におきましては、同性パートナーとの関係を確認し、妥当と判断した場合に診療情報の提供を行うこととしております。」って、仙台市議会平成29年第4回定例会で明言されてます。証明書なんかなくたってこういう取り組みちゃんと進んでるんです。
差別的な対応する施設も、もちろん皆無ではないだろうけど、でもそれはパートナー証明の有無とは無関係に改善されるべきもの。パートナー証明の有無で利用できるサービスに差がつけられてしまうことは、あってはならないことだと思います。
パートナー制度ができたとしても、いろんな事情で制度を使えないカップルだっている。そんな状況で「同性カップル?じゃあパートナー証明持ってきてください!え?ない?じゃあ認められません!」なんて話になって、これまで利用できてたサービスから門前払いされるようになったりしたら、本末転倒なわけです。
パートナー証明もらうことで、「説明がラクになる」というメリットはあるだろうし、全く無意味だとは言いません。でも、パートナー制度推進運動の中で、パートナー証明なくたってすでに可能になってることがあたかもパートナー証明がないと不可能であるかのように宣伝されちゃってる例が見受けられるのは、非常にマズいと思っています。
制度推進するならなおさら、「アレもコレもパートナー証明なくたって利用OKです!いろいろ事情あってパートナー証明もらえない人たちもだから安心してください!」ってしっかりアナウンスする必要あると思います。
・“婚姻相当”などと言いながら現代日本の婚姻制度のキモである「貞操義務」「セックスに応じる義務」には触れずスルーするパートナー制度など欺瞞である。
・よく同性婚やパートナー制度絡みで「愛し合う2人を認めて!」みたいな言説見かけますが、そもそも現代日本の婚姻システムに愛って関係ないですよね。「愛を公的に認めてもらう手段=婚姻orパートナー制度」というのは筋違いなのでは。
そもそも「愛=素晴らしいもの、だから承認されて当然」みたいな恋愛至上主義的思想は人権や平等を謳うスタンスとは相容れないというか。単身者や非モテの蔑視に繋がるし。
「愛=素晴らしい」と無批判に持て囃す姿勢は愛の名のもとに振るわれる暴力の誘発・肯定に繋がりかねない。DVとか虐待とか性暴力とか、愛の名のもとに行われているケースのなんと多いことか。
人権や平等のためにパートナー制度というなら、そういった面にも徹底した配慮が必要ではないでしょうか。
・一部の同性婚法制化推進派が「愛し合ってるんだから良いじゃないか!」などと言っていたりするが冗談じゃない。「愛」を言い訳に自説を正当化する行為は「愛」の名のもとに振るわれる暴力まで正当化しかねない。
愛してるから殴っていい。
愛してるから犯していい。
愛してるから、
冗談じゃない。
・結局、「結婚=愛の承認」みたいな誤解が生まれがちなのって、日本人のほとんどが婚姻制度家族制度についてちゃんと教わっていない、学んでいないからではないでしょうか。子供はもちろん、大人だってろくに知らない。知らないまま結婚して、後でトラブルになったりしている。同性婚だパートナー制度だ云々言う前にまずは「現代日本における婚姻とは何か」しっかり知る必要があると思います。
・パートナー制度といえば、最近では兵庫県明石市等が導入している子供を巻き込んだいわゆる「ファミリーシップ制度」が話題ですが、明石市の要綱見て気になるのが「子供に拒否権がない」こと。
子供のためと言いながら、正直子供が蔑ろにされてる風に感じてしまいます。
日常生活でパートナーの子供との関係性を具体的に示したいってことなら、子供の親と2者間でのパートナー証明だけでも対応可能なのでは?拒否権奪ってまで子供をムリヤリ巻き込まなきゃならないんでしょうか?子供巻き込むならもっと丁寧にやっていただきたいと思います。
・もう6年も前の話なので、10代20代の若い人や最近興味持った人は知らないかもしれませんが、例えばパートナー制度第1号自治体のひとつである渋谷区では制度導入過程の問題点がいろいろ指摘されてました。「良いことやってるんだから大目に見てあげようよ!」で済む話ではありません。人権のため、平等のため、差別解消のためと言うならばこそ、なおさらきちんとやらないといけない。
ブーム化したパートナー制度に関しては全国各地でヒトモノカネがいろいろ動くようになってます。ブラックボックスの中でよく分からないまま制度がつくられるようなことはあってはならないと思います。制度制定過程や運用過程で不正があってはかえって差別偏見が助長されてしまいます。徹底した情報公開としっかりした議論が必要だと思います。
・東日本大震災関連では被災者支援NPO法人の公金横領事件があって警察沙汰にまでなっていたりする。「自分達は正しい」「自分達のやっていることは良いことだ」「目的のためなら手段は正当化される」なんて思い込んで、やって良いことと悪いことの区別がつかなくなってはマズい。
・LGBTブームが女性の人権をむしり取るような風潮、公的機関までがそれを助長するような風潮が昨今感じられなくもないのも非常に気になっているところです。
女性の人権、男女平等ないがしろにしてLGBTだけ生きやすくなるとかあり得ない。男女差別や男女格差にもしっかりと目を向けること。目を背けないこと。絶対に外してはならない視点です。
・他の方も指摘してらっしゃるけど、うちんとこは導入したはいいものの、はっきりと「二人のうちどちらかがセクマイであること」が条件なんですよね。別姓希望や友人同士には開かれていないのはどうなんだろうと思います
・パートナー制度、法律婚できない代わりに養子縁組したカップルについては、すでに制度利用を明確に認めている自治体が複数あるので、これからはコレが主流になっていくのかなあと思っています。
社会承認的な意味で自治体パートナー証明もらいつつ養子縁組も併用して法律的な保障も得る、というのが現状一番お金もテマヒマもかからず同性パートナーとの関係を安定させる方法ではないでしょうか。「公序良俗に反する」等の蔑視的な言葉を使わないのは当然として、さらに踏み込んでパートナー制度の枠組みの中で養子縁組の活用法なんかも積極的にアピールしてもらうのもアリなんじゃないかなあ。
・「直系姻族間の婚姻禁止規定」についてももっと議論して欲しいなと。「姑と婿(あるいは舅と嫁)は一生結婚できない」なんておかしくない?
要するに「配偶者の親は実の親と一緒」って価値観なんだろうけどイマドキそれってどうよ。それでいて相続権はないし。
こういう「現行家族制度婚姻制度のおかしさ」を揺さぶる議論、パートナー制度をきっかけにガンガンやったら良いと思います。LGBTセクマイだけじゃない、すべての人が当事者。
・しかしなんだかんだ言って“第1号”っていうのはやっぱり大変ですよね。前例も何もない中でイチから築き上げなきゃならない。第1号の渋谷や世田谷は、それは問題もすごく大きかったし、制度も穴だらけだったけど、でもやっぱり、すごかったんだなあと思います。
そういう意味では、後続組はラクができる。でも、だからこそ、先達の良いところも悪いところもしっかり学んで、より良い制度にしていかなきゃいけない。それは後続組の責任でしょう。自分のところの自治体でも!と言うなら、自治体の担当者の方には、既存の要綱とか条例とかあるだけ全部チェックして、入念に分析していただきたいです。単なるコピペのまねっこじゃしょうがない。
・パートナー制度、同性カップルだけでなく男女の事実婚カップルも使えるようにしている自治体が複数出てきているので、今後はコレが主流になっていくのかなと思っています。
大半のLGBTは「LGBTのための特別な制度」を求めているわけじゃないと思うんですよね。平等言うなら、異性カップルも同性カップルもまったく同じように使える制度の方が良くないですか?
もちろん「そもそも本丸の法律婚が同性カップルを排除してるじゃないか!」というのはその通りです。でも、だからって、それの向こうを張ってパートナー制度を「同性カップル限定」にする必要はないんじゃないか。
法律婚に関しては、今話題の嫡出推定に関する規定など、同性カップルと異性カップルを同等に扱うのには無理があると思われるテーマもあります。でも自治体パートナー制度レベルだったら、そういうのも特にないような気がするし。「LGBTの方々のために特別な制度をつくってさしあげました!」って特別枠でレインボーな証明書もらうより、カップル友達の異性カップルと同性カップルが一緒に同じ証明書もらって、おたがいお祝いする、とかの方が楽しくないですか?
・パートナー要綱お茶っこ試案は「友達同士OK」になっています。これは利用者の幅を広げるためももちろんありますが、「同性カップルがカミングアウトせずに制度利用できるようになる」ことも大きなポイントです。「カップル限定」にしてしまうと「制度利用=同性愛カミングアウト」になってしまう。「友達同士OK」だったらそれが回避できます。
・パートナー制度に限らずですが、セクマイ系施策に取り組もうとしている公的機関の方々にお願いしたいのが、「当事者からこういう意見があったから」というフレーズで責任逃れをしないでいただきたい、ということです。
セクマイ当事者も多様で、ひとりひとりさまざまな意見があります。当事者の意見にしっかりと耳を傾けることはもちろん重要なことですが、自分にとって都合の良い一部の意見だけを取り上げ「だって当事者がこう言ってるから!」などと言い張って施策を正当化するのは、公的機関の責任逃れ、当事者への責任の押しつけです。
典型的なのがいわゆるLGBTトイレ問題でしょう。LGBT当事者の要望で盛んに設置され、そして、LGBT当事者の要望により撤去されました。設置を求めたのも撤去を求めたのも当事者。そんなふうに当事者の意見も分かれているなかで、じゃあ公的機関としてどうするのか。それは様々な要素を踏まえた上で公的機関として責任を持って判断すべきことでしょう。
パートナー制度についても、セクマイ当事者の間でも意見は分かれています。当事者の意見を聞くことはもちろん重要なことで、そこは丁寧にやっていただきたい。多様な当事者の意見に耳を傾けていただきたい。そしてその上で、てんでバラバラな多様な意見を踏まえて、当事者の意見以外の様々な要素も踏まえて、公的機関として、より良いと思われる施策を責任をもって実施していただきたい。そう願います。
セクマイ当事者に多数決取れば良いってものでもないですからね。そもそもクローゼットの多いセクマイ業界で多数決取るなんてのがほぼ不可能だし、それ以前にマイノリティの問題なのに多数決でなんとかしようっていうのが矛盾なわけで。
・私は党派を問わずに同性婚の法整備を求める意見書の採択を求めて陳情を繰り返していますが
そのときに「パートナー制度があるので同性婚は必要ない」という回答を党派を問わずに投げられています
バラ色のように導入される今のパートナー制度は同性婚の法整備の大切さを間違いなく毀損しています
・自治体として“婚姻相当”の同性カップルがしっかり公的・法的保障得られるようにしてあげよう!というなら、実効性のほぼないパートナー証明出すだけでお茶を濁すより、例えば「公正証書作成支援」、渋谷区等が始めたような、公正証書作成費用助成や、無料法律相談などに取り組んだ方が理に適っているのでは。
・実効性のほぼないパートナー証明だけで“婚姻相当”と主張するのはいろいろと無理があるわけで。その程度の手続きで示せるのはせいぜいが“緊急連絡先”レベルといったところではないでしょうか。
もちろん、“緊急連絡先”だってすごく大事です。でも、“婚姻相当”とは違うよね、と。
ていうか“緊急連絡先”だったら別に「1対1限定」「恋愛関係・性愛関係限定」にする必要なんかない。友達同士だって良い。複数人を“緊急連絡先”にしたって良い。性別だって関係ない。
単身者激増の現代日本社会、“ガチの家族”でも“赤の他人”でもない、そのあいだのゆるい人間関係というものが非常に重要になってきていると思います。そういうゆるい人間関係をゆるく証明してあげる、そんな路線のパートナー制度もアリではないでしょうか。意外と現実的だと思います。
・ていうか、実効性のほぼないパートナー制度について「実効性はないが啓発効果がある!」っていう主張、よく聞きますが、啓発のために実際上は役に立たない制度をつくる、っていうのには正直違和感があります。そういうのっていろいろと誤解招くし、制度化するならするでちゃんと実効性のある、役に立つ制度つくった方が良いのではないでしょうか。啓発は啓発で別に取り組んだ方が良いのではないでしょうか。
・恋愛してるからって偉いわけじゃない。セックスしてるからって偉いわけじゃない。恋愛関係や性愛関係を特別視してもてはやすのはやめてほしい。そういう価値観にパートナー制度が加担するのはとても困ります。人権だ平等だ言うなら本当に気をつけて欲しいです。恋愛しない・したくない・できない人もいる。セックスしない・したくない・できない人もいる。優劣をつけるような話じゃない。
・同性パートナー制度に関連して「職場で同性カップルにも結婚祝い金支給!」なんてのもありますが、そもそもなんで職場で婚姻カップルに祝い金出さないといけないのか?なんでそんな風に婚姻カップルを優遇しなければならないのか?平等と言うならそういった根本からしっかり考え直して公平な視点で見直して欲しいものです。
職場の結婚祝い金っていろんなパターンありますが多くの場合、結婚しない人・できない人から取り立てた金を結婚した人・できた人に流しているわけでしょう。それが本当に人権や平等に配慮したとりくみなんですかね?平等と言うなら性別問わず“婚姻特権”の徹底排除が筋ではないでしょうか。
「同性婚カップルにも結婚祝い金支給させることで同性婚カップルが可視化され社会の理解がすすむので戦略として有効!」みたいな価値観もあるようだけどその戦略の下で踏みにじられている存在のことは忘れないでいただきたいなあと思います。
・昨今流行りのパートナー制度、報道では「婚姻相当」なんて言葉が安直に使われちゃってるけど、各自治体の制度の条文具体的に読んでみるとそんな風には読み取れないケースが実際には多いんですよね。
例えば今夏導入の佐賀県。パートナーシップとは「お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した(中略)二人の者の関係をいう」とのこと。
…コレ読んで「婚姻相当」だって思います?
「かけがえのないパートナーであって、相互に協力しあいながら継続的に共同生活を営んでおり、なおかつ夫婦(婚姻カップル)でない」なんて関係、いくらでもあるでしょう。
「かけがえのないパートナー」みたいなふんわりした意味分かるようで分からない表現が多用されるのは何でなんでしょうね。正直、自治体の責任逃れのように感じるし、こういうのを「婚姻相当」なんて安直に報道しちゃうメディア、ハッキリ言って誤報レベルでは。
・誠にですね。こういう、法律とか人権の問題を精神論というか道徳の問題にしてしまうのはよくないですね。
・だいたい、パートナー、っていう横文字カタカナ言葉が馴染めないのだ。日本語で言って欲しいのだ。
・パートナー制度で「パートナー証明もらえばカップルで市営住宅に入居できます!」みたいなのウリにしてる自治体多いけど、そもそもそんな証明とか同性カップルとか婚姻相当とか関係なく、戸籍上赤の他人同士でも同居認めれば良いだけの話じゃないんですかね。
「他人同士の同居は基本NG、同性カップルは例外的にOK」じゃ、入居=カミングアウト強制になるし、むしろ困るってカップルも多いのでは。
そもそも、友達同士で助け合って暮らしちゃ、なんでダメなの?
友達同士を認めないから結果的に同性カップルもNGになっちゃってるわけでしょ?同性カップルもOKにしろとか限定して言ってないでフツーに友達同士の入居認めるんじゃダメなんですかね? いろいろとよく分からないです。
ていうかセクマイのためって言うならむしろ単身者が安く安全に暮らせる物件もっと増やして欲しいです。
親と絶縁してて保証人確保できないとか親と折り合い悪くなったからすぐにでも実家出たいとかそういう事情抱えてる単身セクマイも多いと思うし。そういう人のためにこそ公営住宅が必要なのでは?
・「同性婚法制化推進してる人が必ずしも自治体パートナー制度推してるわけじゃない」ってことはしっかり認識しておく必要あると思う。夫婦別姓についても同じことが言える。
同性カップルの人と、別姓事実婚の人、それぞれから同じ意見聞いたことがあって。
「自分は本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるので、そんなマガイモノのパートナー制度なんか要らないしむしろ迷惑。自分の住む自治体で導入されても絶対利用しない」
自治体パートナー制度導入が同性婚法制化の推進力になる、っていう意見も根強いけど、それって証明できるものじゃないし。「法制化のためにはむしろ逆効果」っていう意見もあって、それはそれで一理あるわけで。
「本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるからこそ、そんなマガイモノは要らない。バカにするな」っていう意見ももっともだと思う。「同性婚法制化目指してるなら、当然自治体パートナー制度も推してるよね!導入されたら嬉しいよね!」なんて決めつけちゃダメ。
・「同性婚法制化のために自治体として何かするって言うなら“議会で同性婚の法整備を求める意見書を採択する”方が筋が通っているし有効」という意見もある。「パートナー制度ありき」「パートナー制度一択」じゃない。いろんなやり方がありそれぞれにメリットデメリットがある。しっかり比較検討すべき。
・パートナー制度のネーミングですが、個人的には「ネーミングライツ」もアリなんじゃないかなと思ってます。
【メリット】
・収益を関連事業に充てることができ、税金支出を抑えられる。
【デメリット】
・営利企業を関与させることに対する違和感。
・ライバル会社の社員が制度を使いづらくなるのでは。
・自治体パートナー制度絡みでは、推進派の議員が自治体をオセロの駒に例えて「オセロゲームのように、黒だったところを白というか、レインボーに変えていきたい」なんて発言してる記事を見たことがありますが、正直愉快ではなかったですね。
人のまちを、私のまちを運動のための手駒扱いするなと。利用するなと。発言した方に悪気はなかったんでしょうけど。
このまちの制度は、まず第一に、このまちを良くするためにつくるものなんじゃないんですかね。それが結果的に国全体を良くすることに繋がるんだったらもちろんそれはそれで結構なことですが、それはあくまで結果的な話であって。ハナっから運動の手駒扱いされるいわれはない。
・「生涯を共にしたい異性のパートナーいるけど、結婚はイヤ、別の選択肢も欲しい」というニーズは、日本でも自治体パートナー制度の普及の中で可視化されてきています。「性別不問」のパートナー制度導入する自治体も増えてる。仙台でも制度導入議論するなら必須のテーマ。
モノアモリー(単数恋愛)で性別違和のない異性愛者だって、いろいろ多様なわけで。異性間パートナーシップのあり方が多様化していけば、同性カップルなどセクマイの多様性もより肯定されるようになっていくのではないでしょうか。
そういう意味では、パートナー制度を「性別不問」にすることは、同性カップルにもいろいろメリットがあるような気がします。
・各地の自治体パートナー制度、あっちもこっちも必死で「セックス(性行為)」を隠蔽してますよね。それでいて近親者排除したりしてるから矛盾がモリモリ出てくる。
婚姻が「公認セックス契約」だからこそ、多くの人がこんなにも苦しんでるんじゃないか。
セックスの強要。セックスの拒否。セックスの不一致。
夫婦が揉める原因のかなりの割合、セックスでしょ?
だいたい、「婚姻=公認セックス契約」だからこそ、「自分は同性愛者だから同性と結婚したい!」っていう主張が成り立つわけであって。ソコ無視するって、全然同性愛者尊重してないし。
多様な性のあり方、同性婚、婚姻制度、家族制度、「セックス」抜きに語れるわけがない。ものすごく重いテーマなのに、真摯に向き合わず、流行りに乗ってコピペのパートナー制度つくって、「やってます感」出したいだけと言われても仕方ないんじゃないですか。
・最近の自治体パートナー制度、利用条件が「カップルの戸籍上の性別組み合わせは問わない(戸籍上異性カップルでもOK)、だがカップルの一方または双方がセクマイであることを求める」というのが増えてるんですよね。
軽くバイっ気あったり軽~い性別違和がありさえすれば条件満たすから、実質ほぼすべてのカップルが戸籍上の性別問わず使えるかたち。だったら性別不問って言い切っちゃっても良い気がするけど…どうしてもセクマイ強調したいんですかね??なんか不思議ですね、こういう規定。既に「性別不問」のパートナー制度の前例も複数ある中でこのような条件を付与するのは正直違和感を拭えないです。
「バイの男女カップル」は制度利用できて「ノンケの男女カップル」は利用できない、という条件設定に、合理的な説明がつくものでしょうか?
「あなたはバイだから異性の恋人と制度利用OK!でもお友達のノンケカップルはNG!あなたたちセクマイのために作って差し上げた制度ですから~!」なんて言われて、バイ当事者が喜ぶとでも思ってるんですかね。少なくともバイ当事者の私は、そんなこと言われたら物凄く不愉快ですね。
バイ当事者の1人として、これって超ありがちな「LGBTのB無視」の一環のような気がしてしまう。ヒガミかもしれないけど。でも、Bのことまともに考えてくれてたら、こんな雑な制度にならないんじゃない?
・家父長制を強化するパートナー制度は要りません!
・そもそも、現代日本の婚姻制度が排除しているのは「戸籍上同性カップル」。自認は関係なく、あくまで戸籍上の性別の問題なわけでしょう。自認を言い出すなら、既にこの日本に「法律婚してる(自認上)同性カップル」なんかいくらでもいるわけで。
一部自治体のパートナー制度が、性別違和の当事者への配慮などと称して「戸籍上の性別組み合わせは問わない、ただしセクマイであること」といった利用条件を設定していることには、だから違和感がぬぐえない。
パートナー制度、「セクマイ尊重」「性自認尊重」の名のもとに、なんかいろんなことブレまくってない?っていう疑問がすごくある。それ本当に「セクマイ尊重」になってます?むしろ蔑ろにしてません?安易に前例コピペじゃなく根本的なところからしっかり考えて欲しい。
・青森県弘前市でのパートナー制度導入にあたり実施されたパブリックコメント見ると、「前例もあることだし弘前市でもノンケ事実婚OKの制度にして欲しい!」という意見が複数寄せられており、それに対し市が「事実婚については、婚姻に準ずる一定の関係性が認められるなど、性的マイノリティの方とは事情も異なるものと考えており、本制度の対象とはしないものです。」と突っぱねていることが分かります。
ニーズが明らかにあるのに、事実婚の人たちの生き辛さだってあるのに、なぜここまでしてスルーするのか、よく分からない…
・嫌で嫌で拒否したくても難しい、弱い立場の子供の名前を敢えて証明書に書き込むファミリーシップ制度には懐疑的です。親たちのパートナー関係を証明するだけでも、子供に対する地位はある程度示せると思うし。
・特に今考慮すべきなのが、「2022年4月1日に成人年齢が18才となることに伴い、16・17才女子が婚姻できなくなる」事態ではないでしょうか。
これまで婚姻できていた10代後半層が婚姻不可となる。子供がいるケースも多いでしょう。この層に自治体パートナー制度で目配りするのもアリではないでしょうか。
・一部自治体の「自認する性が同性であれば戸籍上異性でもOK!」っていう同性パートナー制度設計、Xジェンダーを標榜する当事者の私としては非常にモヤッとしますね。かなり「排除されてる感」が強い。なんだかなあ。
・ていうか、そもそも日本って単身者でも未成年者を養子に迎えることができる国なわけで(原則家裁の許可いるけど)。
真剣に法律上も同性パートナーの子供の親になりたいなら養子縁組目指した方が良い気がするし、自治体が当事者のためというなら実効性のほぼないファミリーシップ証明なんか出すよりそういうのサポートしてあげた方が良いのでは?
「養子縁組すると実親の親権がなくなる!」っていう問題点は確かにありますが…でもそれ言ったら事実婚で子供もうけて育ててる男女カップルだってどっちかの単独親権だしなあ。実親との親子関係が切れるわけでもないし。
子育て同性カップルで「実親の親権がなくなることを恐れて育ての親と養子縁組しない」ってケース、実際のところどれだけあるんでしょう??
・「きちんと議会通して条例にしないと意味ない!」っていう意見もありますが…どうせ実効性ないんだし一時の流行りモノだしお手軽に要綱で済ましちゃうくらいが程々なのかも??
・パートナー制度導入初日に自治体お膳立てでメディア入れまくって証明書交付式やっておめでとうございまーす!なんて華々しく報道させたりするのも定番ですが、人権や平等のための制度というならやっぱりそういうのにも違和感があります。第1号だからって特別なわけじゃないし、そもそもパートナーいるからって特別扱いされて当然、単身者より偉い、というわけでもないでしょう。証明書交付イベントがLGBTビジネス起業家の売名に使われたと言われても仕方ないようなケースもありましたし。
もちろん、私的にお祝いすること自体は全く否定しませんが、公的機関がやるのには違和感があります。もっとフラットにやっていただきたいものです。実際、神奈川県横須賀市ではあえて証明書交付式はやらなかったとか。他自治体もぜひ参考にしていただきたいものです。
ていうかコレ、男女の法律婚に関しても言えることですけどね。いま生涯未婚率急上昇してるから、あちこちの自治体で婚姻届出した人に窓口で特別祝福サービスしちゃうような流行りがあって、まあ過疎化の現実とか考えると全面否定し難いところもあるのですが…個人的には正直「うわあ…」ってかんじです…
・同性婚に関して言えば。例えば女性同士のカップルが友人男性から精子提供受けて妊娠出産して3人で協力して子供育てる、なんてのは広い意味での複数婚的関係でしょう。そういう家族、すでに現実に存在してるわけで。いわゆるポリアモリーじゃなくても、“3人以上でのパートナーシップ”の話はだから重要なんです。
・パートナー制度導入自治体第1号のひとつ東京都世田谷区、2015年の導入当初は「独身であること」の証明書類一切確認してなかったんですよね。だから「既婚でもイケるじゃん!」とか言われてた。後になってマズイと思ったのか、2019年に「資料提示を求める」って制度改正してましたが。
でも、「証拠なんか要りません!あなたを信じます!」というのもそれはそれでアリだとは思いますけどね。どうせ実効性ない証明なんだし。だったら性善説貫いたって良いんじゃない?申請者の負担減らせるし。
・同性婚法制化推進派の方々が「同性婚できないとパートナーの手術の同意書にサインできなくて困る!入院時の身元保証人になれなくて困る!だから同性婚法制化必要!」なんて主張してるのをいまだに散見するわけですが、正直悪手だと思います。一昔前ならともかく、今となってはもう時代遅れ。
これだけ単身者が増えた現代日本、法律上の家族に依存せずとも医療が受けられる仕組みづくりが急務だし、実際実務上もそういう方向に進んできてる。逆に同性婚ムーブメントが「病人の面倒は家族がみるのが当たり前!」みたいな価値観揺り戻しちゃうのは私も単身者の1人として本当に困ります。
・手術の同意書にしろ、家の賃貸にしろ、制度そのものが根本的に大きな問題を抱えているのに、同性婚論議やパートナーシップ制度論議がそれを隠蔽するようなことになっては困る。そうなりかねない風潮がすごく気になっている。
・必要な医療を受けることを家族が妨げるなんてのは珍しいことじゃない。医療ネグレクトというやつだ。
「出産でもないのに婦人科に行くなんてふしだらだ!」
「身内が精神科にかかるなんて一族の恥だ!」
「身体にメスなんか入れたら醜くなるだろうが!許さない!」
たとえば虐待親が、DV配偶者が、本人の生殺与奪の権利を握ってしまう。生かすも殺すもかれら次第だ。
それって結局、誰のための制度なのか?
万一の場合の責任を回避したい医療者か?
家族の生き死にを管理したい家族か?
その中で、患者本人は尊重されているのか?
家族の同意なしには手術できない、家族の同意なしに手術したら医療者が責任を問われてしまう、そんな医療制度の問題こそなんとかすべきなんじゃないのかと思う。
死ぬときに家族がついていてくれる人ばかりじゃない。
適切な医療判断をしてくれる家族がいる人ばかりじゃない。
・家を借りる保証人も家族じゃないと。手術の同意書のサインも家族じゃないと。家族家族家族。なんだってこんなにも「家族」にいろいろなすりつけるんだろう。「家族」の持ち合わせがない人はどうすれば良いというのか。「家族」がなくてもまっとうな人間として生きられる社会であってほしい。
・お茶っこ試案の良いところは、純粋に「パートナーシップを証明する制度」であることに尽きると思います。
申請した二人の関係を証明するものであり、それ以上でもそれ以下でもない点が良いと思いました。
この証明をもって、法的な婚姻制度と同等の権利や義務が生じるか否かではなく、行政が「申請者二人が合意し、パートナーシップを宣誓した」ということを証明する制度にとどめていることです。
逆に言えば、この証明書がどれほどの効力を持つかは未知数です。
民間のサービスは、サービスの提供者の判断に委ねられますし、税的な優遇や相続権が適用されるのかどうかは、また別の議論・判断が必要になるのではないかと思います。
・パートナーシップ制度を「重病時の面会」や「相続」のために必要だと訴えている方々を目にしますが、たとえ制度的に認められたとしても、家族や周囲の認知が無い場合は、結局揉めることが目に見えています。(婚姻関係にあっても、同じことが起きています)
「国際間のパートナーの永住権」に関わる議論では、権利で守られる人たちがいる一方で、「偽装結婚」の問題が出てくることが想定されます。
この結果、「本当にパートナーシップにあるのか?」というパートナーシップの内容の精査が行われるようになってしまっては、多様なパートナーシップを証明する制度とは程遠くなるのではないでしょうか。
制度の導入ですべてが解決できるわけではなく、制度は一つのツールにすぎないことを念頭に議論が進むことを期待しています。
・お茶っこ試案、有効期限については面白い発想だなと思いました。
結婚記念日にお祝いをする夫婦と似たような関係性がある人達は、更新申請もある意味ライフイベントであり、双方の意思確認(継続性の確認)になるでしょうが、「空気のような存在」としてパートナーシップを結んでいる2人にとっては更新を忘れたり、意思確認がおっくうだったりしそうですね。
※そういう2人は、別の制度(養子縁組など)を使えば良いので、いろいろな制度があって「選択できる」というのは良いことだと思います。
・来年2022年4月1日から民法上の成人年齢が18歳になります。つまり、これまでの導入例では「成人であること」が求められてきた自治体パートナー制度も、18歳以上なら使えるようになるということです。
婚姻よりはるかにライトなパートナー制度、しかもノンケ男女カップルも使える自治体が増えています。たとえば、結婚はまだ早いと感じている10代後半~20代前半のカップルや学生カップルが利用するケースも今後増えてくるのではないでしょうか。
「結婚しちゃう?それともパートナー制度にしとく?」ノンケの若者カップルの間でそんな会話が増えるかもしれませんね。
ノンケの人たちにも「可哀相なセクマイのための救済制度」として見るんじゃなく「自分たちにも直接関わりのある制度」として考えていただきたいです。
・手をつなぐ間柄なら誰にでも適用される制度があってもいいなぁ
・いまの宮城に求めていることは、まずパートナーシップ制度は絶対。そのうえで婚姻制度と同等の医療制度と福利厚生を約束する。それがないとセクマイカップルは安心して宮城にはすめない。
・Xジェンダー自認でアロマンティック・アセクシャルだけど、色々と都合がいいから同様に恋愛しなくていい相手といずれはパートナー関係になりたいと思っている私。
でも、戸籍上の異性と結婚して「結婚したんだから愛し合ってるに違いない」と思われるのも嫌だし、戸籍上の同性と現在の不完全で理解を得てないパートナーシップを結んで「あの人って同性愛者なんだ…」って変に後ろ指さされるのも嫌。
愛の多様な形が認められるなら、「愛さない」も一つの形として認められてもいいじゃないですか。
「なんの力もないけど、二人の愛を多数派の私達が認めて祝福してあげる制度」なんて私には無意味なんです。
「お互いに合意した権利を必要とする人達が当然の権利を受け取れる、それだけのための制度」でいいと思います。そこに性別の確認も愛の確認も必要ない。
・自分の出身地でパートナーシップ制度が導入されたのですが、概要を見ると“戸籍上の性別不問/どちらかがセクマイのカップル”となっていて、真っ先に「バイ同士の異性カップルでもいいのか…?」と思いました(実際どうかは知らないけど、個人的にはイイと思う)。
婚姻にせよパートナー制度にせよ、公権力が個人のセックスのことを決める(貞操ギム)は気持ち悪い。ロマンチックラブの強調も。みんな公正証書つくってふたりのことはふたりで(3人でも4人でも)きめたらいいと思います。