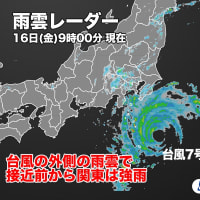https://www.facebook.com/share/r/pUPccdicibgTJprp/?mibextid=UalRPS
映画が面白かったので、すぐにある本を読むことにした。レイ・A・クロック 他4名
『成功はゴミ箱の中に 』レイ・クロック自伝

『その夜 、モ ーテルに戻って 、私は今日一日の出来事を思い返してみた 。すると突然私の脳裏に 、マクドナルドの店舗を 、国中の主要道路に展開させるという考えがひらめいた 。各店に置かれた八台のマルチミキサ ーが 、ブンブン音を立てながら休みなく動き 、お金をどんどんかき出してくれる 。何とも魅力的な商売ではないか 。翌朝 、起きたときには 、すでにプランが頭の中に出来上がっていた 。マクドナルド兄弟とビジネスの契約を結ぶ光景を思い浮かべ 、何度もそのイメ ージシナリオを 、頭の中で繰り返した 。たまらなく魅惑的な光景だった 。前日にマクドナルド兄弟と話ができたおかげで 、様々な知識を得ることができた 。たとえばスタッフの鉄板さばきである 。ピシャリと音を立てて 、ハンバーガーのパティを裏返したり 、鉄板の温度を下げずに 、表面の汚れをこすり落とし 、続けてパティを焼くといった方法等に感心したが 、なかでも最も感銘を受けたのが 、フライドポテトの揚げ方だ 。マクドナルド兄弟も 、事業が成功した理由の一つは間違いなくフライポテトだと言っていた 。ふたりは作り方のプロセスを口頭で説明してくれたのだが 、私はどうしても自分の目でそれを確かめたかった 。そこには 、何か大きな企業秘密が隠されているに違いなかったからである 。普通の人は 、フライドポテトにとりたてて関心など持たない 。ハンバ ーガ ーや 、ミルクシェイクを口にする間の 、間に合わせのような存在 、それがフライドポテトというものだ 。しかしマクドナルド兄弟のポテトは別格だ 。ふたりはフライドポテトにあふれんばかりの情熱を注いでいたのである 。(略)しかし 、それは間違った認識であり 、これがフライドポテトに対するアメリカ人の食欲を減退させる原因となっていた。一方 、マドナルド兄弟は 、フライドポテトを揚げる油は 、ほかの材料には決して使用しない 。第一、そんな誘惑など起こるはずもない 。なぜなら 、揚げ物メニュ ーは 、フライドポテト以外に何もないのだから 。これを考えると 、一袋三オンスで 、一〇セントとは 、非常に安い価格設定だ 。事実 、フライドポテトは飛ぶように売れていた 。アルミニウムの大きな塩入れが 、フライドポテトの受け取り口に 、長い鎖でつながれて置いてあり 、それは 、救世軍のブラスバンドの少女が持つタンバリンを思い起こさせた 。』
The McDonald’s approach to french fries was a very interesting process to me and, I was happy to observe, it was every bit as simple as the McDonald boys had told me it was. I was convinced that I had it down pat in my head, and that anybody could do it if he followed those individual steps to the letter. That was just one of the many mistakes I would make in my dealings with the McDonald brothers. After the lunch-hour rush had abated, I got together with Mac and Dick McDonald again. My enthusiasm for their operation was genuine, and I hoped it would be infectious and rally them in favor of the plan I had mapped out in my mind. “I’ve been in the kitchens of a lot of restaurants and drive-ins selling Multimixers around the country,” I told them, “and I have never seen anything to equal the potential of this place of yours. Why don’t you open a series of units like this? It would be a gold mine for you and for me, too, because every one would boost my Multimixer sales. What d’you say?” Silence. I felt like I’d dragged my tie in my soup or something. The two brothers just sat there looking at me. Then Mac gave that little wince that sometimes passes for a smile in New England and turned around in his chair to point up at the hill overlooking the restaurant. “See that big white house with the wide front porch?” he asked. “That’s our home and we love it. We sit out on the porch in the evenings and watch the sunset and look down on our place here. It’s peaceful. We don’t need any more problems. We are in a position to enjoy life now, and that’s just what we intend to do.” His approach was utterly foreign to my thinking, so it took me a few minutes to reorganize my arguments. But it soon became apparent that further discussion along that line would be futile, so I said they could have their cake and eat it too by getting somebody else to open the other places for them. I could still peddle my Multimixers in the chain. “It’ll be a lot of trouble,” Dick McDonald objected. “Who could we get to open them for us?” I sat there feeling a sense of certitude begin to envelope me. Then I leaned forward and said, “Well, what about me?”
* * The most important item in my plans for the company was to end our relationship with the McDonald brothers. This was partly for personal reasons; Mac and Dick were beginning to get on my nerves with their business game playing. For example, I had introduced them to my good friend and paper supplier, Lou Perlman, and they began buying all of their paper products from him, too. They would come to Chicago and visit Lou and ask him to drive them around to see all the McDonald’s locations in the area, which he did, but they would not come by corporate headquarters or even call me on the telephone; Lou would fill me in later on where they’d gone and what they’d said. But the main reason I wanted to be done with the McDonalds was that their refusal to alter any terms of the agreement was a drag on our development. They blamed their attorney for this lack of cooperation, and he and I certainly were at dagger’s point all the time; but whatever the reason, I wanted to be free of their hold on me. I knew from conversations I’d had with Lou Perlman and others that the McDonald boys could be persuaded to sell. Maurice’s health had not been the best, and Dick had expressed concern about that and talked about retiring. I wanted to help them retire, but I was afraid of what it might cost me. Harry Sonneborn and I had several long sessions hashing over the pros and cons of it, deciding the best approach to take. Finally, we determined that we would hit them right between the eyes with it. No use shilly-shallying, because their lawyer would only waste a lot of time bickering about it, and we would come out at the same place in the end anyhow. So I called Dick McDonald and asked him to name their price. After a day or two he did, and I dropped the phone, my teeth, and everything else. He asked me what the noise was, and I told him that was me jumping out of the 20th floor of the LaSalle-Wacker Building. They were asking $ 2.7 million! “We’d like to have a million dollars apiece after taxes, Ray,” Dick explained. “That’s for all the rights, the name, the San Bernardino store, and everything. You know, we feel we’ve earned it. We’ve been in business over thirty years, working seven days a week, week in and week out.” Very touching. But somehow I just couldn’t seem to work up any tears of pity. This was really going to take some financial wheeling and dealing. I asked Harry to take a run at the three insurance companies that had lent us the million and a half dollars. We had to anyhow, because they had a right of first refusal on McDonald’s borrowing for a period. But John Gosnell said Paul Revere Life couldn’t take any bigger bite than it had, Fred Fideli said State Mutual Life felt the same, and Massachusetts Protective couldn’t swing a deal without the other two. So there we were—three strikes and we were out on the street looking for some Santa Claus with a bagful of money. I was feeling pretty low, so I called Joni and told her about it. I said it would be a lot easier for me if I had her by my side. She said she needed more time. She couldn’t make up her mind. Damn! Harry found our money man in New York. His name was John Bristol, and he was financial advisor to Princeton University, Howard University, Carnegie Tech, the Ford Foundation and others, a total of twelve educational and charitable institutions. The deal we agreed on, I think, put a new wrinkle in American financial arrangements. Harry was delighted with its intricate design. Here’s how it worked: In return for $ 2.7 million in cash from Bristol’s group (who were called The Twelve Apostles in our records) we were to pay them .5 percent of the gross sales of all McDonald’s stores in three periods. In the first period we would pay .4 percent immediately and put aside .1 percent until the third period. The method of computing how much of the .4 percent would go to interest was figured on the basis of 6 percent of $ 2.7 million; whatever remained would go toward retiring the principal. The first period would end when the principal was retired. The second period would be for a length of time equal to the first period, whatever that was. In the second period we would pay a straight .5 percent of our gross. The third period, then, would be the payment of the deferred .1 percent from the first period. Our original projection sheets anticipated that it would take us until 1991 to pay it all off. But that was on the basis of 1961 volume. We managed to pay off the principal in six years and finished paying off the loan completely in 1972. It was an extremely successful deal. All concerned were happy. The Twelve Apostles wound up making about $ 12 million on it, and while that seems like a terrific price to pay, remember that we had been forking over .5 percent to the McDonald brothers all along anyhow. The total cost of the transaction to us—about $ 14 million—was peanuts compared to what the corporation earned in the years that followed by retaining that .5 percent instead of paying it to Mac and Dick McDonald. On today’s systemwide sales of more than $ 3 billion, that .5 percent would be up there over $ 15 million a year. The McDonald brothers retired happily to travel and tend their real estate investments in Palm Springs. Maurice died a few years later and Dick moved back to New Hampshire and married his childhood sweetheart, a pleasant person named Dorothy French, daughter of a Manchester banker. Her first husband had died and Dick and his first wife were divorced, so the reunion was fortunate. I’m told that the marriage has mellowed Dick’s New England crustiness to the point where he now recalls our association as “the finest business relationship we ever had.” I was happy too, except for one part of the deal that stuck in my throat like a fishbone. That was the McDonald brothers’ last minute insistence on retaining their original restaurant in San Bernardino. They were going to have their employees run it for them. What a goddam rotten trick! I needed the income from that store. There wasn’t a better location in the entire state. I screamed like hell about it. But no way. They decided they wanted to keep it, and they were willing to pull the plug on the whole arrangement if they didn’t get it. Eventually I opened a McDonald’s across the street from that store, which they had renamed The Big M, and it ran them out of business. But that episode is why I can’t feel charitable or forgiving toward the McDonald brothers. They went back on their promise, made on a handshake, and forced me into grinding it out, grunting and sweating like a galley slave for every inch of progress in California. California! I was fascinated by the promise I saw out there. The tide of population growth and economic and cultural energy in the country had shifted from the Northeast and was running toward the South and Southwest. I didn’t want McDonald’s to miss out on that rising crest. “You know, I’ve been thinking I ought to go out to California and open an office out there.…” I remarked to Art Trygg. “I knew another guy had ideas like that,” my companion said with mock peevishness as he wheeled my Thunderbird through Michigan Avenue traffic. “The doctor told him to soak his head in beer every night, and it cured him.” “Don’t you like sunshine, Art?” “Not if I can get moonshine, Ray.” I have a whole album of mental snapshots from that period. Turning through them brings back a rush of memories. Not nostalgia, but reaffirmation of my faith in McDonald’s and the people who helped me build it. I speak of faith in McDonald’s as if it were a religion. And, without meaning any offense to the Holy Trinity, the Koran, or the Torah, that’s exactly the way I think of it. I’ve often said that I believe in God, family, and McDonald’s—and in the office, that order is reversed. If you are running a hundred-yard dash, you aren’t thinking about God while you’re running. Not if you hope to win. Your mind is on the race. My race is McDonald’s.
《レイ ・ A ・クロック R a y m o n d A l b e r t K r o c ( 1 9 0 2─1 9 8 4 )アメリカ ・イリノイ州オ ークパ ーク生まれ 。高校中退後 、ペ ーパ ーカップのセ ールスマン 、ピアノマン 、マルチミキサーのセールスマンとして働く 。 1 9 5 4年 、マクドナルド兄弟と出会い 、マクドナルドのフランチャイズ権を獲得 、全米展開に成功 。 1 9 8 4年には世界 8 0 0 0店舗へと拡大した (現在マクドナルドは世界カ国に約 3 0 0 0 0店を展開 ) 。後年にレイ ・クロック財団を設立 。さらにメジャーリーグのサンディエゴ ・パドレス獲得など精力的に活動を行った 。本書原題 〝 G R I N D I N G ・ I T・ O U T 〟はいまも多くのアメリカの学生に読まれ続けている 。》
この場面が印象に残る。ここにはMacdonald兄弟とRayとの間の別の哲学がある。
“See that big white house with the wide front porch?” he asked. “That’s our home and we love it. We sit out on the porch in the evenings and watch the sunset and look down on our place here. It’s peaceful. We don’t need any more problems. We are in a position to enjoy life now, and that’s just what we intend to do.” His approach was utterly foreign to my thinking, so it took me a few minutes to reorganize my arguments.
映画が面白かったので、すぐにある本を読むことにした。レイ・A・クロック 他4名
『成功はゴミ箱の中に 』レイ・クロック自伝

『その夜 、モ ーテルに戻って 、私は今日一日の出来事を思い返してみた 。すると突然私の脳裏に 、マクドナルドの店舗を 、国中の主要道路に展開させるという考えがひらめいた 。各店に置かれた八台のマルチミキサ ーが 、ブンブン音を立てながら休みなく動き 、お金をどんどんかき出してくれる 。何とも魅力的な商売ではないか 。翌朝 、起きたときには 、すでにプランが頭の中に出来上がっていた 。マクドナルド兄弟とビジネスの契約を結ぶ光景を思い浮かべ 、何度もそのイメ ージシナリオを 、頭の中で繰り返した 。たまらなく魅惑的な光景だった 。前日にマクドナルド兄弟と話ができたおかげで 、様々な知識を得ることができた 。たとえばスタッフの鉄板さばきである 。ピシャリと音を立てて 、ハンバーガーのパティを裏返したり 、鉄板の温度を下げずに 、表面の汚れをこすり落とし 、続けてパティを焼くといった方法等に感心したが 、なかでも最も感銘を受けたのが 、フライドポテトの揚げ方だ 。マクドナルド兄弟も 、事業が成功した理由の一つは間違いなくフライポテトだと言っていた 。ふたりは作り方のプロセスを口頭で説明してくれたのだが 、私はどうしても自分の目でそれを確かめたかった 。そこには 、何か大きな企業秘密が隠されているに違いなかったからである 。普通の人は 、フライドポテトにとりたてて関心など持たない 。ハンバ ーガ ーや 、ミルクシェイクを口にする間の 、間に合わせのような存在 、それがフライドポテトというものだ 。しかしマクドナルド兄弟のポテトは別格だ 。ふたりはフライドポテトにあふれんばかりの情熱を注いでいたのである 。(略)しかし 、それは間違った認識であり 、これがフライドポテトに対するアメリカ人の食欲を減退させる原因となっていた。一方 、マドナルド兄弟は 、フライドポテトを揚げる油は 、ほかの材料には決して使用しない 。第一、そんな誘惑など起こるはずもない 。なぜなら 、揚げ物メニュ ーは 、フライドポテト以外に何もないのだから 。これを考えると 、一袋三オンスで 、一〇セントとは 、非常に安い価格設定だ 。事実 、フライドポテトは飛ぶように売れていた 。アルミニウムの大きな塩入れが 、フライドポテトの受け取り口に 、長い鎖でつながれて置いてあり 、それは 、救世軍のブラスバンドの少女が持つタンバリンを思い起こさせた 。』
マクドナルドのフライドポテトの作り方は、私にとってとても興味深いものだった。私は、自分の頭の中でそれを完璧にマスターしており、個々の手順を忠実に守れば誰にでもできると確信していた。それは、マクドナルド兄弟との付き合いの中で私が犯した多くの過ちのひとつに過ぎなかった。ランチタイムのラッシュが一段落した後、私はマックとディック・マクドナルドと再会した。彼らの経営に対する私の熱意は本物であり、それが伝染して、私が心に描いた計画に賛成してくれることを願っていた。「私は全国でマルチミキサーを販売している多くのレストランやドライブインの厨房を見てきたが、君たちの店の可能性に匹敵するものを見たことがない。このようなユニットを何台もオープンさせたらどうですか?あなた方にとっても、私にとっても金鉱となるだろう。どうだい?沈黙。私はネクタイをスープの中に引きずり込んだような気がした。二人の兄弟はただ座って私を見ていた。そしてマックは、ニューイングランドでは時折笑顔と見紛うような、小さなうずくまりを見せ、椅子の上で振り返り、レストランを見下ろす丘を指差した。「あの広い玄関ポーチのある大きな白い家が見える?「あれが僕らの家で、大好きなんだ。夕方、ポーチに座って夕日を眺めながら、ここを見下ろしているんだ。平和なんだ。これ以上の問題は必要ない。私たちは今、人生を楽しむ立場にいる。彼のアプローチは私の考え方とはまったく異なっていたため、自分の主張を整理し直すのに数分かかった。しかしすぐに、これ以上この路線で議論しても無駄だということがわかったので、私は、他の誰かに他の場所を開けてもらえば、彼らもケーキを食べることができると言った。私はまだマルチミキサーをチェーンで売り歩くことができる。「ディック・マクドナルドは反対した。「誰が代わりに開けてくれるんだ?私はその場に座り込み、確信に包まれ始めたのを感じた。そして私は身を乗り出して言った。
* 会社の計画で最も重要なのは、マクドナルド兄弟との関係を終わらせることだった。これは個人的な理由もあった。マックとディックはビジネス上の駆け引きで私の神経を逆なでし始めていたのだ。例えば、私は彼らに私の親友であり製紙業者でもあるルー・パールマンを紹介し、彼らは製紙製品もすべて彼から買うようになった。彼らはシカゴにやってきてはルーを訪ね、その地域のマクドナルドの店舗をすべて見て回ってくれるよう頼んだ。しかし、私がマクドナルドと決別したかった最大の理由は、彼らが契約条件の変更を一切拒否したことが、私たちの発展の足かせになったからだ。彼らはこの非協力的な態度を弁護士のせいにし、私と弁護士は常に短剣を突き合わせていた。ルー・パールマンや他の人たちとの会話から、マクドナルドの息子たちが売るように説得できることはわかっていた。モーリスの健康状態は芳しくなく、ディックもそれを心配して引退を口にした。私は彼らの引退を手助けしたかったが、そのために自分が犠牲になるかもしれないことを恐れていた。ハリー・ソネボーンと私は、その是非について何度も長い時間をかけて話し合い、最善の方法を決めた。最終的に、私たちは彼らの眉間を直撃することに決めた。というのも、彼らの弁護士はそのことで口論して時間を浪費するだけで、いずれにせよ最終的には同じところに行き着くだろうからだ。そこで私はディック・マクドナルドに電話し、彼らの値段を聞いてみた。1日か2日後、彼はそう言って、私は電話も歯も何もかも落とした。彼は私に何の音かと尋ねたので、ラサール・ワッカー・ビルの20階から私が飛び降りた音だと答えた。彼らは270万ドルを要求していた!「税引き後で1人100万ドル欲しいんだ、レイ」とディックは説明した。「権利、名前、サンバーナーディーノ店、すべてだ。もう30年以上商売をしているんだ。私たちは30年以上商売を続け、週7日、毎日働いてきたんだ」。とても感動的だった。しかし、私はなぜか哀れみの涙を流すことができなかった。これは本当に資金繰りに苦労しそうだった。私はハリーに、150万ドルを貸してくれた3つの保険会社を当たってみるよう頼んだ。というのも、保険会社にはマクドナルドの借入れに対する優先交渉権があったからだ。しかし、ジョン・ゴスネルは、ポール・リビア生命はこれ以上大きく食い下がることはできないと言い、フレッド・フィデリは、ステート相互生命も同じ考えだと言い、マサチューセッツ・プロテクティブは、他の2社なしでは取引できないと言った。 私たちは3ストライクで、袋一杯のお金を持ってサンタクロースを探していたんだ。かなり落ち込んでいたので、ジョニに電話してそのことを話した。彼女がそばにいてくれたら、もっと楽になれると言ったんだ。彼女はもっと時間が必要だと言った。決心がつかなかったんだくそっ!ハリーはニューヨークで金の亡者を見つけた。彼の名前はジョン・ブリストルで、プリンストン大学、ハワード大学、カーネギー工科大学、フォード財団など、合計12の教育機関や慈善団体の財務アドバイザーだった。私たちが合意した取引は、アメリカの財政制度に新しい風を吹き込むものだったと思う。ハリーはその複雑な設計に大喜びだった。その仕組みはこうだ:ブリストルのグループ(私たちの記録では「12使徒」と呼ばれていた)から270万ドルの現金を受け取る代わりに、私たちは彼らにマクドナルド全店舗の売上総利益の0.5%を3つの期間に支払うことになった。第1期はすぐに0.4パーセントを支払い、第3期まで0.1パーセントを積み立てる。0.4パーセントのうちいくらが利息に充てられるかの計算方法は、270万ドルの6パーセントを基準に計算された。最初の期間は元本が償還された時点で終了する。第二の期間は、第一の期間と同じ期間である。第二の期間は、総収入の0.5パーセントを支払う。そして第3期は、第1期から繰り延べられた0.1パーセントの支払いとなる。当初の予想では、すべてを返済するには1991年までかかると見込んでいた。しかし、それは1961年の出来高に基づくものだった。私たちはなんとか6年で元本を返済し、1972年にローンを完済した。非常に成功した取引だった。関係者全員が満足した。十二使徒は最終的に約1200万ドルの利益を得ましたが、これは大変な代償のように思えますが、私たちはマクドナルド兄弟にずっと0.5パーセントを支払っていたことを思い出してください。マックとディック・マクドナルドに支払う代わりにその0.5%を保持することで、その後の数年間に企業が得た収入に比べれば、私たちが負担した総費用は約1,400万ドルであった。今日のシステム全体の売上高が30億ドル以上であれば、その0.5%は年間1,500万ドル以上になる。マクドナルド兄弟は、旅行とパームスプリングスでの不動産投資のために幸せに引退した。数年後にモーリスが亡くなり、ディックはニューハンプシャーに戻り、マンチェスターの銀行家の娘で気さくなドロシー・フレンチという幼なじみの恋人と結婚した。彼女の最初の夫は亡くなり、ディックと彼の最初の妻は離婚していたので、再会は幸運だった。この結婚によって、ディックのニューイングランド人特有のギスギスした雰囲気は和らぎ、今では私たちとの付き合いを "最高のビジネス関係だった "と振り返るまでになったと聞いている。私も幸せだった。ただ、契約の中で、私の喉に魚の骨のように引っかかった部分があった。それは、マクドナルド兄弟がサンバーナーディーノにあるオリジナルのレストランを残すことに最後までこだわったことだ。彼らは従業員に店を運営させるつもりだったのだ。なんて腐った手口なんだ!私にはあの店からの収入が必要だった。州全体を見渡しても、これ以上の立地はなかった。私は必死に叫んだ。でもダメだった。彼らはこの店舗を維持したいと考え、もし手に入らなかったら、すべての取り決めを白紙に戻すつもりだった。結局、私はその店の向かいにマクドナルドを開店し、彼らはビッグMと名前を変えた。しかし、このエピソードがあるからこそ、私はマクドナルド兄弟に対して憐れみも許しも感じられないのだ。彼らは握手で交わした約束を反故にし、カリフォルニアの発展のために、厨房の奴隷のように呻き、汗をかきながら、私を無理やり働かせたのだ。カリフォルニア!私はそこで見た約束に魅了された。人口増加と経済的・文化的エネルギーの潮流は、北東部から南部と南西部へと向かっていた。マクドナルドには、その上昇気流に乗り遅れたくなかった。「カリフォルニアに行って事務所を開くべきだとずっと考えていたんだが......」。私はアート・トリッグに言った。「ミシガン・アベニューの渋滞の中を私のサンダーバードを走らせながら、仲間は小馬鹿にしたように言った。「医者が毎晩ビールに頭を浸すように言ったら、治ったんだ」。「太陽の光は嫌いかい、アート?「密造酒が手に入るならね、レイ」。私はその頃のスナップ写真をアルバム一冊分持っている。それをめくると、思い出がふつふつと蘇ってくる。懐かしさではなく、マクドナルドとマクドナルドを支えてくれた人々に対する私の信頼を再確認するのだ。私はマクドナルドへの信仰を宗教のように語っている。そして、三位一体やコーラン、トーラーに悪気はないのだが、まさに私はそう考えているのだ。 私はよく、神、家族、マクドナルドを信じていると言ってきたが、オフィスではその順番が逆になる。もしあなたが100ヤードダッシュをするのであれば、走っている最中に神のことを考えることはない。勝つことを望むなら、そうではない。あなたの心はレースにある。私のレースはマクドナルドだ。
* * The most important item in my plans for the company was to end our relationship with the McDonald brothers. This was partly for personal reasons; Mac and Dick were beginning to get on my nerves with their business game playing. For example, I had introduced them to my good friend and paper supplier, Lou Perlman, and they began buying all of their paper products from him, too. They would come to Chicago and visit Lou and ask him to drive them around to see all the McDonald’s locations in the area, which he did, but they would not come by corporate headquarters or even call me on the telephone; Lou would fill me in later on where they’d gone and what they’d said. But the main reason I wanted to be done with the McDonalds was that their refusal to alter any terms of the agreement was a drag on our development. They blamed their attorney for this lack of cooperation, and he and I certainly were at dagger’s point all the time; but whatever the reason, I wanted to be free of their hold on me. I knew from conversations I’d had with Lou Perlman and others that the McDonald boys could be persuaded to sell. Maurice’s health had not been the best, and Dick had expressed concern about that and talked about retiring. I wanted to help them retire, but I was afraid of what it might cost me. Harry Sonneborn and I had several long sessions hashing over the pros and cons of it, deciding the best approach to take. Finally, we determined that we would hit them right between the eyes with it. No use shilly-shallying, because their lawyer would only waste a lot of time bickering about it, and we would come out at the same place in the end anyhow. So I called Dick McDonald and asked him to name their price. After a day or two he did, and I dropped the phone, my teeth, and everything else. He asked me what the noise was, and I told him that was me jumping out of the 20th floor of the LaSalle-Wacker Building. They were asking $ 2.7 million! “We’d like to have a million dollars apiece after taxes, Ray,” Dick explained. “That’s for all the rights, the name, the San Bernardino store, and everything. You know, we feel we’ve earned it. We’ve been in business over thirty years, working seven days a week, week in and week out.” Very touching. But somehow I just couldn’t seem to work up any tears of pity. This was really going to take some financial wheeling and dealing. I asked Harry to take a run at the three insurance companies that had lent us the million and a half dollars. We had to anyhow, because they had a right of first refusal on McDonald’s borrowing for a period. But John Gosnell said Paul Revere Life couldn’t take any bigger bite than it had, Fred Fideli said State Mutual Life felt the same, and Massachusetts Protective couldn’t swing a deal without the other two. So there we were—three strikes and we were out on the street looking for some Santa Claus with a bagful of money. I was feeling pretty low, so I called Joni and told her about it. I said it would be a lot easier for me if I had her by my side. She said she needed more time. She couldn’t make up her mind. Damn! Harry found our money man in New York. His name was John Bristol, and he was financial advisor to Princeton University, Howard University, Carnegie Tech, the Ford Foundation and others, a total of twelve educational and charitable institutions. The deal we agreed on, I think, put a new wrinkle in American financial arrangements. Harry was delighted with its intricate design. Here’s how it worked: In return for $ 2.7 million in cash from Bristol’s group (who were called The Twelve Apostles in our records) we were to pay them .5 percent of the gross sales of all McDonald’s stores in three periods. In the first period we would pay .4 percent immediately and put aside .1 percent until the third period. The method of computing how much of the .4 percent would go to interest was figured on the basis of 6 percent of $ 2.7 million; whatever remained would go toward retiring the principal. The first period would end when the principal was retired. The second period would be for a length of time equal to the first period, whatever that was. In the second period we would pay a straight .5 percent of our gross. The third period, then, would be the payment of the deferred .1 percent from the first period. Our original projection sheets anticipated that it would take us until 1991 to pay it all off. But that was on the basis of 1961 volume. We managed to pay off the principal in six years and finished paying off the loan completely in 1972. It was an extremely successful deal. All concerned were happy. The Twelve Apostles wound up making about $ 12 million on it, and while that seems like a terrific price to pay, remember that we had been forking over .5 percent to the McDonald brothers all along anyhow. The total cost of the transaction to us—about $ 14 million—was peanuts compared to what the corporation earned in the years that followed by retaining that .5 percent instead of paying it to Mac and Dick McDonald. On today’s systemwide sales of more than $ 3 billion, that .5 percent would be up there over $ 15 million a year. The McDonald brothers retired happily to travel and tend their real estate investments in Palm Springs. Maurice died a few years later and Dick moved back to New Hampshire and married his childhood sweetheart, a pleasant person named Dorothy French, daughter of a Manchester banker. Her first husband had died and Dick and his first wife were divorced, so the reunion was fortunate. I’m told that the marriage has mellowed Dick’s New England crustiness to the point where he now recalls our association as “the finest business relationship we ever had.” I was happy too, except for one part of the deal that stuck in my throat like a fishbone. That was the McDonald brothers’ last minute insistence on retaining their original restaurant in San Bernardino. They were going to have their employees run it for them. What a goddam rotten trick! I needed the income from that store. There wasn’t a better location in the entire state. I screamed like hell about it. But no way. They decided they wanted to keep it, and they were willing to pull the plug on the whole arrangement if they didn’t get it. Eventually I opened a McDonald’s across the street from that store, which they had renamed The Big M, and it ran them out of business. But that episode is why I can’t feel charitable or forgiving toward the McDonald brothers. They went back on their promise, made on a handshake, and forced me into grinding it out, grunting and sweating like a galley slave for every inch of progress in California. California! I was fascinated by the promise I saw out there. The tide of population growth and economic and cultural energy in the country had shifted from the Northeast and was running toward the South and Southwest. I didn’t want McDonald’s to miss out on that rising crest. “You know, I’ve been thinking I ought to go out to California and open an office out there.…” I remarked to Art Trygg. “I knew another guy had ideas like that,” my companion said with mock peevishness as he wheeled my Thunderbird through Michigan Avenue traffic. “The doctor told him to soak his head in beer every night, and it cured him.” “Don’t you like sunshine, Art?” “Not if I can get moonshine, Ray.” I have a whole album of mental snapshots from that period. Turning through them brings back a rush of memories. Not nostalgia, but reaffirmation of my faith in McDonald’s and the people who helped me build it. I speak of faith in McDonald’s as if it were a religion. And, without meaning any offense to the Holy Trinity, the Koran, or the Torah, that’s exactly the way I think of it. I’ve often said that I believe in God, family, and McDonald’s—and in the office, that order is reversed. If you are running a hundred-yard dash, you aren’t thinking about God while you’re running. Not if you hope to win. Your mind is on the race. My race is McDonald’s.
《レイ ・ A ・クロック R a y m o n d A l b e r t K r o c ( 1 9 0 2─1 9 8 4 )アメリカ ・イリノイ州オ ークパ ーク生まれ 。高校中退後 、ペ ーパ ーカップのセ ールスマン 、ピアノマン 、マルチミキサーのセールスマンとして働く 。 1 9 5 4年 、マクドナルド兄弟と出会い 、マクドナルドのフランチャイズ権を獲得 、全米展開に成功 。 1 9 8 4年には世界 8 0 0 0店舗へと拡大した (現在マクドナルドは世界カ国に約 3 0 0 0 0店を展開 ) 。後年にレイ ・クロック財団を設立 。さらにメジャーリーグのサンディエゴ ・パドレス獲得など精力的に活動を行った 。本書原題 〝 G R I N D I N G ・ I T・ O U T 〟はいまも多くのアメリカの学生に読まれ続けている 。》
この場面が印象に残る。ここにはMacdonald兄弟とRayとの間の別の哲学がある。
“See that big white house with the wide front porch?” he asked. “That’s our home and we love it. We sit out on the porch in the evenings and watch the sunset and look down on our place here. It’s peaceful. We don’t need any more problems. We are in a position to enjoy life now, and that’s just what we intend to do.” His approach was utterly foreign to my thinking, so it took me a few minutes to reorganize my arguments.