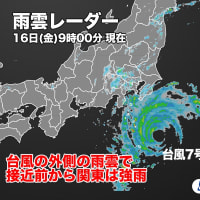ライプニッツは論理的思考の人なので、
四七 そこで神だけが、原初的な「一」、つまり本源的な単一実体で、創造されたモナド、つまり派生的モナドはすべてその生産物にほかならない。これらのモナドは、いわば時々刻々、神の身から不断に放射されている閃光(57)によって生みだされるが、本性上有限な被造物のならいとして、(神のささえを)うけなければ生きてゆけないということが、モナドの立場を制限しているわけなのである。
訳者註(57)「閃光 fulguration」という語を使ったのは、創造と流出との中間を示すためであるという。「形而上学叙説」14では、流出という語を用いているが、このことばを使えば、神と被造物とは連続的につながっていることになり、創造といえば両者の関係は非連続的な性格を強める。神にたいする被造物の依存関係には、非連続、連続の両面があるという見地から、閃光という語が用いられたものと考えられる。
神の「閃光」とライプニッツが呼ぶ作用はエンテレケイア(日本語訳「現実性」は適切ではない むしろ詩的に神の閃光がいいと思う)とも別に表現されている、これによりライプニッツはアリストテレス哲学と接続点を持つ体系であることを主張しているように見える。多世界宇宙論にも通じる思弁を展開したライプニッツであったが当時の常識であるアリストテレス哲学と予定調和論に矛盾しないように工夫されているモナドロジーは現代的に、思弁哲学を乗り越えて再解釈しモナド論を《モナドもつれ関数の群論的アトミズム》として発展させたいと思っている私にとって窮屈で中途半端である。 もつれ:対象を認識するさまざまな仕方全般の物理的基礎

六〇 とにかく、いまお話ししたところから、なぜものごとの起こるのがこうであって、それ以外ではないかということの、ア・プリオリな理由がわかる。というのも、神は全体を統治するかたわら、おのおのの部分、つまりくわしくいえば、おのおののモナドについても心にかけているからであり、また、モナドは表現ということが本性であるため、何ものもそれに制限をくわえて、事物の一部分しか表現しないようにすることはできないからである。もっともこの表現作用も、宇宙全体の細部では、錯雑したものであって、判明なのは事物のごく小部分においてにすぎない。つまり、おのおののモナドにたいする関係から見て、いちばん近いもの(68)とか、いちばん大きなものとかの場合にすぎない。でないと、どのモナドも神になってしまう。つまりモナドが制限をうけているのは、その対象についてではなく、対象を認識するさまざまな仕方においてなのである。どのモナドも、錯雑した仕方ではあるが、みな無限へむかい、全体へむかっている(69)。しかし、それぞれ制限をうけていて、表象の判明さの度合に応じて、区別されている。
Entelechy (entelechia)
Entelechy, in Greek entelécheia, was coined by Aristotle and transliterated in Latin as entelechia. According to Sachs (1995, p. 245):
Aristotle invents the word by combining entelēs (ἐντελής, 'complete, full-grown') with echein (= hexis, to be a certain way by the continuing effort of holding on in that condition), while at the same time punning on endelecheia (ἐνδελέχεια, 'persistence') by inserting telos (τέλος, 'completion'). This is a three-ring circus of a word, at the heart of everything in Aristotle's thinking, including the definition of motion.
Sachs therefore proposed a complex neologism of his own, "being-at-work-staying-the-same".[17]Another translation in recent years is "being-at-an-end" (which Sachs has also used).[2]
Entelecheia, as can be seen by its derivation, is a kind of completeness, whereas "the end and completion of any genuine being is its being-at-work" (energeia). The entelecheia is a continuous being-at-work (energeia) when something is doing its complete "work". For this reason, the meanings of the two words converge, and they both depend upon the idea that every thing's "thinghood" is a kind of work, or in other words a specific way of being in motion. All things that exist now, and not just potentially, are beings-at-work, and all of them have a tendency towards being-at-work in a particular way that would be their proper and "complete" way.[17]