先日、弘前こぎん研究所にお邪魔させていただいた時、
成田所長をおみかけしました。
「こんにちは~」と気さくに声をかけて下さいました。
art-bookshop“ abcgallery”でされた
こぎん刺しの講演会には行けなかったんですが、
まさかこんなにあっさりとお見受けするとは!
ま、本拠地ですもんね。会ってもおかしくないですよね。
まずは、1Fの事務所の中で、
こぎん刺しの製品を拝見
バッグや、箸入れや、ネクタイや、くるみボタン各種…
…そして、受付(?)をされていた女性が、
特注で受けたタペストリーの刺繍過程を
見せてくれました。
特注品以外は、内職でこぎんを刺してもらっているそうです。
たぶん、私はそわそわしていたと思います。
早く、工房を見せていただきたくて…。
とにかく職人の技を見たくて…。
そんな私の気を察したのか、早々に
別棟にある工房へ案内してくれました。
スリッパに履き替え、2Fにあがると、
違う女性に説明がバトンタッチされ。
入り口近くにある はた織り機には、
(たぶん)帯にする麻布を織り途中でした。
奥では、刺し上がったものにアイロンをかけている方が。
その説明をしてくださったんですが、
気分が舞い上がって聞いてませんでした
アイロンかけに一区切りついたところで、
こぎん刺しの実演を見せていただきました。
紺の麻布で、すでに布の真ん中を定め、
10段近く刺してあるものの続きをしてくださいました。
図案は、1/4しか書かれておらず、
(ほとんどそれも見ていませんでしたが)
それはもう素早い手さばきで
何目拾って、何目捨ててるのかわからないスピードで
一山仕上げてしまいました。
良く見ると、刺し進む方向にうっすらと後が…。
最新の機械で、
模様が浮き出ているのかと思っていたらそうではなく、
いったん内職に出して刺してもらったものをチェックしたら、
布の裏表が間違っていたので、
ほどいてもう一度刺し直しているとのことでした。
それを聞いてあわてて私、
「布に裏表があるんですか 」と質問。
」と質問。
今まで、そんなの全然気にした事ないしっ
すると「そんなに気にしなくてもいいですが、
染めむらやちょっとしたほつれがある方が表だと
製品として出せないんですよ」との答え。
やはり売り物としてお客さんの手にするものだから、
気をつかっているようです。
そこで私「ほどいた糸はまた使われるんでしょうか?」
(最近、図案の見方を忘れてしまって、
何度も何度もほどいて糸がすり切れたので)
職人の方「使いますよ。もったいないので」
それを聞いて妙に納得。
こぎん刺しも昔は普段着として活用していて、
すり切れてもまた補修してボロボロになっても
着ていたそうです。
こぎん研究所では、布も織っておられ、
(全ての製品分かは未確認です)
糸もオリジナル色(業者に染めてもらっているそうですが)。
そうしてこだわっている分、
もったいないという気持ちは大切ですね。
ちなみに、ほどいた糸も使用するということですが、
2、3段ほどいた場合で、あまりたくさんほどいたものは、
糸の状態がよくないので、流石に使わないそうです。
一山仕上がる間に、
自己流でやっている私の疑問に
いろいろ答えて下さり、見本も見せて下さいました。
以下、その内容をまとめてみます
・針は、一段の刺し途中で表に出さない。
布がクシャクシャになっても皿付指ぬき(確か中指の付け根にはめていた)で端まで送り続ける。
(その時は約30cm幅の麻布に刺していた)
・布を伸ばして、糸を引く。
その際、縒りがなくならないように針を右手に持ち、右にまわしながら左端の糸のたるみを約4~5cm残し糸を引く。
糸を引いた時、左端の糸がぐるぐるとトグロをまいていたら、縒りがかかりすぎているので、針をひっかけて左側に多少糸を戻す。
そして、縒りを緩めるため、針を左にまわしながら糸を引く。
縒りがちょうど良くなるまで、糸を左に引っぱり右に引っぱりを繰り返す。
・裏に渡っている糸(刺した長さの半分ぐらいのところ。中継地点と考える)に針をひっかけて引き、糸こき。
左手は糸の輪のすぐ横に、右手は糸を引っぱった中継地点を摑み、布をぐるぐるまわすように引っぱる。こぎん糸と布をなじませる感じ。
左端の糸の輪を2、3mmたるませるのを忘れないように。具合を見ながら。
・次に中継地点に少し糸をたるませ(たぶん2、3mmでいいと思います)右端まで糸を引ききり、今度は左手で中継地点の左横を摑み、右手で右端の糸の出口をつかみ、ぐるぐると糸こき。
・一段がそんなに長くないときは、中継地点は設けないようです。
(感覚で刺されているのでそれを見極めるには経験が必要だと感じました)
・糸が終わったらその都度 糸処理。布の裏側。
糸処理する段の一段上の、糸が裏に渡ってないところを一目ずつひろって1.5cm程刺し戻る。余った糸を切る。
・刺し終わったら、裏からアイロンをかける。
※あまり幅の広い布にこぎんを刺す時は、やはり途中でいったん糸を引くようですが、詳しくは聞いてきませんでした。



研究所で見た過程を思い出しながら
箇条書きにしてみましたが、
やはり、映像を文章で表すのは難しいですね。
後で読み直したとき自分でもこの 内容わかるかな?
内容わかるかな?
もっといろいろ聞きたいことがあったんですが、
普段の仕事中にお邪魔させてもらって、
ただで、アレやコレやと質問するのも
相手の善意に乗っかっている気がして
厚かましいかなぁと思い、遠慮しました。
あれ…、十分厚かましいです…?
この実演を見学させてもらった後、1Fの事務所に戻り、
くるみボタン(小)を1ヶ購入したのですが、
どうしても、こぎん糸や布が欲しくて事務所の方に聞くと、
布は生産量が少ないので販売はせず、
糸はさっきの2F工房に置いてある ということなので、
再び工房へお邪魔。
箱に入っている糸をあさらせてもらい、
5色の糸を購入させていただきました。
こぎん研究所では、特に糸の太さは変えてないそうで、
みな同じ太さで刺しているということです。
糸の見本帳を持っていきましたが、
【つきや】でも、こぎん研究所でもついに一度も
出さずに終わり……。あれっ?
まぁ、結局は糸見本帳も自己満足のためだよね~
しかし、こぎん刺しを見てきたら、
なんかますます疑問が…
いろいろ聞きたい!
解消したい!
うーむ、それにはやはり習いに行くしかないか…?
こぎん刺し教室、通いた~~いです
成田所長をおみかけしました。
「こんにちは~」と気さくに声をかけて下さいました。
art-bookshop“ abcgallery”でされた
こぎん刺しの講演会には行けなかったんですが、
まさかこんなにあっさりとお見受けするとは!
ま、本拠地ですもんね。会ってもおかしくないですよね。
まずは、1Fの事務所の中で、
こぎん刺しの製品を拝見

バッグや、箸入れや、ネクタイや、くるみボタン各種…
…そして、受付(?)をされていた女性が、
特注で受けたタペストリーの刺繍過程を
見せてくれました。
特注品以外は、内職でこぎんを刺してもらっているそうです。
たぶん、私はそわそわしていたと思います。
早く、工房を見せていただきたくて…。
とにかく職人の技を見たくて…。
そんな私の気を察したのか、早々に
別棟にある工房へ案内してくれました。
スリッパに履き替え、2Fにあがると、
違う女性に説明がバトンタッチされ。
入り口近くにある はた織り機には、
(たぶん)帯にする麻布を織り途中でした。
奥では、刺し上がったものにアイロンをかけている方が。
その説明をしてくださったんですが、
気分が舞い上がって聞いてませんでした

アイロンかけに一区切りついたところで、
こぎん刺しの実演を見せていただきました。
紺の麻布で、すでに布の真ん中を定め、
10段近く刺してあるものの続きをしてくださいました。
図案は、1/4しか書かれておらず、
(ほとんどそれも見ていませんでしたが)
それはもう素早い手さばきで
何目拾って、何目捨ててるのかわからないスピードで
一山仕上げてしまいました。
良く見ると、刺し進む方向にうっすらと後が…。
最新の機械で、
模様が浮き出ているのかと思っていたらそうではなく、
いったん内職に出して刺してもらったものをチェックしたら、
布の裏表が間違っていたので、
ほどいてもう一度刺し直しているとのことでした。
それを聞いてあわてて私、
「布に裏表があるんですか
 」と質問。
」と質問。今まで、そんなの全然気にした事ないしっ

すると「そんなに気にしなくてもいいですが、
染めむらやちょっとしたほつれがある方が表だと
製品として出せないんですよ」との答え。
やはり売り物としてお客さんの手にするものだから、
気をつかっているようです。
そこで私「ほどいた糸はまた使われるんでしょうか?」
(最近、図案の見方を忘れてしまって、
何度も何度もほどいて糸がすり切れたので)
職人の方「使いますよ。もったいないので」
それを聞いて妙に納得。
こぎん刺しも昔は普段着として活用していて、
すり切れてもまた補修してボロボロになっても
着ていたそうです。
こぎん研究所では、布も織っておられ、
(全ての製品分かは未確認です)
糸もオリジナル色(業者に染めてもらっているそうですが)。
そうしてこだわっている分、
もったいないという気持ちは大切ですね。
ちなみに、ほどいた糸も使用するということですが、
2、3段ほどいた場合で、あまりたくさんほどいたものは、
糸の状態がよくないので、流石に使わないそうです。
一山仕上がる間に、
自己流でやっている私の疑問に
いろいろ答えて下さり、見本も見せて下さいました。
以下、その内容をまとめてみます

・針は、一段の刺し途中で表に出さない。
布がクシャクシャになっても皿付指ぬき(確か中指の付け根にはめていた)で端まで送り続ける。
(その時は約30cm幅の麻布に刺していた)
・布を伸ばして、糸を引く。
その際、縒りがなくならないように針を右手に持ち、右にまわしながら左端の糸のたるみを約4~5cm残し糸を引く。
糸を引いた時、左端の糸がぐるぐるとトグロをまいていたら、縒りがかかりすぎているので、針をひっかけて左側に多少糸を戻す。
そして、縒りを緩めるため、針を左にまわしながら糸を引く。
縒りがちょうど良くなるまで、糸を左に引っぱり右に引っぱりを繰り返す。
・裏に渡っている糸(刺した長さの半分ぐらいのところ。中継地点と考える)に針をひっかけて引き、糸こき。
左手は糸の輪のすぐ横に、右手は糸を引っぱった中継地点を摑み、布をぐるぐるまわすように引っぱる。こぎん糸と布をなじませる感じ。
左端の糸の輪を2、3mmたるませるのを忘れないように。具合を見ながら。
・次に中継地点に少し糸をたるませ(たぶん2、3mmでいいと思います)右端まで糸を引ききり、今度は左手で中継地点の左横を摑み、右手で右端の糸の出口をつかみ、ぐるぐると糸こき。
・一段がそんなに長くないときは、中継地点は設けないようです。
(感覚で刺されているのでそれを見極めるには経験が必要だと感じました)
・糸が終わったらその都度 糸処理。布の裏側。
糸処理する段の一段上の、糸が裏に渡ってないところを一目ずつひろって1.5cm程刺し戻る。余った糸を切る。
・刺し終わったら、裏からアイロンをかける。
※あまり幅の広い布にこぎんを刺す時は、やはり途中でいったん糸を引くようですが、詳しくは聞いてきませんでした。



研究所で見た過程を思い出しながら
箇条書きにしてみましたが、
やはり、映像を文章で表すのは難しいですね。
後で読み直したとき自分でもこの
 内容わかるかな?
内容わかるかな?もっといろいろ聞きたいことがあったんですが、
普段の仕事中にお邪魔させてもらって、
ただで、アレやコレやと質問するのも
相手の善意に乗っかっている気がして
厚かましいかなぁと思い、遠慮しました。
あれ…、十分厚かましいです…?
この実演を見学させてもらった後、1Fの事務所に戻り、
くるみボタン(小)を1ヶ購入したのですが、
どうしても、こぎん糸や布が欲しくて事務所の方に聞くと、
布は生産量が少ないので販売はせず、
糸はさっきの2F工房に置いてある ということなので、
再び工房へお邪魔。
箱に入っている糸をあさらせてもらい、
5色の糸を購入させていただきました。
こぎん研究所では、特に糸の太さは変えてないそうで、
みな同じ太さで刺しているということです。
糸の見本帳を持っていきましたが、
【つきや】でも、こぎん研究所でもついに一度も
出さずに終わり……。あれっ?
まぁ、結局は糸見本帳も自己満足のためだよね~

しかし、こぎん刺しを見てきたら、
なんかますます疑問が…

いろいろ聞きたい!
解消したい!
うーむ、それにはやはり習いに行くしかないか…?
こぎん刺し教室、通いた~~いです



















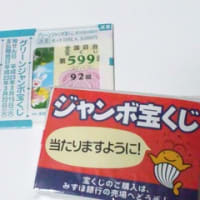

やはり針は一段全て刺すまで抜かないのですね。
私はちょっと刺しては糸を抜いて・・・を繰り返していたので、それが糸がつったり縒りが戻ったりする原因だったのかもしれません。
最後の糸の始末もすごくわかりやすくて、次に刺す時は早速試してみます。
私もこぎん研究所に行きたくなりました!
私も早速、端から端まで針を通そうとやってみたのですが、コングレスではとても難しかったです…。こぎん研究所、1度は行ってみることをオススメします! ただ、職人は15時には帰ってしまうそうです。一度TELしてから訪れた方がいいかもしれません。