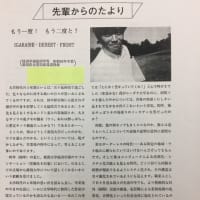●地方創生交付金を活かせ(その2)
私が出向で燕市役所に赴任した平成28年度において、国による地方創生に関する交付金は様相が変わってきていた。それまでは国主導で始まった地方創生の取組の初度段階を支援するということから、国が認めた事業費に対して国費100%の交付金を措置するものであったのだが、初期立ち上がりの段階はもう過ぎたことと、そもそも自治体自身の人口の維持増進のための取組でもあるのだから自治体自らも応分の費用負担すべきという、ある意味当然の論理から、地方創生の交付金は事業費の1/2を国費負担するということにされたのだ。
事業費の半分の自主財源を持ち出さなくてはならないとなると、国費交付金の活用についてのスタンスは大きく変わってくる。地方自治体で財政に余裕があるというのは、よほどの企業城下街とか都心近くの人口密集地域であり、そもそも地方創生が急務なような地方都市や過疎地域ほど財源が乏しいために思い切った手が打てないという実情がある。そうした自治体は、人件費など義務的で経常的な経費に自主財源の殆どを費やしているため、新たな打ち出し事業に回せる財源か乏しいのだ。
燕市の財政に責任を追うことになった私は、赴任して早々に直面した新たな地方創生関連の交付金にどう対応するかということに悩んだ。市が単独財源で進めている既往の事業に充当するだけという活用方法は当然のことながら国から認められない。さりとて新規事業を構築すればその半分の財源を市財政から新たに工面することになる。人口減少対策など地方創生に資する予算事業ともなればある程度の規模も必要となろう。そうなれば、既往のどの事業も余裕の無い中でしわ寄せを生じてしまうだろう。また、長年の積み重ねによる今の人口減に対して単発の事業で即座に成果が出る特効薬のような事業は考えにくく、費用対効果についての責任も持てないだろう。新参者でもある私は、確証の無い博打のようなことをではきるわけでもなく、この国費50%補助となる「地方創生推進交付金」を初めて活用するための7月臨時議会における市補正予算案においては、新たに実施する小規模のイベントなど控えめなラインナップとする手堅いものとしたのだ。
市議会側からも大きな異議はなく補正予算は臨時議会で可決されたのだが、暫くして地方創生推進交付金の全国的な活用状況などが報道され、その中で積極的に取り込んでいる市町村がクローズアップされたりし始めた9月の定例会になると、本会議において、「地方創生推進交付金の活用が少ない当市は地方創生への積極姿勢が足りないのではないか」という趣旨の質問まで出されるようになってきた。答弁案を考える私としては市費による負担を踏まえた費用対効果などで抗弁を展開したのであるが、他所のそれほど裕福でも無い自治体において財政負担をしながらも積極的に活用している事例を見聞きすると少し落ち着かなくなっては来た。石橋を叩くようにリスクとコストに基づいて慎重に査定する財政課長であると同時に、少ない財源を効果的効率的に活かす施策を如何に立案調整するかという企画課長でもあるという立場が、もっと知恵を出せないのかと私自身を責め立ててきたのだ。
事業費の半分の自主財源を持ち出さなくてはならないとなると、国費交付金の活用についてのスタンスは大きく変わってくる。地方自治体で財政に余裕があるというのは、よほどの企業城下街とか都心近くの人口密集地域であり、そもそも地方創生が急務なような地方都市や過疎地域ほど財源が乏しいために思い切った手が打てないという実情がある。そうした自治体は、人件費など義務的で経常的な経費に自主財源の殆どを費やしているため、新たな打ち出し事業に回せる財源か乏しいのだ。
燕市の財政に責任を追うことになった私は、赴任して早々に直面した新たな地方創生関連の交付金にどう対応するかということに悩んだ。市が単独財源で進めている既往の事業に充当するだけという活用方法は当然のことながら国から認められない。さりとて新規事業を構築すればその半分の財源を市財政から新たに工面することになる。人口減少対策など地方創生に資する予算事業ともなればある程度の規模も必要となろう。そうなれば、既往のどの事業も余裕の無い中でしわ寄せを生じてしまうだろう。また、長年の積み重ねによる今の人口減に対して単発の事業で即座に成果が出る特効薬のような事業は考えにくく、費用対効果についての責任も持てないだろう。新参者でもある私は、確証の無い博打のようなことをではきるわけでもなく、この国費50%補助となる「地方創生推進交付金」を初めて活用するための7月臨時議会における市補正予算案においては、新たに実施する小規模のイベントなど控えめなラインナップとする手堅いものとしたのだ。
市議会側からも大きな異議はなく補正予算は臨時議会で可決されたのだが、暫くして地方創生推進交付金の全国的な活用状況などが報道され、その中で積極的に取り込んでいる市町村がクローズアップされたりし始めた9月の定例会になると、本会議において、「地方創生推進交付金の活用が少ない当市は地方創生への積極姿勢が足りないのではないか」という趣旨の質問まで出されるようになってきた。答弁案を考える私としては市費による負担を踏まえた費用対効果などで抗弁を展開したのであるが、他所のそれほど裕福でも無い自治体において財政負担をしながらも積極的に活用している事例を見聞きすると少し落ち着かなくなっては来た。石橋を叩くようにリスクとコストに基づいて慎重に査定する財政課長であると同時に、少ない財源を効果的効率的に活かす施策を如何に立案調整するかという企画課長でもあるという立場が、もっと知恵を出せないのかと私自身を責め立ててきたのだ。
(「燕市企画財政課19「地方創生交付金を活かせ(その2)」編」終わり。県職員としては異例の職場となる燕市役所の企画財政課長への出向の回顧録「燕市企画財政課20「地方創生交付金を活かせ(その3)」編」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea