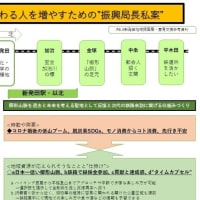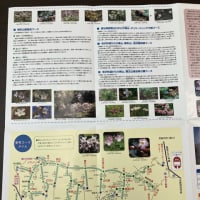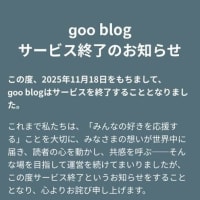■JR羽越本線100年を機に新発田地域の振興を考えます。
******************************************************************
◆新発田駅以北編・平木田駅
羽越本線100周年を機に、鉄路の利用増進と沿線の振興を絡めて何か考えられないかと、新発田地域振興局管内の各駅と周辺を巡る視察旅もいよいよ最後の「平木田駅」に近づいた。
出発地の新発田駅から1kmほど直ぐに国道7号で加治川を渡って「加治駅」周辺を見て以来、「中条駅」とその少し先までの8kmほどは、右手に常に一定距離で緑の小高い山景色が続いてきた。それは日本一低い山脈と呼ばれる「櫛形山脈」の裾野づたいに国道7号が通じているためであったのだが、その道筋は、胎内川により山脈が途切れるところで山裾づたいに川の上流側に一旦は引き込まれるようになるのだが、川を越えて次に控える高坪山の山裾へと進路を切り替えることで、また西側の海岸線と並行に進路を取ることになる。新潟市を起点に日本海側を遠く青森市まで559.6kmを結ぶこの道が、あたかも”寄り道や遠回りは最小限に”と言われているかのようなトレースラインだ。
国道7号から駅に向かう道に左折すると後は見事な一直線の1kmほどで特に遮るもの無く、駅舎とホームを結ぶ歩道跨線橋が見えて来た。直前に美しく整備された中条駅と周辺を見て来たばかりだったので、またもヒビが入る古いコンクリ造の小さな無人駅舎を前にすると、少し寂しい思いになる。
そんな廃れた雰囲気にもかかわらず、駅前の敷地は広い上に、舗装されて30台分くらいの駐車区画線が引かれており、そこに結構な数の乗用車が停められていたので驚いた。駅前施設の利用者かと思いきや、特に商業施設があるわけでもない。周辺を少し散策すると鉄路の東側に位置する駅舎から半径約500mくらいで、丁度半円を描くように、住宅が立ち並んでいることがわかる。
衛星写真の地図を見ると駅の西側は日本海近くまで広く水田が広がっていて、これまでも見て来たように稲作田園地帯にありがちなものなのだが、数十件の農家と思しき住宅がまとまる集落が散在していて、水田の間を縫うような農道で繋がっている。
どう考えても公共交通機関がネットし難いエリアであり、徒歩圏内に現代的な商業施設なども無いし、近くの都市部である中条地区や、新発田地域を越境した北の都市部である村上市あたりに職を持つ人がパークアンドライドで使用しているのかもしれない。これまで見て来た羽越本線の幾つかの無人駅と同様の利用形態が想像できる。
衛星写真を眺めてみると平木田駅の西側海方面は妙に綺麗に木々が密集しているように見える。駅の西側に行って見ると、枯れた草木の中に電柱並みの太さで3mほどの高さの濃い茶色の木材が4本建ち並んでいて、各々上部に鳥や鮭などの彫刻が細工されておりトーテムポールのようになっている。更に近づいてみると、真ん中の2本の一方に「新しい鉄道林」と、もう一方に「羽越本線平木田1号林植樹式 平成30年9月22日」と大きく文字が刻まれている。その間が通り道のようになっていて、奥には杉の様な木々が十数メートルくらいに高さをそろえてびっしり林立しているのが見える。
左のトーテムポールには「welcome」とも看板が着いているので、鉄道林の理解を深めて親しんでもらうために5年前に賑々しく開設された場なのだったのかもしれない。しかし、直後のコロナ禍でそれどころではなくなり、今や人も寄らずに入口は荒れ野原ということか。
調べてみると、鉄道林は日本では1893年から整備されてきたという。昨年が丁度130年の節目だったというのであれば、それにちなんで鉄道の恩恵再認識や緑化等の啓発などを切り口にして、新発田地域や羽越本線の盛り上げ策を企画展開すればよかったなあ。
少し後悔しながら、新発田地域における羽越本線の各駅とその周辺現場を見ながら考えてみる一連の視察旅は一応終わりとなった。ここまで見てきた各地の現状において、羽越本線の利用増と周辺地域の活性化を絡めて考えて、何ができるかをまとめてみることにしよう。
(「活かすぜ羽越本線100年15「新発田駅以北編・平木田駅」」終わります。「活かすぜ羽越本線100年16「新発田駅以北・私の提案(その1)」」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea
☆現在進行型の仕事遍歴あります。