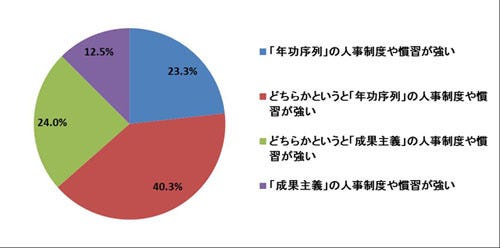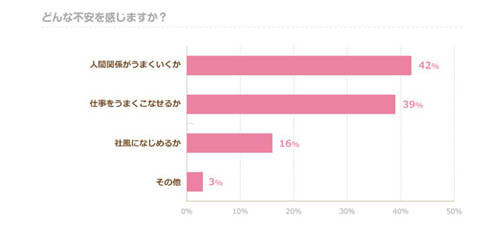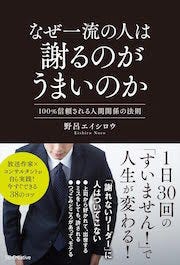
仕事をしていれば誰でも、失敗をして他人に迷惑をかけてしまうことがある。そんな時には普通、「謝罪」をすることになる。自分の間違った行為によって相手に迷惑をかけたら頭を下げて謝る――これはとても自然なことだ。
もっとも、現実に仕事で謝罪をするのは必ずしもこちらに非がある時ばかりではない。時には、全然自分は悪くないのになぜか頭を下げなければならないような理不尽な状況に遭遇することがある。当然ながら、これは気分のよいことではない。「納得いかないな……」と心では思いながら、とりあえず頭を下げて悔しい気持ちをぐっとこらえることになる。
このような「自分は悪くないのに謝罪をする」という行為は、できるなら誰でもしたくないと思っているはずだ。しかし、この「自分は悪くないのに謝罪をする」という行為が、実は人間関係を円滑にする最強のツールだとしたらどうだろうか。今回紹介する『なぜ一流の人は謝るのがうまいのか』(野呂エイシロウ/SBクリエイティブ/2015年2月/1300円+税)は、そんな謝罪のポジティブな側面について様々な角度から説明をしている本である。「謝罪にポジティブな側面なんてあるの?」と疑問に思った人は、ぜひ手にとってみてほしい本だ。
謝ることは「おもてなし」
野呂エイシロウ『なぜ一流の人は謝るのがうまいのか』(SBクリエイティブ/2015年2月/1300円+税)
本書における「謝罪」は、「自分に非があることを認め、相手に詫びる」ということだけにとどまらない。たとえば、本書ではミーティングのために来てくれた相手に対して、
「お忙しいのに時間をつくっていただいて申し訳ありません」
「雨の中、ご足労いただいて申し訳ありません」
「すいません、缶コーヒーしかなくて」
「こんな狭い場所ですいません」
と、ミーティングの冒頭からできるだけ謝ることが推奨されている。
これは、別に悪いことをしかたら相手に詫びているわけではない。コミュニケーションを円滑にするために、挨拶の一種として謝っているだけだ。「別に悪いことをしているわけでもないのに、ペコペコ頭を下げるなんて」と思ってしまう人もきっといるだろうが、実際このような「挨拶としての謝罪」を冒頭に行うことで、ミーティングを和やかな雰囲気で進められるようになることはよくある。ある意味では、このような謝罪は「おもてなし」の一種だと言えるかもしれない。
「こっちに非がない限り頭は下げない」と意固地になるのは簡単だ。論理的には、そちらのほうがスジが通っているのかもしれない。しかし、そうやってスジを通したところで得られるものは別になにもない。それならいっそのこと「おもてなし」のつもりでとりあえず頭を下げてしまったほうがよいのではないだろうか。本書はそういった「損して得取れ」的なコミュニケーション術を教えてくれる。
「許されるキャラ」をいかに作るか
また、本当にこちらに非があって謝らなければならない時に、どうやって謝るかはとても重要だ。挨拶の代わりに謝る場合とは違って、こちらでは「とりあえずペコペコしていればいい」というわけにはいかない。相手に許してもらえるような謝り方を考える必要がある。
本書では、「事前に根回しをすること」「キーマンに対して謝ること」「相手が納得する正しい言い訳を説明すること」などが謝罪時のポイントとして挙げられている。これらは、謝罪時のチェックリストとして活用するといいだろう。
そのような謝り方の説明とは別に、著者のまわりにいる「謝罪の達人」の例も紹介されているのだが、これが面白い。たとえば、放送作家の安達元一氏は、超売れっ子であるがゆえにたいてい会議には遅刻してくるという。その時安達氏は、
「すいません、すいません、すいません……」
と「すいません」を連発しながら入室し、その怒涛の謝罪攻勢で場の雰囲気を変えて許されてしまう。遅刻よりもずっと深刻な事態であっても、安達氏は同じように謝罪によってピンチを乗り越えてしまうそうである。
もちろん、これをそのまま普通の人がマネすればよいとは言わない。逆効果になる場合も当然あるだろう。それでも、謝ることで危機を乗り越えて才能を発揮している人がいるということは、知っておいてよいはずだ。
謙虚を武器に
海外の場合はわからないが、少なくとも日本では謙虚な人はそれだけで周囲からよい扱いを受けることができる。つまり、謙虚は武器になるのだ。この武器を活用しないのはもったいない。
基本的に、頭を下げることで失うものは何もない。それで得られるものがあるなら、どんどん謝っていけばよい。こんなふうに、謝罪についての考え方や態度を変える力が本書にはある。「悪いのはあいつだ。それなのに自分が頭を下げなければならないのは納得がいかない」と日頃からよく思っているという人は、ぜひ一読してみてほしい。
日野瑛太郎
ブロガー、ソフトウェアエンジニア。経営者と従業員の両方を経験したことで日本の労働の矛盾に気づき、「脱社畜ブログ」を開設。現在も日本人の働き方に関する意見を発信し続けている。著書に『脱社畜の働き方』(技術評論社)、『あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。』(東洋経済新報社)がある。