
『スターリンからフルシチョフへ』(ギウセッペ・ボッファ 石川善之訳 三一新書)
ロシア・ソ連の指導者について調べている過程でみつけた。いわゆるスターリン批判が行われた、第20回党大会の前後5年間をモスクワに滞在したイタリア共産党員によるルポルタージュである。
西側の人間でありながら、共産党員という絶妙な立ち位置の著者が見る激動の5年間。これは古本屋の片隅で忘れ去られるには惜しい記録である。
スターリンの伝記、フルシチョフによるスターリン批判を読んだ上で手にしたので、大変面白く、話の辻褄が合っていくのを追うように読めた。
著者は「個人崇拝」への批判に出くわした当初の驚きをこのように書いている。
“これらの慣習は、たしかに長い目で見れば有害であったにしても、ある時期には歴史的に必要なことだったのではないか”
難しい問題だ。信じがたいほどの犠牲をもって、ナチス・ドイツから国土を守るために。あるいはかつての同盟国・ソ連を目の敵にする、共産主義の波及を恐れる各国との対立。国内を強く引き締め、これに対抗するには、独裁者が必要悪だった・・・これは否定できない。
また、著者はスターリン批判の歴史的必要性をこう説明する。
“沈黙が守られているかぎり、1953年以後のもろもろの改革が、単なる思いつきの、その場限りのもののように思われる危険があったということである”
つまりは、フルシチョフがソ連共産党で正当な権力を継承するのに、“スターリン批判”という手順が必要だったともいえる。
以前、“批判”の全文を読んで、私はフルシチョフの民主主義的な、あるいはマルクス・レーニン主義に立ち返ろうとする純粋な革命家の良心を感じた。しかしそれは一つのパフォーマンスでもあったわけだ。上に引用したように、著者は手続き上の必要性には言及するが、しかし権力闘争上のパフォーマンスとまでは言わない。私の第一印象と同じく、著者は概ねフルシチョフを誉め、歓迎してしまっている。(皮肉にもその無批判性に、私は“個人崇拝”の慣例を感じてしまった)
と、手厳しく書いてしまったが、「スターリン批判」は、冷静に受け止め得ないほど、共産党員には青天の霹靂だったようだ。以下、著者がソ連で聞き取ったエピソードがそれを如実に表している。
“会議か終って出てきた大抵の人の顔には、明らかに狼狽の色があった。あとできいたことだが、かれらのあるものは、家に走って帰り、スキー道具をかついで、市外に出かけ、夜中まで森の中をほっつきまわったということだ、疲労で、くたくたになり、何もかも忘れてしまいたかったのだ。そして翌日になってもまだ完全に自分をとりもどすことができなかったということである”
とはいえ時間が経つにつれ、さまざまな冷静な意見が持ち上がった。
著者の説明を引用しよう。
“どうしていっさいをスターリンの個人的欠点だけに帰することができるのか? 何故原因をもっと深くつきつめないのか? 今日の指導者の諸君は昨日までどこにいたのか? ”
特に三つ目の疑問は辛辣である。フルシチョフの報告では、あたかも自分らが民主主義的な、人民の側を代表しているかのように見える。しかし、フルシチョフ本人がそもそもスターリンの下で出世を遂げてきた者である。
著者は、これらの疑問に真摯に向き合い、本書で丁寧な分析を行う。けれどフルシチョフ自身に批判・疑問を向けることはない。西側の人間とはいえ、共産党員である著者の限界が露呈しているといっては、意地悪に過ぎるだろうか。
とはいえ、著者の舌鋒は、過去の失政に対しては鋭く機能する。
“驚きにたえないことは、だれかが罪を宣告されると、しばしばその背後に凶悪な外国の敵の手の働いていることが証明されたことである。この敵は、当該第三国の「秘密機関」によって代表され、あらゆるところに網をはっていると考えられていた。あのようにしばしばくりかえされたこうした非難を当時の人々が、かくも容易に信ずることができたということは、嘘のように思われる”
・・・嘘のようなことが、今のロシアでも繰り返されている。反政府的活動は、外国のスパイとみなされ、投獄や暗殺の対象だ。ロシアという国の、普遍的な政治風土なのかと思ってしまう。
と、鋭い見方をする一方で、著者のおめでたいような論述も散見された。
“ソ連における社会主義建設は、私的な資本家や銀行家もなく、外国からの借款もなく、植民地的利潤もない状態のもとで実現された。たしかにこれを軌道にのせるためには長期にわたる苦しいぎせいが必要だった。しかしこれらのぎせいは住民の大多数によって自由意志で受諾された”
まだ、スターリン治世の悲劇が明るみになっていなかったからか。あるいは、党員たる著者の目は曇っていたのだろうか。ウクライナの飢饉は“大多数”の外に数えられる少数の犠牲に数えられているのか。
最後に、どうしてフルシチョフが権力を握ったかの疑問に応えるフルシチョフ本人の寓話が紹介されている。これは単純に面白かった。
“四人の男がウクライナの監獄にくらしていた。四人とも自分たちの運命のことを余りくよくよしていない。一人は無政府主義者、一人は社会民主主義者、一人は共産主義者、それからチビのユダヤ人だった。小包がとどいて、なかみを仲よくわける段になると、最初の三人は、それぞれもっともらしい理由を見つけて、この仕事を敬遠した。それでいつもチビのユダヤ人が分配の役を引き受けさせられた。ある日、地下にトンネルを掘って、脱走することにきまった。しかし最初にトンネルを出たやつは、歩哨にみつかって、鉄砲のお見舞いを受けるかもしれない。ところでユダヤ人は一番チビだったので、彼が一番先に出ることになった”
あるいは、私利私欲でなく、ソ連建て直しのために、フルシチョフは難しい役を買って出たのかもしれない。
興味は尽きない。フルシチョフのウクライナ時代のことや、クリミア移管の経緯など、もっと調べてみたい。
脇にそれたが、本書は歴史的限界を露呈しているとはいえ、資料的価値は小さくない。また一人の人間のルポルタージュとしても、読み甲斐があった。
ロシア・ソ連の指導者について調べている過程でみつけた。いわゆるスターリン批判が行われた、第20回党大会の前後5年間をモスクワに滞在したイタリア共産党員によるルポルタージュである。
西側の人間でありながら、共産党員という絶妙な立ち位置の著者が見る激動の5年間。これは古本屋の片隅で忘れ去られるには惜しい記録である。
スターリンの伝記、フルシチョフによるスターリン批判を読んだ上で手にしたので、大変面白く、話の辻褄が合っていくのを追うように読めた。
著者は「個人崇拝」への批判に出くわした当初の驚きをこのように書いている。
“これらの慣習は、たしかに長い目で見れば有害であったにしても、ある時期には歴史的に必要なことだったのではないか”
難しい問題だ。信じがたいほどの犠牲をもって、ナチス・ドイツから国土を守るために。あるいはかつての同盟国・ソ連を目の敵にする、共産主義の波及を恐れる各国との対立。国内を強く引き締め、これに対抗するには、独裁者が必要悪だった・・・これは否定できない。
また、著者はスターリン批判の歴史的必要性をこう説明する。
“沈黙が守られているかぎり、1953年以後のもろもろの改革が、単なる思いつきの、その場限りのもののように思われる危険があったということである”
つまりは、フルシチョフがソ連共産党で正当な権力を継承するのに、“スターリン批判”という手順が必要だったともいえる。
以前、“批判”の全文を読んで、私はフルシチョフの民主主義的な、あるいはマルクス・レーニン主義に立ち返ろうとする純粋な革命家の良心を感じた。しかしそれは一つのパフォーマンスでもあったわけだ。上に引用したように、著者は手続き上の必要性には言及するが、しかし権力闘争上のパフォーマンスとまでは言わない。私の第一印象と同じく、著者は概ねフルシチョフを誉め、歓迎してしまっている。(皮肉にもその無批判性に、私は“個人崇拝”の慣例を感じてしまった)
と、手厳しく書いてしまったが、「スターリン批判」は、冷静に受け止め得ないほど、共産党員には青天の霹靂だったようだ。以下、著者がソ連で聞き取ったエピソードがそれを如実に表している。
“会議か終って出てきた大抵の人の顔には、明らかに狼狽の色があった。あとできいたことだが、かれらのあるものは、家に走って帰り、スキー道具をかついで、市外に出かけ、夜中まで森の中をほっつきまわったということだ、疲労で、くたくたになり、何もかも忘れてしまいたかったのだ。そして翌日になってもまだ完全に自分をとりもどすことができなかったということである”
とはいえ時間が経つにつれ、さまざまな冷静な意見が持ち上がった。
著者の説明を引用しよう。
“どうしていっさいをスターリンの個人的欠点だけに帰することができるのか? 何故原因をもっと深くつきつめないのか? 今日の指導者の諸君は昨日までどこにいたのか? ”
特に三つ目の疑問は辛辣である。フルシチョフの報告では、あたかも自分らが民主主義的な、人民の側を代表しているかのように見える。しかし、フルシチョフ本人がそもそもスターリンの下で出世を遂げてきた者である。
著者は、これらの疑問に真摯に向き合い、本書で丁寧な分析を行う。けれどフルシチョフ自身に批判・疑問を向けることはない。西側の人間とはいえ、共産党員である著者の限界が露呈しているといっては、意地悪に過ぎるだろうか。
とはいえ、著者の舌鋒は、過去の失政に対しては鋭く機能する。
“驚きにたえないことは、だれかが罪を宣告されると、しばしばその背後に凶悪な外国の敵の手の働いていることが証明されたことである。この敵は、当該第三国の「秘密機関」によって代表され、あらゆるところに網をはっていると考えられていた。あのようにしばしばくりかえされたこうした非難を当時の人々が、かくも容易に信ずることができたということは、嘘のように思われる”
・・・嘘のようなことが、今のロシアでも繰り返されている。反政府的活動は、外国のスパイとみなされ、投獄や暗殺の対象だ。ロシアという国の、普遍的な政治風土なのかと思ってしまう。
と、鋭い見方をする一方で、著者のおめでたいような論述も散見された。
“ソ連における社会主義建設は、私的な資本家や銀行家もなく、外国からの借款もなく、植民地的利潤もない状態のもとで実現された。たしかにこれを軌道にのせるためには長期にわたる苦しいぎせいが必要だった。しかしこれらのぎせいは住民の大多数によって自由意志で受諾された”
まだ、スターリン治世の悲劇が明るみになっていなかったからか。あるいは、党員たる著者の目は曇っていたのだろうか。ウクライナの飢饉は“大多数”の外に数えられる少数の犠牲に数えられているのか。
最後に、どうしてフルシチョフが権力を握ったかの疑問に応えるフルシチョフ本人の寓話が紹介されている。これは単純に面白かった。
“四人の男がウクライナの監獄にくらしていた。四人とも自分たちの運命のことを余りくよくよしていない。一人は無政府主義者、一人は社会民主主義者、一人は共産主義者、それからチビのユダヤ人だった。小包がとどいて、なかみを仲よくわける段になると、最初の三人は、それぞれもっともらしい理由を見つけて、この仕事を敬遠した。それでいつもチビのユダヤ人が分配の役を引き受けさせられた。ある日、地下にトンネルを掘って、脱走することにきまった。しかし最初にトンネルを出たやつは、歩哨にみつかって、鉄砲のお見舞いを受けるかもしれない。ところでユダヤ人は一番チビだったので、彼が一番先に出ることになった”
あるいは、私利私欲でなく、ソ連建て直しのために、フルシチョフは難しい役を買って出たのかもしれない。
興味は尽きない。フルシチョフのウクライナ時代のことや、クリミア移管の経緯など、もっと調べてみたい。
脇にそれたが、本書は歴史的限界を露呈しているとはいえ、資料的価値は小さくない。また一人の人間のルポルタージュとしても、読み甲斐があった。










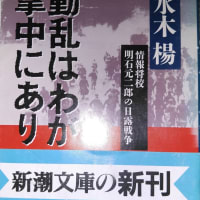





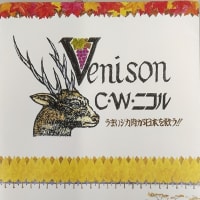

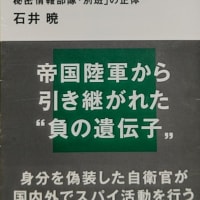

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます