皆さま、GEIT(Governance of Enterprise Information Technology)のエバンジェリストこと、ITコーディネータの元村憲一です。
「おっ! 何か役立つまたは、面白そうな事が書いてありそうだ」と思われたら、是非読者登録してください。
ブログの第240回目は、このブログの本題になっている GEITについての続きです。
これまでほとんどは、ISACAの話題を中心にお伝えして来ましたが、第210回目からは、ISACAを離れて、日本のGEIT人材であるITコーディネータについて、お伝えしています。
【IT経営とは?】
ITコーディネータ制度は、経済産業省が、日本の競争力を回復する高度人材として、未来を見据えた構想の中で制度化した割には、10年以上経った現在でも、非常に認知度が低い状態が続いています。
前回に続き「IT経営」と言う言葉につて、お伝えして行きます。
経済産業省のIT経営ポータル(以下を参照)
URL:
http://www.it-keiei.go.jp/index.html
IT経営とは何か?
経済産業省が行っているIT経営の定義は、以下の様に書かれています。
IT投資本来の効果を享受するためには、目的なく、単に現業をIT化するだけでは、不十分であり、自社のビジネスモデルを再確認したうえで、経営の視点を得ながら、業務とITとの橋渡しを行っていくことが重要です。
このような、経営・業務・ITの融合による企業価値の最大化を目指すことを「IT経営」と定義します。
IT経営について
IT経営ポータルには、IT経営についてとして、以下の5項目が記載されています。
・7つの機能と20の行動指針
・IT経営力指標と4つのステージ
・IT経営協議会とIT経営憲章
・IT経営ロードマップ
・各種報告書
・IT経営ロードマップ
【IT経営ロードマップとは】
IT経営憲章に基づき、企業がIT経営を実際に推進するにあたっての取り組みを、IT経営における先進企業の事例を踏まえて、以下の2点として整理したものです。
平成20年6月に初版が発行され、平成22年3月に改定版が発行されています。
1. IT経営の実践に向けた取組
2. マネジメント上の課題
【IT経営ロードマップの詳細】
・IT経営に向けた構造的課題
背景となる課題の構図として、経営とITの好循環に入り込めない企業を見ると、以下のような共通の特徴が見られると書かれています。
1.経営者自身のIT投資に対する考え方が不明確
2.経営目標実現に向けた基本的な「絵図面」の不在
3.「絵図面」を具体化するための業務設計作業の不在
「絵図面」? ずいぶんと酷い言葉を選んでいると思います。
最後にITへの実装をするためには、ポンチ絵では役に立ちません、事業構造を正確に表す図面が必要です。
そして、以下の様に続けられています。
確かに、こうした構造的課題の解決がない状態で、発注仕様や開発作業の改善に向けた取組を始めても、IT投資そのものの生産性を上げ、戦略的な投資に結びつけて行くのは困難である。
成功事例を分析すると、経営者による企業改革や業務改革の指針の提示をスタートに、経営とITの好循環に入っている状況は多く見られる。
現場レベルの課題解決の鍵は、むしろ、これらの構造的課題の方が握っている事を示唆している。
・課題の詳細
1.経営目標
経営者自身のIT投資に対する考え方が不明確について。
・経営戦略上の目標とポジショニングが明確でない
・経営者が、IT投資と経営戦略とは関係が希薄だと思っている
2.IT経営戦略
経営目標実現に向けた基本的な「絵図面」の不在について。
・経営目標実現に向けたIT活用の基本的な「絵図面」(IT経営アーキテクチャ)がない
3.狭義のIT投資
「絵図面」を具体化するための業務設計作業の不在について。
・「絵図面」どおりに、業務・データを振る舞わせるための具体的な設計作業(業務モデル構築)をユーザもベンダも行っていない
情報化のスコープ
↓
業務モデル(概念)
↓
システムモデル(論理)
↓
技術モデル(物理)
う~ん? と言う感じです。
「絵図面」と言う言葉もそうですが、未だに40年前のやり方で何とかしようとしています。
この後、EA(Enterprise Architecture)の図も出てくるのですが、長年効果がない事は実証されてきた以下のやり方です。
・現場に行ってユーザヒアリング(参与観察)
・DMM、DFDとE-R図(+クラス図もどき)
ここに書かれているのは、未だに変換の断絶が起こる以下のやり方です。
× 概念 → 論理 → 物理
私たちの推奨する手法TMは、これを以下の様にします。
◎ 概念 = 論理 = 物理
現実の事態をモデルにとってそのままDB(コンピュータ)に乗せます。
分析 = 設計 = 実行 とも言えるやり方(Concurrent Engineering)です。
※RDBの内部は、セット理論で作られていて、そのまま乗せると非常に早いのです。
これによって、高品質・低コスト・短納期(QCD全てを満たす)を実現します。
更に、IT経営に向けた構造的課題は、以下の様に続きます。
とはいえ、取組初期の時点で、こうした構造的課題といきなり対峙し、一度に全ての解決を目指すことは、事実上困難である。
先進的な企業の例を見ると、まず、個々の課題の「見える化」に取り組み、次に、「見える化」が十分に進んだ段階で、「見える化」した情報や業務の「共有化」に取組を進めているものが多い。
また、最終的には、将来の外部環境の変化に備え、ユーザーの業務・システムの「柔軟化」に取り組む、という整理が可能である。
上記のような構造的課題については、こうした取組を進めながら、一つ一つ徐々に解決している様子が伺われる。
このため、IT経営の改善に向けた着実な取組と、その背景にある構造的課題の解決とは、並行して、段階を追って取り組むべき課題と見ることも出来るのではないか。
もちろん、経営課題が大きく、短期に抜本的な改革を要する場合、IT投資においても、大がかりな共有化レベルの取組から開始するケースも十分あり得る。
成功事例を見る限り、「経営戦略や事業戦略の実現のために、IT活用が必要不可欠である」ということを導出することに、丁寧に時間とコストをかけているケースが多い。
ITを利活用して経営目標を達成するということについての納得感と「場の醸成」を、経営層から現場まで一気通貫で行うことに力を入れているのである。
IT経営実現に向けた取組は、いきなり全体に対して行なうのではなく、その時々に可能な範囲で段階的に行うことが肝要である。
前回もお伝えしましたが、成熟度だから徐々に段階を踏まないとできないと述べられている様に感じます。
しかし、これに時間をかけている間、急速に大きく変化する経営環境は、待っていてくれるのでしょうか?
経営者がいくら本気になっても、40年前のやり方で対処していては、本来経営を支援するはずのITが、急速に大きく変化する環境のスピードに即応できず、経営戦略の足を引っ張ってしまいます。
以前からこのブログでお伝えしているTMと言う手法は、「見える化」「共有化」「柔軟化」を同時並行的に実現します。
このTMこそが、私の考えるIT経営への実現解なのです。
IT経営ロードマップに書かれている事を素早く実現できるように支援をして行く事は、IT経営を実現するプロフェッショナルと言われている、私達ITコーディネータに課せられた重要な使命の1つです。
少し長くなりましたので、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの説明の途中で、終了します。
次回もこのシーズからは、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの続きを説明して行きます。
この続きは、次回以降に、ITコーディネータ資格の変遷や、ITコーディネータのバイブルと言われるプロセスガイドラインの内容についても紹介して行きます。
最後まで、お付き合いくださいまして、ありがとうございます。
次回以降も、本題のGEITの話題として、ITコーディネータを中心に、ISACAが認定している資格の最新版が明らかになった段階で、順次お伝えして行きます。
皆さまからの、ご意見・ご感想をお待ちしております。
この記事を、気に入ってくださった方は、クリックをしていただけると励みになります。
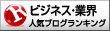
【資格】
・ITコーディネータ
・公認情報システム監査人
Certified Information Systems Auditor (CISA)
・公認情報セキュリティマネージャー
Certified Information Security Manager (CISM)
・公認ITガバナンス専門家
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
・Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
■Facebook
https://www.facebook.com/kenichi.motomura.1/
■公式ブログ
http://blog.kazatsukuri.jp/
■Ameblo
http://ameblo.jp/motomuranet/
■Twitter
https://twitter.com/motomuranet/
■YouTube
https://www.youtube.com/user/motomuranet/
■まぐまぐ
http://www.mag2.com/m/0001626008.html
「おっ! 何か役立つまたは、面白そうな事が書いてありそうだ」と思われたら、是非読者登録してください。
ブログの第240回目は、このブログの本題になっている GEITについての続きです。
これまでほとんどは、ISACAの話題を中心にお伝えして来ましたが、第210回目からは、ISACAを離れて、日本のGEIT人材であるITコーディネータについて、お伝えしています。
【IT経営とは?】
ITコーディネータ制度は、経済産業省が、日本の競争力を回復する高度人材として、未来を見据えた構想の中で制度化した割には、10年以上経った現在でも、非常に認知度が低い状態が続いています。
前回に続き「IT経営」と言う言葉につて、お伝えして行きます。
経済産業省のIT経営ポータル(以下を参照)
URL:
http://www.it-keiei.go.jp/index.html
IT経営とは何か?
経済産業省が行っているIT経営の定義は、以下の様に書かれています。
IT投資本来の効果を享受するためには、目的なく、単に現業をIT化するだけでは、不十分であり、自社のビジネスモデルを再確認したうえで、経営の視点を得ながら、業務とITとの橋渡しを行っていくことが重要です。
このような、経営・業務・ITの融合による企業価値の最大化を目指すことを「IT経営」と定義します。
IT経営について
IT経営ポータルには、IT経営についてとして、以下の5項目が記載されています。
・7つの機能と20の行動指針
・IT経営力指標と4つのステージ
・IT経営協議会とIT経営憲章
・IT経営ロードマップ
・各種報告書
・IT経営ロードマップ
【IT経営ロードマップとは】
IT経営憲章に基づき、企業がIT経営を実際に推進するにあたっての取り組みを、IT経営における先進企業の事例を踏まえて、以下の2点として整理したものです。
平成20年6月に初版が発行され、平成22年3月に改定版が発行されています。
1. IT経営の実践に向けた取組
2. マネジメント上の課題
【IT経営ロードマップの詳細】
・IT経営に向けた構造的課題
背景となる課題の構図として、経営とITの好循環に入り込めない企業を見ると、以下のような共通の特徴が見られると書かれています。
1.経営者自身のIT投資に対する考え方が不明確
2.経営目標実現に向けた基本的な「絵図面」の不在
3.「絵図面」を具体化するための業務設計作業の不在
「絵図面」? ずいぶんと酷い言葉を選んでいると思います。
最後にITへの実装をするためには、ポンチ絵では役に立ちません、事業構造を正確に表す図面が必要です。
そして、以下の様に続けられています。
確かに、こうした構造的課題の解決がない状態で、発注仕様や開発作業の改善に向けた取組を始めても、IT投資そのものの生産性を上げ、戦略的な投資に結びつけて行くのは困難である。
成功事例を分析すると、経営者による企業改革や業務改革の指針の提示をスタートに、経営とITの好循環に入っている状況は多く見られる。
現場レベルの課題解決の鍵は、むしろ、これらの構造的課題の方が握っている事を示唆している。
・課題の詳細
1.経営目標
経営者自身のIT投資に対する考え方が不明確について。
・経営戦略上の目標とポジショニングが明確でない
・経営者が、IT投資と経営戦略とは関係が希薄だと思っている
2.IT経営戦略
経営目標実現に向けた基本的な「絵図面」の不在について。
・経営目標実現に向けたIT活用の基本的な「絵図面」(IT経営アーキテクチャ)がない
3.狭義のIT投資
「絵図面」を具体化するための業務設計作業の不在について。
・「絵図面」どおりに、業務・データを振る舞わせるための具体的な設計作業(業務モデル構築)をユーザもベンダも行っていない
情報化のスコープ
↓
業務モデル(概念)
↓
システムモデル(論理)
↓
技術モデル(物理)
う~ん? と言う感じです。
「絵図面」と言う言葉もそうですが、未だに40年前のやり方で何とかしようとしています。
この後、EA(Enterprise Architecture)の図も出てくるのですが、長年効果がない事は実証されてきた以下のやり方です。
・現場に行ってユーザヒアリング(参与観察)
・DMM、DFDとE-R図(+クラス図もどき)
ここに書かれているのは、未だに変換の断絶が起こる以下のやり方です。
× 概念 → 論理 → 物理
私たちの推奨する手法TMは、これを以下の様にします。
◎ 概念 = 論理 = 物理
現実の事態をモデルにとってそのままDB(コンピュータ)に乗せます。
分析 = 設計 = 実行 とも言えるやり方(Concurrent Engineering)です。
※RDBの内部は、セット理論で作られていて、そのまま乗せると非常に早いのです。
これによって、高品質・低コスト・短納期(QCD全てを満たす)を実現します。
更に、IT経営に向けた構造的課題は、以下の様に続きます。
とはいえ、取組初期の時点で、こうした構造的課題といきなり対峙し、一度に全ての解決を目指すことは、事実上困難である。
先進的な企業の例を見ると、まず、個々の課題の「見える化」に取り組み、次に、「見える化」が十分に進んだ段階で、「見える化」した情報や業務の「共有化」に取組を進めているものが多い。
また、最終的には、将来の外部環境の変化に備え、ユーザーの業務・システムの「柔軟化」に取り組む、という整理が可能である。
上記のような構造的課題については、こうした取組を進めながら、一つ一つ徐々に解決している様子が伺われる。
このため、IT経営の改善に向けた着実な取組と、その背景にある構造的課題の解決とは、並行して、段階を追って取り組むべき課題と見ることも出来るのではないか。
もちろん、経営課題が大きく、短期に抜本的な改革を要する場合、IT投資においても、大がかりな共有化レベルの取組から開始するケースも十分あり得る。
成功事例を見る限り、「経営戦略や事業戦略の実現のために、IT活用が必要不可欠である」ということを導出することに、丁寧に時間とコストをかけているケースが多い。
ITを利活用して経営目標を達成するということについての納得感と「場の醸成」を、経営層から現場まで一気通貫で行うことに力を入れているのである。
IT経営実現に向けた取組は、いきなり全体に対して行なうのではなく、その時々に可能な範囲で段階的に行うことが肝要である。
前回もお伝えしましたが、成熟度だから徐々に段階を踏まないとできないと述べられている様に感じます。
しかし、これに時間をかけている間、急速に大きく変化する経営環境は、待っていてくれるのでしょうか?
経営者がいくら本気になっても、40年前のやり方で対処していては、本来経営を支援するはずのITが、急速に大きく変化する環境のスピードに即応できず、経営戦略の足を引っ張ってしまいます。
以前からこのブログでお伝えしているTMと言う手法は、「見える化」「共有化」「柔軟化」を同時並行的に実現します。
このTMこそが、私の考えるIT経営への実現解なのです。
IT経営ロードマップに書かれている事を素早く実現できるように支援をして行く事は、IT経営を実現するプロフェッショナルと言われている、私達ITコーディネータに課せられた重要な使命の1つです。
少し長くなりましたので、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの説明の途中で、終了します。
次回もこのシーズからは、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの続きを説明して行きます。
この続きは、次回以降に、ITコーディネータ資格の変遷や、ITコーディネータのバイブルと言われるプロセスガイドラインの内容についても紹介して行きます。
最後まで、お付き合いくださいまして、ありがとうございます。
次回以降も、本題のGEITの話題として、ITコーディネータを中心に、ISACAが認定している資格の最新版が明らかになった段階で、順次お伝えして行きます。
皆さまからの、ご意見・ご感想をお待ちしております。
この記事を、気に入ってくださった方は、クリックをしていただけると励みになります。
【資格】
・ITコーディネータ
・公認情報システム監査人
Certified Information Systems Auditor (CISA)
・公認情報セキュリティマネージャー
Certified Information Security Manager (CISM)
・公認ITガバナンス専門家
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
・Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
https://www.facebook.com/kenichi.motomura.1/
■公式ブログ
http://blog.kazatsukuri.jp/
■Ameblo
http://ameblo.jp/motomuranet/
https://twitter.com/motomuranet/
■YouTube
https://www.youtube.com/user/motomuranet/
■まぐまぐ
http://www.mag2.com/m/0001626008.html










